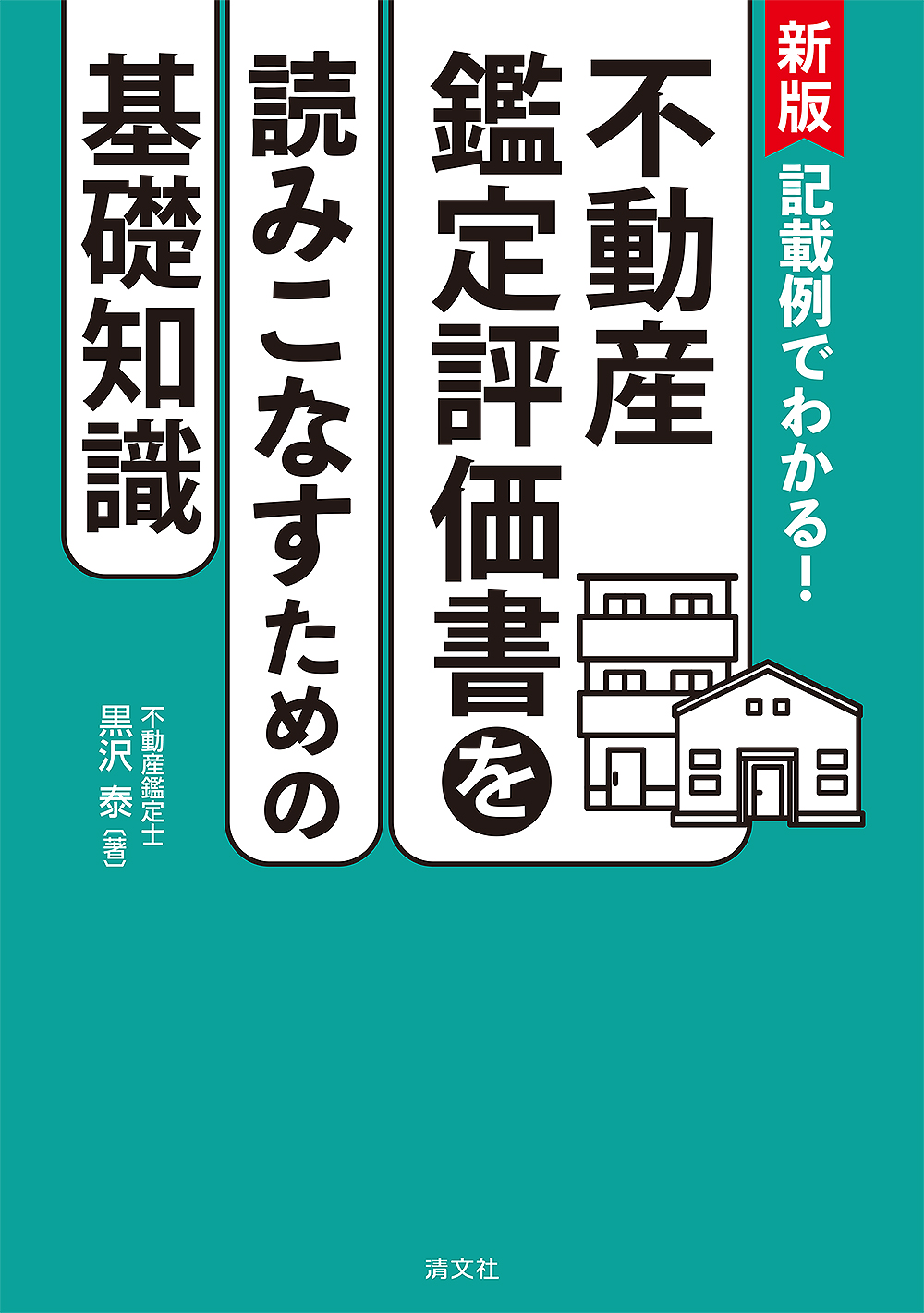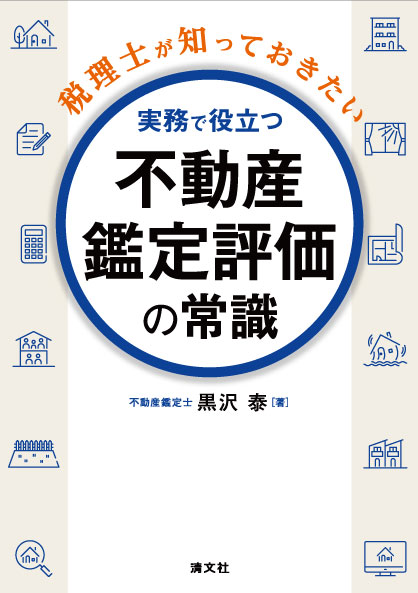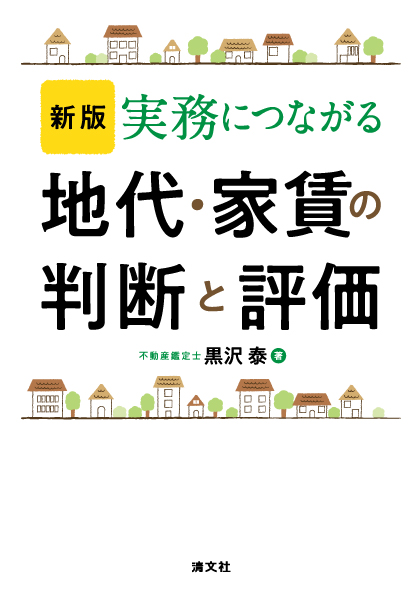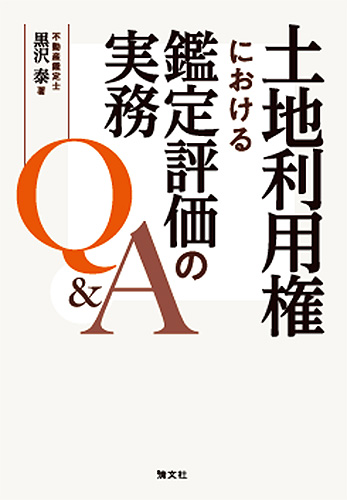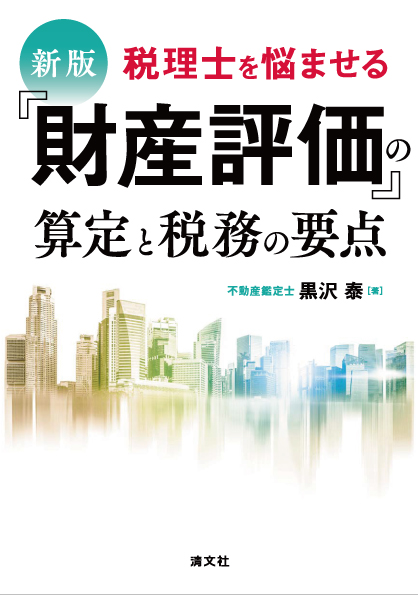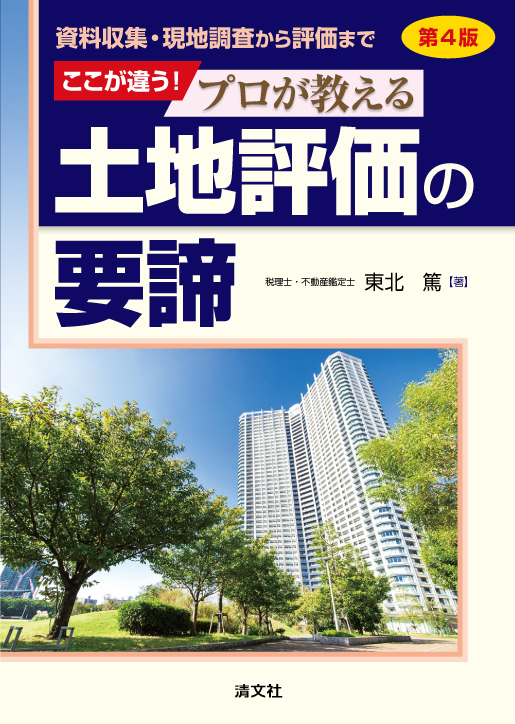税理士が知っておきたい
不動産鑑定評価の常識
【第45回】
「鑑定評価書には表立って登場しない「不動産の価格に関する諸原則」」
不動産鑑定士 黒沢 泰
1 はじめに
不動産鑑定評価基準(以下、単に「基準」と呼ぶ場合はこの基準を指します)には、「不動産の価格に関する諸原則」という独立した1つの章が設けられています(総論第4章)。
「不動産の価格に関する諸原則」は、基準の根底にあって鑑定評価の理論的基礎をなすものであり、不動産鑑定士が単なる経験的感覚のみによって鑑定評価額を導き出すことのないよう合理的な指針を定めたものです。この原則自体、鑑定評価書には表立って登場しませんが、決して机上の空論ではなく、現実に発生する不動産の価格現象を分析する上で重要な拠り所となっています。
今回は、「不動産の価格に関する諸原則」とはどのようなものであるかにつき、全体的なイメージを捉えた上で、特に鑑定実務に直接かかわりの深いいくつかの原則を掲げて鑑定評価書を読む際の手助けとしたいと思います。
この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員登録およびログインが必要です。
すでに会員登録をされている方は、下記ボタンからログインのうえ、ご覧ください。
Profession Journalのすべての記事をご覧いただくには、「プレミアム会員(有料)」へのご登録が必要となります。
なお、『速報解説』については「一般会員(無料)」へのご登録でも、ご覧いただけます。
※他にもWebセミナー受け放題のスーパープレミアム会員などがございます。
会員登録がお済みでない方は、下記会員登録のボタンより、ご登録のお手続きをお願いいたします。