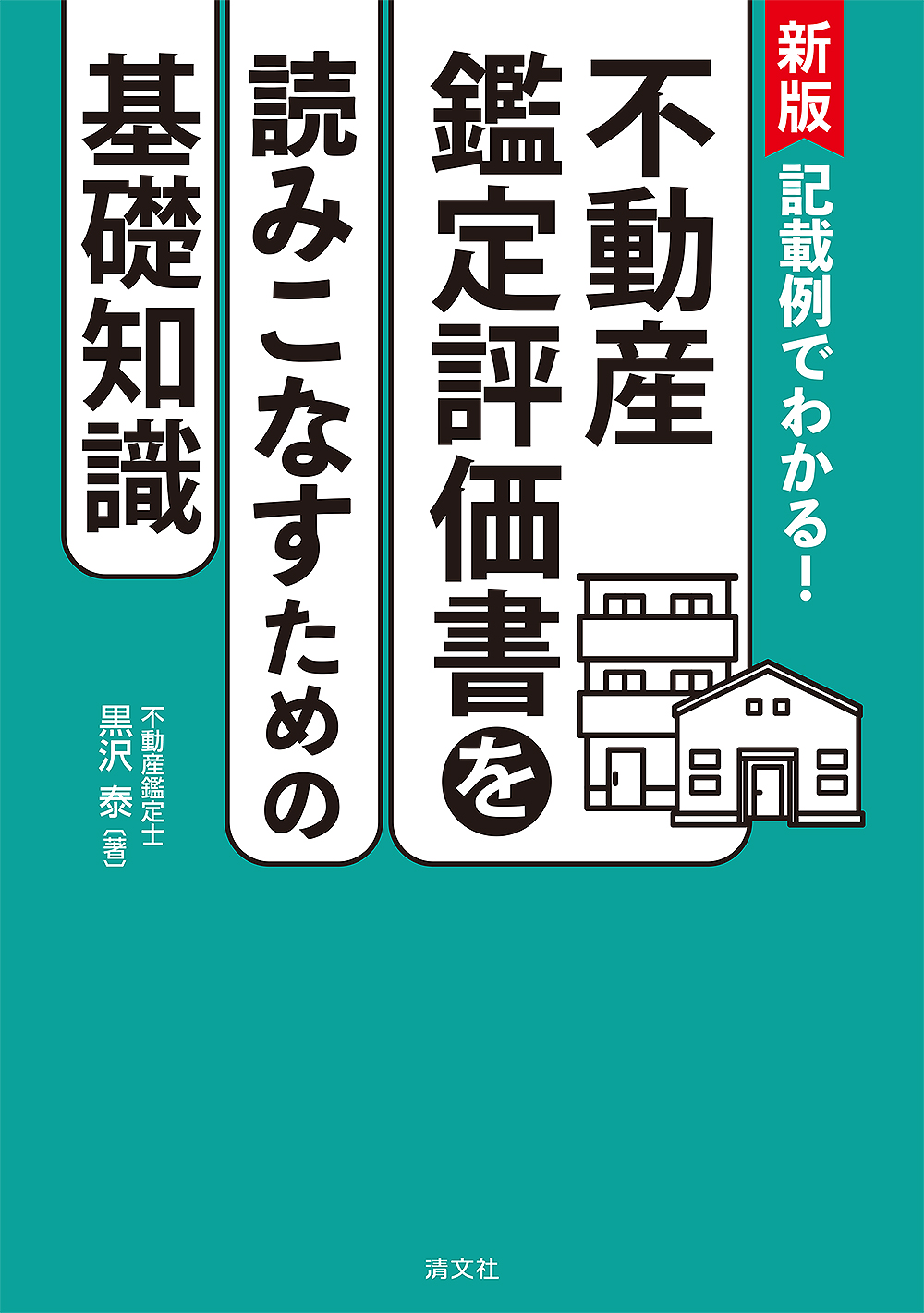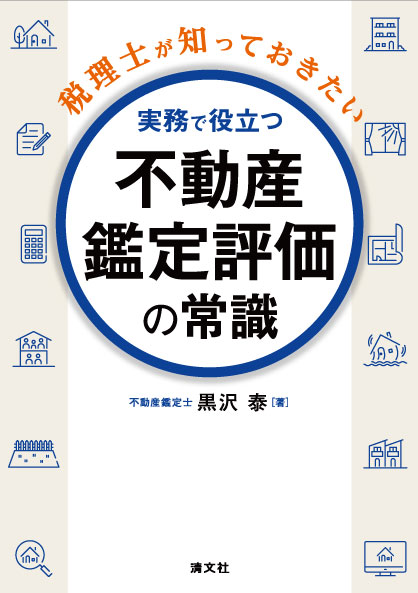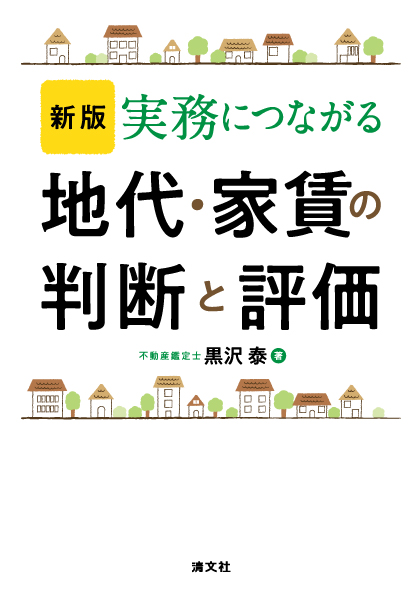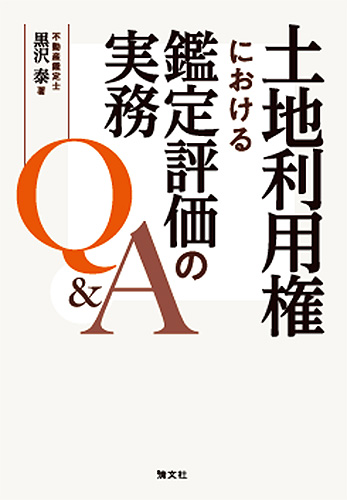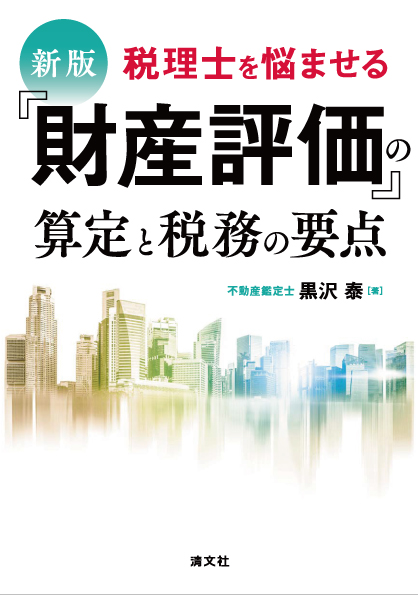税理士が知っておきたい
不動産鑑定評価の常識
【第71回】
「底地取引をめぐる新しい動向と鑑定評価」
不動産鑑定士 黒沢 泰
1 はじめに
旧借地法の下で締結された土地の賃貸借契約で長期間にわたり継続しているものについて、地代の利回り(=年額地代÷更地価格×100%)を計算した場合、経済合理性という観点からみて著しく低いものとなっているのが一般的な傾向です。
その理由は、旧借地法による借主保護という観点から、地価が上昇してもこれに見合う十分な地代に改定することが難しいという事情が大きく影響していたことが様々な方面から指摘されています。
そのため、土地の賃借人がいる状態でその土地の所有権(すなわち、底地の所有権)を取得しようと考える人は、一般市場においてはきわめて限られているのが実情です。
しかし、平成4年8月1日から新しい借地借家法が施行され、事業用定期借地権が活用されるに伴い、ここ最近、従来とは異なるスタイルでの底地取引が見受けられるようになってきました。
例えば、J-REITによる事業用不動産の敷地の取得です(ここで取得の対象とされているのは、あくまでも土地の賃借人がいる状態における土地の所有権であり、これがまさに底地に他なりません)。
このような新しい動向は、2025年9月29日付日本経済新聞朝刊にも「『底地ビジネス』10兆円市場」(※1)という大きな見出しで掲載されています。
(※1) この記事では、土地と建物の所有権を分離し、土地のみを取引する「底地ビジネス」が拡大しているとし、それは企業が資産の効率化に向けて土地の売却を進めていることが要因であり、米投資ファンドのKKRやイオンリテールが活用している旨が紹介されています。
そこで、今回はこのような動向を鑑定評価という視点も交えながら分析してみたいと思います。
この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員登録およびログインが必要です。
すでに会員登録をされている方は、下記ボタンからログインのうえ、ご覧ください。
Profession Journalのすべての記事をご覧いただくには、「プレミアム会員(有料)」へのご登録が必要となります。
なお、『速報解説』については「一般会員(無料)」へのご登録でも、ご覧いただけます。
※他にもWebセミナー受け放題のスーパープレミアム会員などがございます。
会員登録がお済みでない方は、下記会員登録のボタンより、ご登録のお手続きをお願いいたします。