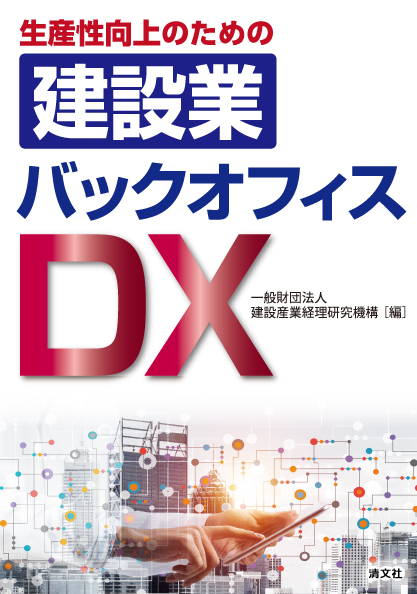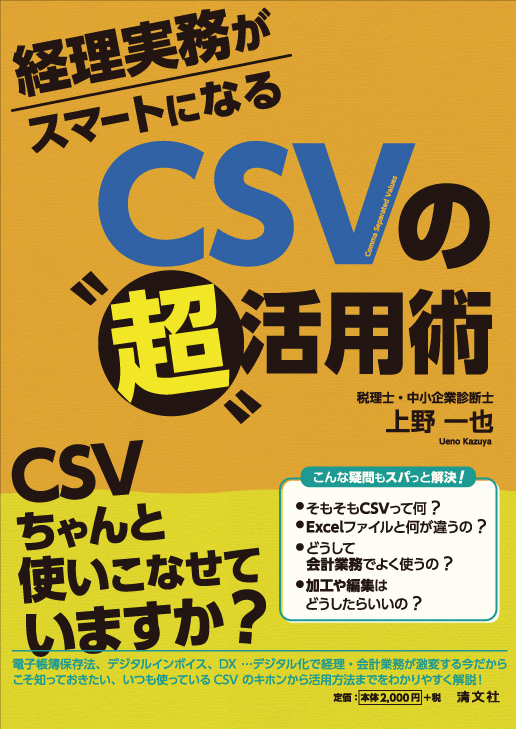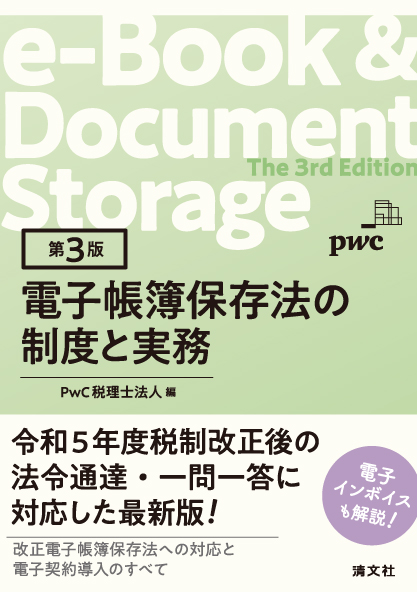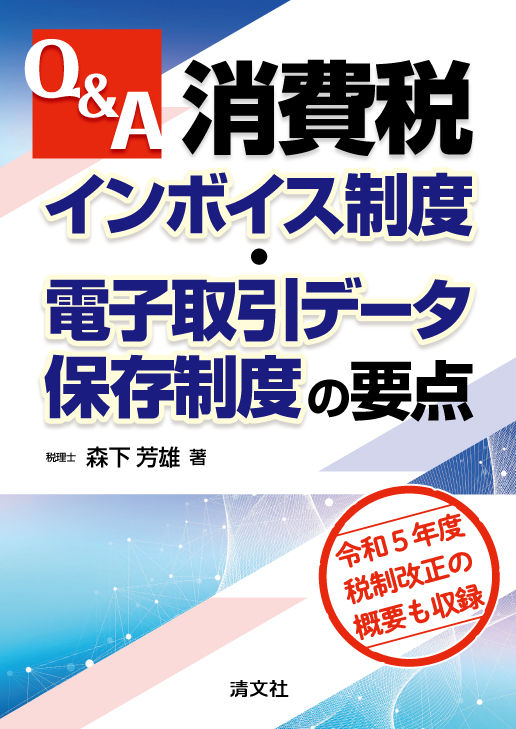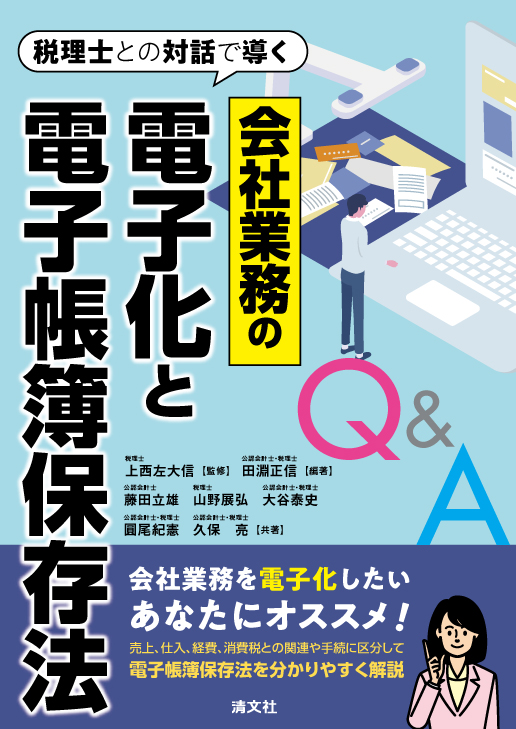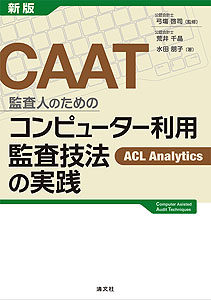〈IT会計士が教える〉
『情報システム』導入のヒント (!)
【第1回】
「自社に最適な『会計システム』を選定する手順」
公認会計士 坂尾 栄治
-連載に当たって-
この連載は、「日本IT会計士連盟」に所属する者が有志により、企業がさまざまな形態の『情報システム』を導入する際に遭遇し抱え込んでしまう“ありがちな疑問・問題”について取り上げ、その解決の糸口を示すことで、企業がスムーズにそのシステムを導入・運営できるよう手助けすることを目的とする。
筆者は職業柄、企業の成長や企業統合を機に、会計システムの更改を検討する企業のお手伝いをすることが多い。
では、それらの企業が、自社の業務に合った会計システムを選定するために、どのようなことを行っているのであろうか。
▼自社が『やりたいこと』を知る▼
システムを選定するためには、「そのシステムで何ができるのか」を知る必要がある。
しかしそれ以前に、「そのシステムに何をさせたいのか」を知ることのほうが、より重要である。
これには「どのような帳票が出力できる必要があるのか」とか、「どのようなシステムと連携させたいのか」等々、さまざまな要求がある。
乱暴な言い方をすれば、「機能が多いシステム=良いシステム」ということになるが、一般的には機能が多い分、価格も高くなる。このため、たとえ機能が多くても、その中の一部しか使わないのであれば、必要最低限の機能が備えられているシステムを選択したほうが経済的である。
また、機能が多いからといって自社の使いたい機能がより多く満たされているとも言いきれず、やはり自社に合ったシステムを選定するべきであり、そのための手続きを行うことが望ましいのは、お分かりいただけると思う。
▼「やりたいこと」⇒「要求定義書」として文書化▼
「要求定義」とは、利用者が「システムに何を求めているのか」を明らかにすることである。
つまり、その会計システムで何がしたいのか、何ができないと困るのかといった、システムに求める機能や満たすべき性能を定義することである。
通常は、これらの要求を「要求定義書」として文書化する。
「要求定義書」は、この後に続く会計システムの選定作業のために作成する「RFI」や「RFP」、あるいはその後の「要件定義書」のための基礎資料として使われるのが一般的である。
会計システムに限らず、一般にシステムを選定する上で、事前に要求定義を行い、自社が何をしたいのかを明らかにすることは、自社の業務に合ったシステムを選定する上で大変重要なプロセスである。
▼ベンダーは絞り込め▼
要求定義が終わると、いよいよシステムを選定することになるのだが、システムの開発会社(システムベンダー、以下「ベンダー」)へ、やみくもに声をかけデモンストレーションをしてもらうのは効率的ではない。
会計システムのベンダーは非常にたくさんあるため、それらのベンダーに片っ端からデモンストレーションや提案をしてもらっていたら、システムの選定だけで何ヶ月もかかってしまうし、あまりに多数のシステムを比較すると、選定する側が混乱してしまい、正しい評価ができなくなってしまう。
そしてそれ以前に、自社の要求に合っていないシステムのデモンストレーションに時間を割くのは無駄である。
そのため、デモンストレーションや提案を受ける前に、ベンダーを絞り込む作業を行うのが一般的である。
では、どのようにベンダーを絞り込んでいけばよいのであろうか。
▼「RFI」を使って選定の第一関門に▼
ベンダーの絞込みに加え、有意義なデモンストレーションや提案を受けるための手続きとして、「RFI」や「RFP」を作成し、ベンダーに提示することが多い。
「RFI」とは“Request for Information”(情報提供依頼書)の略で、ベンダーに情報提供を依頼する文書である。「RFI」は後述する「RFP」に先立ってベンダー提示されることがあるが、「RFI」の提示は必ずしも必須の手続きではない。
企業側が、発注を検討しているシステムについての十分な知見や情報を持っていない場合や、取引したことのないベンダーに発注する場合、あるいはシステムの構成や機能などがベンダーのホームページ等の公開情報からは正しく把握できない場合などに発行される。
「RFI」への回答により、必要な情報を入手するのは当然であるが、加えて、おおよそのシステムの適合度やベンダーの力量を判断し、ベンダーを絞り込むための第1のゲートとする場合も多い。
ただし、会計システムの選定に際して、必ずしも「RFI」が作成されるわけではない。「RFI」を作らない場合でも、「要求定義書」にまとめた要求事項と、会計システムのおおよその適合度については、ベンダーのホームページから情報を取ることができるし、それ以外にもインターネットやIT関係の雑誌、データショウなどで情報を収集し判断することができる。
このような情報を元に、選定対象となるベンダーを数社(一般的には3社から5社程度)に絞り込むことができる。
▼「RFP」を使ってさらなる絞込みを▼
これに対して「RFP」は、会計システムの選定に際し、筆者の知る限りほとんどのケースで作成されている(とはいっても一定規模以上の企業に限定された話であるが)。
「RFP」とは“Request for Proposal”(提案依頼書)の略で、ベンダーに提案を依頼する文書である。
「RFP」は上述した「要求定義書」や「RFI」を元に作成される場合が多く、会計システムに求められる機能やハードウエア、ソフトウエアの概要、依頼事項、保証要件、契約事項などを記述する。
とはいいながらも、実際には各社各様で、パワーポイントで数十枚に及ぶものもあればワードで3枚程度しか記載していないものもある。「RFP」の記載内容が多すぎるとベンダーが全体を把握しきれず、適切な提案をしてくれないことが多くなるが、逆に少なすぎると、本来の要求事項が提案に十分には盛り込まれず、選定後に「こんなはずじゃなかった・・・」といった結果になる場合も多い。
このため、「RFP」は適度なボリュームにすることが重要であり、何より各要求事項の重要度を、この要求は「必須」で、この要求は「nice to have(てきれば尚可)」、といったように判別できるようにしておくのがよいだろう。
「RFP」の発行は、3~5社のベンダーに対して行うのが一般的と思われるが、より多くのベンダーに「RFP」を提示し、デモンストレーションや提案の前に、提案書の提示を求め、その提案書で書類審査をし、デモンストレーションや提案を実施するベンダーを絞り込むといった作業を行う企業もある。
▼提案・デモに対する評価基準を決めておく▼
「RFP」を受けて、ベンダーはデモンストレーションや提案を行うことになる。企業側は、ベンダーのデモンストレーションや提案について評価を行い、会計システムを決定することになる。
ここで注意するのは、あらかじめ『評価基準』をちゃんと決めておく必要があるということである(「RFP」作成時には評価基準を決めてあるのが理想的である)。
この評価基準を決めずにデモンストレーションや提案を受けると、デモンストレーションや提案から受けた印象に流されてしまい、適切な評価ができなくなる可能性が高い。つまり、後から提案したベンダーの方が印象が良くなったり、提案の上手いベンダーの評価が高くなったりと、「RFP」の記載項目に対する対応レベルとは異なるところで評価してしまう場合がある。
▼最適な『会計システム』の選定は時間をかけて▼
このような手続きを経ることで、ようやく自社の業務に合った会計システムを選定することができる。
この手続きには、要求定義の深さや範囲にもよるが、数ヶ月から半年くらいかかるのが一般的である。自社の業務に合った会計システムを選ぶのは、結構大変な作業なのである。
しかし、高いお金をかけて導入するものでもあるし、また導入してから数年、長いときは十数年使い続けるものでもあるので、選定段階における労力については、致し方ないのかもしれない。
(了)
「〈IT会計士が教える〉『情報システム』導入のヒント(!)」は、各回の担当筆者により、毎月第3週に掲載します。