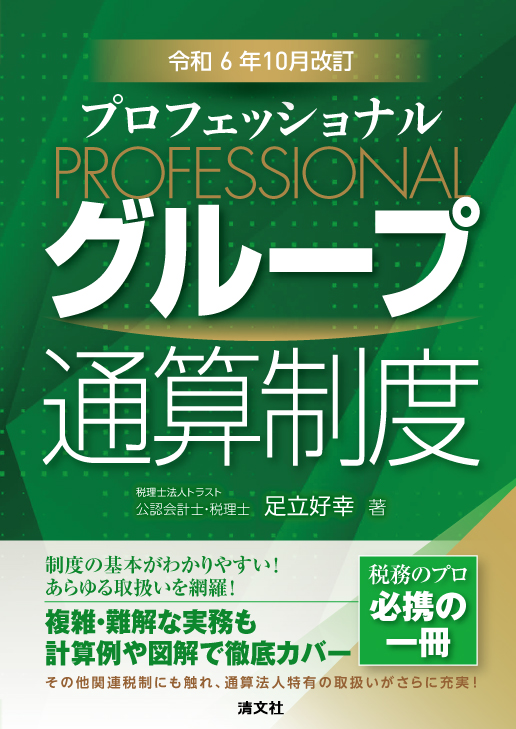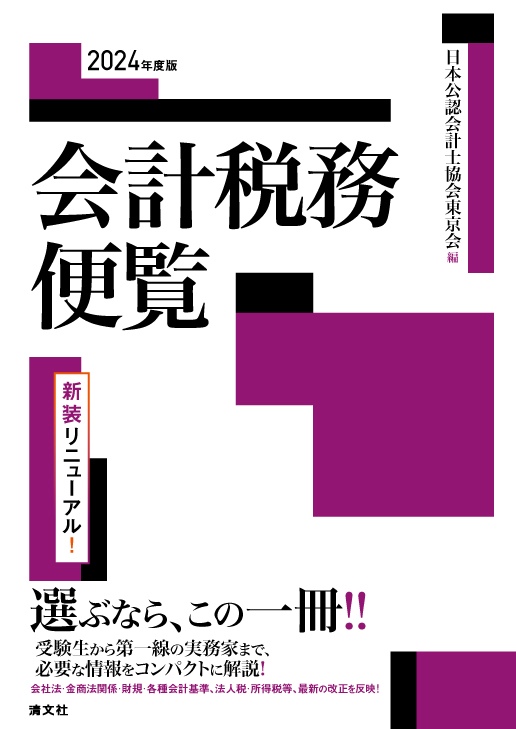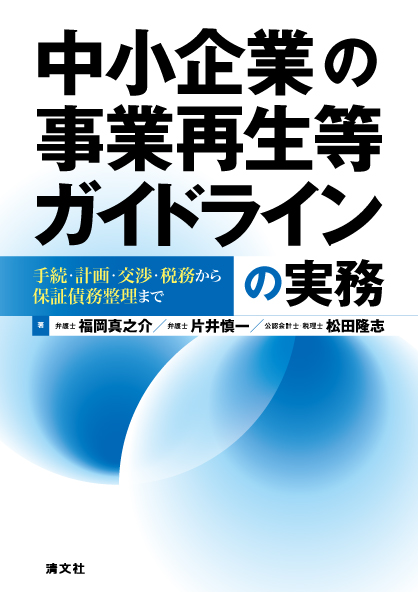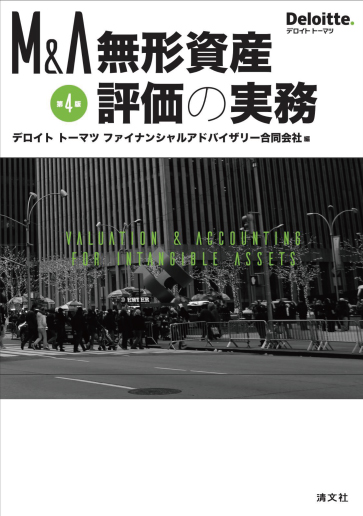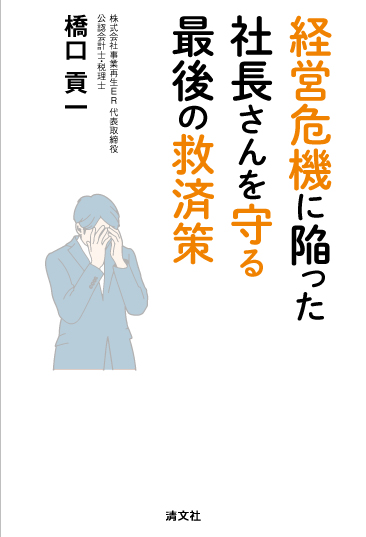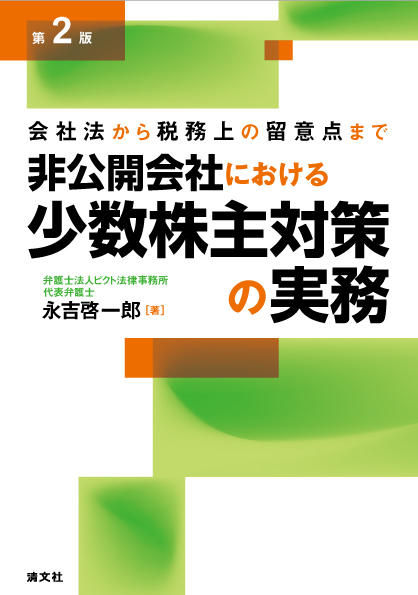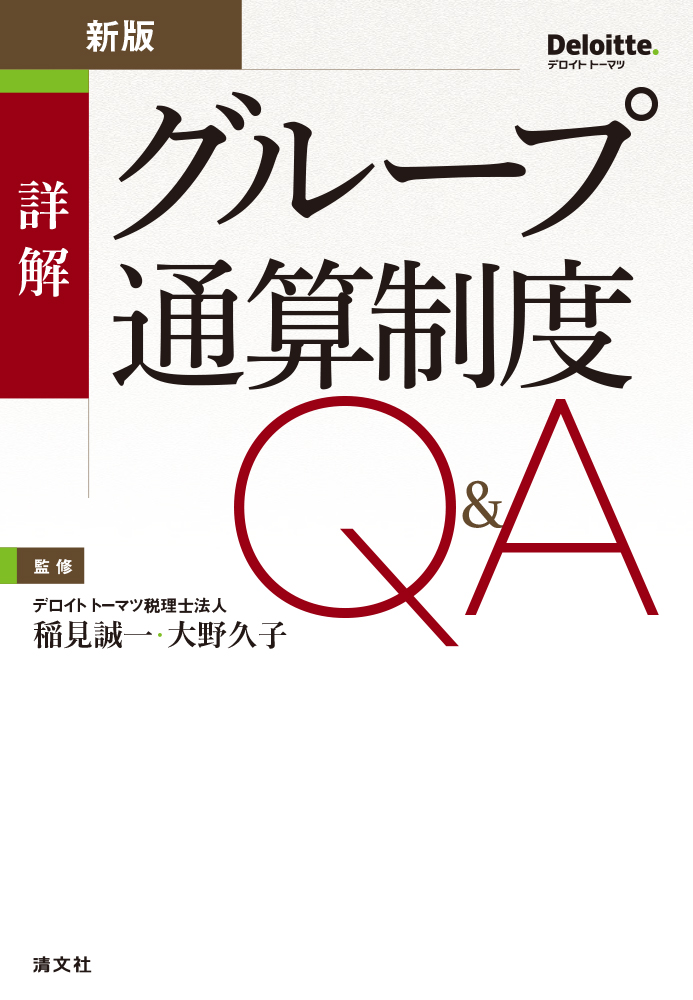〔中小企業のM&Aの成否を決める〕
対象企業の見方・見られ方
【第3回】
「買い手が好意を抱く「売り手の外見」」
~その2:経営者~
公認会計士・税理士
荻窪 輝明
《今回の対象者別ポイント》
買い手企業
⇒買い手の売り手経営者に対する見方や考え方を知る。
売り手企業
⇒売り手経営者が買い手からどう見られるかを知る。
支援機関(第三者)
⇒買い手の売り手経営者に対する見方を知り支援に活かす。
その他の対象者
⇒買い手側の立場からM&A対象企業の見方を知る。
1 中小企業の経営者は企業そのもの
【第2回】で解説した「企業ウェブサイト・SNS」は、対象企業の情報を効率的に収集する手段としては有効です。とはいえM&Aは、これから長い間パートナーとして互いに認めあえる、納得のいく相手を探すものです。おのずとプロフィールや肩書以上に企業そのものが重要になります。その最たるものが「経営者」です。
この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員登録およびログインが必要です。
すでに会員登録をされている方は、下記ボタンからログインのうえ、ご覧ください。
Profession Journalのすべての記事をご覧いただくには、「プレミアム会員(有料)」へのご登録が必要となります。
なお、『速報解説』については「一般会員(無料)」へのご登録でも、ご覧いただけます。
※他にもWebセミナー受け放題のスーパープレミアム会員などがございます。
会員登録がお済みでない方は、下記会員登録のボタンより、ご登録のお手続きをお願いいたします。