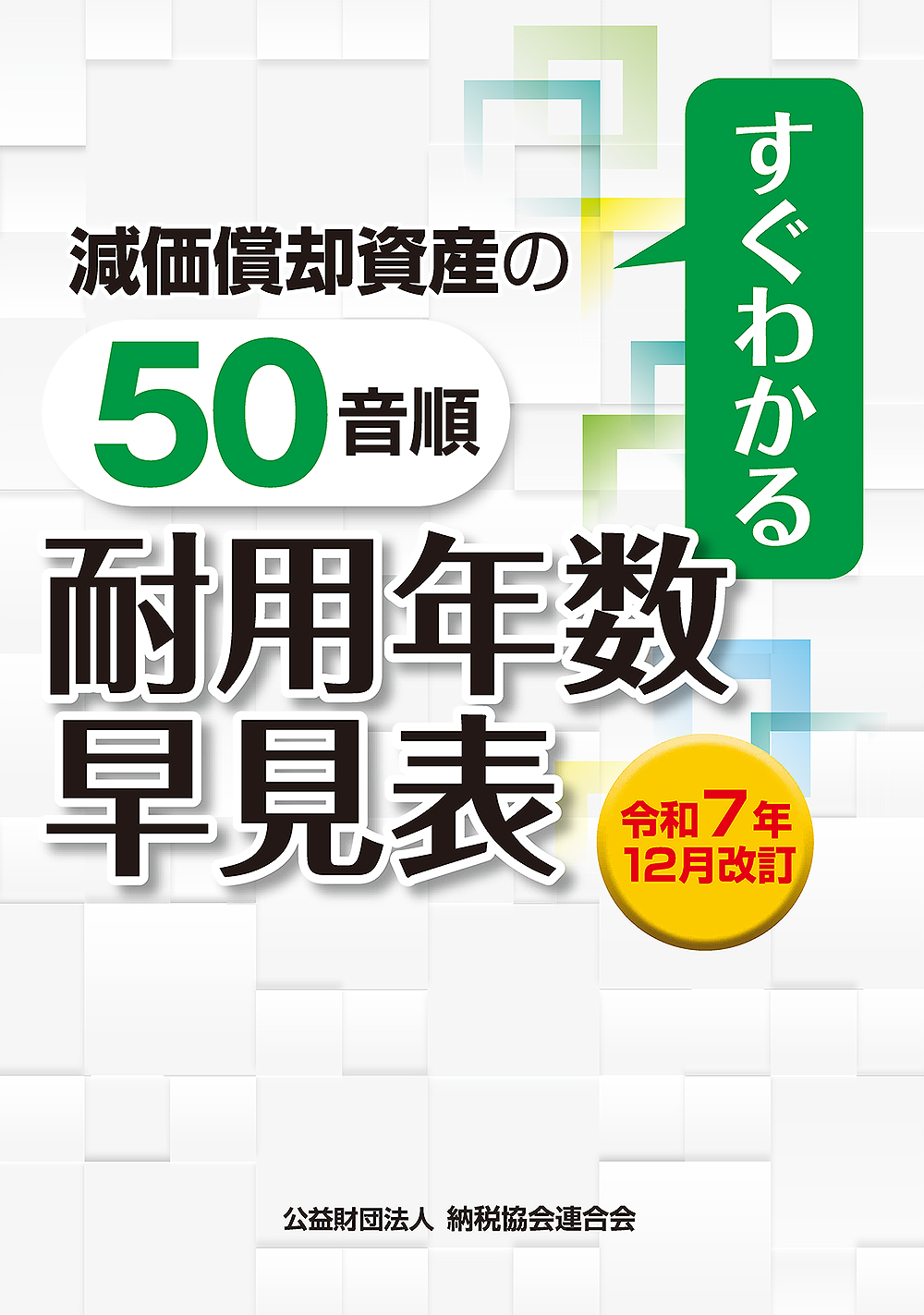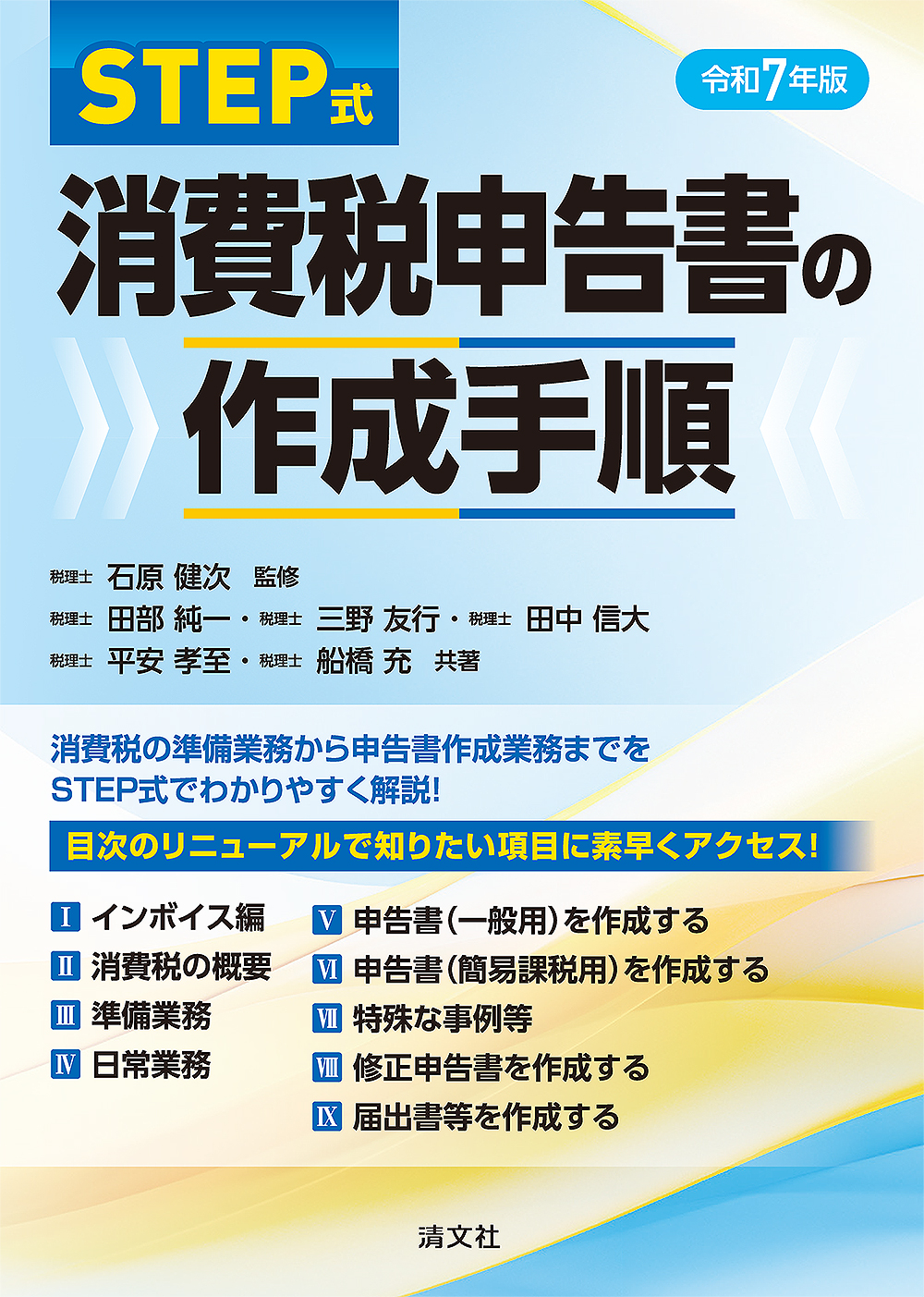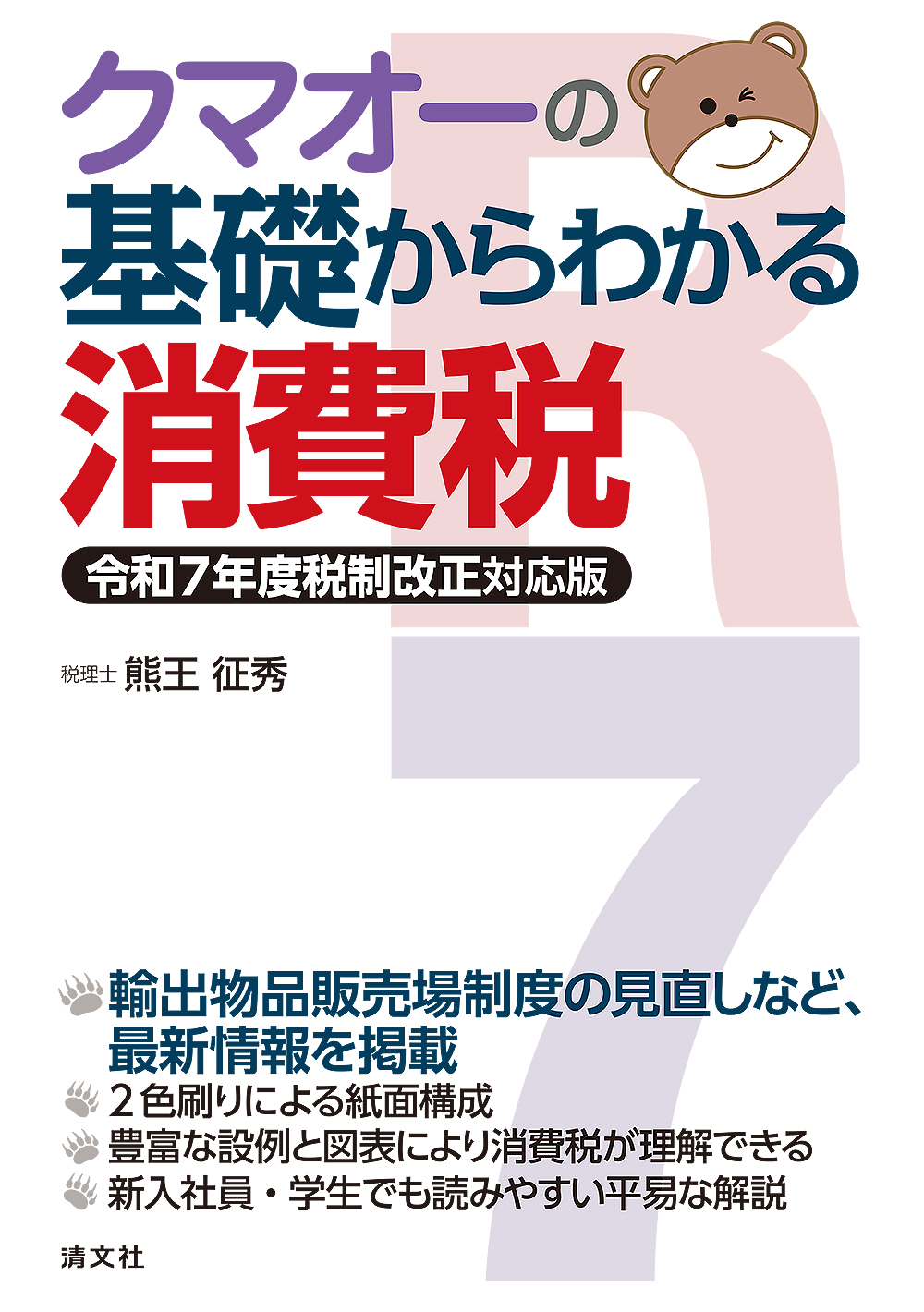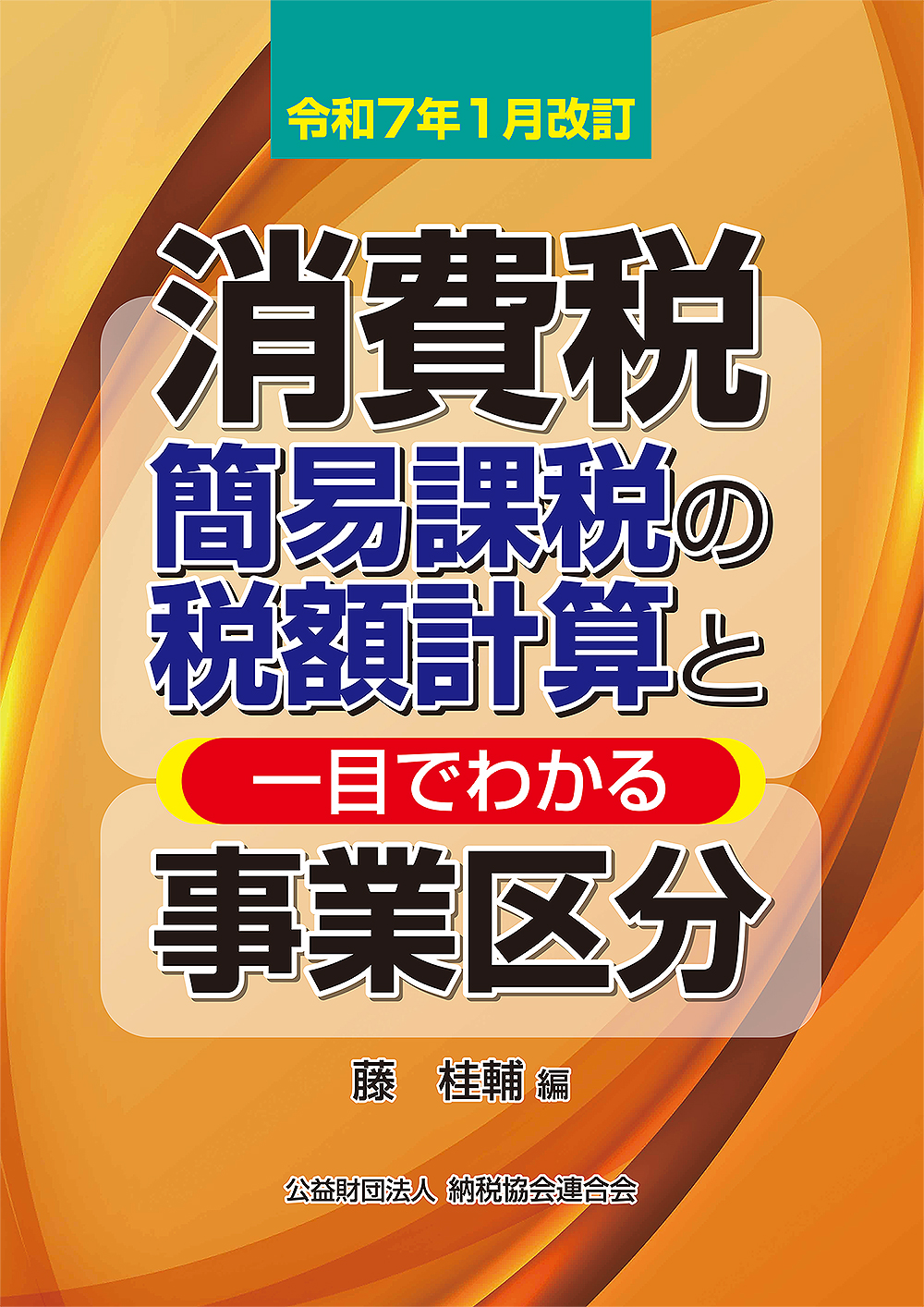固定資産をめぐる判例・裁決例概説
【第47回】
「検収事業年度の前事業年度において設置された機械装置を使用して収益を上げたとしても、まだ取得していないことから減価償却費等の損金算入が認められなかった事例」
税理士 菅野 真美
▷固定資産の減価償却と「取得日」「事業供用日」
減価償却は、時の経過や使用により価値の減少する資産については、その資産について使用可能な期間を通じて、一定の方法に基づいて費用化することであるが、これは企業会計において「適正な費用配分を行なうことによって、毎期の損益計算を正確ならしめること」が求められていることによる(「企業会計原則と関係諸法令との調整に関する連続意見書」「第三 有形固定資産の減価償却について」「第一 企業会計原則と減価償却」)。
税法も企業会計の考え方を原則的には踏襲しているが、課税の公平を実現するために減価償却資産の耐用年数等に関する省令において、必要経費や損金に算入することが認められる金額の計算の基となる耐用年数が定められている。
減価償却資産を取得した場合、減価償却は事業の用に供した日からとされている(法人税法施行令13条)。ここで「事業の用に供した日」とは、一般的にはその減価償却資産の持つ属性に従って本来の目的のために使用を開始するに至った日をいうことから、例えば、機械等を購入した場合は、機械を工場内に搬入しただけでは事業の用に供したとはいえず、その機械を据え付け、試運転を完了し、製品等の生産を開始した日が「事業の用に供した日」とされている。
では「取得の日」はいつかということであるが、所得税基本通達33-9(資産の取得の日)において、次のように定められている。
◆所得税基本通達33-9(資産の取得の日)
法第33条第3項第1号に規定する取得の日は、次による。
(1) 他から取得した資産については、36-12に準じて判定した日とする。
(2) 自ら建設、製作又は製造(以下この項において「建設等」という。)をした資産については、当該建設等が完了した日とする。
(3) 他に請け負わせて建設等をした資産については、当該資産の引渡しを受けた日とする。
法人税も原則的には所得税と同じ考え方によるものと考えられる。一般的には、減価償却資産の「取得の日」以後に「事業の用に供した日」がある。
では、「事業の用に供した日」が「取得の日」より前であった場合、事業の用に供した日から減価償却をすることができるか。今回はこの件で争われた事例を検討する。
この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員登録およびログインが必要です。
すでに会員登録をされている方は、下記ボタンからログインのうえ、ご覧ください。
Profession Journalのすべての記事をご覧いただくには、「プレミアム会員(有料)」へのご登録が必要となります。
なお、『速報解説』については「一般会員(無料)」へのご登録でも、ご覧いただけます。
※他にもWebセミナー受け放題のスーパープレミアム会員などがございます。
会員登録がお済みでない方は、下記会員登録のボタンより、ご登録のお手続きをお願いいたします。