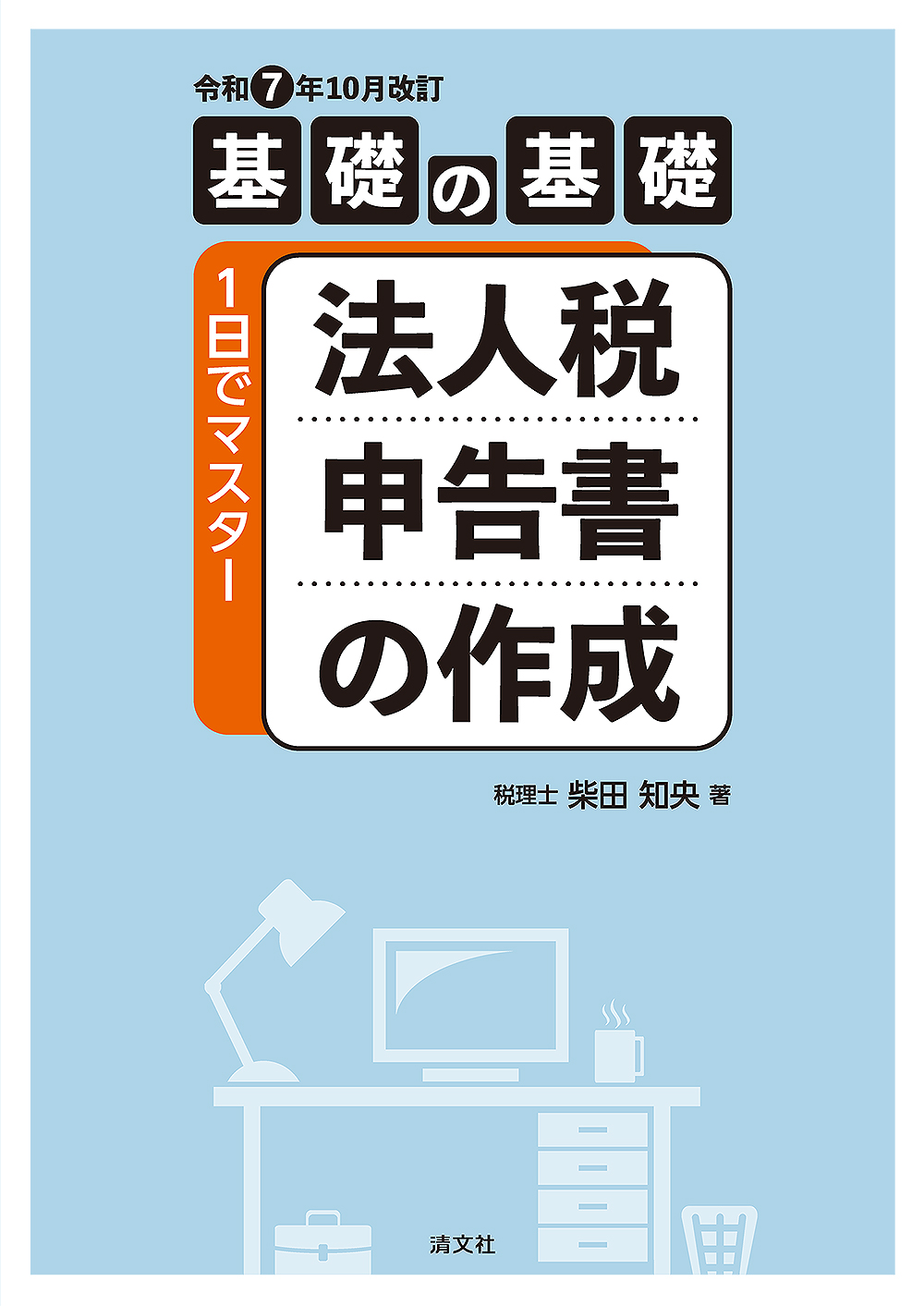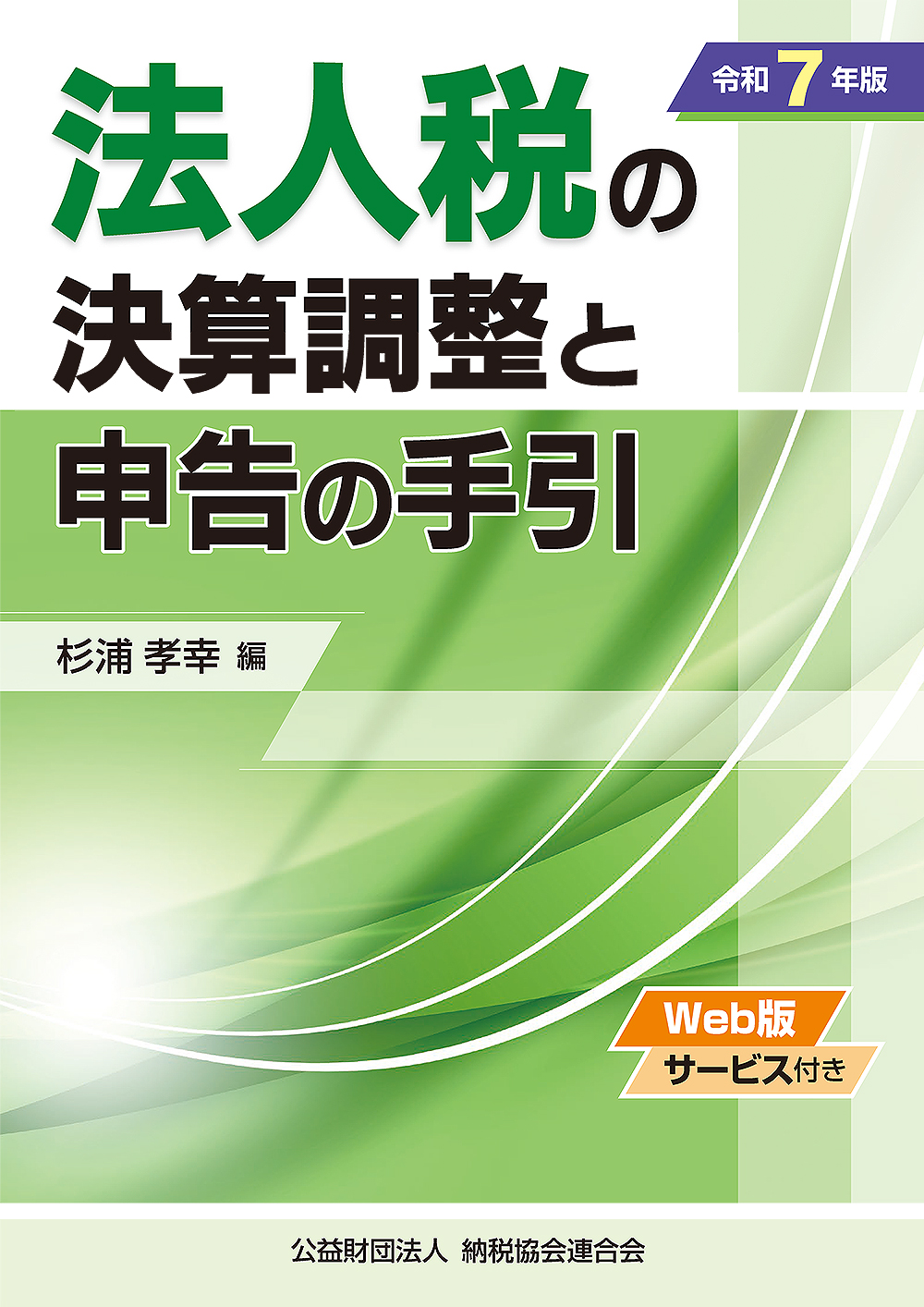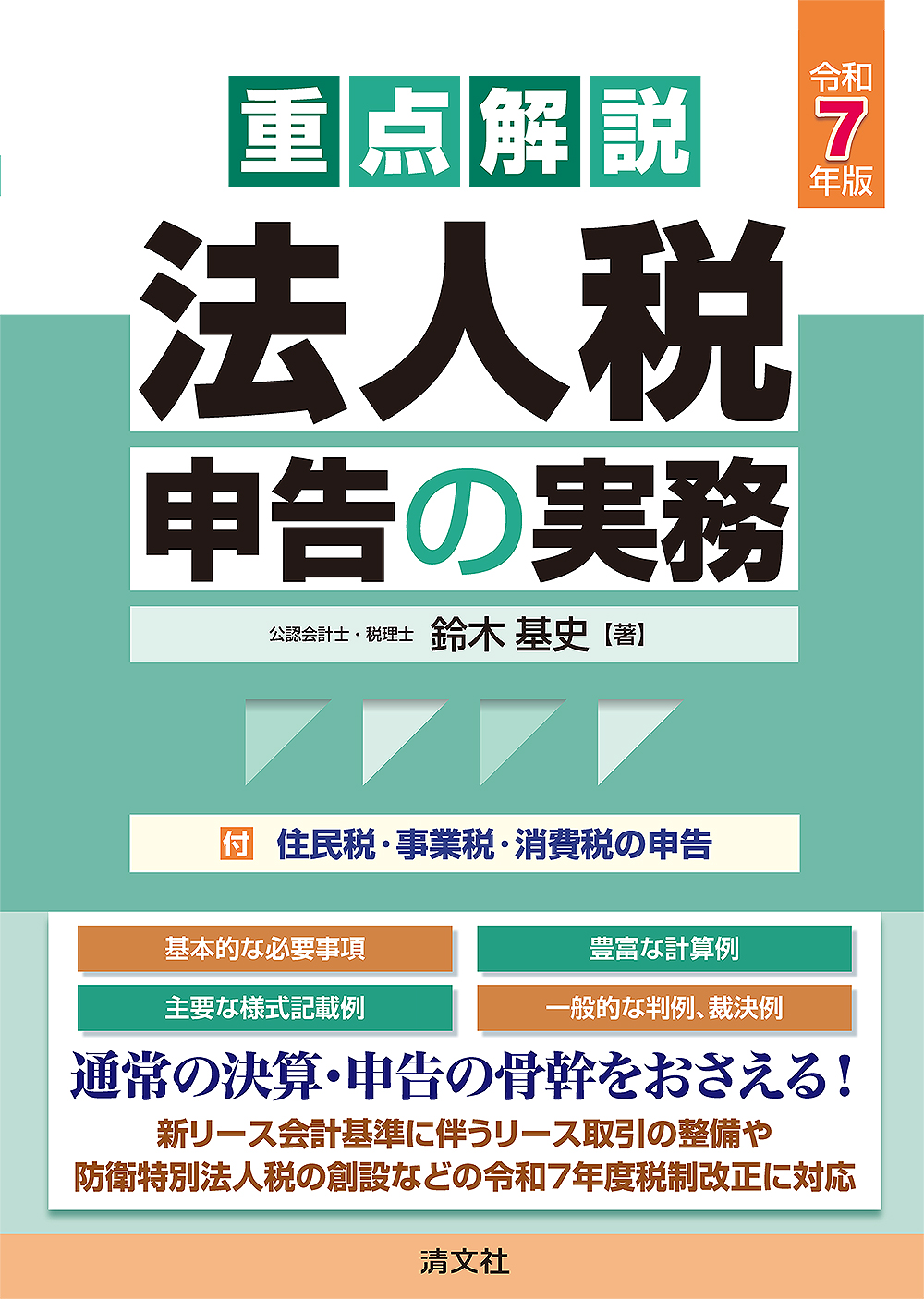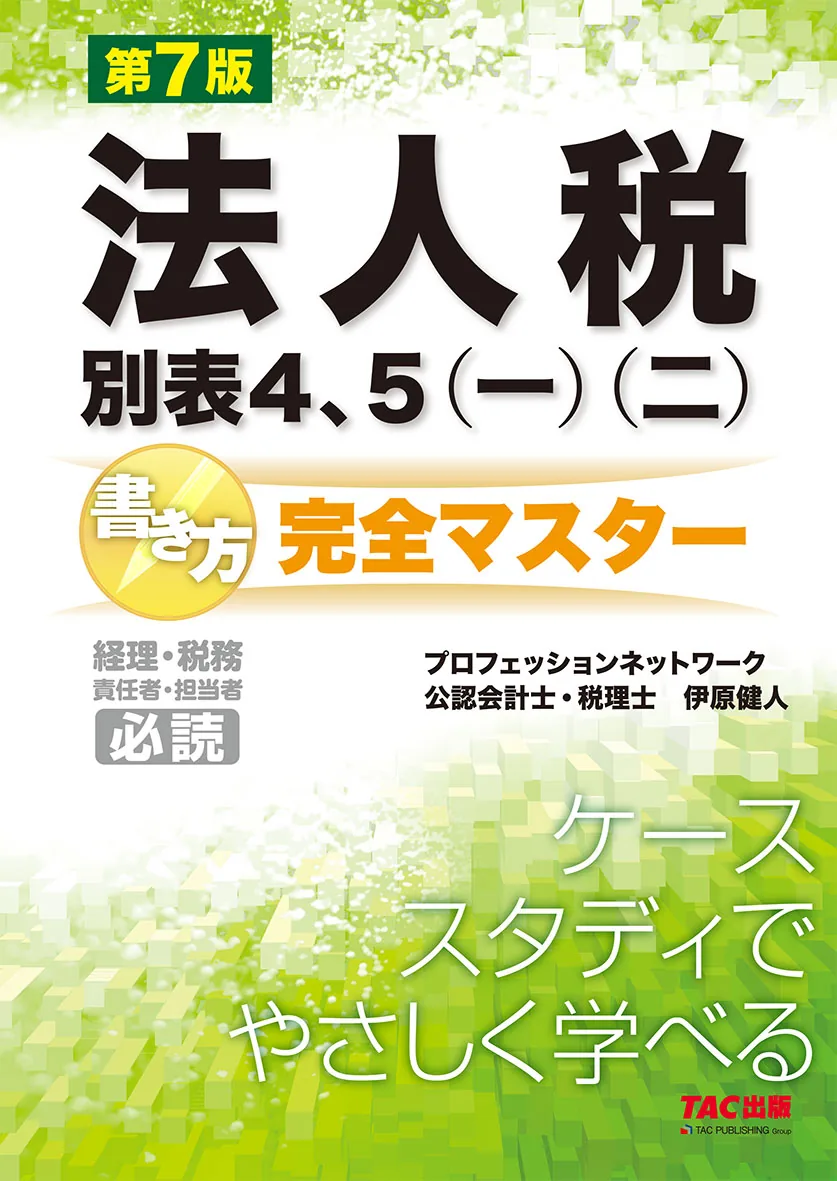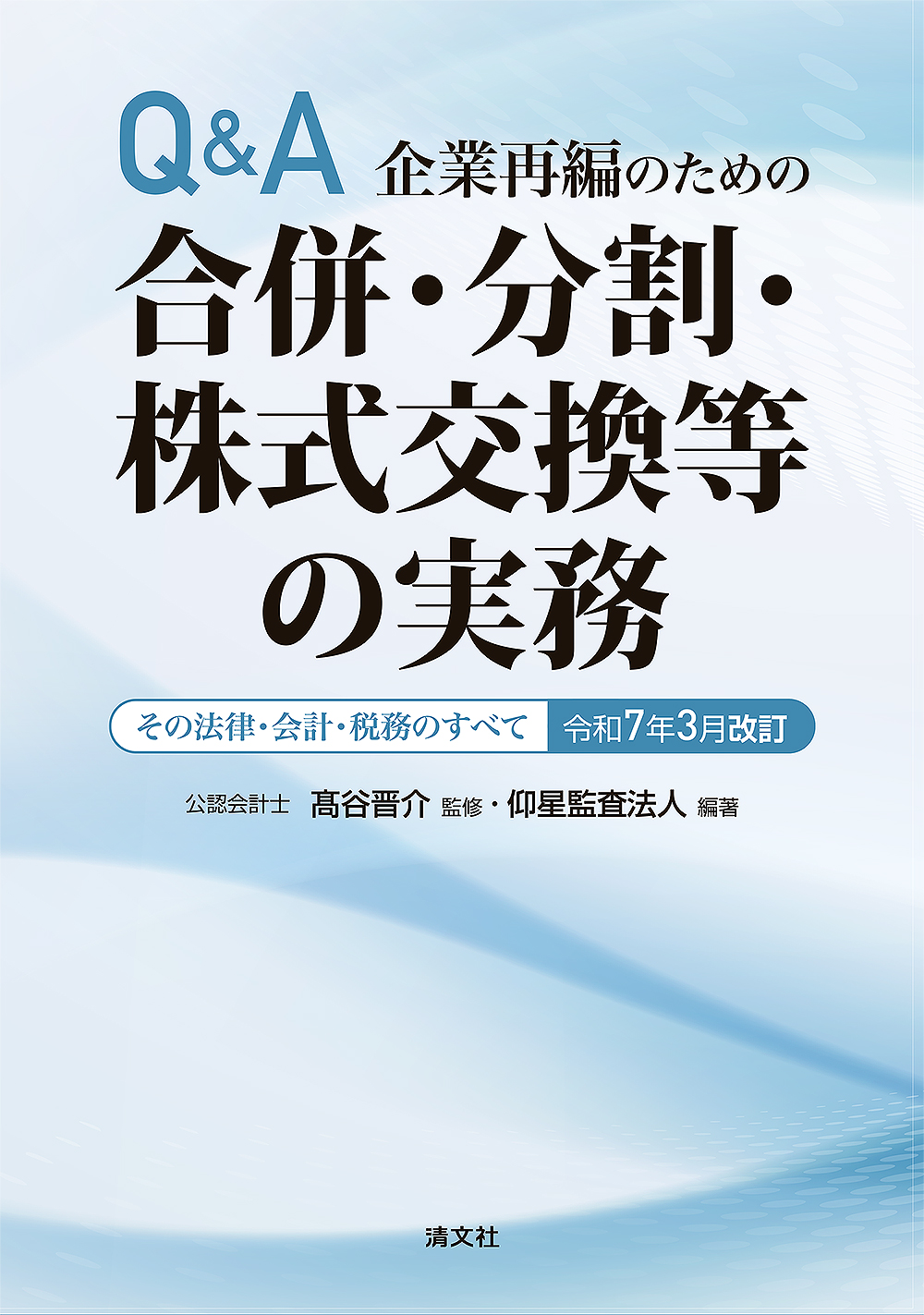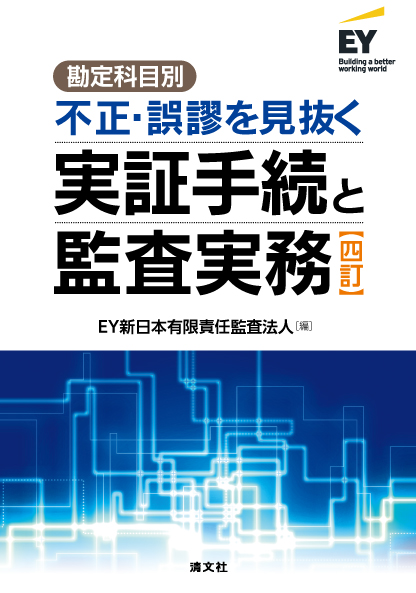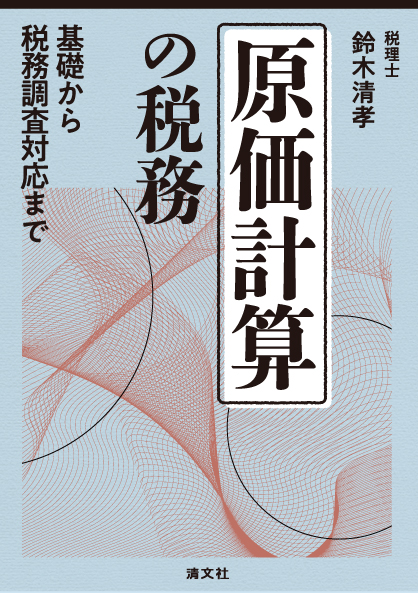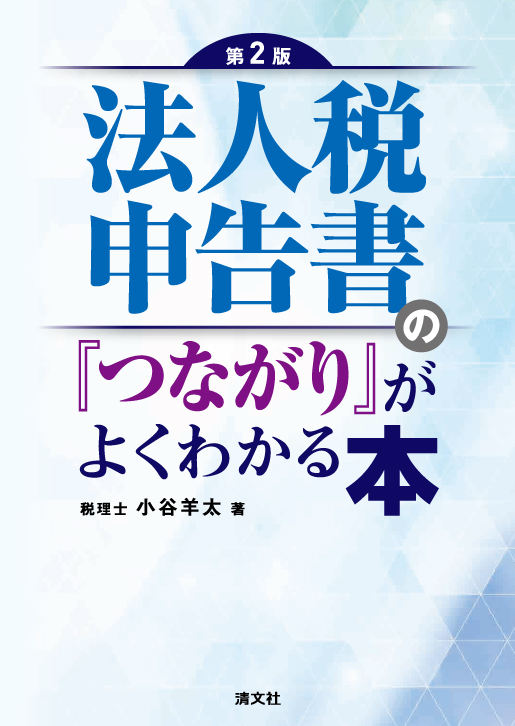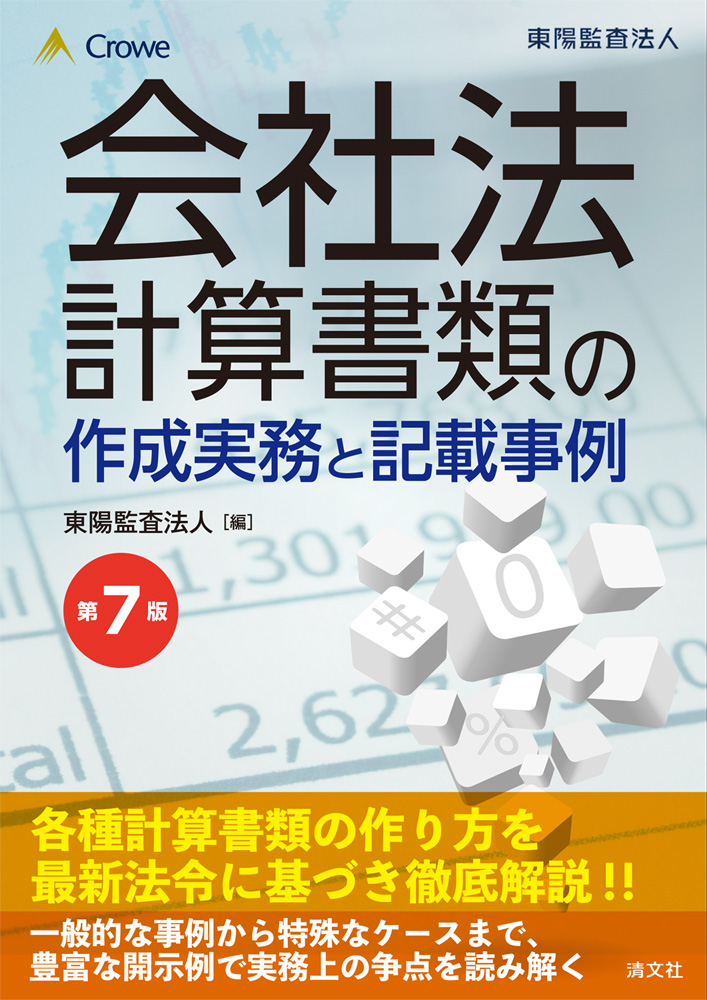XI 金融庁の平成29年度有価証券報告書レビューを踏まえた留意事項
2018年3月23日に金融庁より「平成29年度有価証券報告書レビューの審査結果及び審査結果を踏まえた留意すべき事項」が公表された。これは、平成29年度の有価証券報告書レビューに関して、2018年3月23日時点までの実施状況を踏まえ、複数の会社に共通して記載内容が不十分であると認められた事項に関し、記載に当たっての留意すべき点を取りまとめたものである。
「有価証券報告書の作成・提出に際しての留意すべき事項及び有価証券報告書レビューの実施について(平成30年度)」
レビュー結果の内容は、上場会社のみならず、非上場会社の2019年3月期決算においても参考となる箇所がある。
1 繰延税金資産の回収可能性
過去(3年)及び当期の事業年度において、課税所得が期末における将来減算一時差異を下回る年度があるにもかかわらず、(分類1)に該当すると判断している事例
《留意点》
企業を(分類1)に分類するためには、原則として、以下の要件をいずれも満たす必要がある(回収可能性指針17)。
① 過去(3年)及び当期のすべての事業年度において、期末における将来減算一時差異を十分に上回る課税所得が生じている。
② 当期末において、近い将来に経営環境に著しい変化が見込まれない。
過去(3年)及び当期の事業年度において、課税所得(臨時的な原因により生じたものを除く)が生じていない年度があるにもかかわらず、(分類2)に該当すると判断している事例
《留意点》
企業を(分類2)に分類するためには、原則として、以下の要件をいずれも満たす必要がある(回収可能性指針第19)。
① 過去(3年)及び当期のすべての事業年度において、臨時的な原因により生じたものを除いた課税所得が、期末における将来減算一時差異を下回るものの、安定的に生じている。
② 当期末において、近い将来に経営環境に著しい変化が見込まれない。
③ 過去(3年)及び当期のいずれの事業年度においても重要な税務上の欠損金が生じていない。
(分類3)に該当する企業において、退職給付引当金や建物の減価償却超過額に係る将来減算一時差異などの解消見込年度が長期にわたる将来減算一時差異について、スケジューリングが行われていない事例
《留意点》
(分類3)に該当する企業においては、退職給付引当金や建物の減価償却超過額に係る将来減算一時差異などの解消見込年度が長期にわたる将来減算一時差異について、将来の合理的な見積可能期間(おおむね5年)において当該将来減算一時差異のスケジューリングを行う必要がある(回収可能性指針35)。
繰延税金資産の計上額の見積りに用いた業績予測において、現時点において必ずしも合理性を欠くものではないが、将来の大幅な損益改善を見込んでおり、その達成状況によっては当該業績予測を適切に修正する必要があると考えられる事例
《留意点》
繰延税金資産の計上額を見積る場合に用いる将来の業績予測については、合理的な仮定に基づく必要がある(回収可能性指針32)。
2 企業結合及び事業分離等
企業結合が期首に完了したと仮定したときの連結損益計算書に及ぼす影響の概算額について、算定が困難と認められる特段の事情がないにもかかわらず省略しているなど、取得による企業結合が行われた場合の注記の一部を記載していない事例
《留意点》
企業結合等が行われた場合には、重要性が乏しい場合を除き、企業結合等の概要等を法令に従って具体的に記載する必要がある(連結財務諸表規則第15条の12、第15条の14、第15条の16、財務諸表等規則第8条の17、第8条の20、第8条の23等)。
取得の会計処理において、取得関連費用(外部のアドバイザー等に支払った特定の報酬・手数料等)を、発生した事業年度の費用として処理せず、取得原価に含めている事例
《留意点》
取得の会計処理においては、取得関連費用を発生した事業年度の費用として処理する必要がある(企業結合に関する会計基準26)。
連結キャッシュ・フロー計算書において、連結範囲の変更を伴わない子会社への投資に係る支出について、「財務活動によるキャッシュ・フロー」の区分に記載せず、「投資活動によるキャッシュ・フロー」の区分に記載している事例
《留意点》
連結範囲の変動を伴わない子会社株式等の取得等に係るキャッシュ・フローは、当該変動に関連するキャッシュ・フロー(法人税等に関するキャッシュ・フローを除く)を、非支配株主との取引として「財務活動によるキャッシュ・フロー」の区分に記載する必要がある(連結財務諸表等におけるキャッシュ・フロー計算書の作成に関する実務指針第9-2項)。
社内基準により重要性が乏しいとして企業結合等の注記が省略されている場合において、当該社内基準を翌期以降継続することの要否について検討が必要と考えられる事例
《留意点》
➤重要性の基準は継続的に適用することが必要である。
➤ただし、会社の状況により、変更が必要ないかどうかも検討する必要がある。