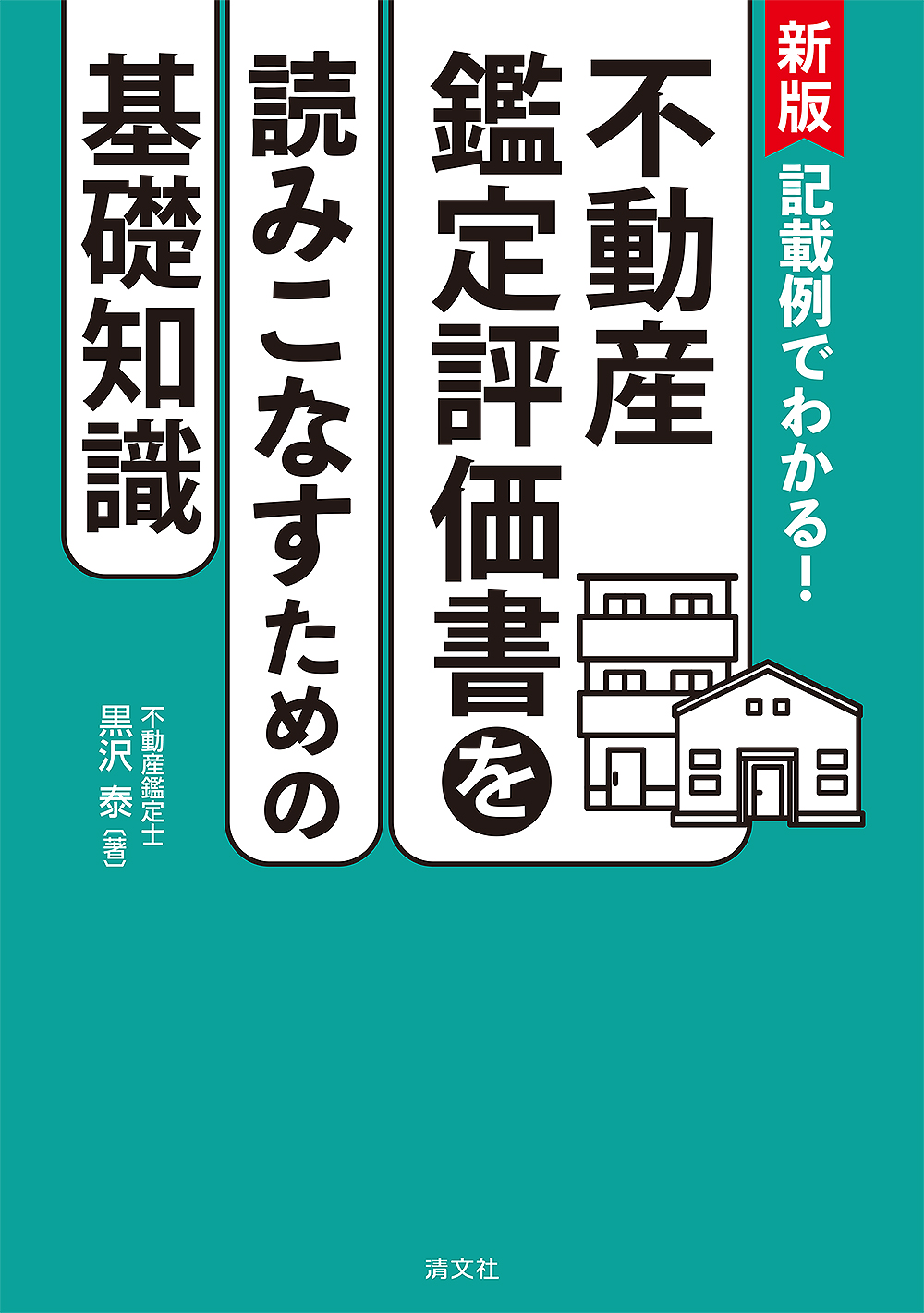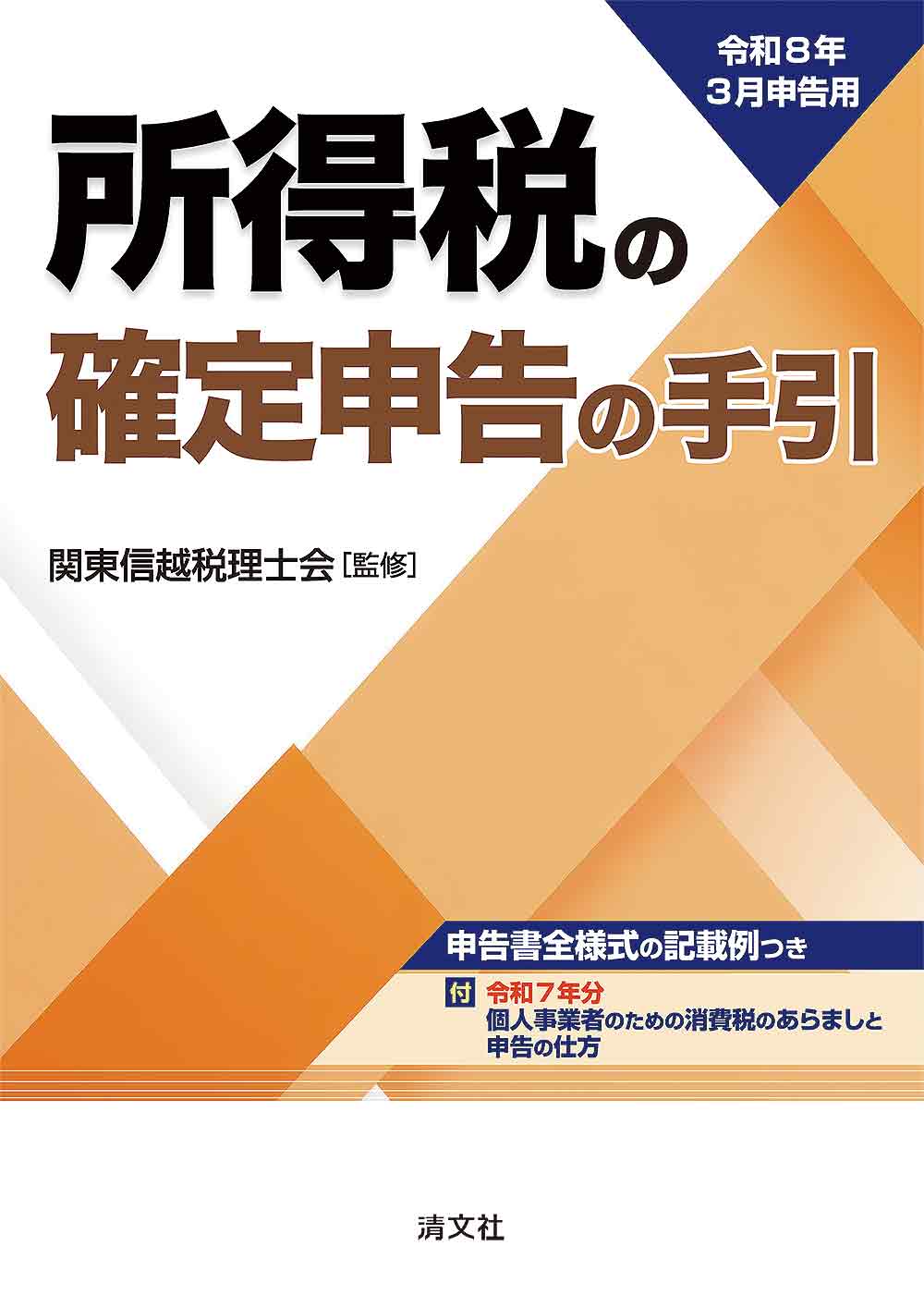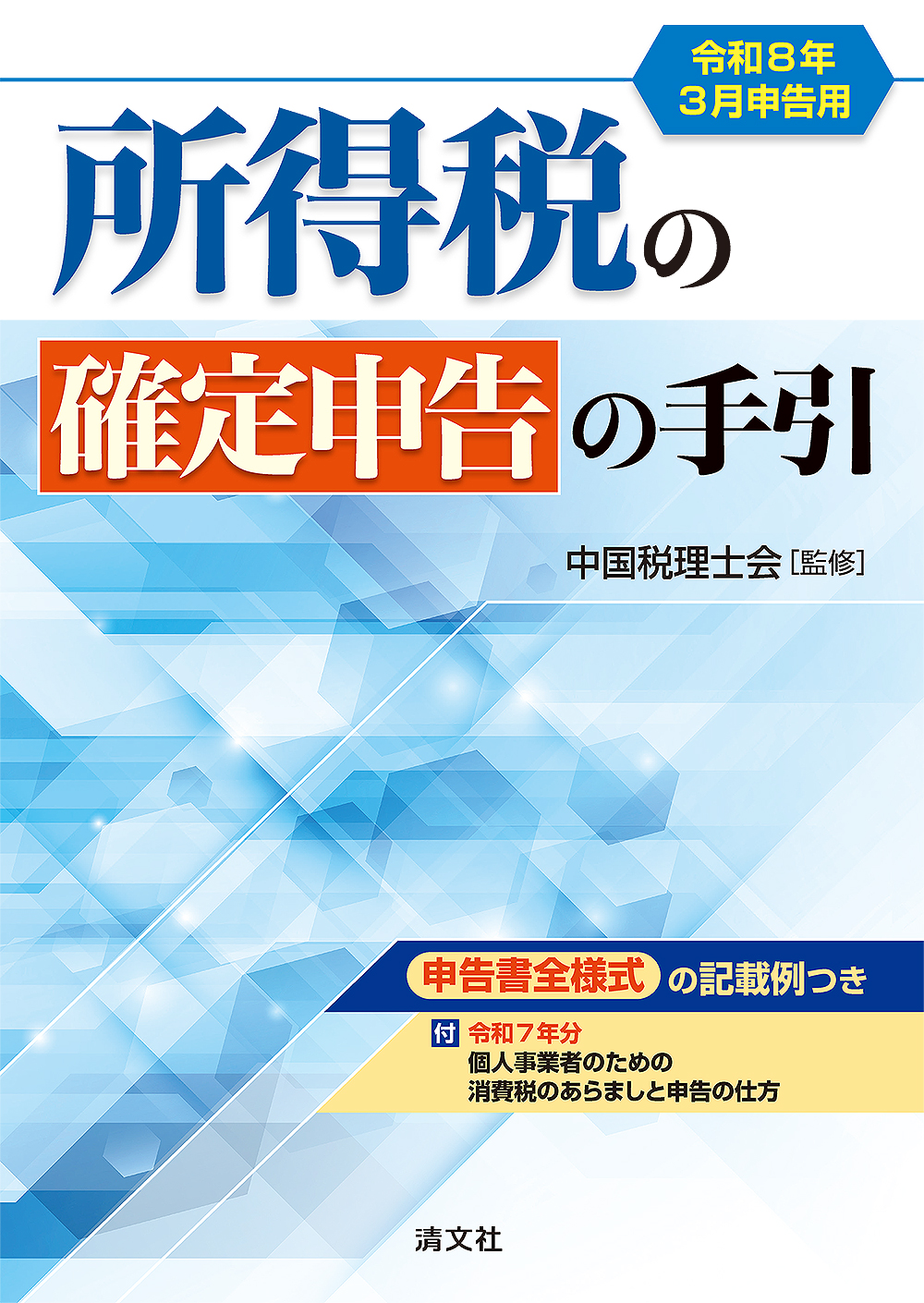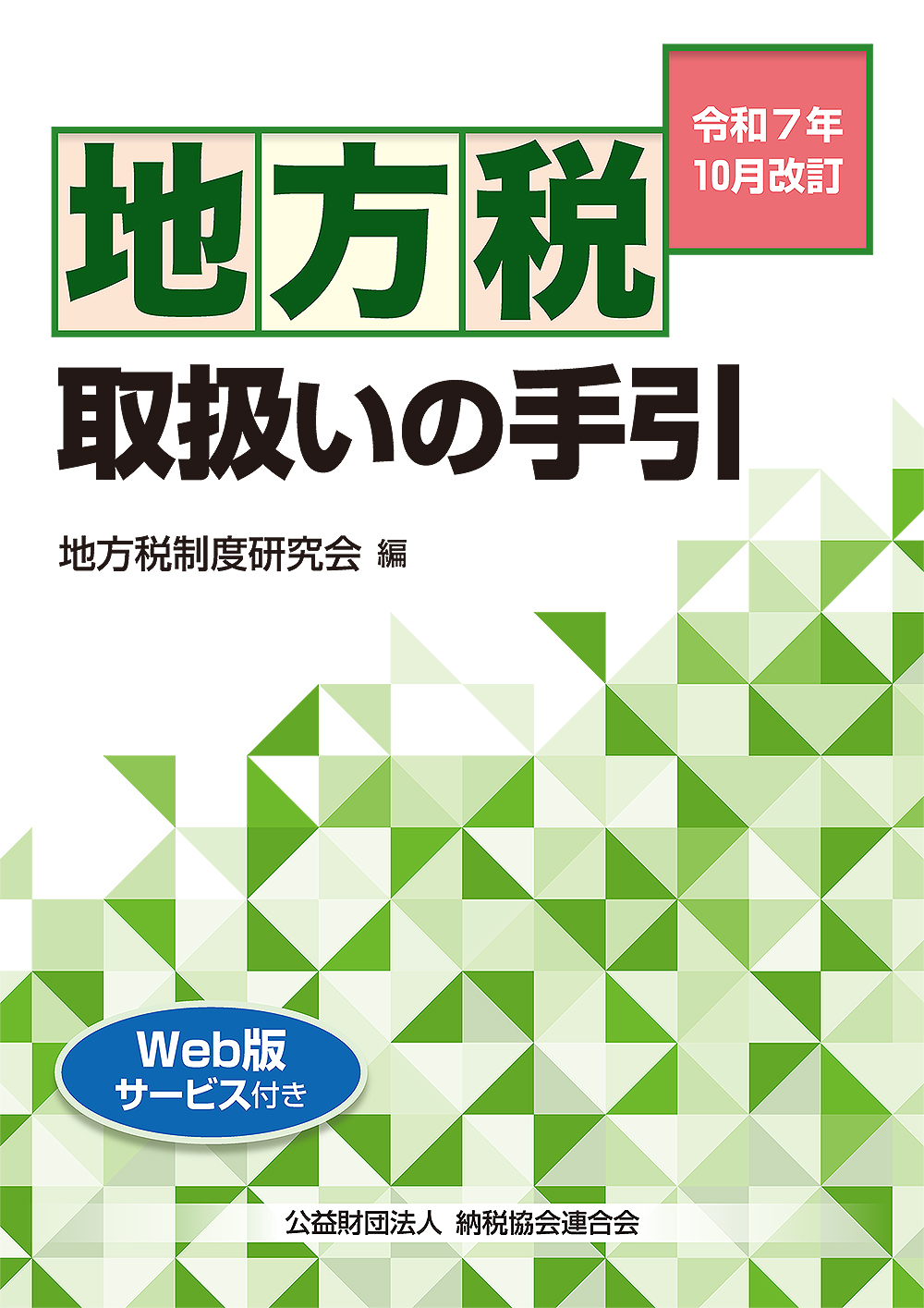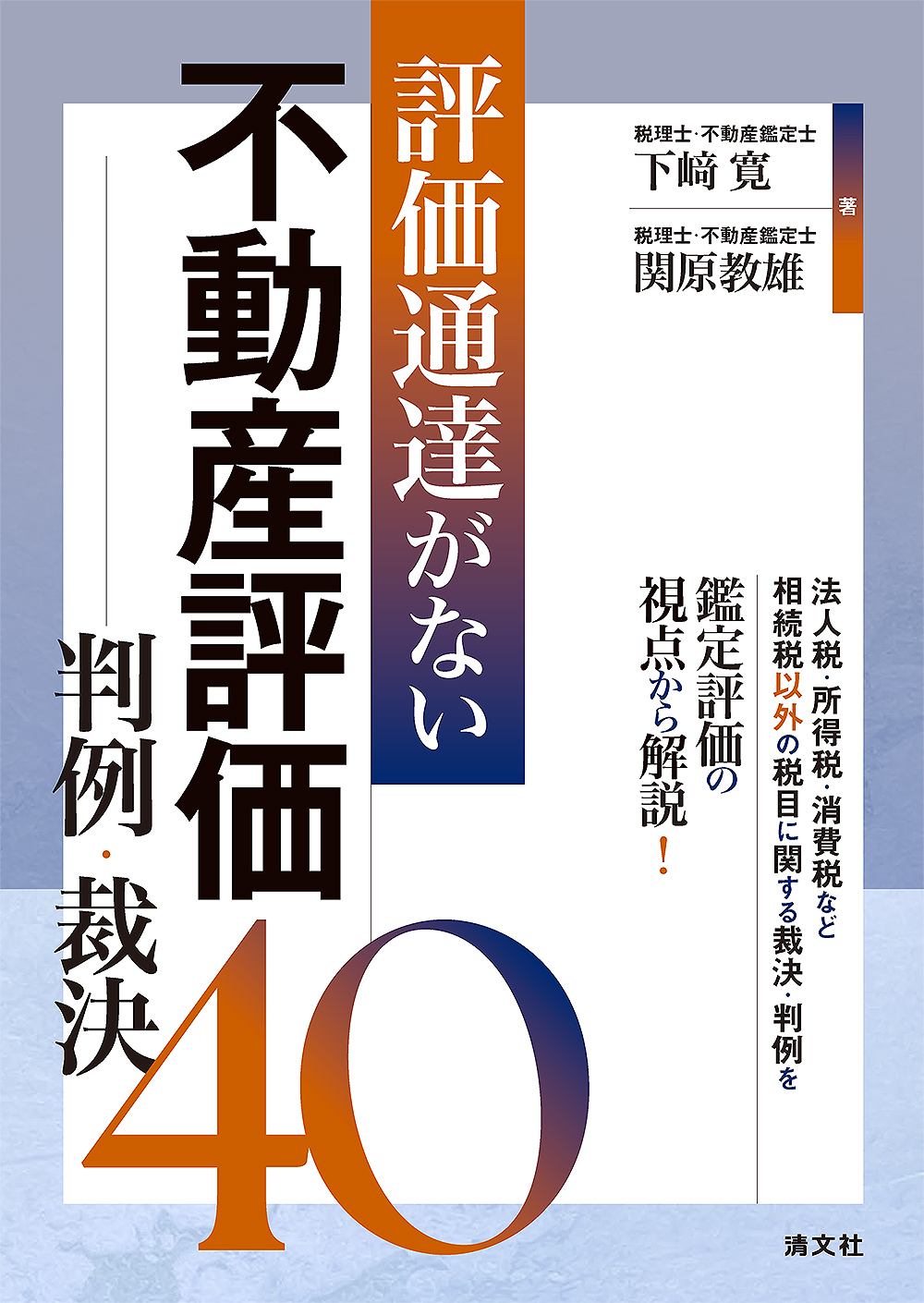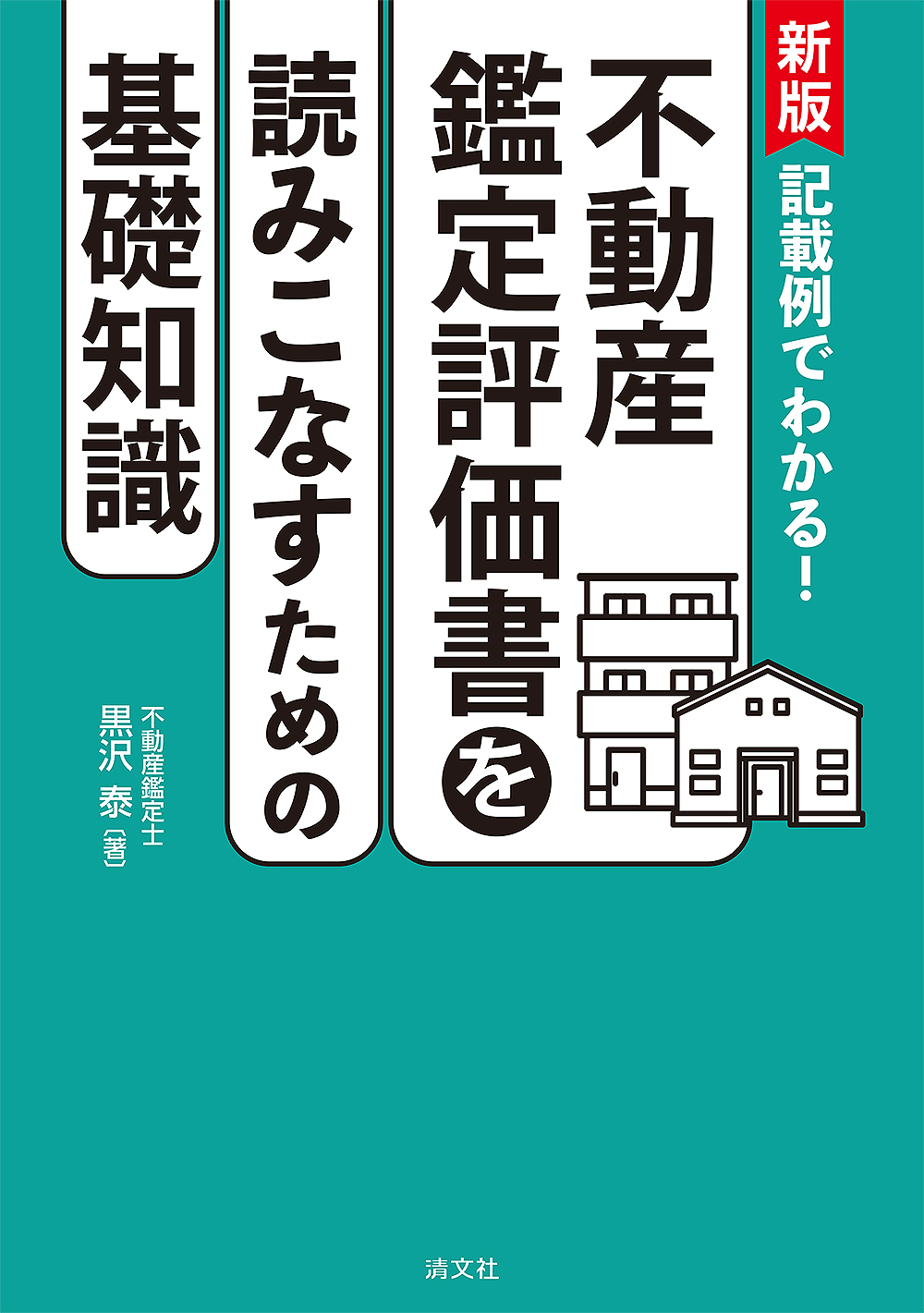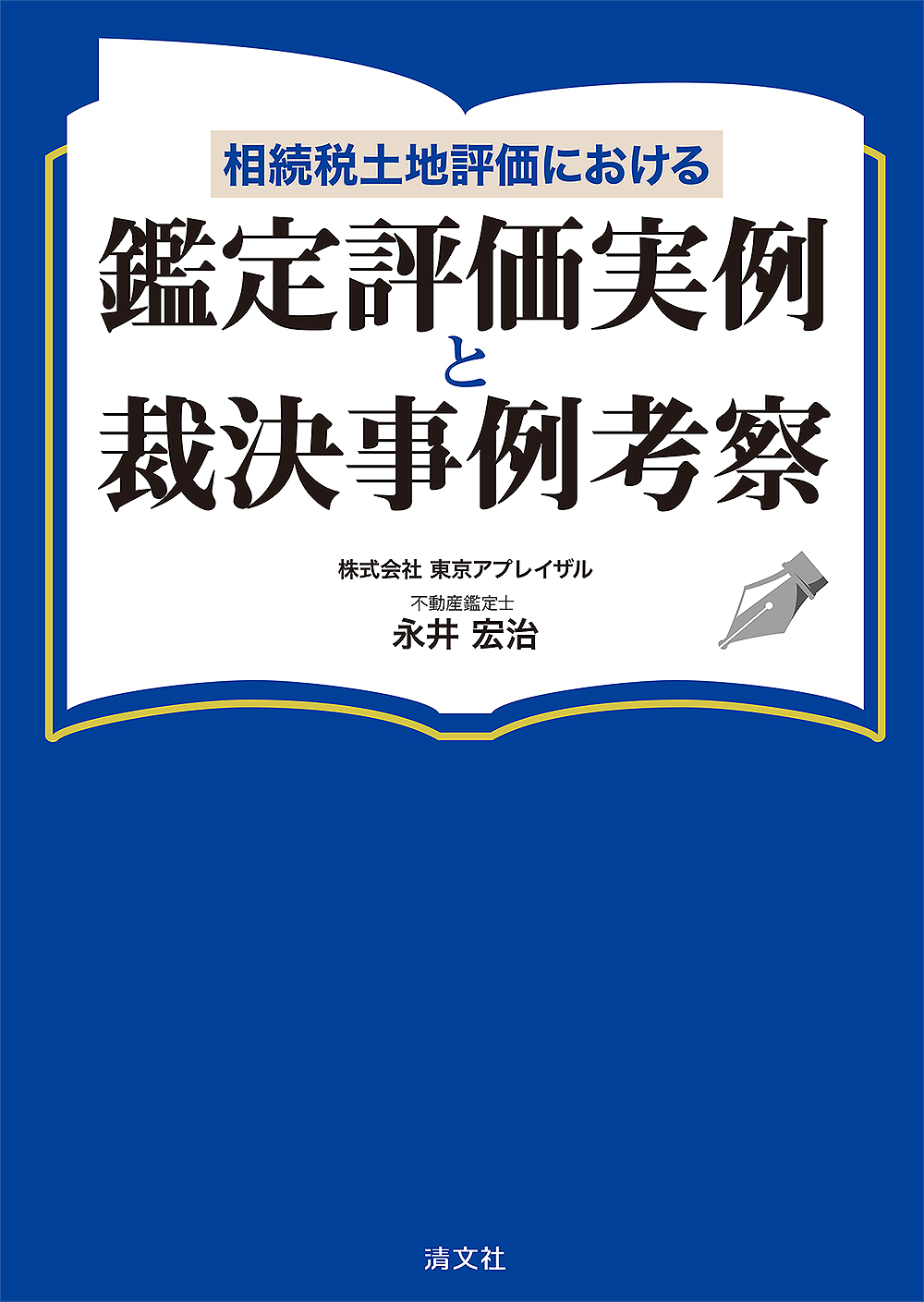税理士が知っておきたい
不動産鑑定評価の常識
【第13回】
「争いが生じやすい中古建物の評価」
~鑑定評価で重視される市場性の観点~
不動産鑑定士 黒沢 泰
前回、貸宅地(鑑定評価でいえば底地)の評価をめぐる税務の常識と鑑定評価の常識の相違について取り上げましたが、建物に関してもそれぞれの常識との間に隔たりが存在するケースがあります。それは中古建物の評価に係る場合です。
例えば、ある人が建築後相当期間の経過した建物を相続で取得し、それを親族で居住用に使用していたとします。相続人は、税申告の関係もあり不動産鑑定士に鑑定評価を依頼したところ、その建物は老朽度からして市場性に欠ける(= そのままでは建物の価値を見い出しえない)という理由で、家屋の撤去を前提とした評価額が求められたとします(すなわち、「建物及び敷地の評価額 = 更地価格 - 家屋の撤去費」という算式が適用されます)。
これに対し、財産評価基本通達にはこのような考え方はなく、「家屋の相続税評価額 = 固定資産税評価額 × 1.0」(= 固定資産税評価額そのもの)という算式が適用されることは税理士の皆様もご承知のことと思います。加えて、固定資産評価基準では、建築後一定年数を経過した建物であっても、評価額が再建築費の一定割合よりも下がらない仕組みとなっています。
そのため、納税者からすれば、「建物が古い割には相続税評価額が高いのではないか」という疑問が生じ、課税庁との間に紛争が生ずるケースもしばしば見受けられるようです。すなわち、そこには税務の常識と鑑定評価の常識の乖離が生じており、これを発端として国税不服審判所に審査請求が行われるという具合です。今回は、このようなよくあるケースについて、両者間には何故上記のような隔たりが生ずるのかを本質面から捉えてみます。
この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員登録およびログインが必要です。
すでに会員登録をされている方は、下記ボタンからログインのうえ、ご覧ください。
Profession Journalのすべての記事をご覧いただくには、「プレミアム会員(有料)」へのご登録が必要となります。
なお、『速報解説』については「一般会員(無料)」へのご登録でも、ご覧いただけます。
※他にもWebセミナー受け放題のスーパープレミアム会員などがございます。
会員登録がお済みでない方は、下記会員登録のボタンより、ご登録のお手続きをお願いいたします。