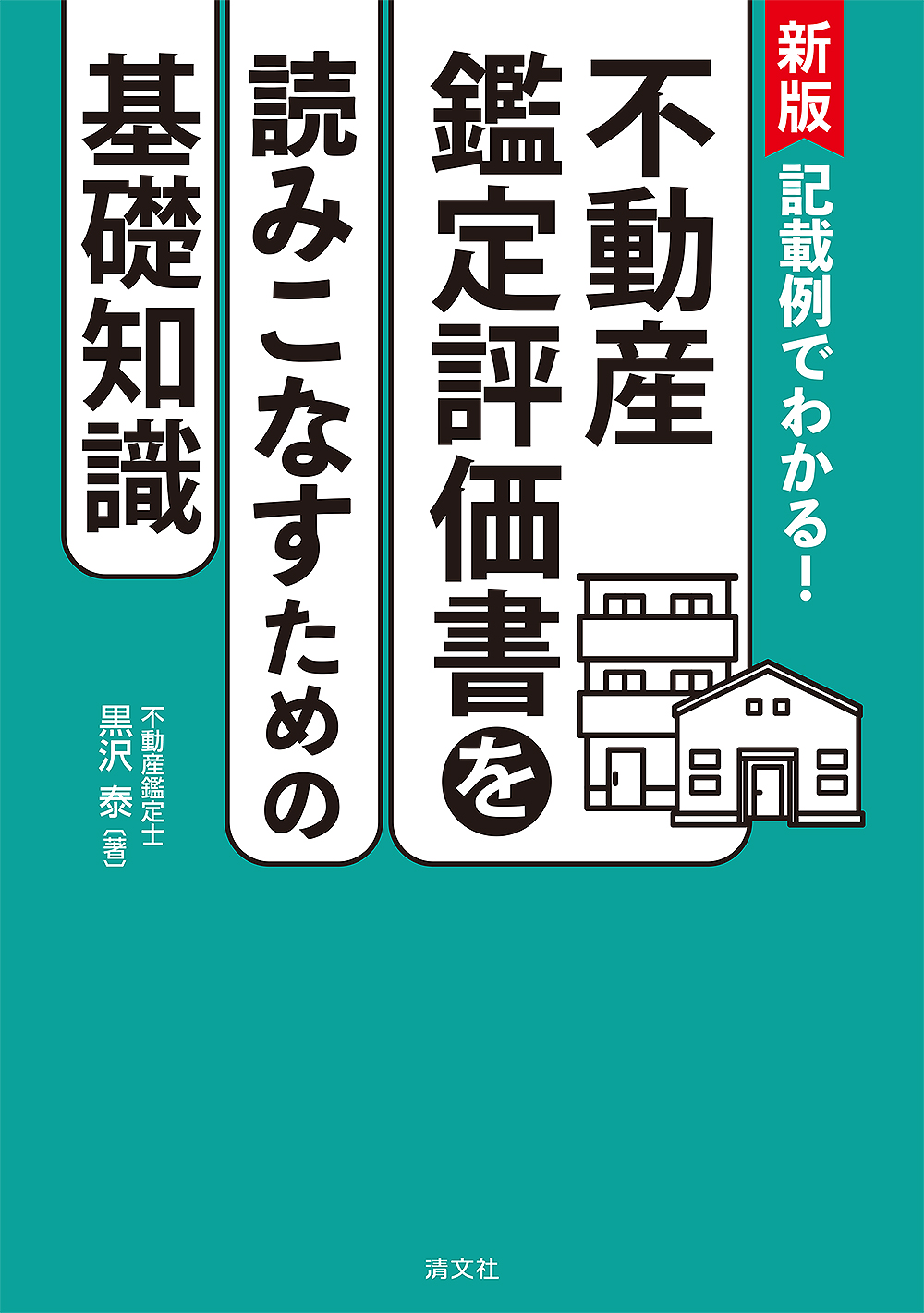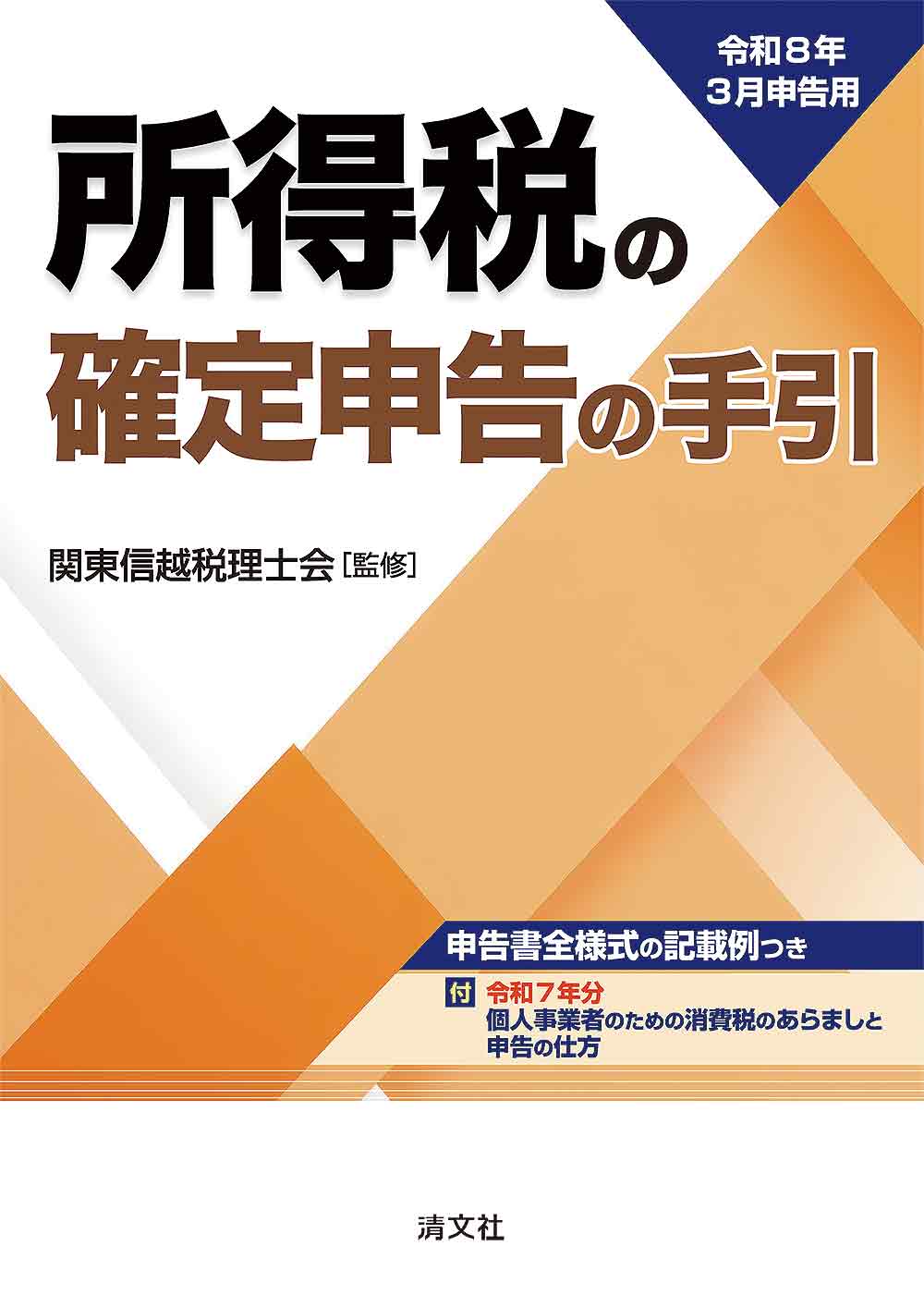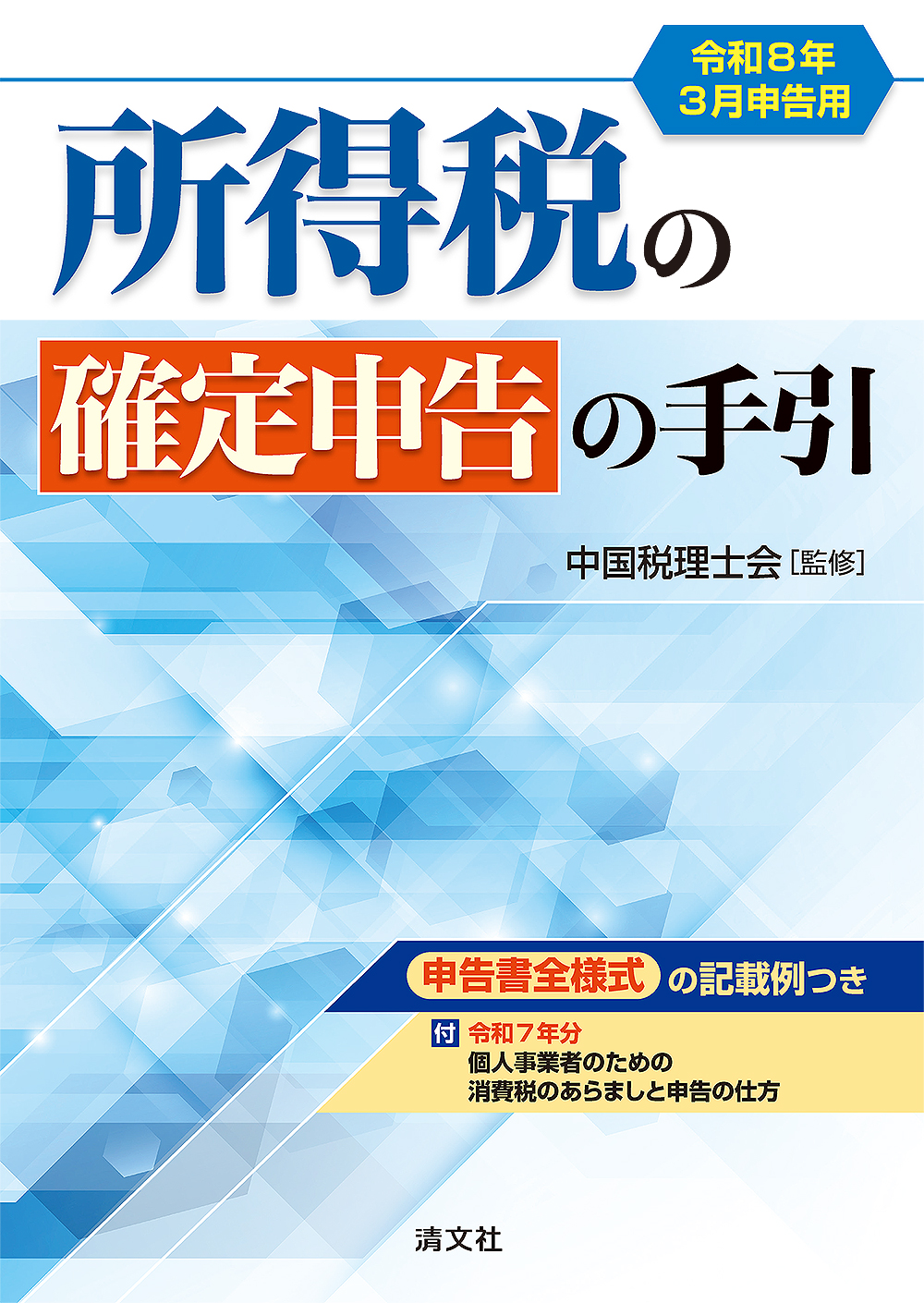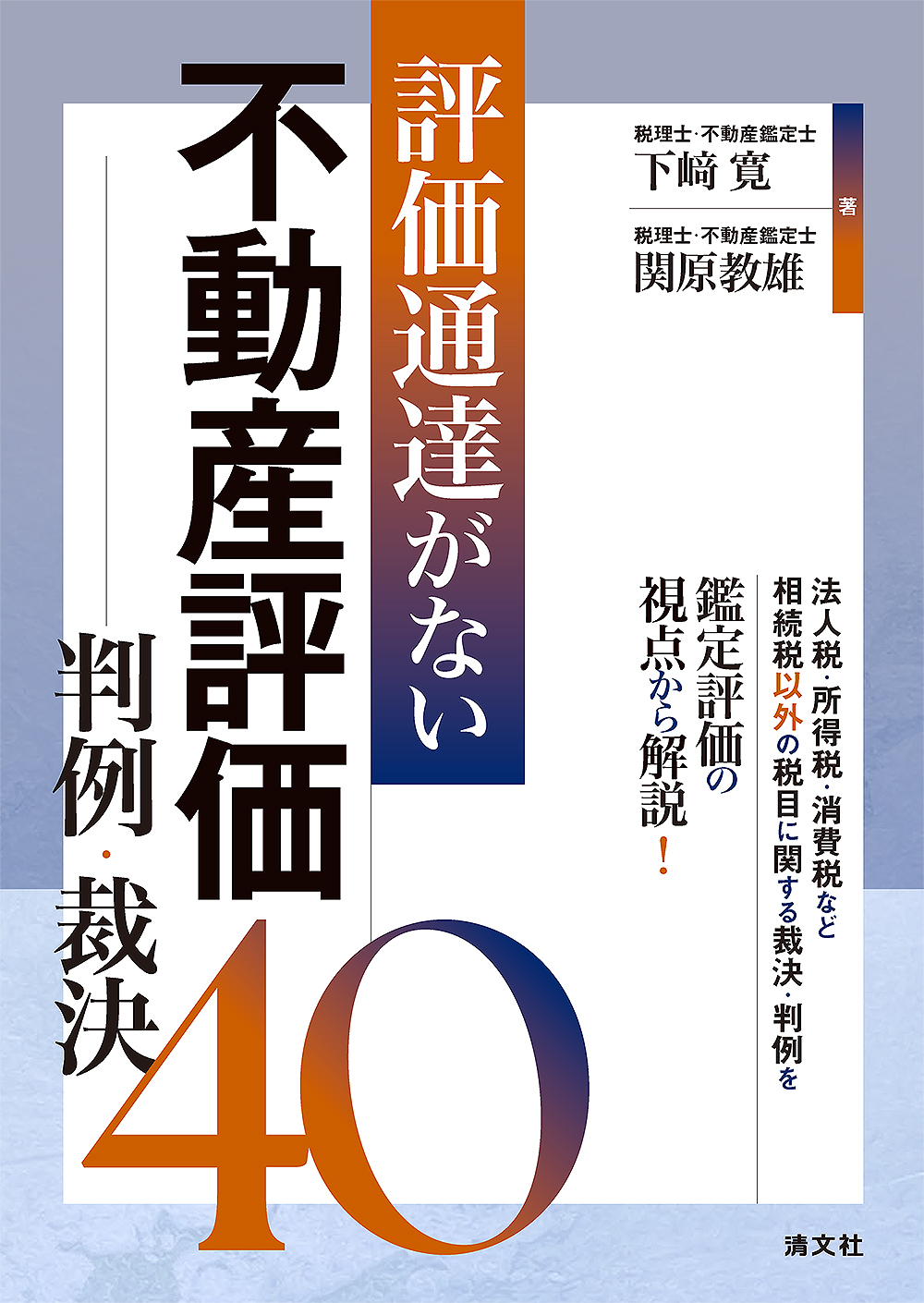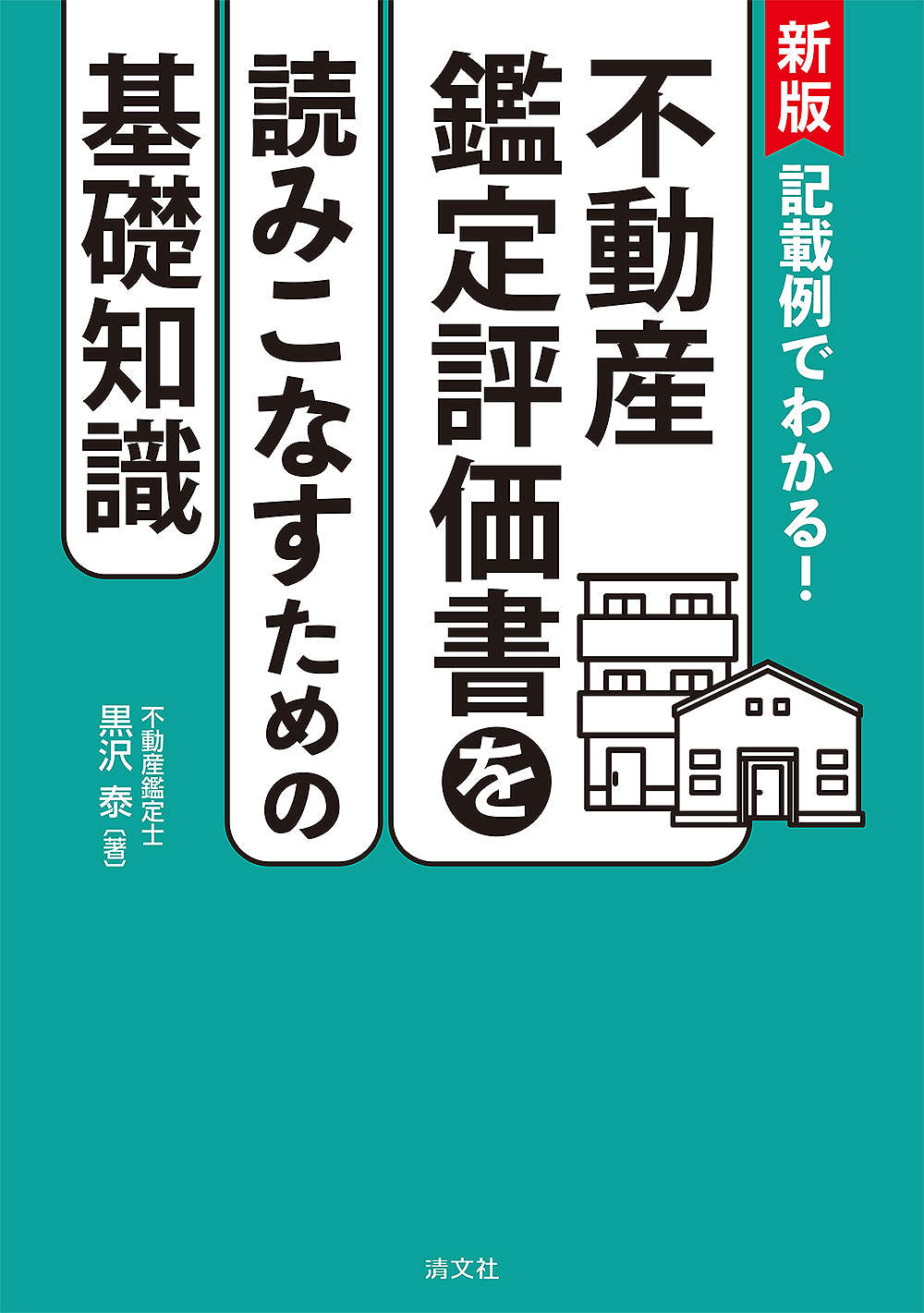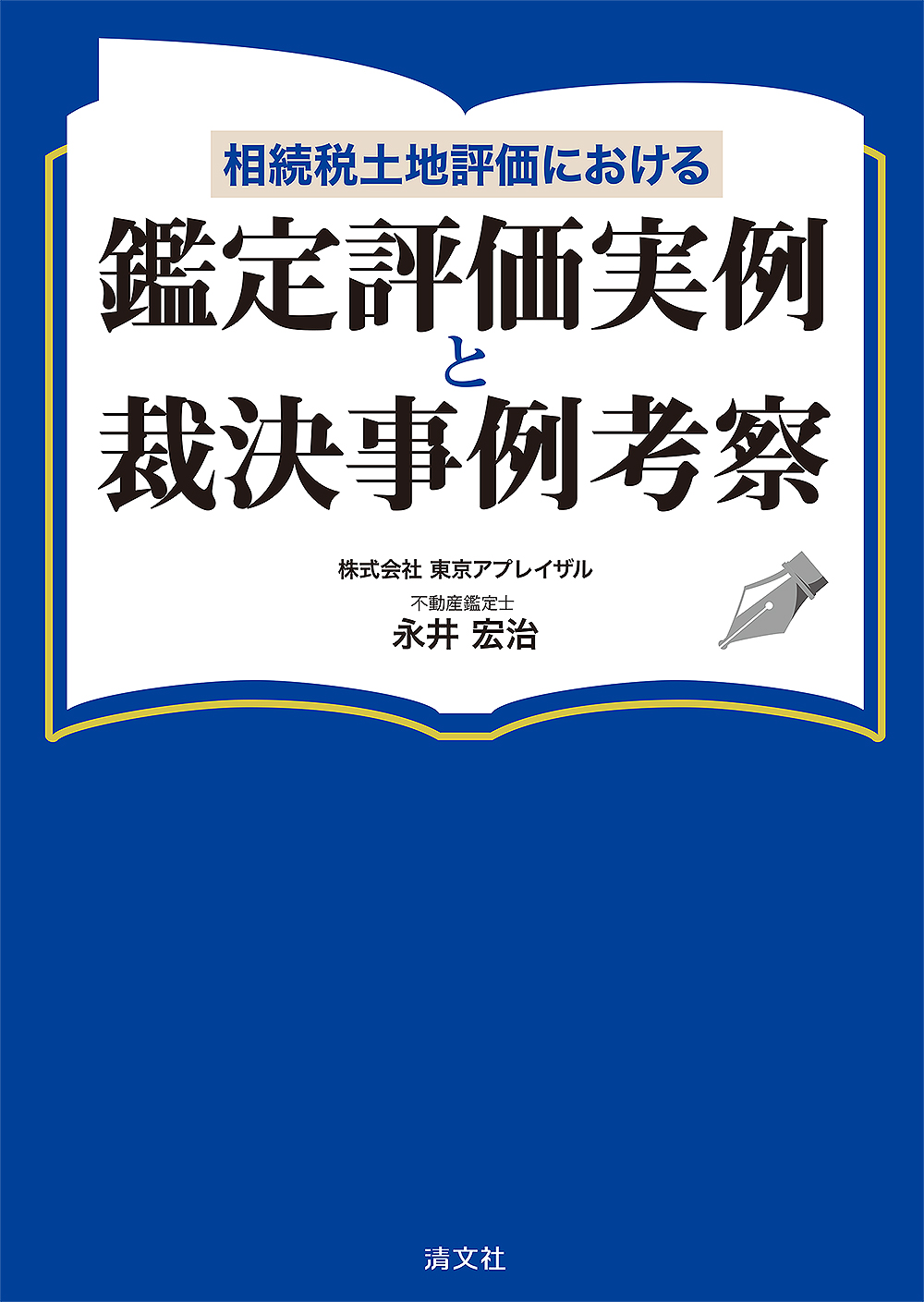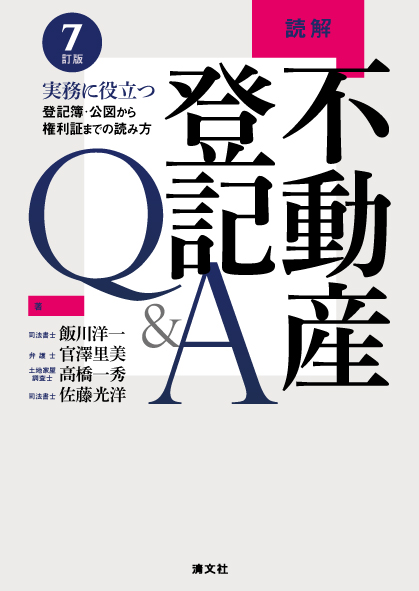税理士が知っておきたい
不動産鑑定評価の常識
【第21回】
「評価方法の選定に影響を与える「特別の事情」とは何か」
~鑑定評価額が採用されたレアケース~
不動産鑑定士 黒沢 泰
前回は、財産評価基本通達(以下「評価通達」といいます)による評価方法によっては適正な時価を適切に算定することのできない特別の事情の存しない限り、相続財産の評価に当たっては、評価通達の定める評価方法によって評価を行うのが相当である旨、税務上取り扱われていることを述べました。すなわち、相続税の財産評価に用いる時価は評価通達により算定した評価額が原則であり、例外的に(すなわち特別の事情のある場合に限り)他の合理的な方法(鑑定評価等)による評価額が許容されるということです。
その際の「特別の事情」とは何かについては前回紹介したとおりですが、上記の考え方による限り、評価通達以外の評価方法による評価額が許容された事例は(筆者の調査による範囲では)事実上きわめて少ない傾向にあります。
前回、納税者と課税庁の間で評価額をめぐり争いとなった事例をいくつか掲げましたが、最後に鑑定評価の結果が活用されたケースとして東京地方裁判所令和元年8月27日判決(相続した不動産の時価について評価通達の定めによることなく鑑定評価額によって評価することが許されるとした事例)(※1)を簡単に紹介しました。この裁判例は、特別の事情の解釈を検討するに当たり、各方面から注目を浴びているということも耳にします。そこで、今回は、この事案の概要と争点、裁判所の判断について全体像を要約した上で、鑑定評価の位置付けに関し筆者なりのコメントを付しておきたいと思います。
(※1) 金融・商事判例No.1583(2020年2月1日号)、TAINSコード:Z888-2271。
この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員登録およびログインが必要です。
すでに会員登録をされている方は、下記ボタンからログインのうえ、ご覧ください。
Profession Journalのすべての記事をご覧いただくには、「プレミアム会員(有料)」へのご登録が必要となります。
なお、『速報解説』については「一般会員(無料)」へのご登録でも、ご覧いただけます。
※他にもWebセミナー受け放題のスーパープレミアム会員などがございます。
会員登録がお済みでない方は、下記会員登録のボタンより、ご登録のお手続きをお願いいたします。