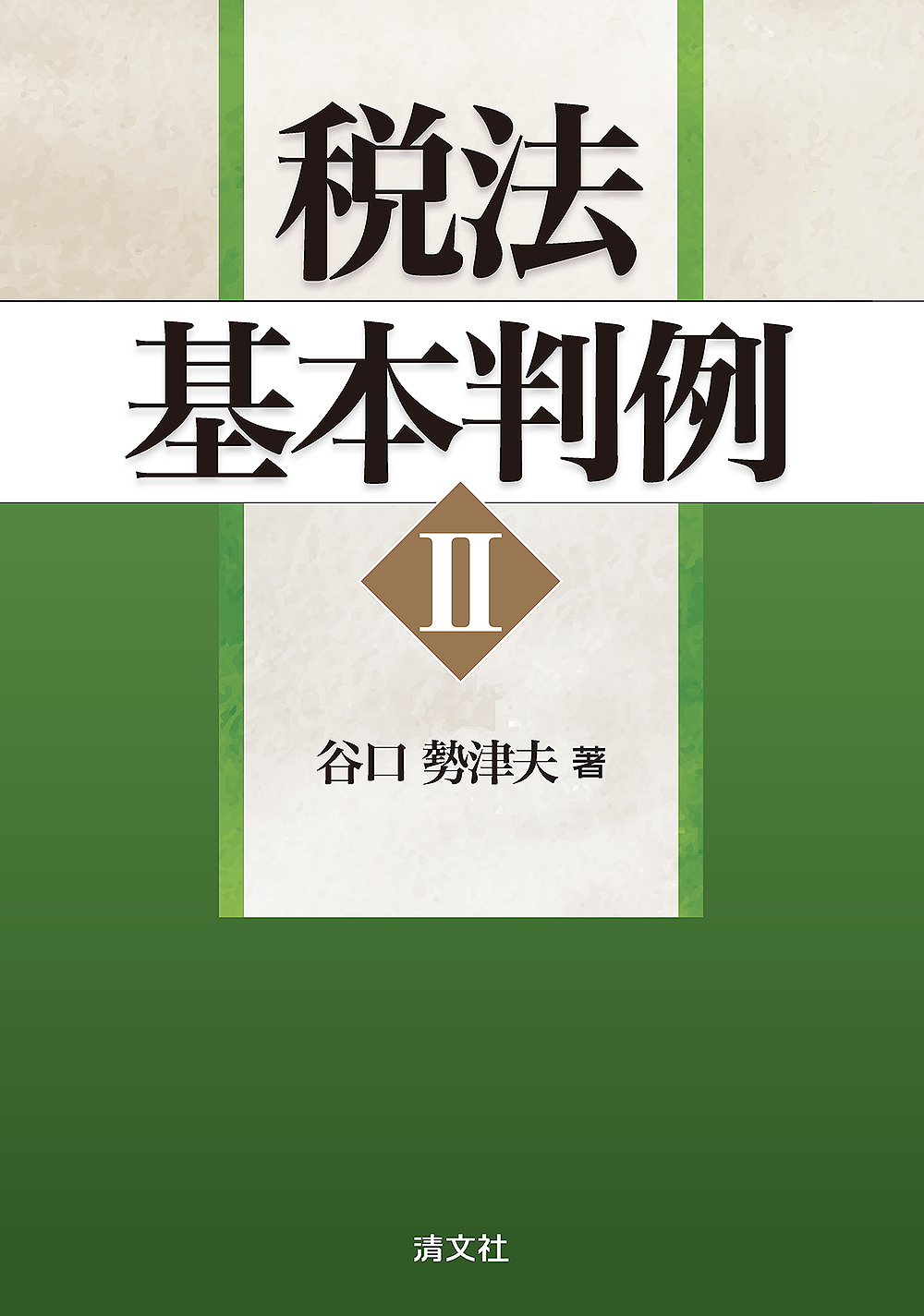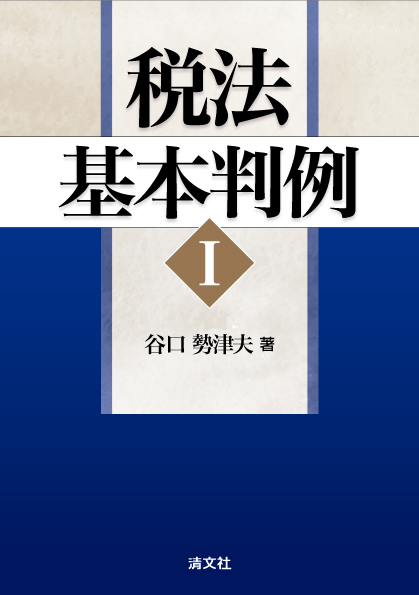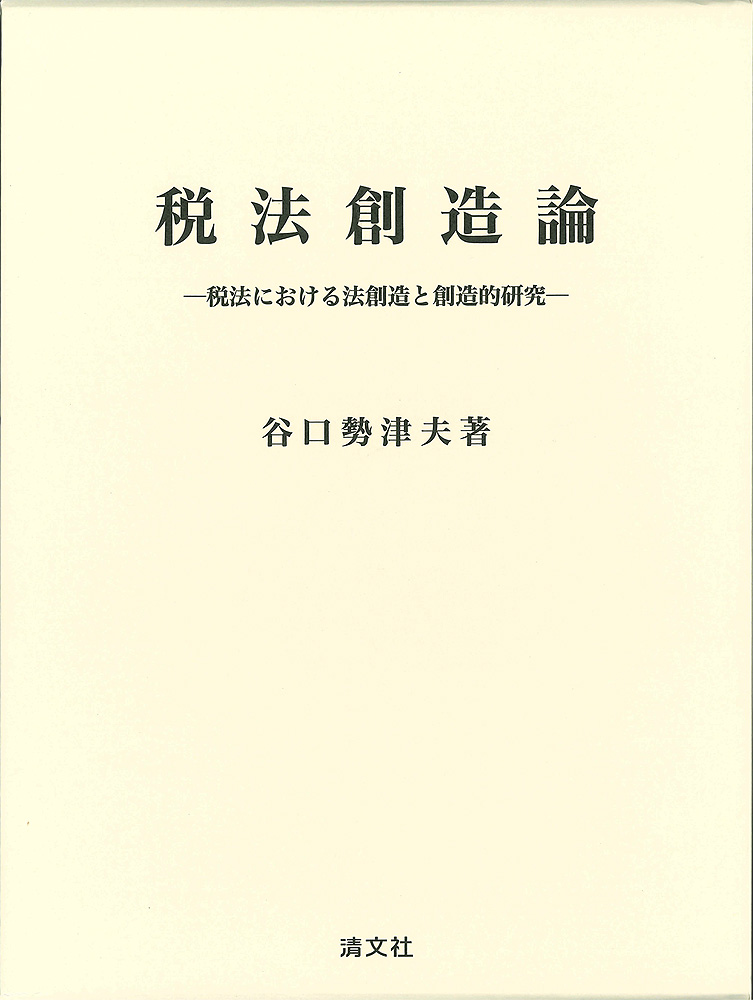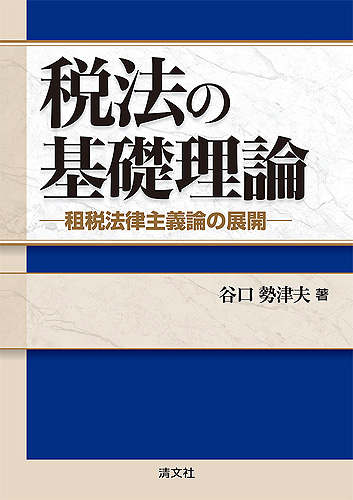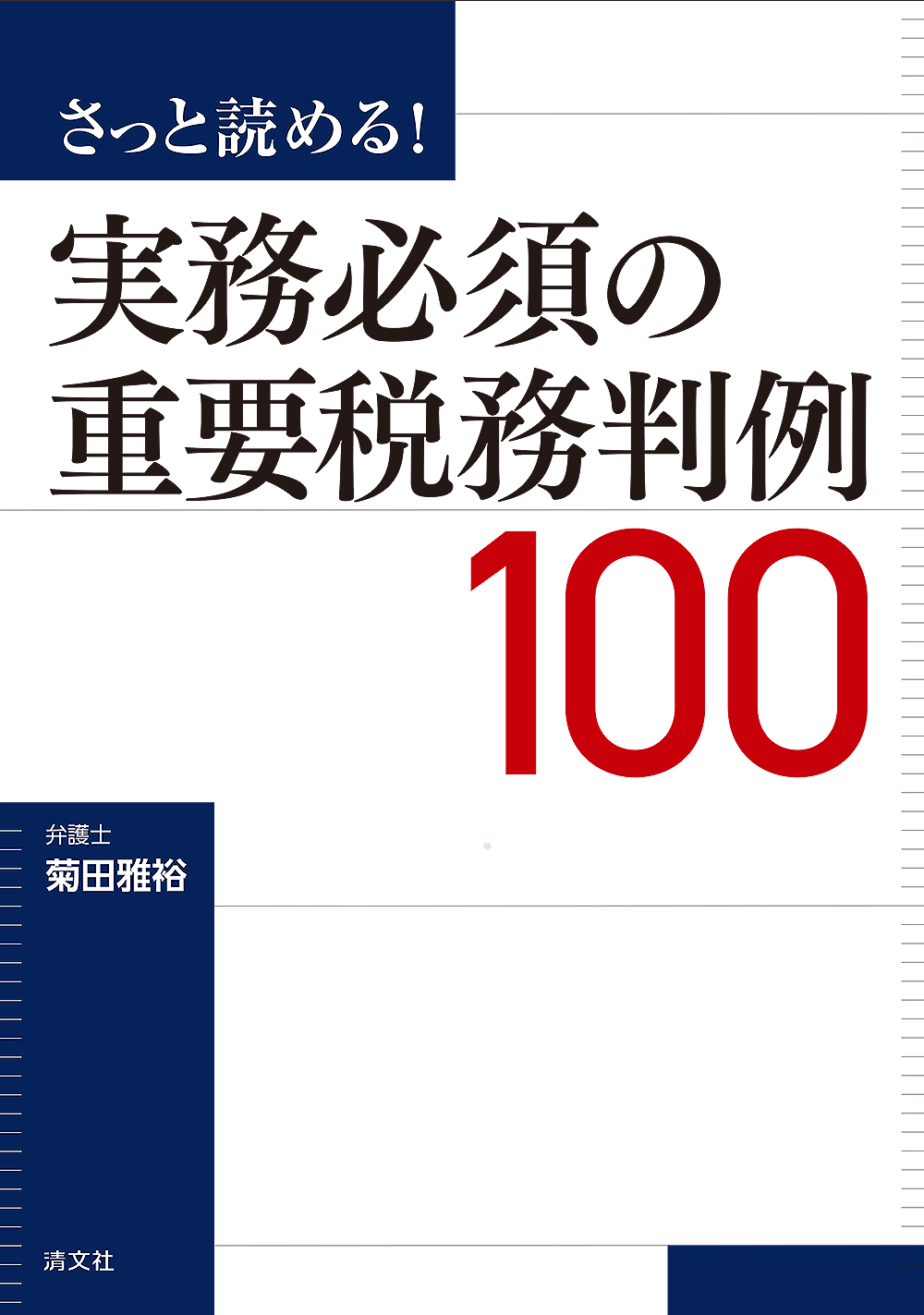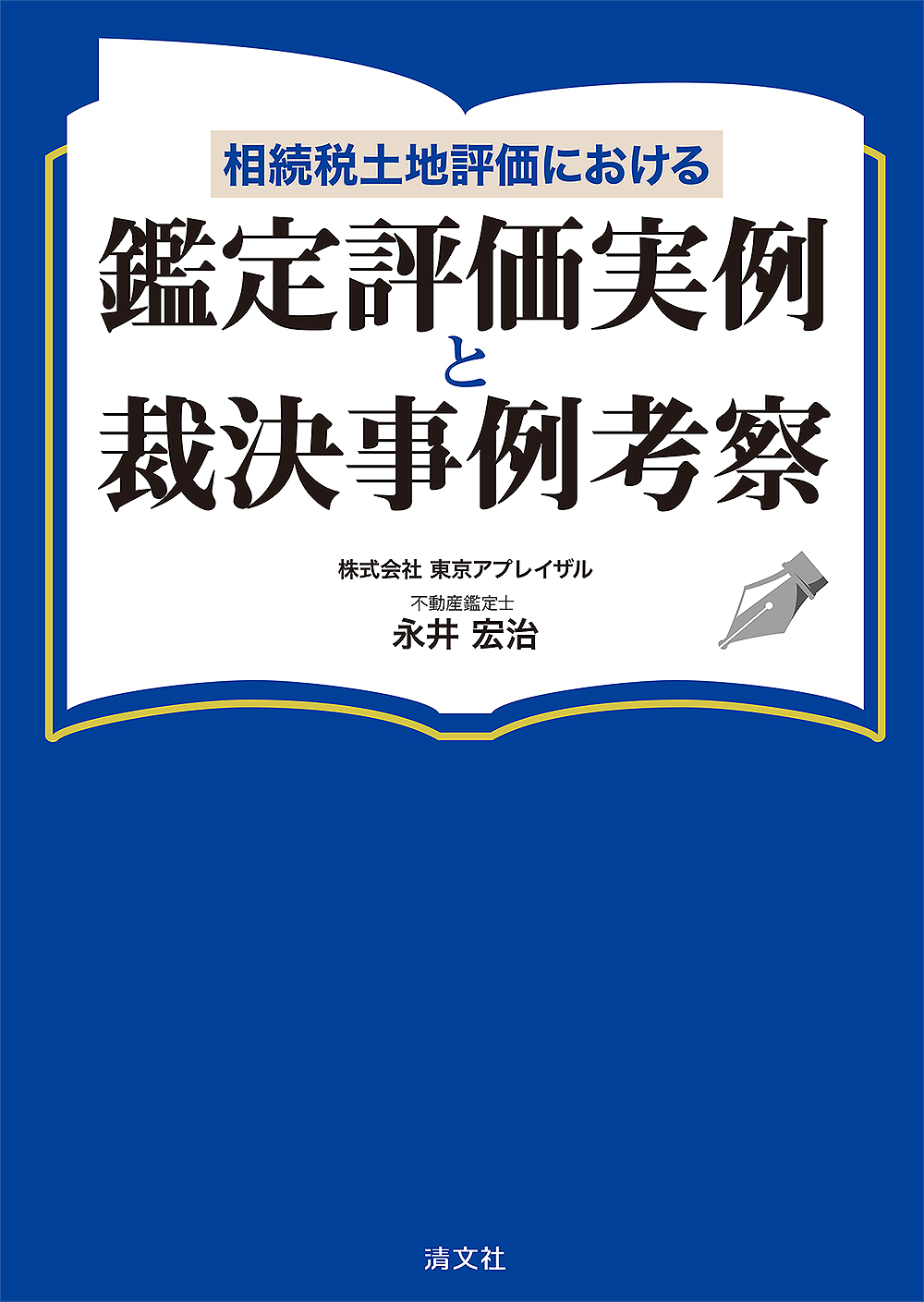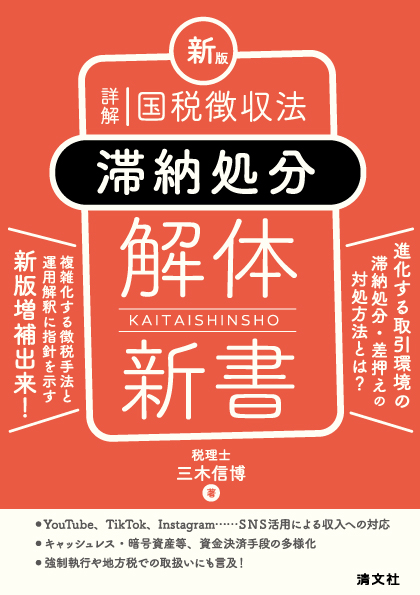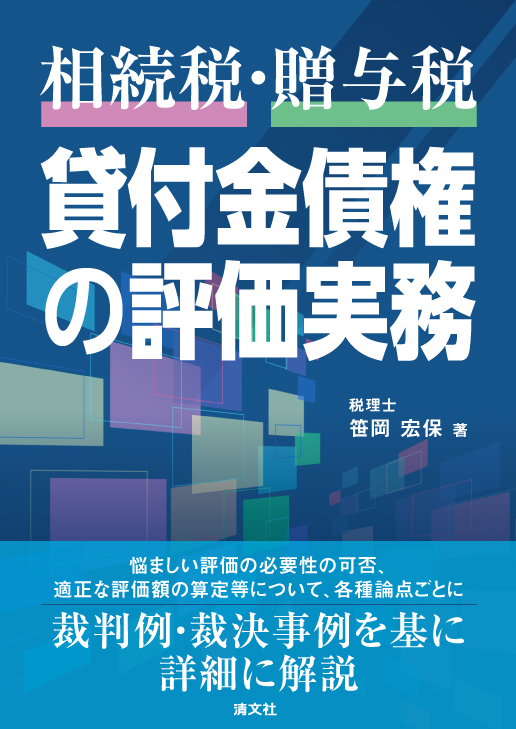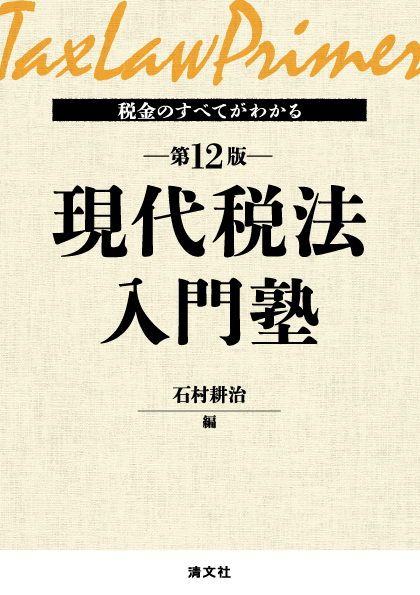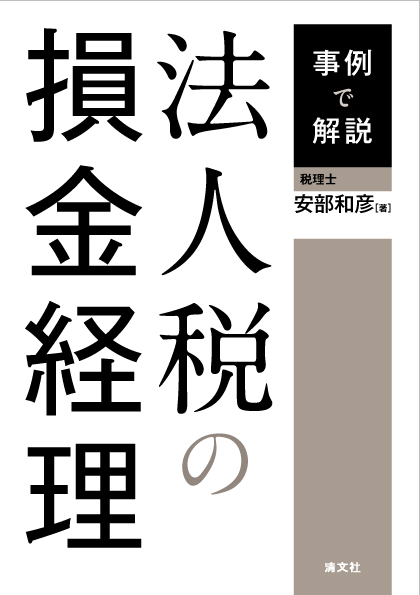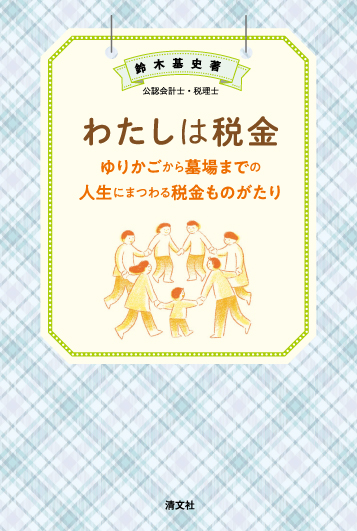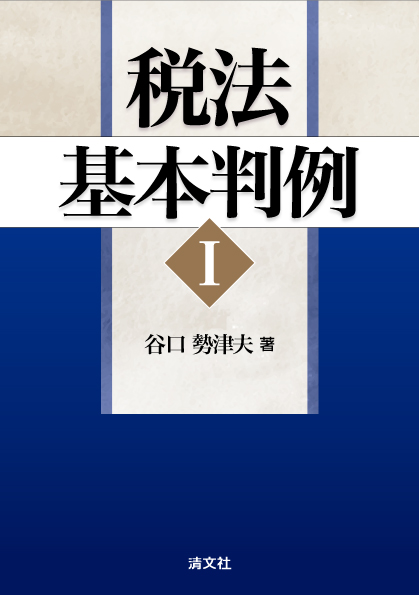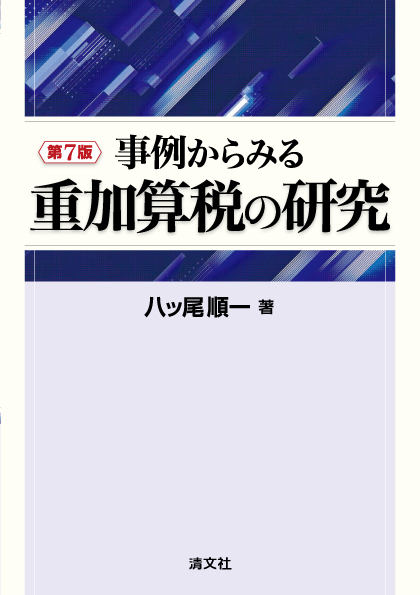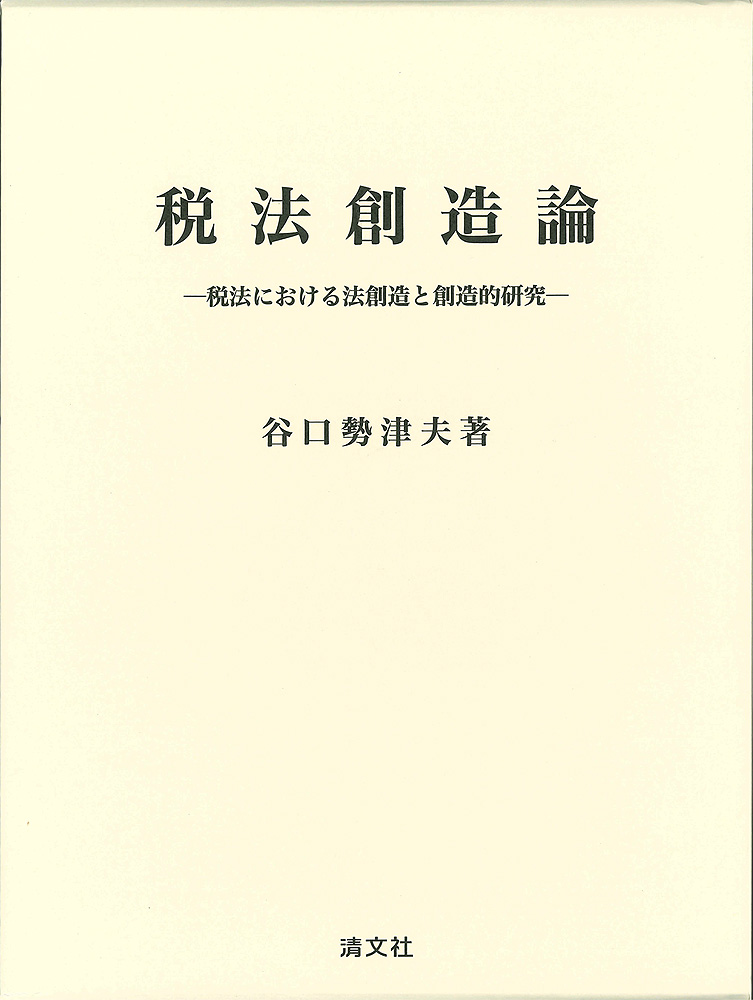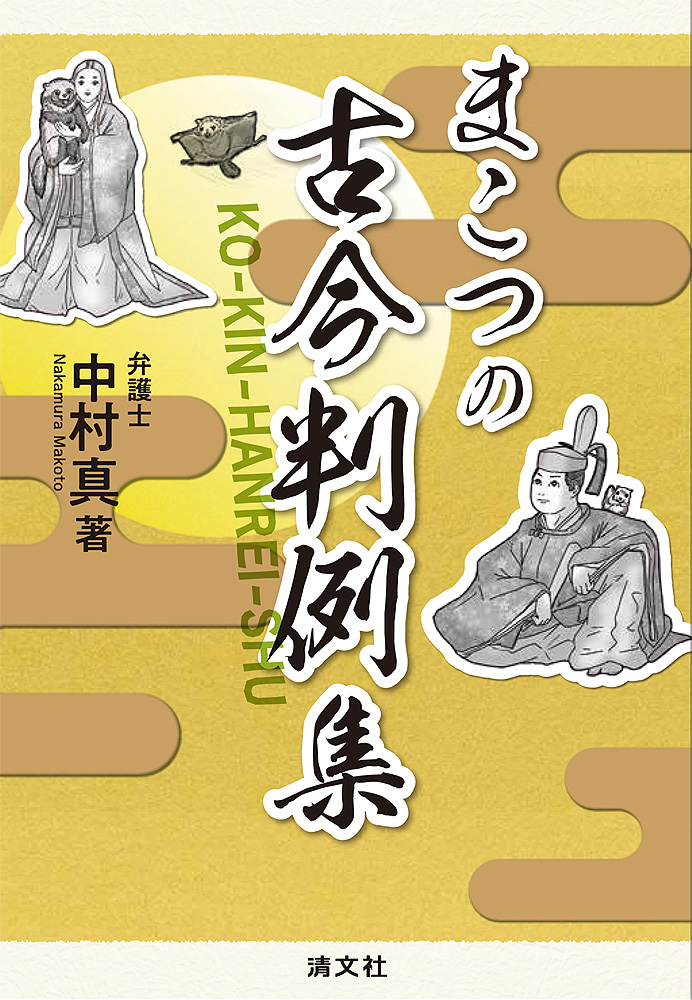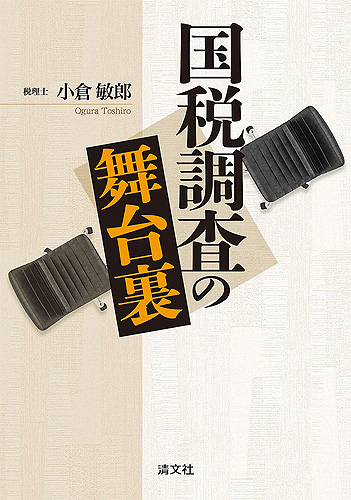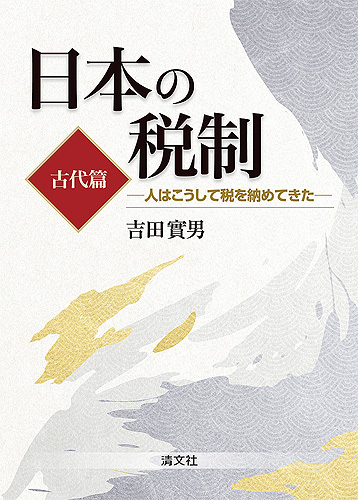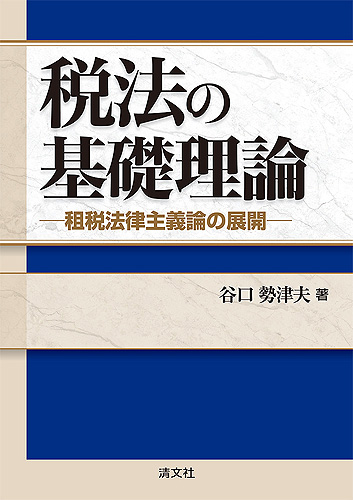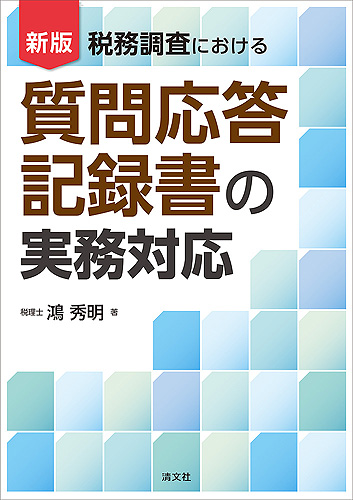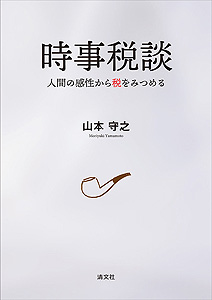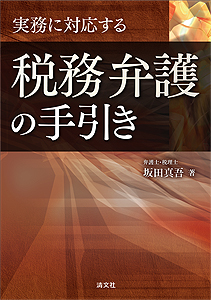谷口教授と学ぶ
税法の基礎理論
【第1回】
「租税法律主義の意義と分類」
-連載の「プラットホーム」-
大阪大学大学院高等司法研究科教授
谷口 勢津夫
Ⅰ はじめに-連載を始めるに当たって-
「税法の基礎理論」と題して本誌に連載をさせていただくことになったが、本連載で「税法の基礎理論」という言葉は、「税法の基礎にある考え方」あるいは(もう少し厳密にいえば)「実定税法の体系及び諸規定を支える基本原則」というような意味で用いている。
「税法の基礎理論」のこのような意味・用語法は、拙著『税法基本講義〔第5版〕』(弘文堂・2016年)の「第1編 税法の基礎理論」のそれと同じである。そこでは、「税法の基礎理論」として租税法律主義を基軸に据えて、税法の制定及び解釈適用に関する総論的な問題について体系的に解説を加えることにしているが、本連載も同じく租税法律主義を「税法の基礎理論」の基軸とするものではあるものの、ただ、教科書とは異なる原則1回読み切りの「読み物」(もちろん各回の叙述内容は租税法律主義を介して相互に関連するものではあるが)として執筆するものであることから、取り上げるトピックは、体系的叙述の観点からではなく、そのときどきの筆者の問題関心により選定させていただくことにする。
もっとも、読者に各回の叙述内容を体系的に理解していただく一助として、各回の叙述の中で必要に応じて前掲拙著の関連箇所の欄外番号(【 】内の数字で表記する)を参照することにしたい。本連載が、税法の分野における研究と実務の(「理論」による)架橋に、多少なりとも寄与することができれば望外の喜びである。研究の「理論」は基礎理論、実務の「理論」は応用理論であるが、研究と実務とは「理論」を介して架橋は可能であり、かつ、すべきであると考えるところである。
さて、前置きはこれくらいにして、連載を始めるに当たって、今回は、少し長くなるが、本連載のいわば「プラットホーム」として、租税法律主義の意義と分類について述べておくことにしよう(【10】【11】【14】【15】【17】【28】参照)。
Ⅱ 租税法律主義の意義
租税法律主義は、課税権者に対して被課税者たる国民の同意に基づく課税を義務づける考え方である。租税法律主義は、歴史的には、1215年のマグナ・カルタ(大憲章)において、当時のイングランド国王ジョンが諸侯との間で当時の租税(楯金・援助金)につき、「いかなる楯金又は援助金も、朕の王国においてはこれを課さないものとする。」と確約したことを起源とし、それ以降、一方では政治的側面において、議会制民主主義の成立・発展に、他方では法的側面において、法の支配・法治主義の成立・発展に、それぞれ貢献してきた。
租税法律主義は、今日、多くの国で、議会制民主主義の下、議会制定法に基づく課税を要請する憲法原則として確立されており、日本国憲法は法律に基づく課税を、課税権者の側から(84条)及び被課税者の側から(30条)それぞれ規定している。租税法律主義の目的は、マグナ・カルタの「精神」を受け継ぎ、課税権者による恣意的・不当な課税から、国民の財産及び自由を保護することである。つまり、租税法律主義は、日本国憲法の基本理念の中核にある自由主義(基本的人権尊重主義)の、税法の場面での現れである。
その意味では、税法は、そのような目的を達成するための手段であり、自由主義的税法(自由主義に基づく租税法律主義を根本原理とする税法)として性格づけられるべきものである。もちろん、税法は本来的には税収確保という目的を達成するための手段であるから、これらの2つの目的の間でいかにしてバランスをとるかが、税法の制定においてはいうまでもなく、場合によっては税法の解釈適用においても、重要な課題となる。本連載において扱う問題のほとんどは、突き詰めれば、この課題に関するものといってよかろう。
租税法律主義の前記の目的からすれば、租税法律主義の機能は、本来的には、課税の適法性を保障すること(適法性保障機能)である。この本来的機能から派生して、租税法律主義は、そのような適法な課税を受けることに対して納税者に予測可能性・法的安定性を保障する機能(予測可能性・法的安定性保障機能)をもつことになる。租税法律主義の機能についてこのように本来的機能と派生的機能とを区別して理解しておくことは、税法の基礎理論に関してだけでなく、実際の問題に関しても、重要な意味をもつことがある。
例えば、一定のスキームに基づく外国税額控除余裕枠の利用を「外国税額控除制度を濫用するもの」として否認した判例(最判平成17年12月19日民集59巻10号2964頁、最判平成18年2月23日訟月53巻8号2447頁)について、法律上の明文の規定なしに否認を認めるものとして租税法律主義違反を問題にする批判的見解(私見については【47】参照)に対して、納税者に「濫用」の認識がある場合には「濫用」を否認してもその否認に基づく課税は、納税者の予測可能性を害することにはならず、したがって、租税法律主義に反することにはならないと主張されることがある。
しかし、「濫用」を認識することと、「濫用」が許されないと判断することとは、論理的にも法律論的にも、別問題である。外国税額控除制度の趣旨・目的(上記判例参照)を探知すれば同制度の利用が「濫用」(趣旨・目的に反する利用)に該当するか否かを認識することはできるが、しかし、「濫用」の認識から直ちに、同制度の「濫用」を許容しないとする価値判断を導き出すことはできない。租税法律主義の下では、同制度の「濫用」を否認するためには、上記の価値判断を法律上明文化した規定(濫用否認規定)が必要である。
もし前記の主張が明文の濫用否認規定を援用することなく、同制度にはいわば「不文の濫用否認規定」が内在しているので「濫用」の否認は租税法律主義に反しないと強弁するものであるならば、そのような主張を容認することは租税法律主義の「自己否定」につながることになろう。
要するに、租税法律主義の予測可能性・法的安定性保障機能は、法律上の明文の規定に基づく(適法な)課税についてのみ認められるべきものであり、その意味で、適法性保障機能の枠内で認められる派生的機能にとどまるのである。
Ⅲ 租税法律主義の分類
租税法律主義は、法律に基づく課税という場合における法律の「形式」と「内容」の観点から、次の2つに分類することができる。すなわち、1つは、法律という「形式」の法(議会制定法)によらない課税を禁止する考え方であり、筆者はこれを「形式的租税法律主義」と呼んでいる。もう1つは、法律の「内容」が憲法の人権保障に抵触するものであってはならないという考え方であり、これを「実質的租税法律主義」と呼んでいる。この分類は、法治主義に関する形式的法治主義(法律による行政の原理)と実質的法治主義(人権保障を第一義的な目的とする法治主義)の分類に対応するものである。
1 形式的租税法律主義
まず、形式的租税法律主義は、法律によらない課税の禁止原則として、主に税務行政に対して税法の厳格な解釈適用を命じる憲法原則であり、通常、合法性の原則あるいは税務行政の合法律性の原則と呼ばれる。本連載で取り上げるトピックは税法の解釈適用に関するものが多くなるであろうが、それらを合法性の原則の観点から論じることにしたい。筆者の主たる研究テーマである租税回避の問題も、適宜、その一環として論じるつもりである。
もっとも、法律によらない課税の禁止は、税務行政との関係だけで問題になるものではない。法律の定め方如何によっては、形式的には法律に従って課税が行われるかのようにみえても、実質的には法律によらずに課税が行われるとみられる場合(「法律があっても無きが如き場合」)には、そのような課税は法律によらない課税であり禁止されるべきものであるから、租税立法との関係においても、法律によらない課税の禁止は問題になる。
「法律があっても無きが如き場合」として極端な例を挙げると、もし〇〇税法が「〇〇税に関する事項は全て政令の定めるところによる。」との一条のみを定め、〇〇税に関する事項を全て政令に委任したとすれば、そのような法令の規定に基づく〇〇税の課税が法律によらない課税の禁止に反することは、明らかである。このような命令(行政立法)への白紙委任の場合についてだけでなく、法律の定めが極めて不明確であり税務行政による自由な解釈を許すような場合についても、同様のことがいえる。租税法律主義からその内容として課税要件法定主義や課税要件明確主義が導き出されるが、これらは法律によらない課税の禁止を実効あらしめるための憲法原則とみることができるので、形式的租税法律主義に属するものと考えるところである。
2 実質的租税法律主義
次に、実質的租税法律主義は、租税法律の「内容」に関して憲法の人権規定との適合性を要請する租税立法上の原則であり、税法の分野における憲法の最高法規性(98条1項)の現れとして違憲審査権(81条)によって担保されている。
とはいえ、確立された判例(大嶋訴訟・最大判昭和60年3月27日民集39巻2号247頁)によれば、租税立法の違憲審査基準は、①民主主義的租税観(「およそ民主主義国家にあつては、国家の維持及び活動に必要な経費は、主権者たる国民が共同の費用として代表者を通じて定めるところにより自ら負担すべきものであ[る]」として、租税を国民共同の費用とみる考え方)と、②租税立法における財政・経済・社会政策等に係る政策手段性及び課税要件等に係る専門技術性に基づく裁量的判断の尊重の見地から、立法目的の正当性の基準、(立法目的の達成のために用いられる手段の)合理性の基準及び明白性の原則によって、構成されているところ、そのような違憲審査基準によれば、租税立法は原則として合憲性の推定を受け、違憲と判断されることは実際上まずあり得ないことになろう。
しかし、だからといって、判例の立場が租税法律主義の下での違憲審査のあり方として妥当でないとは、直ちにはいえないであろう。というのも、民主主義的租税観によって、憲法上、納税義務(30条)及び課税(84条)を根拠づけ正当化する場合には、やはり、国民の代表者たる立法者の裁量的判断ができる限り尊重されるべきであるからである。
もっとも、租税立法者の裁量的判断は、民主主義的租税観において「想定」される議会制民主主義を前提にして、尊重されるべきものである。したがって、租税立法の違憲審査権に関する判例の立場に対する評価は、究極的には、わが国の議会制民主主義の実態や現状をどのように評価するかにもかかっているといえよう。
今日における議会制民主主義の「劣化」に加え、財政状況の悪化、租税負担の増加傾向等をも考慮すると、税法の制定を「国家財政、社会経済、国民所得、国民生活等の実態についての正確な資料を基礎とする立法府の政策的、技術的な判断にゆだねる」(前掲大嶋訴訟・最大判)ことの意味を問い直すべきであろう。租税立法に関する裁量統制についても、司法の役割はやはり重要である。
(了)
この連載の公開日程は、下記の連載目次をご覧ください。