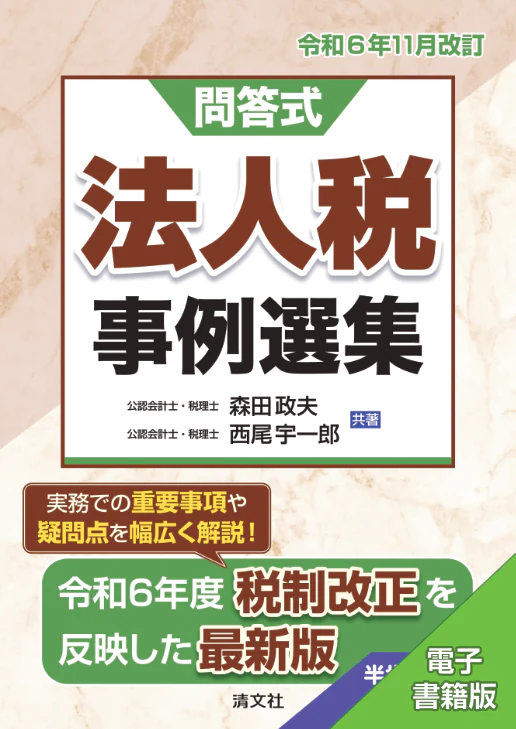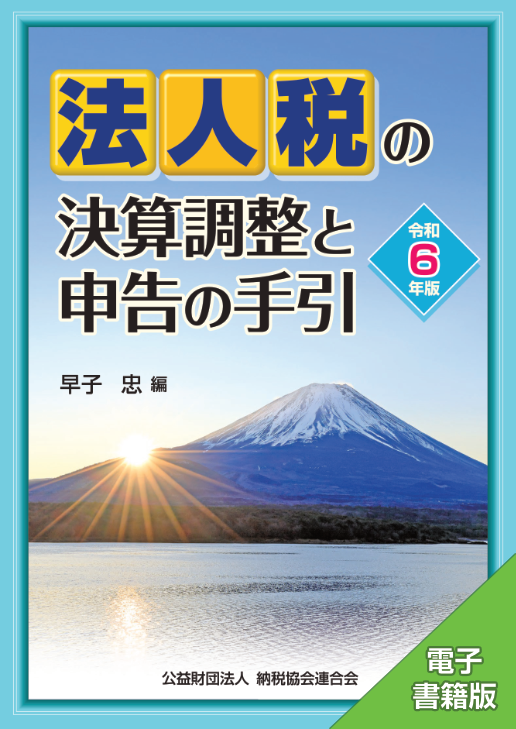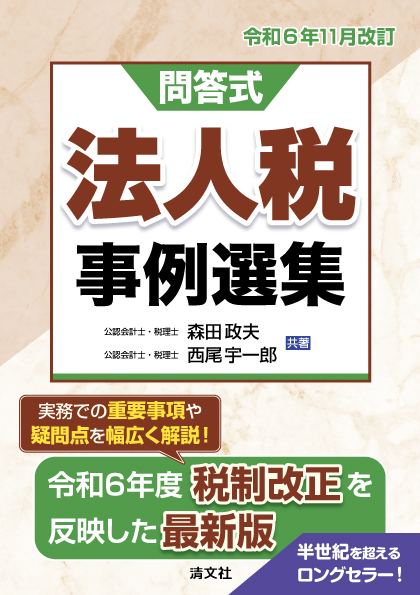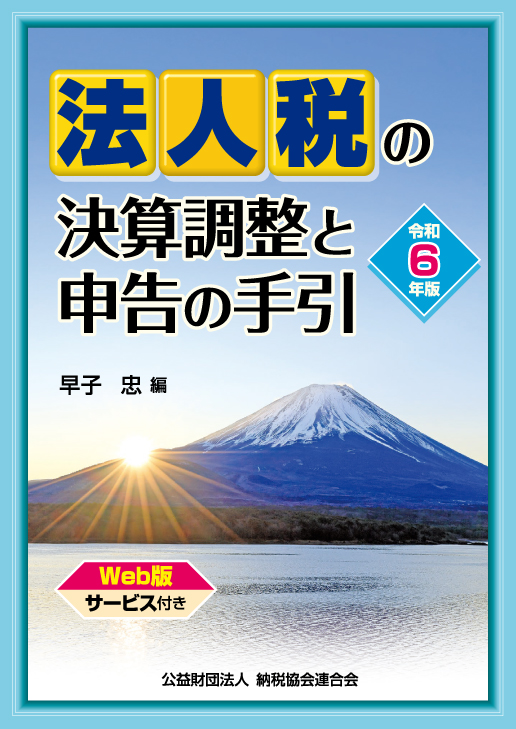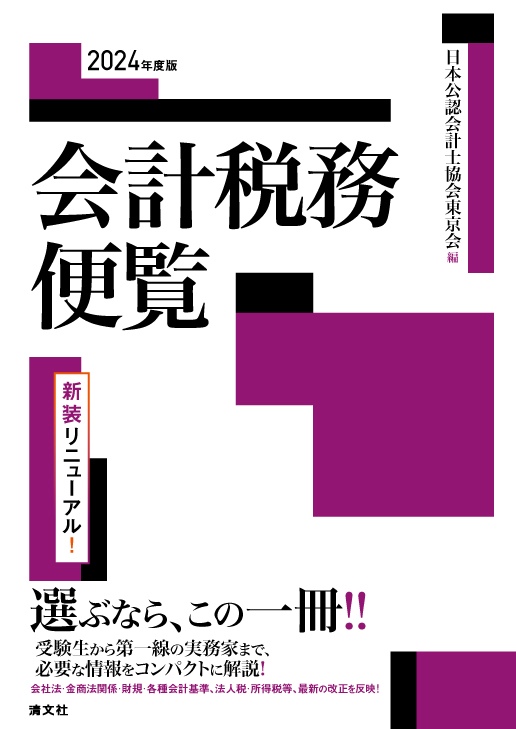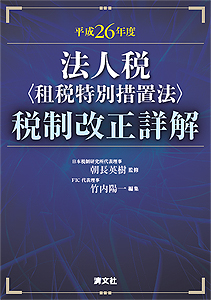《速報解説》
研究開発投資の質の向上と量の増加を目指す研究開発税制の改正
~令和5年度税制改正大綱~
弁護士 羽柴 研吾
1 改正の背景
令和4年12月23日(金)に閣議決定された「令和5年度税制改正大綱」において、研究開発税制の拡充と延長が行われることになった。
研究開発投資を通じたイノベーションは、社会課題を成長のエンジンへと転換するために不可欠なものであるが、我が国の研究開発投資の伸び率は他の主要国に比して低いことが指摘されてきた。また、スタートアップとのオープンイノベーションや高度研究人材の活用も欧米に比して十分に進んでいないことも指摘されてきたところである。
そこで、令和5年度税制改正において、主として次の3つの観点から改正が行われることになった。なお、従来の控除率の上限引上げ、控除上限・控除率の上乗措置の時限措置については、3年間延長されることになっている。
この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員登録およびログインが必要です。
すでに会員登録をされている方は、下記ボタンからログインのうえ、ご覧ください。
Profession Journalのすべての記事をご覧いただくには、「プレミアム会員(有料)」へのご登録が必要となります。
なお、『速報解説』については「一般会員(無料)」へのご登録でも、ご覧いただけます。
※他にもWebセミナー受け放題のスーパープレミアム会員などがございます。
会員登録がお済みでない方は、下記会員登録のボタンより、ご登録のお手続きをお願いいたします。