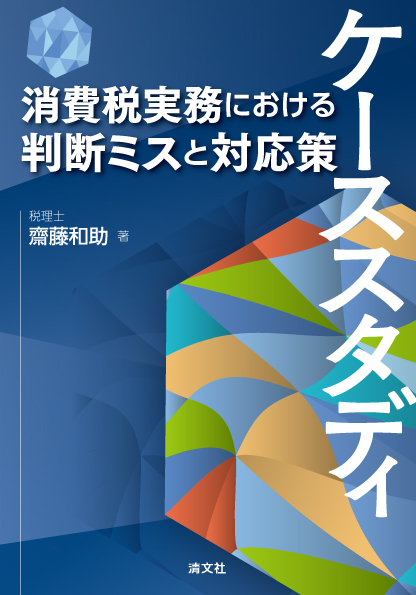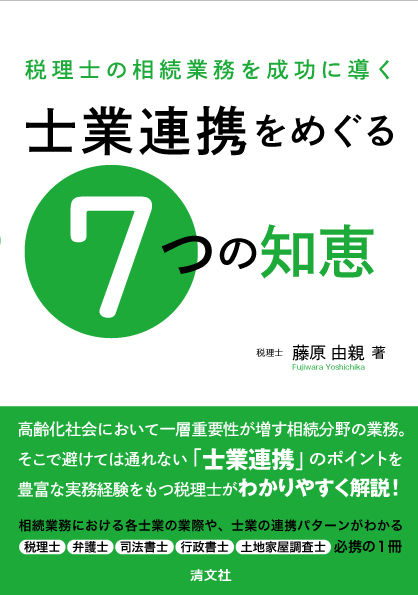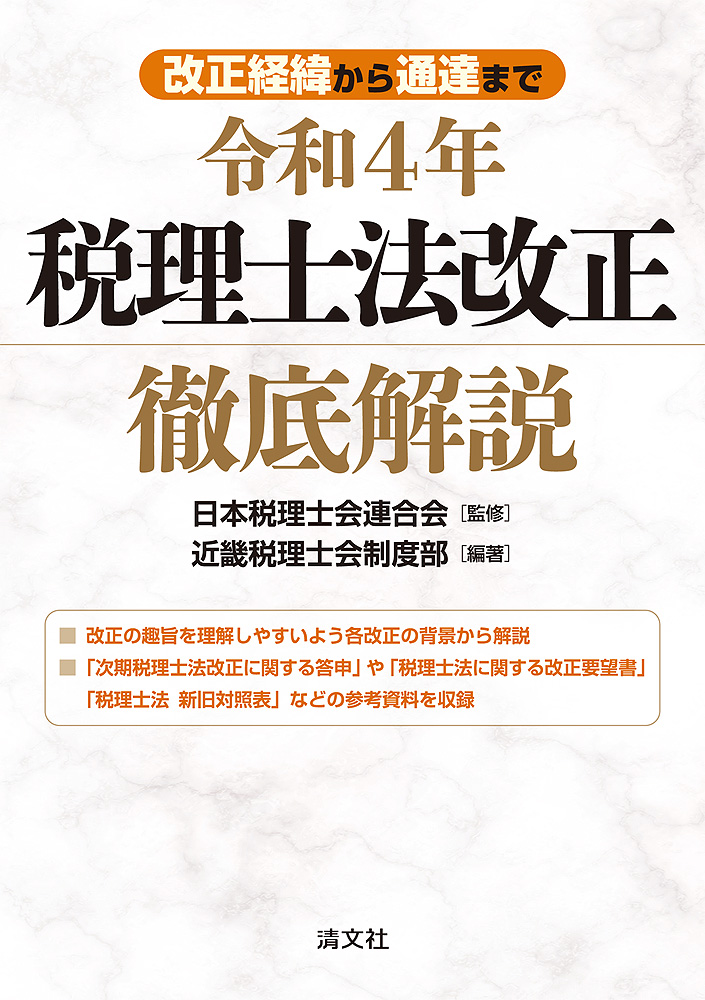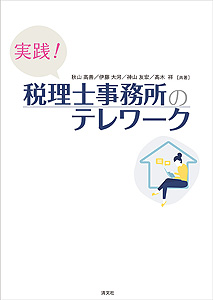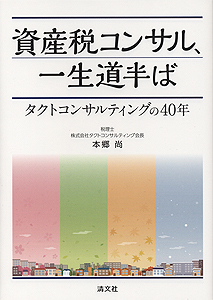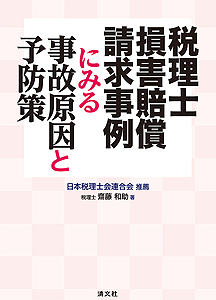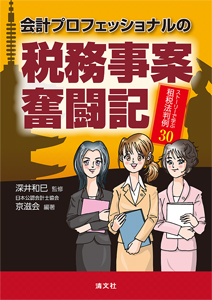〔一問一答〕
税理士業務に必要な契約の知識
【第1回】
「退職税理士による顧客の引抜きの防止」
-その1:その税理士が「在職中」の場合-
虎ノ門第一法律事務所
弁護士 山口 智寛
◆連載開始にあたって◆
税理士は会社や事業体の税務・会計に直接関与する立場にあるが、実際には、本来的な業務以外の事柄に触れることも多いと聞く。
顧客から契約や交渉に関する質問を受けたり、自らの税理士事務所の経営において法律問題に直面したりすることも少なくないのではないか。このような事態に遭遇したときに、自信を持って回答し、誤った選択を回避するにはどうすればよいだろうか。
本稿の連載は、判断に迷うような未知の問題について、最低限の内容や対応方針を把握していただくことを主眼とするものである。これまでに多くの税理士先生方からお寄せいただいた質問のうち、特に問い合わせの多かったものを類型化してQ&Aの形にして解説していく。
契約に関するテーマが多くなることから連載のタイトルを「税理士業務に必要な契約の知識」としたが、実際には、契約に留まらず税理士業務において直面し得る法律問題全般について取り上げる所存である。
〔質 問〕
当事務所の所属税理士(税理士法人の社員ではない)が退職することになりました。
ところが、この税理士が退職を見越して、当事務所の顧客を勧誘して引抜きにかかっているらしいのです。このような場合、契約上の有効な対応策はないでしょうか。
〔回 答〕
就業規則等に秘密保持義務あるいは競業避止義務の規定があれば、それらを根拠として、その税理士に引抜きの中止を求めることができます。
また、秘密保持義務あるいは競業避止義務の規定がないとしても、就業規則の服務規律には誠実労働義務、職務専念義務が規定されているので、これらを根拠に引抜きの中止を求めることもできます。
なお、就業規則がない場合についても、雇用契約上当然に誠実労働義務、職務専念義務を従業員は雇用主に対して負うとされているので、上記と同様に対処することができます。
◆◆◆◆ 解 説 ◆◆◆◆
1 在職中の引抜き行為を止めさせる法的根拠
(1) 秘密保持義務、競業避止義務
税理士事務所の立場とすれば、退職する所属税理士による顧客の引抜きは直ちに止めてもらいたいところである。それでは、どういった法的根拠をもってこの引抜き行為を止めさせることができるだろうか(なお、元所属税理士が税理士法人の社員である場合は、税理士法の規定に基づいた考慮が必要であるため、別稿で改めて取り上げる(第3回で解説予定))。
まず、就業規則に「業務上の秘密を自ら又は第三者のために利用してはならない」という秘密保持義務、あるいは、「就業中に顧客勧誘行為を行ってはならない」という競業避止義務の規定があれば、秘密保持義務違反(顧客の引抜きは顧客情報を利用している点で秘密保持義務違反といえる)ないし競業避止義務違反であるとして、退職予定の所属税理士に対して引抜き行為の中止を求めることができる。採用時に秘密保持や競業避止の誓約書や同意書を取得している場合も、同様にこれらの文書の規定に従って引抜き行為の中止を求めることができる。
厳密にいえば、顧客の引抜きが税理士事務所の顧客情報を利用しているといえるかどうかは判断が難しいところであるが、税理士事務所の立場からすれば、差し当たり、就業規則や誓約書・同意書といった個別文書における秘密保持義務を所属税理士による引抜き行為を止めさせせるための法的根拠として考えておくこと自体は差し支えない。
(2) 誠実労働義務、職務専念義務
秘密保持義務や競業避止義務の根拠となる規定が存在しない場合であっても、就業規則には通常、服務規律のところに「誠実に職務を遂行する」という誠実労働義務・職務専念義務が規定されているから、この誠実労働義務・職務専念義務を根拠に、退職予定の所属税理士に対して引抜き行為の中止を求めることができる。
では、小規模の税理士事務所で就業規則すらない場合はどうか(労働基準法89条は「常時10人以上の労働者を使用する使用者」に対して就業規則の作成及び届出義務を課している)。この場合でも、従業員は雇用主に対して雇用契約上当然に誠実労働義務・職務専念義務を負うと解釈されているから、この雇用契約上の義務を根拠として上記と同様に対処できる。
したがって、結局のところ、特段の明示的な規定がなくても、雇用契約関係に基づいて当然にその税理士に対して引抜き行為の中止を求めることができる。
2 具体的な対応方法
このように、在職中の所属税理士に対しては、就業規則や雇用契約それ自体が、引抜き行為を止めさせる法的根拠となり得る。もっとも、法的根拠があるからといって、そのとおりに引抜き行為を止めさせることができるとは限らず、税理士事務所の側としては「できる限りの対応を行う」というスタンスで臨むしかない。
(1) 証拠がない場合
そもそも、その所属税理士が本当に税理士事務所の顧客に対してアプローチしているかどうか、また、例えば独立や退職を告知するという限度を超えて具体的な契約切替えの打診等にまで及んでいるかどうかは、簡単に裏付けを取れるものではない。
もし、具体的な勧誘行為の証拠や裏付けが取れていないのであれば、その所属税理士が「引抜きを行っている」ということを前提とした対応を取ることはできない。このような場合、税理士事務所側としてできることといえば、退職時に秘密保持義務や顧客の引抜きをしないという限度での競業避止義務の誓約書や同意書を提出してもらう形で、間接的に引抜きを牽制することくらいだろう。
証拠がないのにもかかわらず、勧誘行為があったと決め付けて対応を取るようなことがあると、事後的に所属税理士の側から「引抜きをしたと言いがかりを付けられて事務所を辞めさせられた」などとクレームを受けたり、更に場合によっては損害賠償請求を受けるなどの紛争に発展したりする可能性もあるので、性急な対応は自制すべきである。
(2) 証拠がある場合
退職予定の所属税理士が発したメール等の証拠や、勧誘を受けた顧客の側からの情報提供等の裏付けがある場合には、積極的な対応が可能である。
具体的には、まず、本人に対して直接警告を与えて、自発的に引抜きを止めるよう促すべきである。「声をかけただけだ」などと反論されるかもしれないが、現時点で実際に引抜きが実現していなくとも、引き抜こうとしている時点(引抜準備行為を行っている時点)で従業員としての義務に反するので、所属税理士側からのそのような反論は成り立つものではない。
警告を与える場合には、在職中で日常的なコミュニケーションを取ることが可能であれば、あえて文書を出すまでの必要はなく、口頭で警告を与えた上で、その警告日時、方法、場所等を記録として控えておけば十分である。
一方、その所属税理士が退職日を待つばかりであり既に事務所での実働はないという場合には、口頭での警告は困難であるから、メールや自宅宛の文書で警告するしかない。文書を発送する場合は、普通郵便だと発送した事実を証拠として残しておくことができないので、内容証明郵便又は特定記録郵便を利用したほうが良い。
口頭の場合であれ文書の場合であれ、警告を与える際には、「引抜きを止めない場合には損害賠償を請求する可能性がある」ということを告げれば、所属税理士の側により大きな心理的な圧力を加えることが可能である(もっとも、後述するとおり実際に損害賠償を請求するかどうかは別の問題である)。
(3) 警告を無視された場合
警告を行ったにもかかわらず引抜き行為を止めない場合には、どうすればよいか。
このような場合は、就業規則における懲戒解雇の規定に基づいて、退職の予定日を待たずにその所属税理士を懲戒解雇することもやむを得ないだろう。また、実際に引抜きがなされて、その顧客からの売上がなくなってしまった場合には、引抜きを行った所属税理士に対して、売上減少分について損害賠償を請求することも可能である。
文書で損害賠償を請求したにもかかわらず、その所属税理士側がこれに応じない場合には、訴訟を提起することも選択肢に入ってくる。
ただし、実際に訴訟を提起した場合、具体的な引抜き行為や顧客の側の契約変更との間の因果関係を立証することは、相当の困難を伴う。
大阪地方裁判所平成30年11月13日判決は、個人事業主である税理士が、元従業員である税理士に対して在職中及び退職後に顧問先を勧誘して引き抜いたとして損害賠償を求めた事案において、「被告らが原告の顧問先に対し、原告との顧問契約を解約して被告らと新たに顧問契約を締結するよう積極的に働き掛けた」行為を認めるだけの証拠は存在しないと判断している。また、売上減少分の損害といっても、何年分の売上をもって損害といえるのかは判然とせず、裁判実務上の基準といえるようなものも存在しない。
このようなことを前提とすると、「訴訟すれば勝てる」と安易に思い込むべきではなく、むしろ「訴訟提起もあり得る」ということを交渉材料にして訴訟外での解決を図ることを第一に考えるべきである。
(了)
「〔一問一答〕税理士業務に必要な契約の知識」は、毎月第2週に掲載されます。