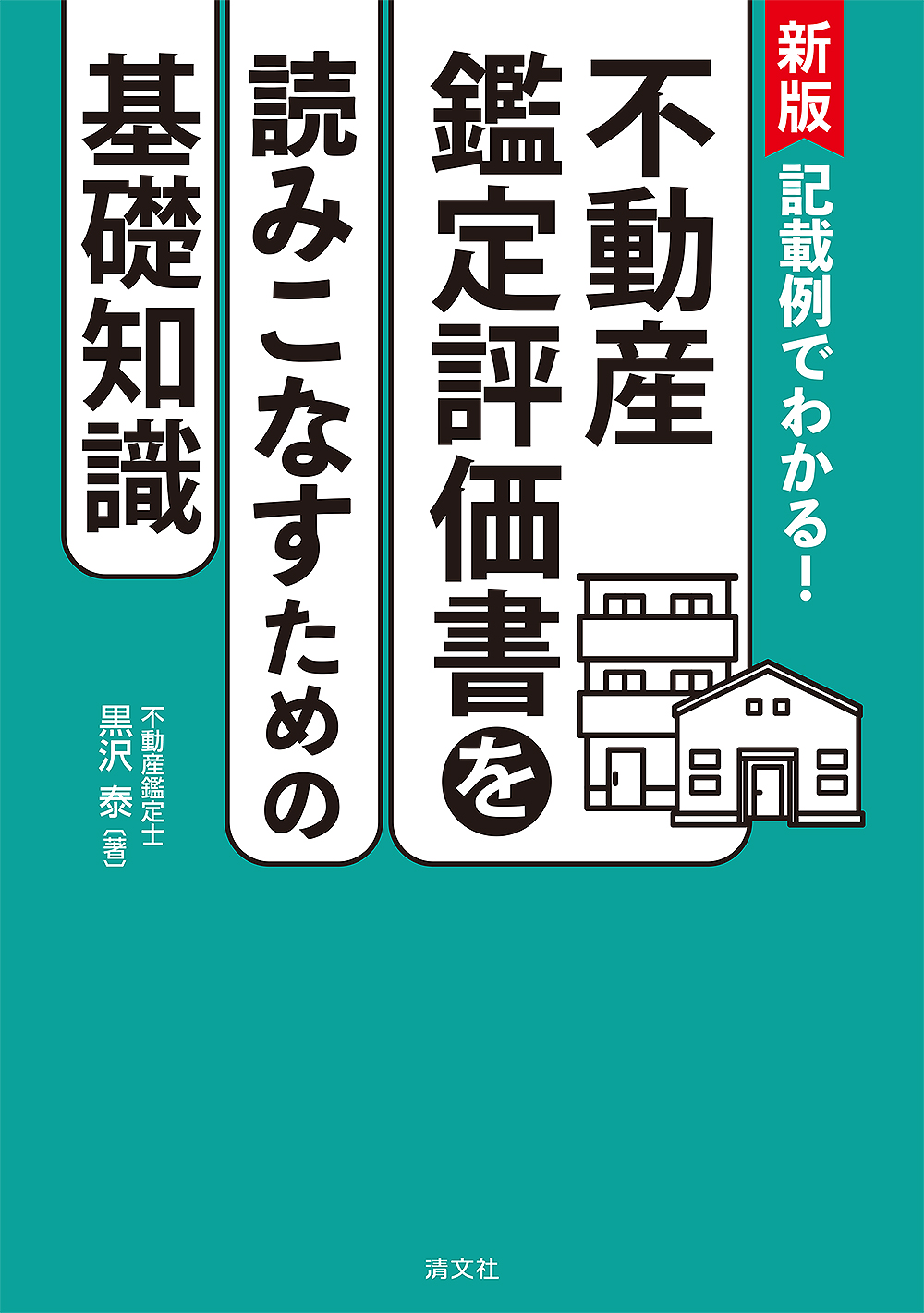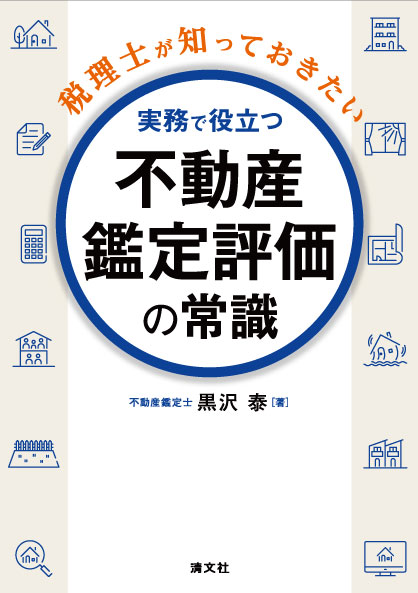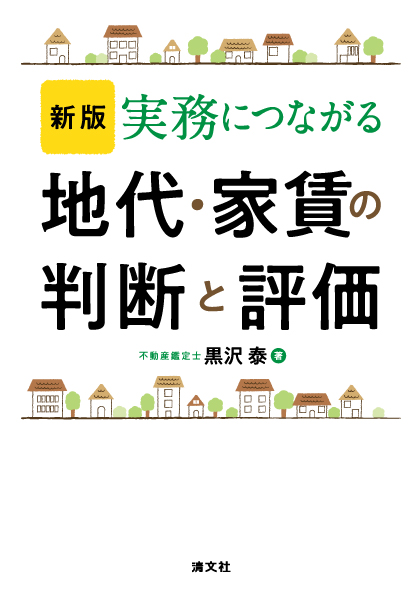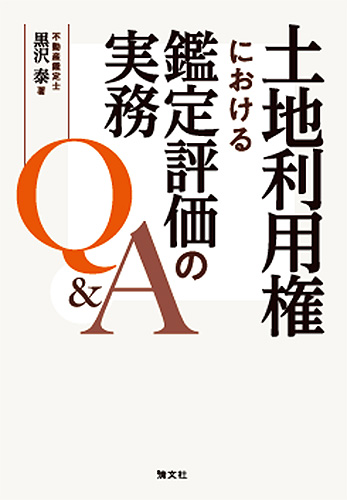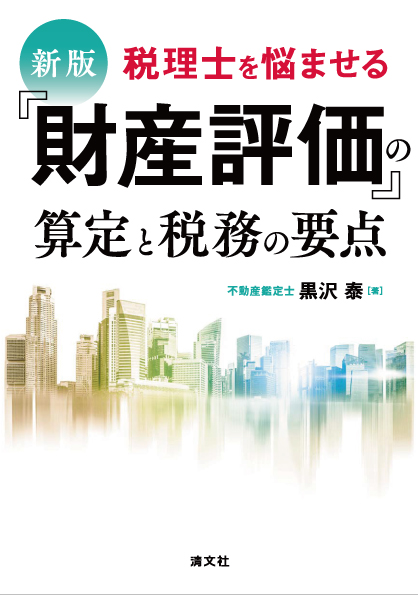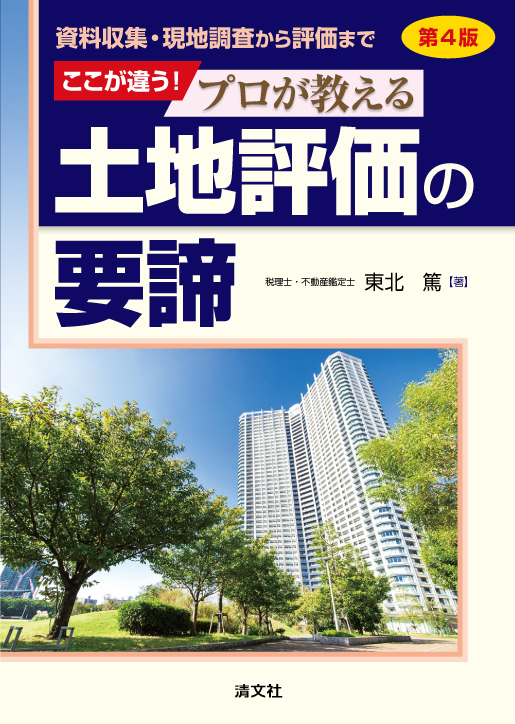税理士が知っておきたい
不動産鑑定評価の常識
【第41回】
「鑑定評価における条件とは」
~条件の設定はどのような場合に許されるか~
不動産鑑定士 黒沢 泰
1 はじめに
鑑定評価額は評価の前提条件により異なってくる場合があります。
同じ土地を評価するにしても、例えば、隣接土地の所有者が購入する場合とそれ以外の不特定の人が購入する場合とでは、価格が異なっても何ら不合理でないケースがあります。
仮に、評価対象地の隣接土地が形状の悪い土地であったとします。隣接土地の所有者が対象地を買い取って一体利用することにより、もともと所有していた土地が形状の良い土地の一部となり、使い勝手も著しく向上するということになれば、他の人よりも少々割高な価格で購入しても損はないといえます。
このように、「隣接者が購入することを前提とした場合の価格は〇〇〇〇万円」であるとか、「市場において不特定多数の人が購入を検討する場合の価格は〇〇〇〇万円」であるという具合に、条件次第で評価額が異なることがあり得る点に鑑定評価の特徴があります。
今までの連載では、「鑑定評価の条件」そのものに関しては立ち入った説明をしてこなかったため、今回、その意義を改めて振り返ってみたいと思います。
この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員登録およびログインが必要です。
すでに会員登録をされている方は、下記ボタンからログインのうえ、ご覧ください。
Profession Journalのすべての記事をご覧いただくには、「プレミアム会員(有料)」へのご登録が必要となります。
なお、『速報解説』については「一般会員(無料)」へのご登録でも、ご覧いただけます。
※他にもWebセミナー受け放題のスーパープレミアム会員などがございます。
会員登録がお済みでない方は、下記会員登録のボタンより、ご登録のお手続きをお願いいたします。