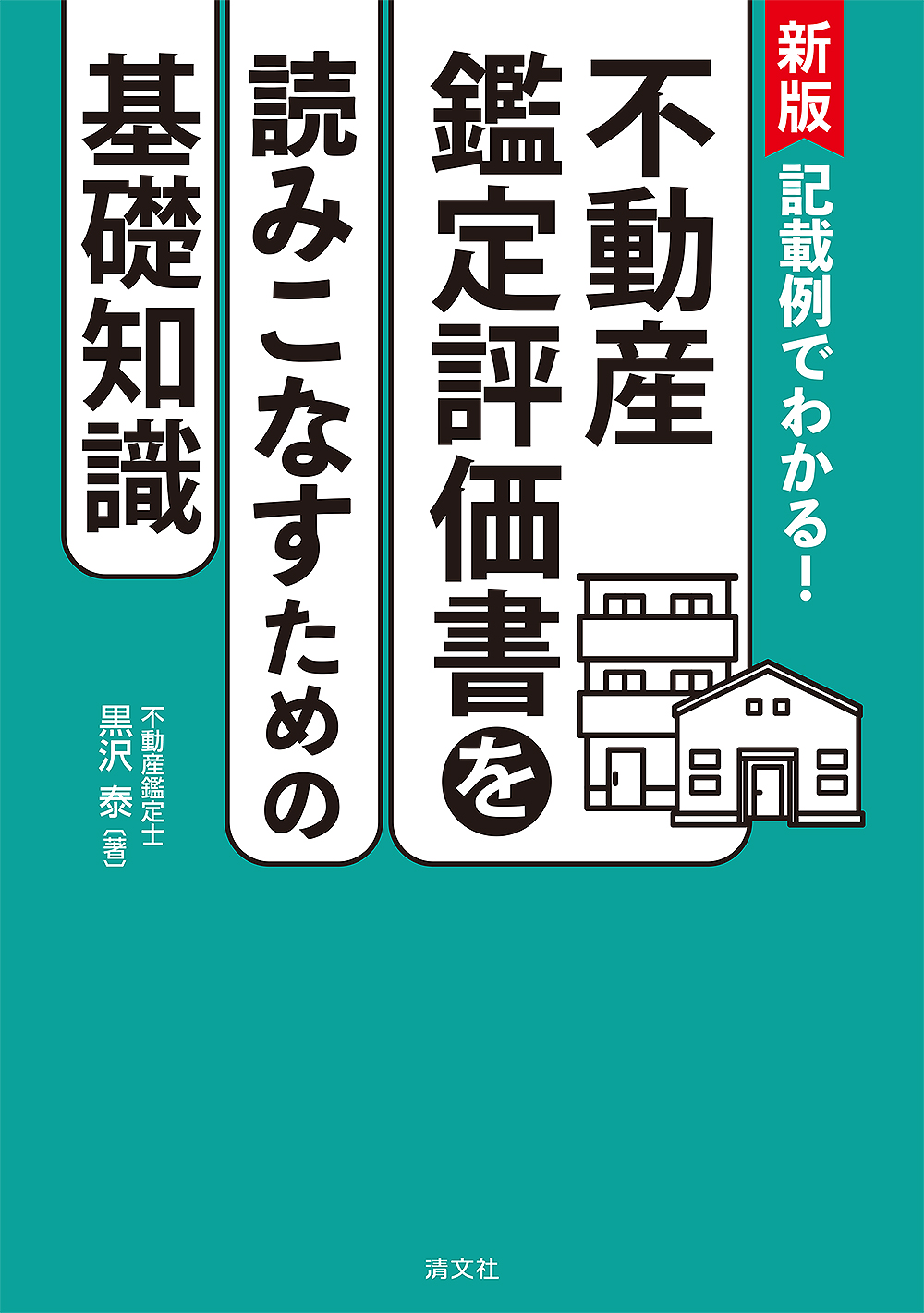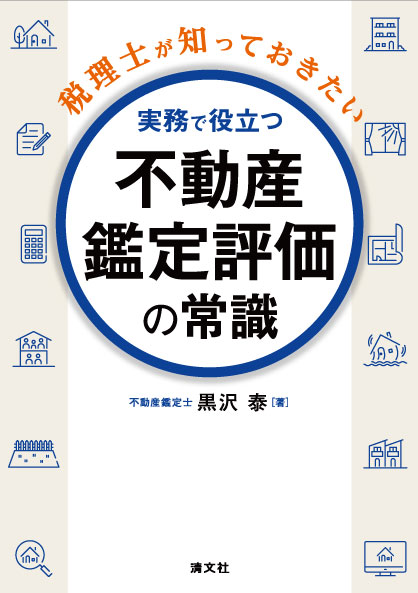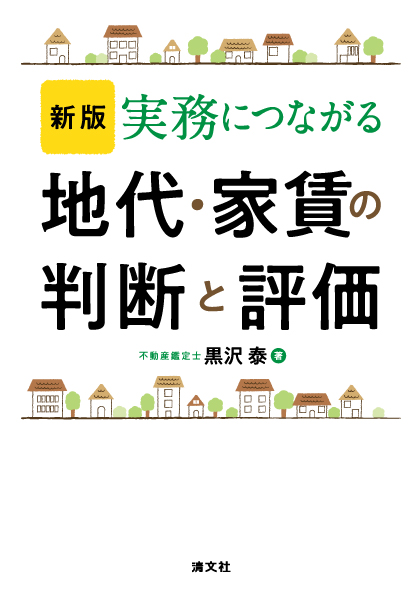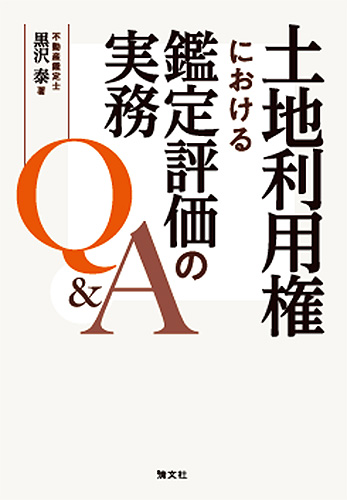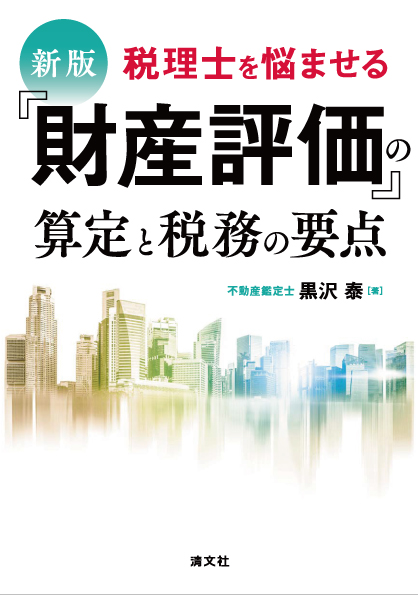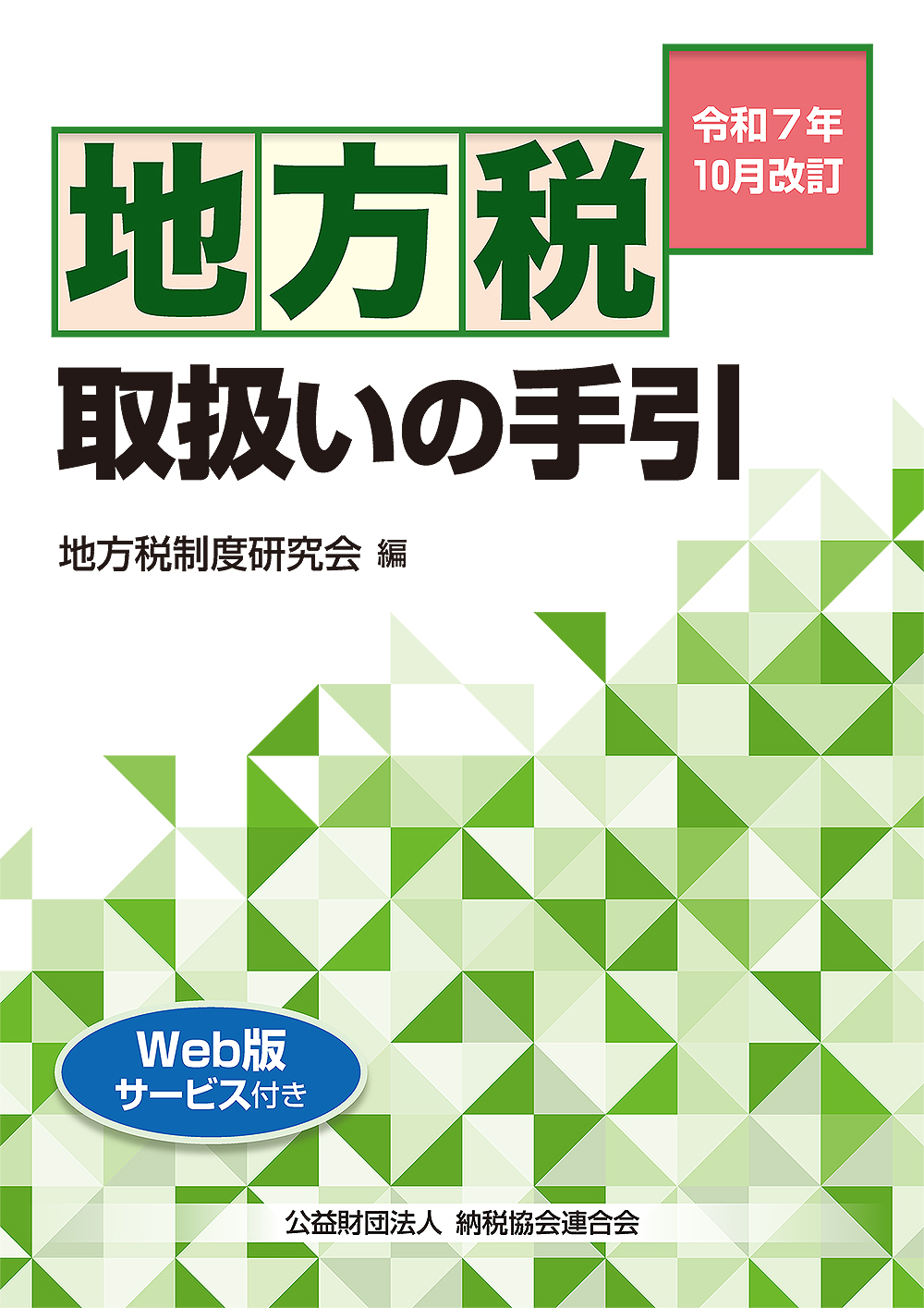税理士が知っておきたい
不動産鑑定評価の常識
【第48回】
「減価の査定にそれなりの判断を伴う土地(その2)」
~地上阻害物(高速道路、鉄道高架線、高圧線等)が存在する場合~
不動産鑑定士 黒沢 泰
1 はじめに
前回は、減価の査定にそれなりの判断を伴う土地の1回目として、地下阻害物(地下鉄等)が存在する土地の評価について取り上げました。
ところで、土地利用に影響を与える阻害物と呼ばれるものは地下だけでなく、地上にも存在します。例えば、高速道路、鉄道高架線、高圧線等がこれに該当します。対象地の近くにこのような阻害物があったり、高架下を建物の敷地の用に供したりしている場合には様々な影響を受け、利用価値が低下していることが多いといえます。
そこで、今回は、地上阻害物が存在する土地の評価について取り上げます。
この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員登録およびログインが必要です。
すでに会員登録をされている方は、下記ボタンからログインのうえ、ご覧ください。
Profession Journalのすべての記事をご覧いただくには、「プレミアム会員(有料)」へのご登録が必要となります。
なお、『速報解説』については「一般会員(無料)」へのご登録でも、ご覧いただけます。
※他にもWebセミナー受け放題のスーパープレミアム会員などがございます。
会員登録がお済みでない方は、下記会員登録のボタンより、ご登録のお手続きをお願いいたします。