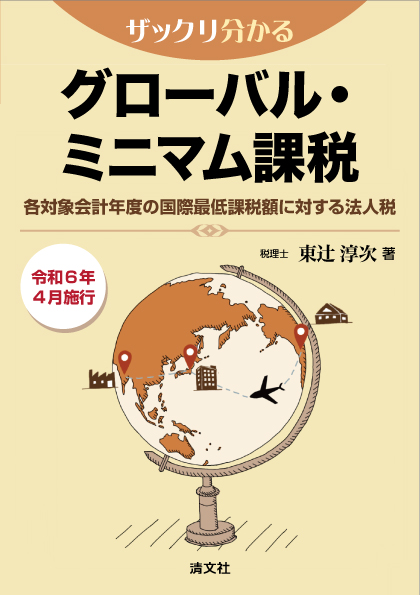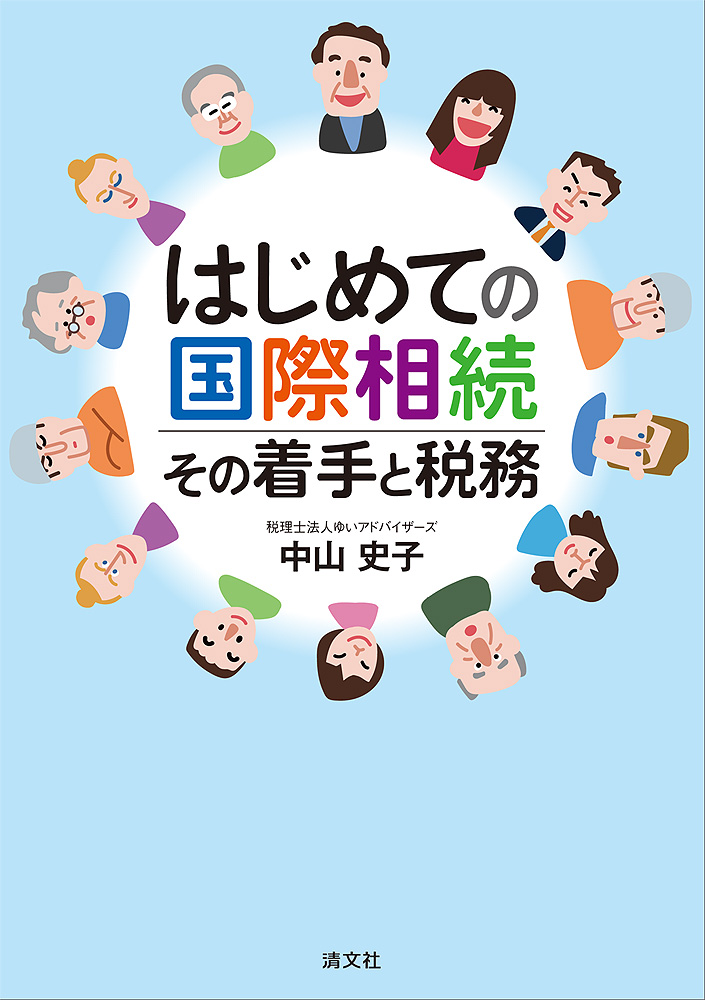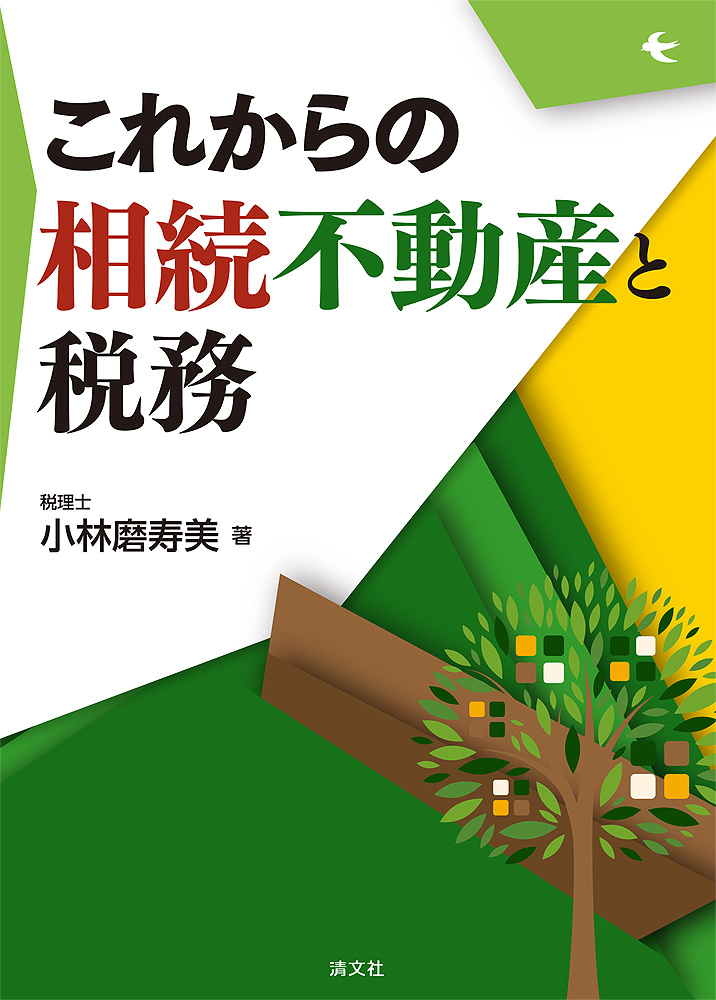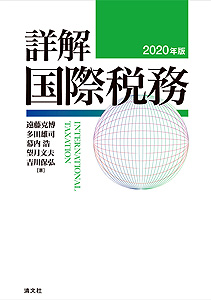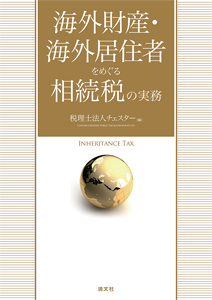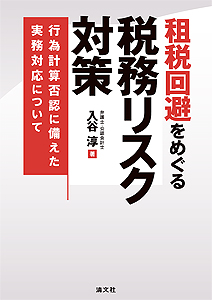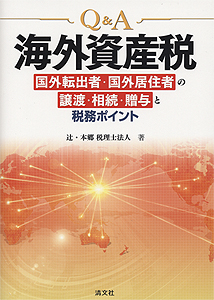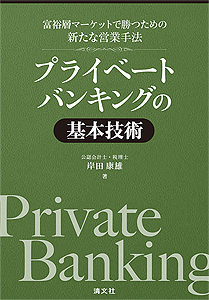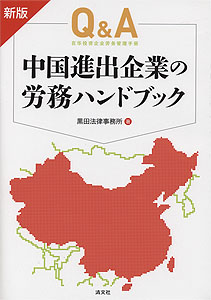これからの国際税務
【第1回】
「変化する国際税務の焦点」
早稲田大學大学院会計研究科 教授
青山 慶二
1 グローバル化の進展と税制
近年の経済のグローバル化の特徴は、①国際経済取引の担い手である多国籍企業間の激しい競争と、②国際取引におけるサービスの比重の拡大である。
これら2つの進展は、国際課税ルールの有効性に深刻な疑問を呈する要因となった。
すなわち、前者の要因からは、各国の財政主権の下で協調が十分に進展しない所得課税法制の良いところ取りをする多国籍企業が、事業体の立地選択などを利用して二重非課税を狙うアグレッシブな租税回避行動を拡大することになったのであり、また後者の要因からは、IT技術や人的資源などの付加価値の国境を越える移転取引(専門的役務提供や無形資産の供与等)に対する伝統的課税ルールの硬直性を利用した源泉地国での課税漏れ狙いのスキームを跋扈させてきたのである。
これら2つの課題に対し、企業の健全な国際競争条件を取り戻し、かつ、税源を侵食された国に正当な税収を回復させる目的で取り組まれてきたのが、G20/OECDによる「BEPS(税源浸食・利益移転)プロジェクト」と「税の透明性を促進するプロジェクト」であった。
両プロジェクトは、2015~2016年にかけて国際協調の下に実行する処方箋をまとめた報告書を採択し、現在は、強力な政治的なイニシアティブに基づき、各国が税制改正や条約改定に取り組んでいる。
これらにより、第2次大戦後約70年にわたって君臨してきた「旧OECD型レジーム」とも呼ぶべき国際課税のスタンダードが、実体法と手続法の両面で大幅に更新される見込みである。
本連載では今後、新しい国際課税スタンダードを項目別に順次紹介する予定であり、初回では、まず両プロジェクトの改革理念のエッセンスを概説する。
2 国際的租税回避防止に向けた税制の調和
BEPSプロジェクトは、租税回避行為に対する耐久力劣化が目立つ「旧OECD型レジーム」の主として実体法に着目したオーバーホール作業である。
実体法ルールでは、特に、デジタル経済の進展によるサービス・無形資産取引の変容に対応できる課税ルール見直しに焦点を当て、移転価格税制、タックスヘイブン税制などの抑止措置並びに租税条約の濫用への対応措置等につき改正案を提示している。ただし、改正案の提示に当たっては、各国の租税政策のニュアンスの違いを尊重して、一本化した処方箋のみならず、「ベストプラクティス」や参照すべき「共通アプローチ」を提示しながら、その中で一定の選択肢を各国に許容する方式も項目によっては採用している。
なお、過去1世紀にわたって国際課税の基本理念として信奉されてきた「独立企業原則」及び「事業所得の閾値としての恒久的施設要件」そのものは保持されており、ルールの更新はその実施に向けたガイダンスの追加や修正であると整理されている。しかし、内容を詳細に検証すると、一般的な利子控除制限の導入や移転価格税制における所得相応性基準の導入、更には、抜本的な条約濫用防止規定の常備化など、伝統的課税理論の外延をはみ出す提案も多く含まれており、近年では最大規模の国際課税ルールの更新パッケージと評価できよう。
併せて、租税回避による税源浸食リスクの測定材料を提供し上記新課税ルールの適用を可能にするために、多国籍企業の国別事業体経営情報や課税当局によるルーリングの開示も新たに求められている。
これらの情報開示は、その後の課税当局によるアクション発動にとって不可欠の前提条件と位置付けられ、2年以内の紛争解決を約束すべしとする勧告と並び、実体法勧告に許容されている選択の幅を含まない「ミニマムスタンダード」という強力な勧告形式をとっている。
3 納税者の税務情報の透明化
2016年4月に存在が公表されたパナマ文書では、外国投資家のタックスヘイブン事業体の設立・管理にかかる法務・財務情報が流出し、低課税国事業体への実体を欠く投資を利用した租税計画のリスクを全世界に、改めて警告することとなった。
折しも、米国市民によるスイスUBS口座を利用した脱税スキャンダル(2008年)に端を発した米国の外国口座税務コンプライアンス法施行をきっかけに、OECDを中心としたグローバルフォーラムにおいて、外国金融口座情報の自動的情報交換に向けた合意が達成され、約100か国により2018年からの情報交換開始が期待される状況であった。
我が国を含めた主要国では情報交換に必要な国内法改正をすでに終えており、交換情報のセキュリティ確保に向けた技術的手当ても行われ、現在実施を待つばかりである。
富裕者による海外への投資を介在する金融口座の取引情報の取得に際しては、スイスにみられた銀行秘密の国内法的制約や条約の不備、更には協調した執行体制の不備により、不当な租税計画を防止する上で深刻な障害に長い間直面してきた。
今回の自動的情報交換が実施されると、多国籍企業の租税回避を防止するBEPS勧告と並んで、高額所得者の国境越え租税回避行為の情報端緒が課税当局に常備されることとなり、けん制効果は絶大なものになると考えられる。
4 当面の課題
“So far, so good”で進行してきた上記の新しい国際協調の潮流に、最近影を差す兆候が表れた。「欧州における英国のEU離脱後の税制協調」と「米国におけるトランプ政権の税制改革」の行方である。
いずれも、自国ファーストの政策を掲げてグローバル協調から離脱するベクトルに向かう懸念があり、せっかく達成されたコンセンサスの実現を困難にする可能性もある。それに加えて、アイルランドを舞台とした米国多国籍企業の租税計画に対するEU委員会の課税権の遡及適用は、国際的な税源獲得競争へ転化するリスクも内包している。
両地域を主要市場としてグローバルビジネスを展開する我が国企業への影響は無視できず、当分の間動向を注視する必要があろう。
(了)
次回は6月の掲載予定です。