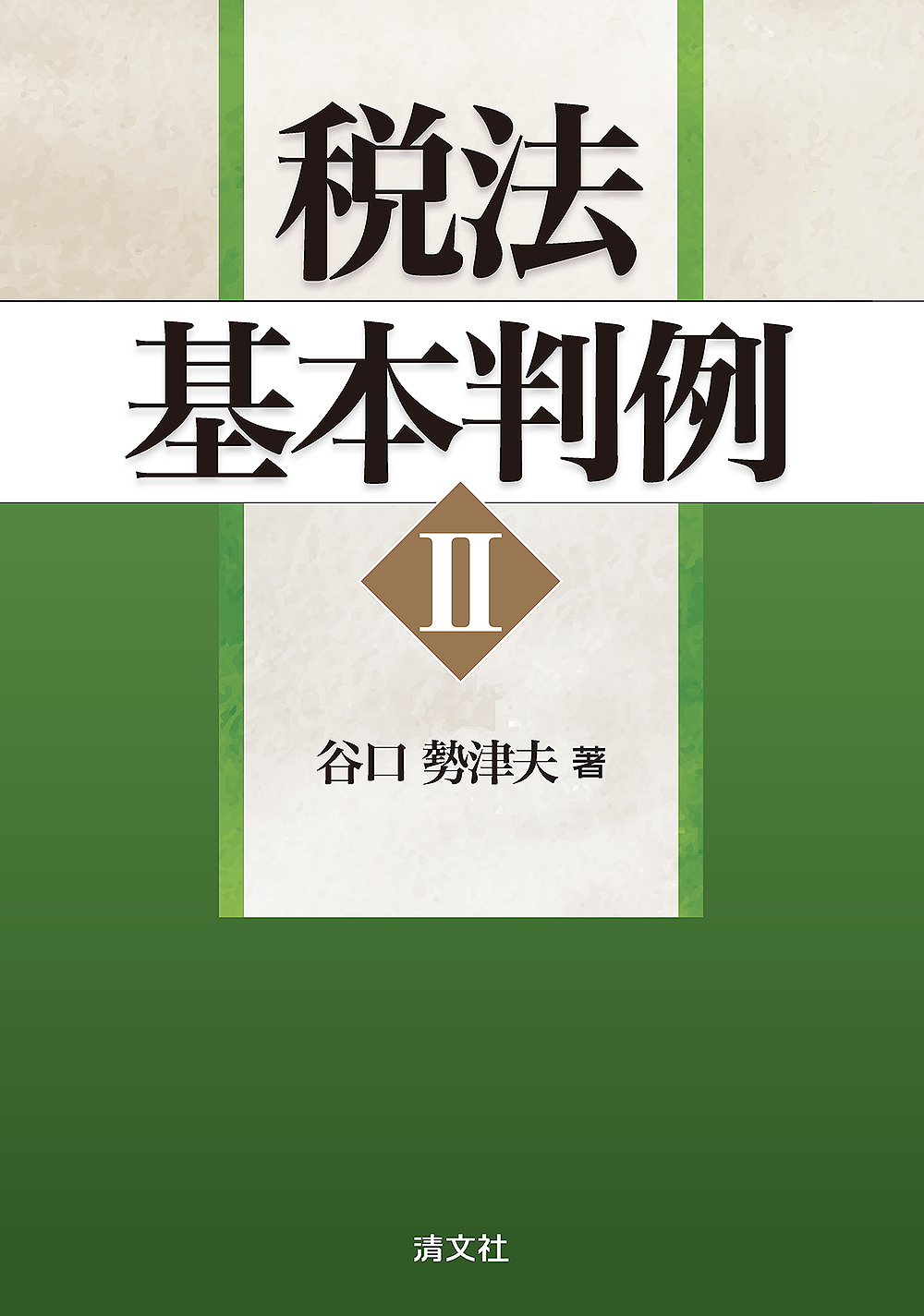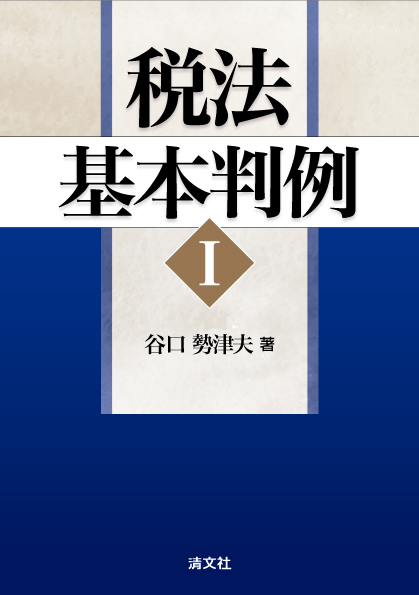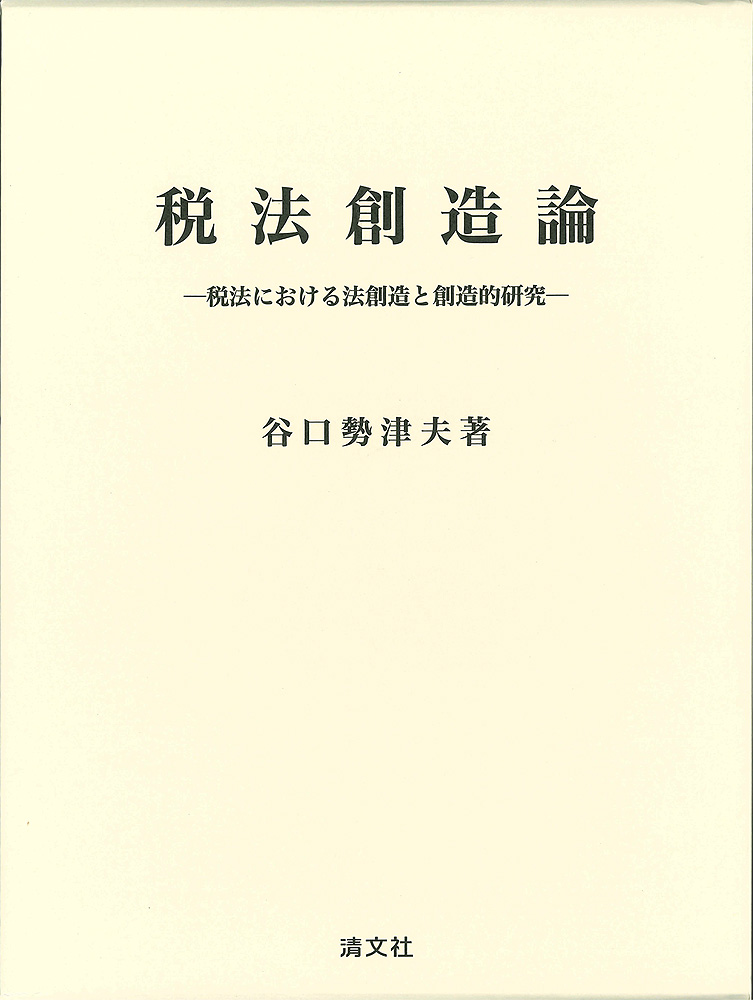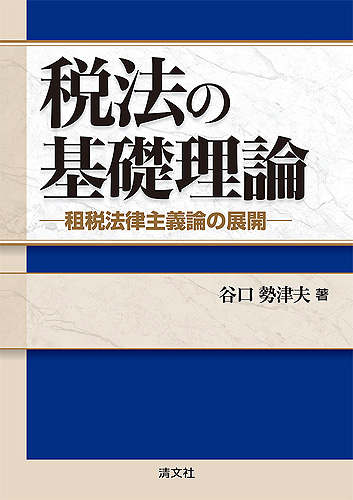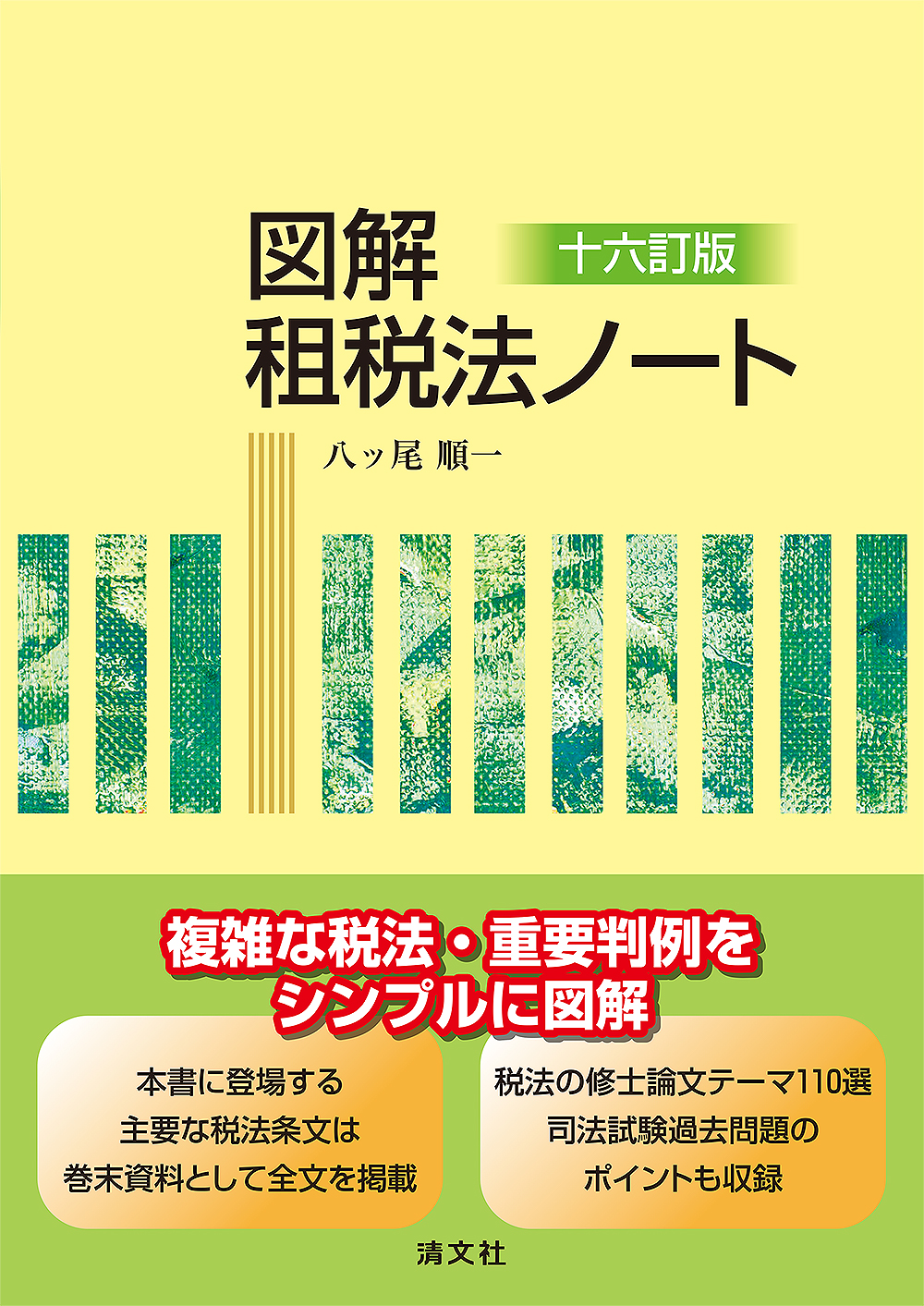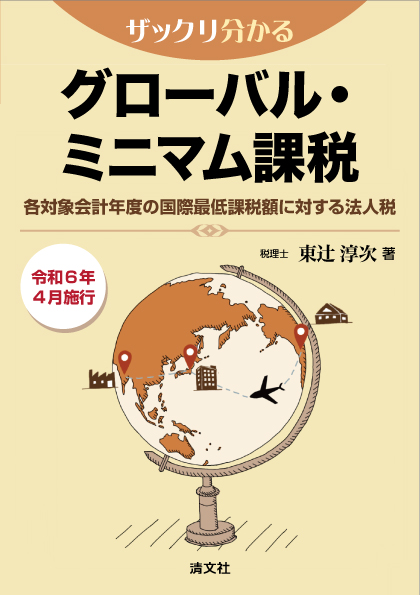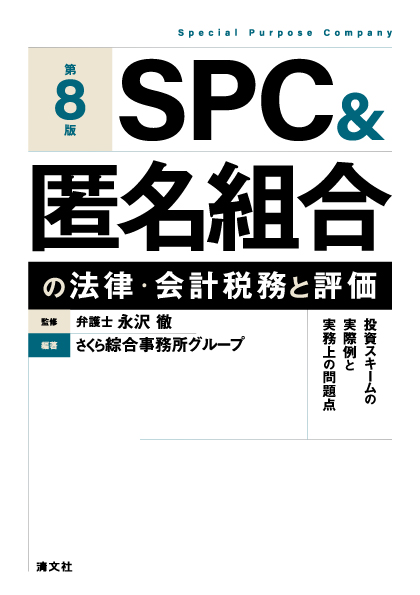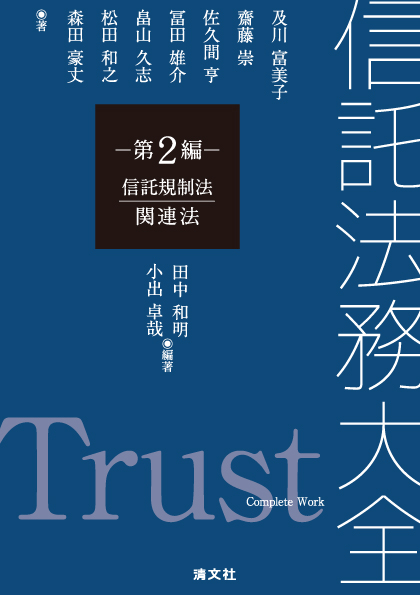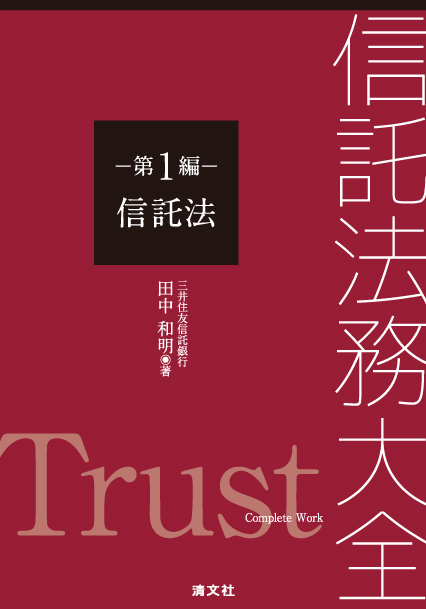谷口教授と学ぶ
税法の基礎理論
【第12回】
「租税法律主義と実質主義との相克」
-税法の目的論的解釈の過形成③-
大阪大学大学院高等司法研究科教授
谷口 勢津夫
Ⅰ はじめに
第7回では、課税減免制度濫用の法理を租税法規の趣旨・目的の法規範化論として性格づけ検討した(第10回も参照)。租税法規の趣旨・目的の法規範化論は、租税法規についてその趣旨・目的を解釈基準としてではなく「規範」そのものとして用いる考え方であるが、これについては、その趣旨・目的を立法資料等に基づき探知・確認し得ることを「前提」にして、目的論的解釈の過形成を検討した。
ところが、税法の目的論的解釈の過形成に関する研究の過程で、そのような「前提」それ自体を問題とせず、いわば「措定」した趣旨・目的を基準として目的論的解釈を行ったものと解される裁判例を「発見」した。それは、信託の利用による贈与税回避スキームの事案に関する名古屋高判平成25年4月3日訟月60巻3号618頁(以下「本判決」という)である。
拙稿「租税回避と税法の解釈適用方法論-税法の目的論的解釈の『過形成』を中心に-」岡村忠生編著『租税回避研究の展開と課題〔清永敬次先生謝恩論文集〕』(ミネルヴァ書房・2015年)1頁、29頁以下では、上記のような「措定」した趣旨・目的を基準として目的論的解釈を行う考え方を「租税法規の趣旨・目的の措定論」と呼び、その観点から本判決について検討を行ったが、以下の叙述は、その検討をベースにして、これに加筆したものである。
本論に入る前に、本判決の内容について本論と関連する要点を整理しておこう。この事件では、相続税法上のみなし贈与財産のうち平成19年度改正前相続税法(以下単に「相続税法」という場合これを指す)4条1項にいう「受益者」の意義が争点の1つであったが、本判決はこの争点について次のとおり判示した。
この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員登録およびログインが必要です。
すでに会員登録をされている方は、下記ボタンからログインのうえ、ご覧ください。
Profession Journalのすべての記事をご覧いただくには、「プレミアム会員(有料)」へのご登録が必要となります。
なお、『速報解説』については「一般会員(無料)」へのご登録でも、ご覧いただけます。
※他にもWebセミナー受け放題のスーパープレミアム会員などがございます。
会員登録がお済みでない方は、下記会員登録のボタンより、ご登録のお手続きをお願いいたします。