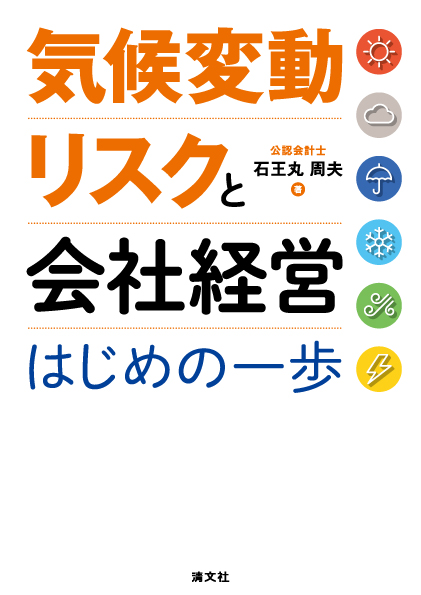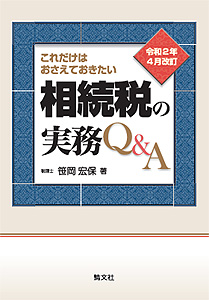各ステップに移動する場合はこちらをクリック
【STEP3】外貨建その他有価証券の評価
時価のある外貨建その他有価証券と時価を把握することが極めて困難と認められる外貨建その他有価証券で検討方法が異なるので、まず時価の有無を検討する必要がある。その後に、時価及び実質価額の低下の程度を検討し、さらに、通常時の評価と減損に分けて検討する。
(1) 時価の有無
(2) 時価の著しい低下の有無
(3) 実質価額の著しい低下の有無
(4) 通常時の評価
① 時価のある外貨建その他有価証券の通常時の評価
② 時価を把握することが極めて困難と認められる外貨建その他有価証券の通常時の評価
(5) 減損
① 時価のある外貨建その他有価証券の減損
② 時価を把握することが極めて困難と認められる外貨建その他有価証券の減損

(1) 時価の有無
時価の有無により、この後の検討過程が異なる。そのため、時価のある外貨建その他有価証券の場合、「(2) 時価の著しい低下の有無」を検討する。時価を把握することが極めて困難と認められる外貨建その他有価証券の場合、「(3) 実質価額の著しい低下の有無」を検討する。
(2) 時価の著しい低下の有無
時価のあるその他有価証券で、時価の著しい低下(【STEP1】(2)①(ⅰ)~(ⅲ)参照)がある場合、減損が必要かどうかの検討が必要となるため、(5)①を検討する。時価の著しい低下がない場合は、(4)①を検討する。
外貨建有価証券の場合、時価が「著しく下落した」かどうかは、外貨建ての時価と外貨建ての取得原価を比較して判断する(外貨実務指針19)。
(3) 実質価額の著しい低下の有無
実質価額が著しく低下している場合(【STEP2】(4)参照)、(5)②を検討する。実質価額が著しく低下していない場合、(4)②を検討する。
外貨建有価証券の場合、実質価額が「著しく下落した」かどうかは、外貨建ての実質価額と外貨建ての取得原価を比較して判断する(外貨実務指針18)。
(4) 通常時の評価
時価のある外貨建その他有価証券と時価を把握することが極めて困難と認められる外貨建その他有価証券では、通常時の評価方法も異なる。
① 時価のある外貨建その他有価証券の通常時の評価
時価のあるその他有価証券は、時価をもって貸借対照表価額とする(基準18)。決算時の円貨額は、原則として外貨による時価を決算時の為替相場により換算する(外貨実務指針15)。
時価と取得価額の差額である評価差額は、全部純資産直入法又は部分純資産直入法のいずれかの方法により、税効果を考慮の上、貸借対照表に「その他有価証券評価差額金」として計上する。原則は、全部純資産直入法であるが、継続適用を条件として部分純資産直入法を適用することもできる。また、株式、債券等の有価証券の種類ごとに両方法を区分して適用することも認められる(以下は、全部純資産直入法を前提に解説する。基準18、実務指針73)。
(ⅰ) 全部純資産直入法
→ 評価差額の合計額を純資産の部に計上する方法
(ⅱ) 部分純資産直入法
→ 時価が取得原価を上回る銘柄に係る評価差額は純資産の部に計上し、時価が取得原価を下回る銘柄に係る評価差額は当期の損失として処理する方法
決算時の為替相場で換算した際の換算差額も「その他有価証券評価差額金」として計上する(外貨建実務指針16)。
ただし、時価のある外貨建その他有価証券で債券の場合、換算差額を「その他有価証券評価差額金」として計上するのが原則であるが、容認処理として、価額変動リスク部分を「その他有価証券評価差額金」として計上し、為替変動リスク部分を「為替差損益」として計上することも認められる(外貨実務指針16)。
なお、期末に計上した「その他有価証券評価差額金」は翌期首に税効果も含めて、洗い替え処理する(基準18、実務指針73)。
《設例》
外貨建その他有価証券に該当する時価のある債券を保有している。
額面金額と取得価額は同額である。
税効果は考慮しない。
- 取得価額(ドル)・・・100ドル
- 取得時の為替相場・・・100円
- 取得価額(円)・・・10,000円
- 期末時価(ドル)・・・110ドル
- 期末時の為替相場・・・120円
- 期末時価(円)・・・13,200円
(1) 原則処理
![]()
(※1) 期末時価 13,200-取得価額10,000
(2) 容認処理

(※2) (期末時価(ドル)110-取得価額(ドル)100)×期末時の為替相場120円
(※3) (期末時の為替相場120円-取得時の為替相場100円)×取得価額(ドル)100
② 時価を把握することが極めて困難と認められる外貨建その他有価証券の通常時の評価
株式や証券投資信託等の場合、取得原価をもって貸借対照表価額とする(基準19(2))。
債券の場合も原則として、取得原価をもって貸借対照表価額とする。ただし、債券を債券金額より低い価額又は高い価額で取得した場合において、取得価額と債券金額との差額の性格が金利の調整と認められるときは、償却原価法に基づいて算定された価額をもって貸借対照表価額とする(基準16、19(1))。
決算時の円貨額は、上記①と同様に、原則として外貨による取得原価(又は償却原価)を決算時の為替相場により換算する(外貨実務指針15)。
決算時の為替相場で換算した際の換算差額も上記①と同様に「その他有価証券評価差額金」として計上する(外貨建実務指針16)。
ただし、時価を把握することが極めて困難と認められる外貨建その他有価証券で債券の場合、「為替差損益」として計上する(外貨基準一2(2)、外貨実務指針16)。
(5) 減損
減損の検討は、時価のある外貨建その他有価証券と時価を把握することが極めて困難と認められる外貨建その他有価証券で検討過程が異なる。
① 時価のある外貨建その他有価証券の減損
時価のある外貨建その他有価証券における減損の検討は、時価のある外貨建満期保有目的の債券(【STEP1】(2)①参照)や外貨建子会社株式等(【STEP2】(7)①参照)と同様である。
② 時価を把握することが極めて困難と認められる外貨建その他有価証券の減損
時価を把握することが極めて困難と認められる外貨建その他有価証券の場合、債券と株式でその検討過程が異なる。
(ⅰ) 時価を把握することが極めて困難と認められる外貨建その他有価証券(株式)の減損
時価を把握することが極めて困難な外貨建その他有価証券(株式)は、株式発行会社の財政状態の悪化により実質価額が著しく低下したときは、減損処理を行う。ただし、時価を把握することが極めて困難と認められる外貨建その他有価証券(株式)の実質価額について、回復可能性が十分な証拠によって裏付けられる場合には、減損処理をしないことも認められる(実務指針92)。
減損処理を行った場合、外貨建ての実質価額を決算時の為替相場により円換算し、この場合に生じる換算差額は、為替差損益ではなく、当期の有価証券の評価損として処理する(外貨実務指針18)。
ここでは、(イ)財状状態の悪化、(ロ)実質価額の著しい低下、(ハ)減損の判定を検討する必要がある。
(イ) 財政状態の悪化の判定
財政状態とは、原則として資産等の時価評価に基づく評価差額等を加味して算定した1株当たりの純資産額をいう。「財政状態の悪化」とは、この1株当たりの純資産額が、当該株式を取得したときのそれと比較して相当程度下回っている場合をいう(実務指針92)。
相当程度下回っているとは、どの程度かが基準等で定められていないため、各社で相当程度下回っている場合を決定する必要がある。
なお、財政状態の悪化がなくても、減損処理が必要な場合(下記(ハ)参照)があるため、財政状態が悪化しているか否かに関わらず、下記(ロ)、(ハ)を検討する必要がある。
(ロ) 実質価額の著しい低下の判定
上記(3)より、すでに実質価額の著しい低下があると判定されているため、ここで改めて判定する必要はない。
(ハ) 減損の判定
上記(イ)、(ロ)より、財政状態の悪化により実質価額が著しく低下している場合には、減損処理を行う。なお、特定のプロジェクトのために設立された会社で、中長期の事業計画等を入手することが可能な場合、当該事業計画等において、開業当初の累積損失が一定期間経過後に解消されることが合理的に見込まれており、かつ、その後の業績が当該事業計画等を大幅に下回っていなければ、当該会社の株式の実質価額の下落は恒久的なものではないとして、減損処理の対象としないことができる(Q&A Q33、実務指針92)。
また、財政状態の悪化がなくても、以下のような場合、実質価額の著しい低下のみで減損処理を行う。
企業買収においては、会社の超過収益力や経営権等を反映して、財務諸表から得られる1株当たり純資産額に比べて相当高い価額で当該会社の株式を取得することがある。その後、超過収益力等が減少したために実質価額が大幅に低下することがある。このような場合には、たとえ発行会社の財政状態の悪化がないとしても、将来の期間にわたってその状態が続くと予想され、超過収益力が見込めなくなった場合には、実質価額が取得原価の50%程度を下回っている限り、減損処理をしなければならない(Q&A Q33)。
【補足:子会社等でない場合の投資損失引当金】
特定のプロジェクトのために設立された会社や事業投資会社等で、当該会社の経営に参画すること等により、子会社等と同程度に株式の実質価額の回復可能性等を判定できる会社の株式についても投資損失引当金の計上を検討する(取扱い3.(2))。
(ⅱ) 時価を把握することが極めて困難と認められる外貨建その他有価証券(債券)の減損
時価を把握することが極めて困難と認められる外貨建その他有価証券(債券)の減損の検討は、【STEP1】(2)②と同様に、償却原価法を適用した上で、債権の貸倒見積高の算定方法に準じて信用リスクに応じた償還不能見積高を算定し、会計処理を行う(実務指針93)。
したがって、時価を把握することが極めて困難と認められる外貨建その他有価証券(債券)を期末時の為替相場で換算(換算差額は為替差損益)した上で、償還不能見積高を算定する。
また、償還不能見積高の算定は、原則として、個別の債券ごとに行う(実務指針93)。
* * *
以上、5つのステップをまとめたフロー・チャートを再掲する。
※画像をクリックすると、別ウィンドウでPDFが開きます。

(了)
「フロー・チャートを使って学ぶ会計実務 」は、毎月最終週に掲載されます。