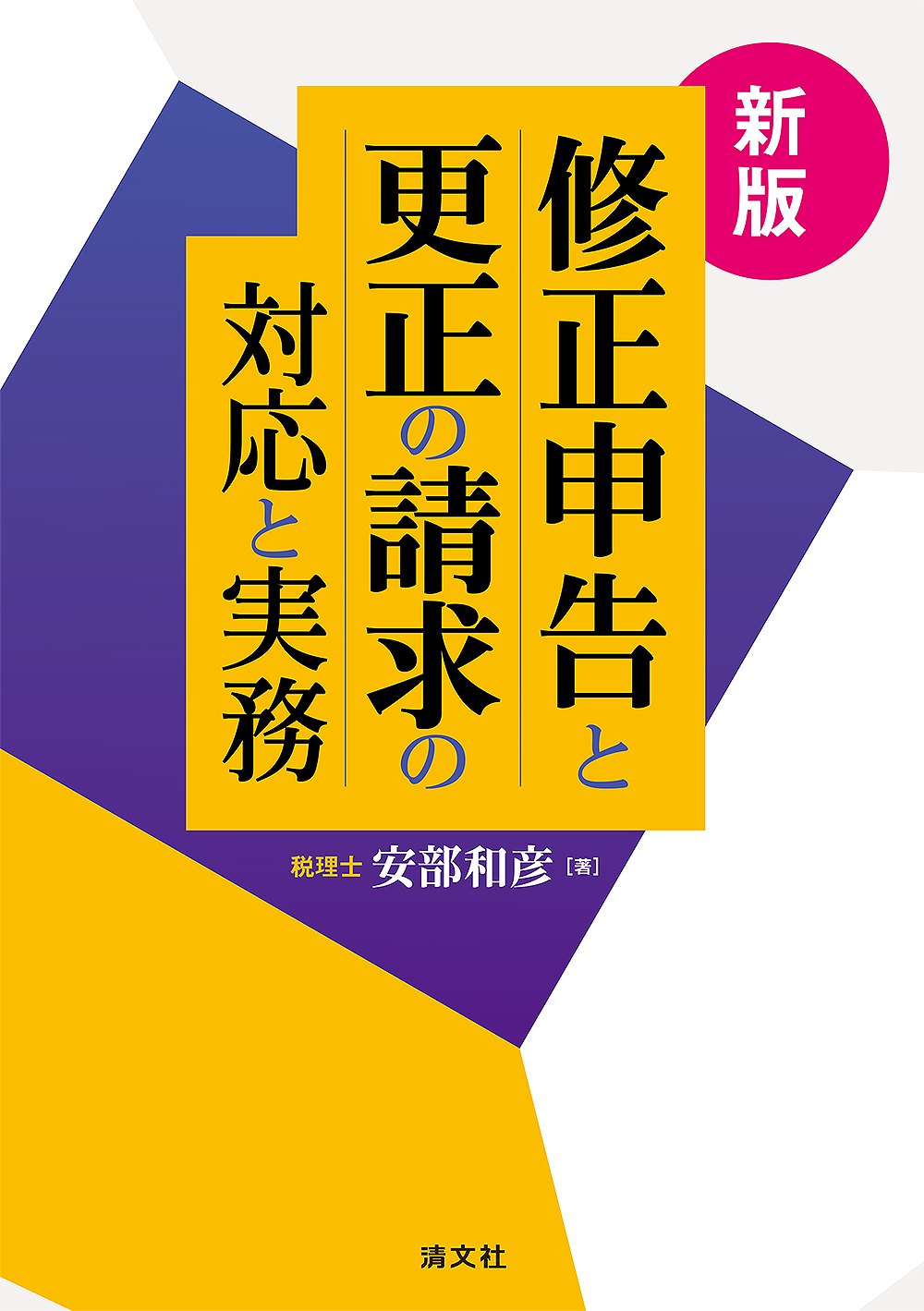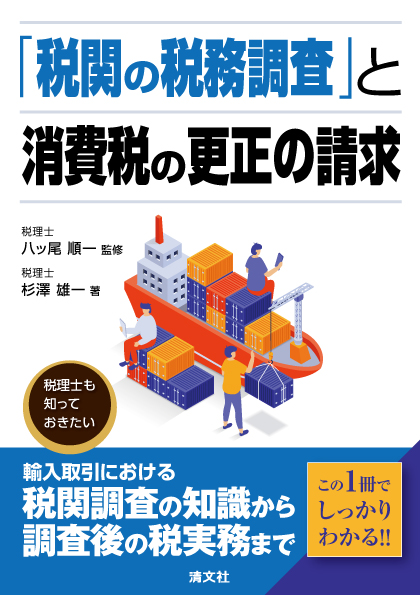〔顧問先を税務トラブルから救う〕
不服申立ての実務
【第8回】
「実質審理に入る前の国税不服審判所の手続」
公認会計士・税理士 大橋 誠一
1 形式審査
(1) 形式審査の意義
形式審査とは、審査請求が法令に定める手続に従って適法にされたか否かについての手続要件の審査である。
審査請求書を受理した場合には、審査請求書の副本を原処分庁に送付するとともに、原処分庁に形式審査に必要な書類の提出を求め、その審査請求事件の担当審判官及び分担者として指定されることが予定される者を形式審査担当者に指名し、その形式審査担当者により形式審査が行われる。
この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員登録およびログインが必要です。
すでに会員登録をされている方は、下記ボタンからログインのうえ、ご覧ください。
Profession Journalのすべての記事をご覧いただくには、「プレミアム会員(有料)」へのご登録が必要となります。
なお、『速報解説』については「一般会員(無料)」へのご登録でも、ご覧いただけます。
※他にもWebセミナー受け放題のスーパープレミアム会員などがございます。
会員登録がお済みでない方は、下記会員登録のボタンより、ご登録のお手続きをお願いいたします。