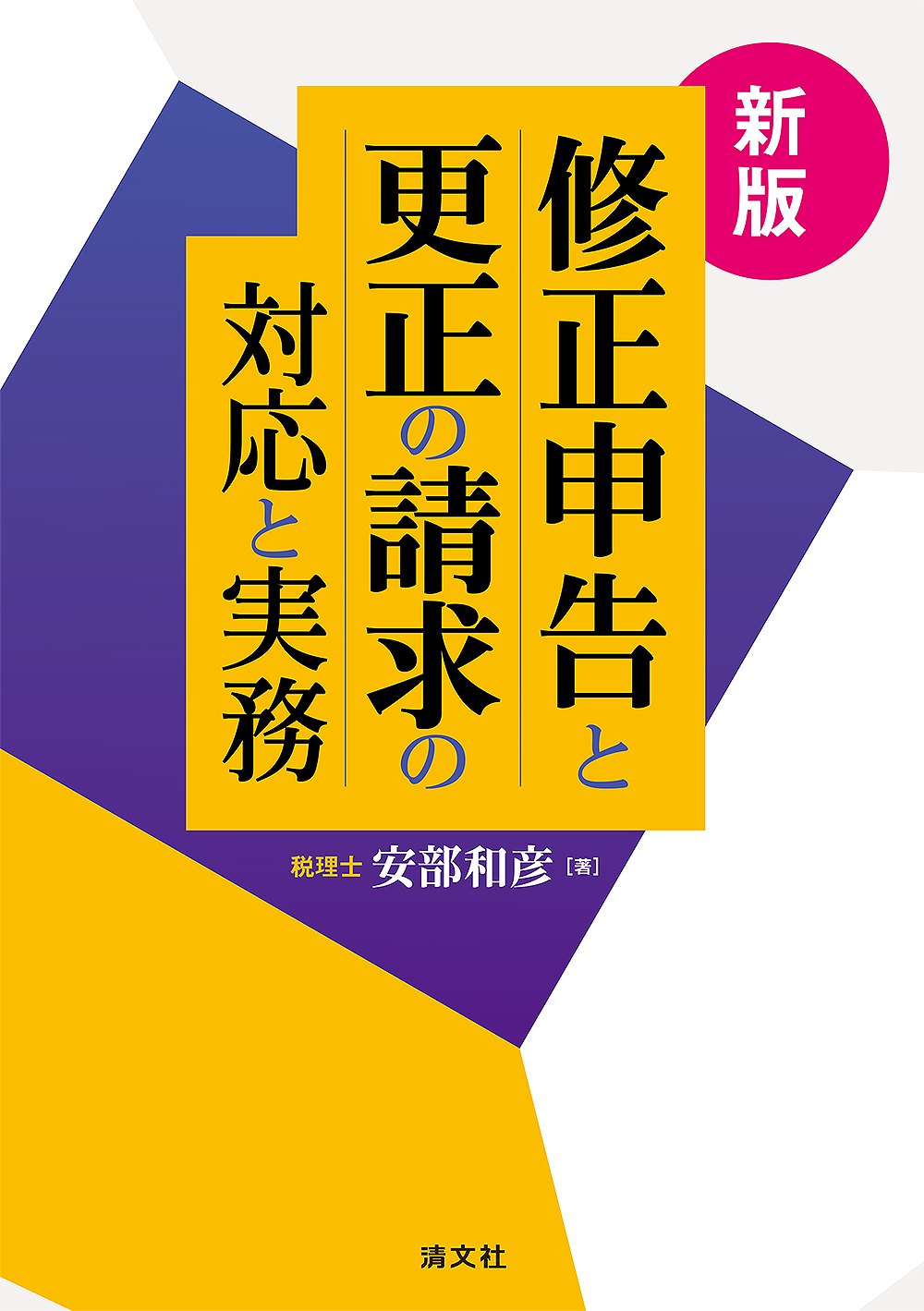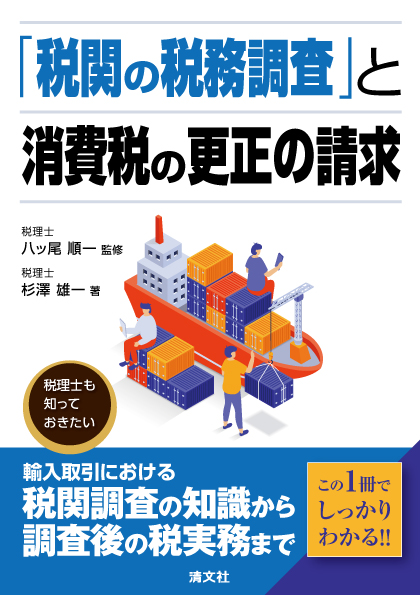〔顧問先を税務トラブルから救う〕
不服申立ての実務
【第16回】
「請求人面談の留意点(その2)」
公認会計士・税理士 大橋 誠一
1 釈明陳述録取書と質問調書
(1) 主張と証拠は別々の書面に著される
担当審判官は、質問採取手続の結果を可視化するために、審査請求人の主張に関する回答については釈明陳述録取書に、主張を裏付けるための証拠としての回答については質問調書に分けて作成することになる。
このうち、釈明陳述録取書は主張書面であることから、相手方である原処分庁に送付して反論の機会を与えることになる。
一方、質問調書は国税不服審判所の判断のために用いるものであり、原処分庁に内容が共有されることはない。
たとえ原処分庁から閲覧請求があったとしても、質問調書は担当審判官の職権による質問(国税通則法第97条第1項第1号)をもとに作成された書面であり、同号は同法第97条の3第1項の閲覧対象から除外されているためである。
この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員登録およびログインが必要です。
すでに会員登録をされている方は、下記ボタンからログインのうえ、ご覧ください。
Profession Journalのすべての記事をご覧いただくには、「プレミアム会員(有料)」へのご登録が必要となります。
なお、『速報解説』については「一般会員(無料)」へのご登録でも、ご覧いただけます。
※他にもWebセミナー受け放題のスーパープレミアム会員などがございます。
会員登録がお済みでない方は、下記会員登録のボタンより、ご登録のお手続きをお願いいたします。