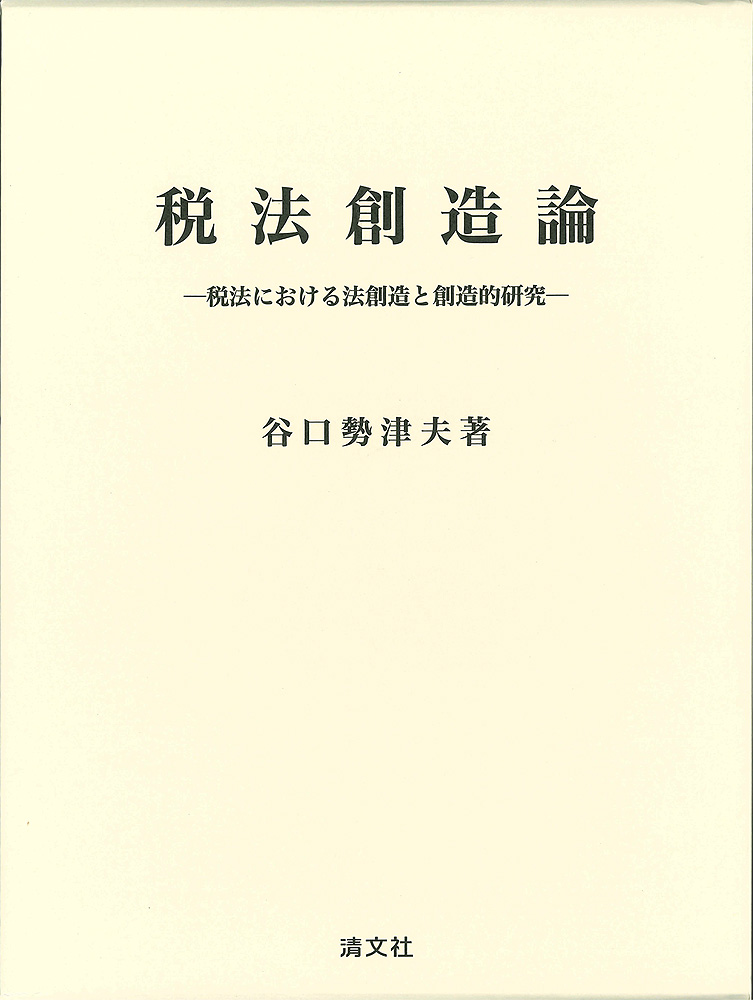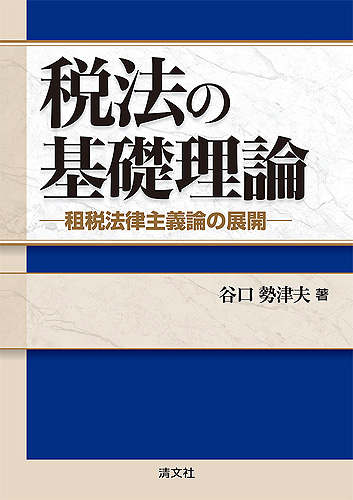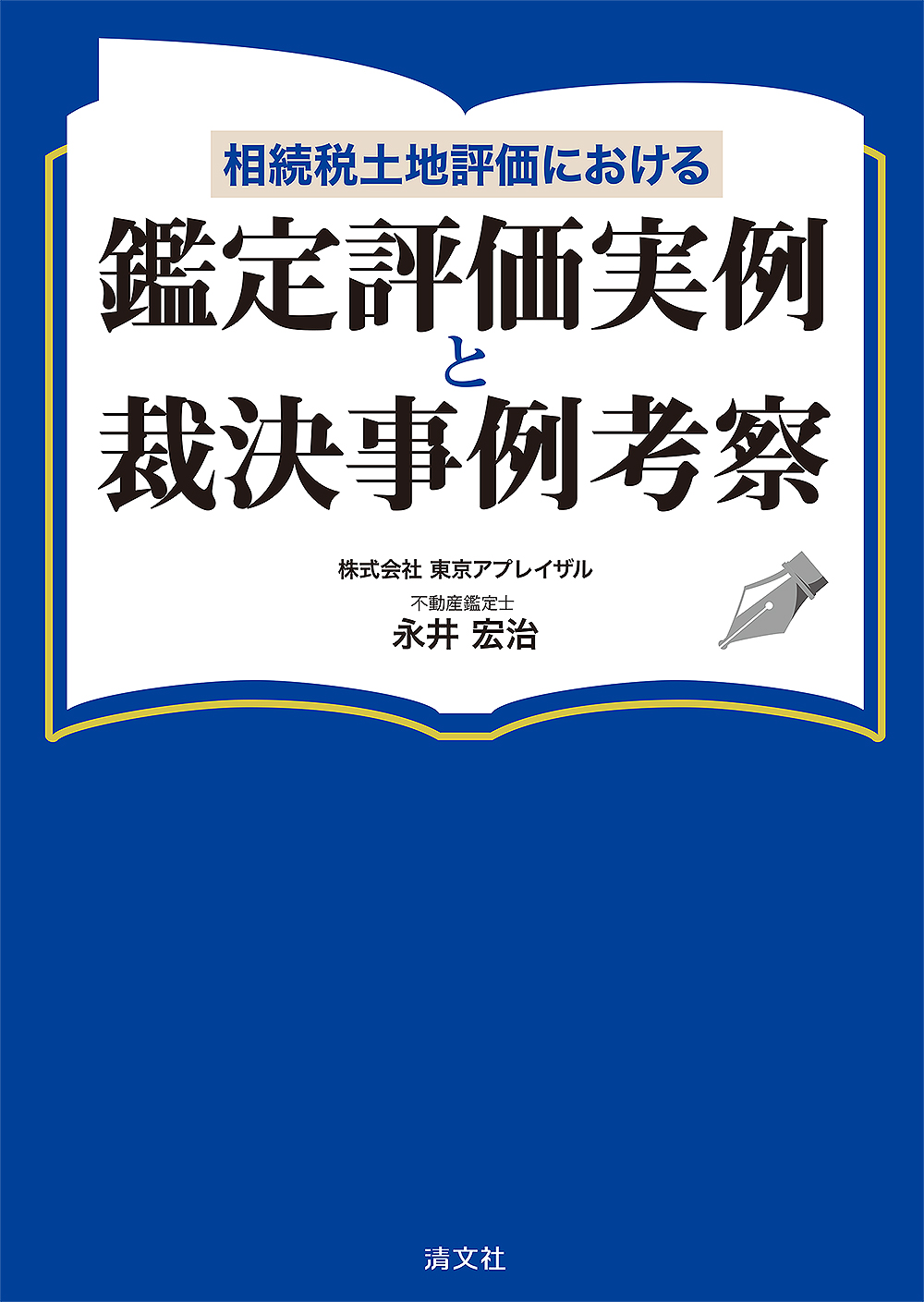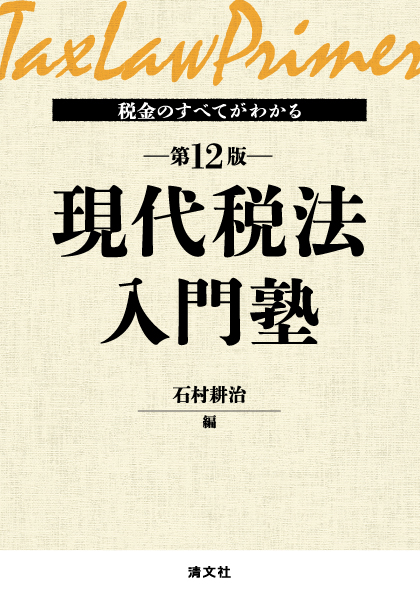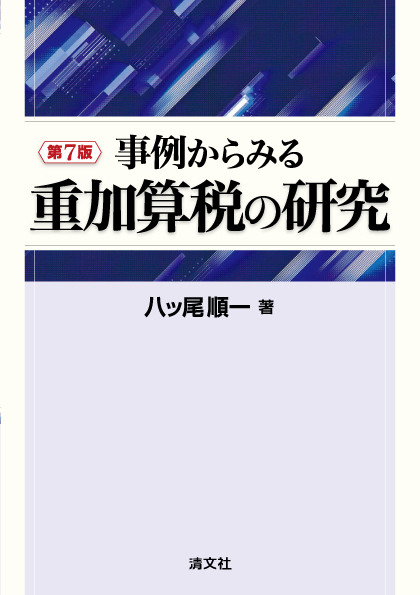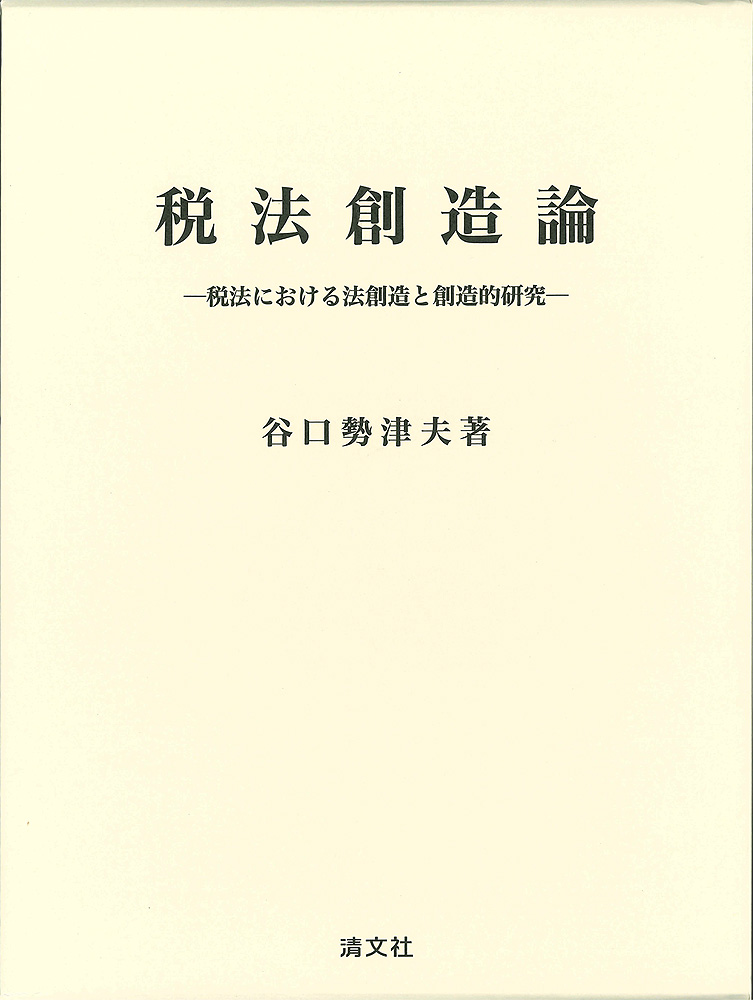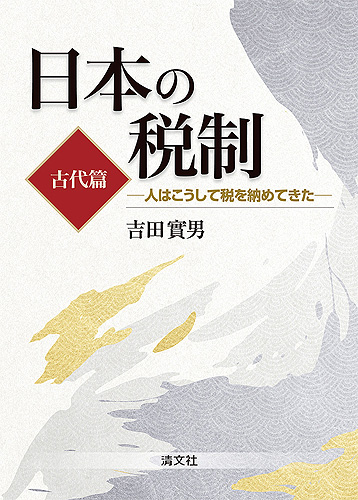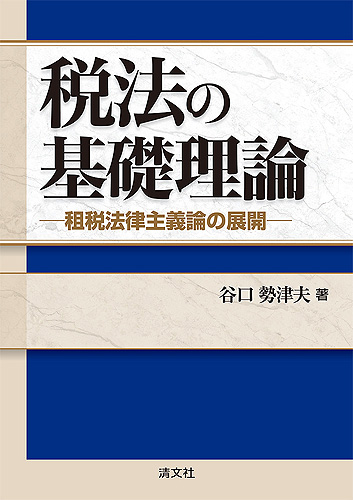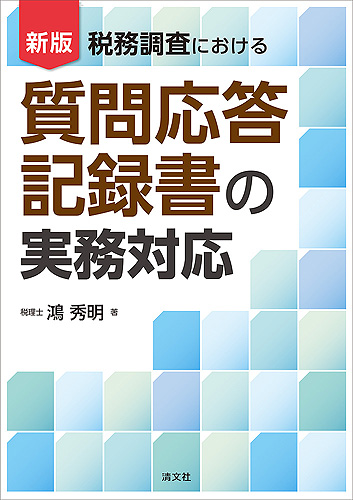谷口教授と学ぶ
税法の基礎理論
【第14回】
「租税法律主義と実質主義との相克」
-税法の目的論的解釈の過形成⑤-
大阪大学大学院高等司法研究科教授
谷口 勢津夫
Ⅰ はじめに
前回は、競馬事件を素材にして、大阪事件・最判平成27年3月10日刑集69巻2号434頁と、これに対する「面従腹背判決」ともいうべき札幌事件・東京地判平成27年5月14日訟月62巻4号628頁について、それぞれの判断枠組みを比較することによって、後者が示した判断枠組みを、文理解釈の「潜脱」による目的論的解釈の過形成として批判的に検討した。ただ、札幌事件では東京地裁の判断は、控訴審・東京高判平成28年4月21日判時2319号10頁及び上告審・最判平成29年12月15日民集71巻10号2235頁で否定され、馬券払戻金の所得区分に関する判例の判断枠組みは、下記のとおり、「文理に照らし」行う解釈(文理解釈)を「起点」とする判断枠組みとして、確立されることになった(下線筆者)。
【大阪事件最判】
営利を目的とする継続的行為から生じた所得であるか否かは、文理に照らし、行為の期間、回数、頻度その他の態様、利益発生の規模、期間その他の状況等の事情を総合考慮して判断するのが相当である。
【札幌事件最判】
営利を目的とする継続的行為から生じた所得であるか否かは、文理に照らし、行為の期間、回数、頻度その他の態様、利益発生の規模、期間その他の状況等の事情を総合考慮して判断するのが相当である(最高裁平成26年(あ)第948号同27年3月10日第三小法廷判決・刑集69巻2号434頁参照)。
前回の検討では、上記の判断枠組みの「起点」を「文理に照らし」行う解釈(文理解釈)として理解し、「終点」に係る判示部分のうち、1つ目の下線部分を「行為の数量的態様」といい、2つ目の下線部分を「行為の客観的利益状況」ということにしたが(前回Ⅱ参照)、今回も前回同様それらの語を用いることにする。
ところで、競馬事件における2つの最高裁判決を受けて、所得税基本通達34-1(2)が2度改正された(税通令6条1項5号も参照)。まず、大阪事件最判を受けて所得税基本通達34-1(2)に平成27年5月改正により注記が追加された(平27課個2-8、課審5-9改正。以下「第一次改正」という)。次に、札幌事件最判を受けて上記注記が平成30年7月に改正された(平30課個2-17、課審5-1改正。以下「第二次改正」という)。
今回は、所得税基本通達34-1(2)に関するこの2度の改正の意味を、税法の目的論的解釈の過形成に関する研究の一環として、検討することにしたい。
この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員登録およびログインが必要です。
すでに会員登録をされている方は、下記ボタンからログインのうえ、ご覧ください。
Profession Journalのすべての記事をご覧いただくには、「プレミアム会員(有料)」へのご登録が必要となります。
なお、『速報解説』については「一般会員(無料)」へのご登録でも、ご覧いただけます。
※他にもWebセミナー受け放題のスーパープレミアム会員などがございます。
会員登録がお済みでない方は、下記会員登録のボタンより、ご登録のお手続きをお願いいたします。