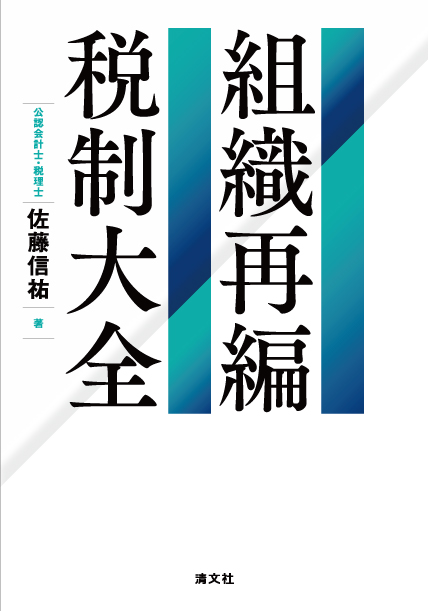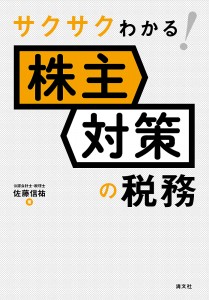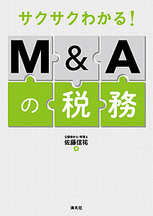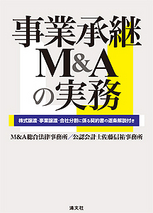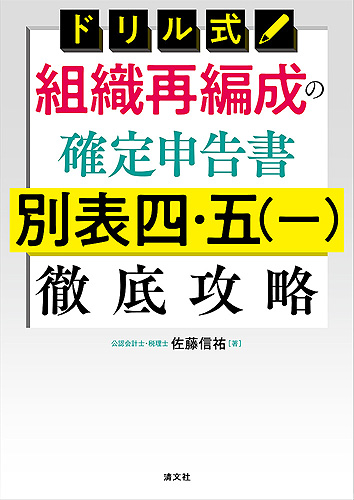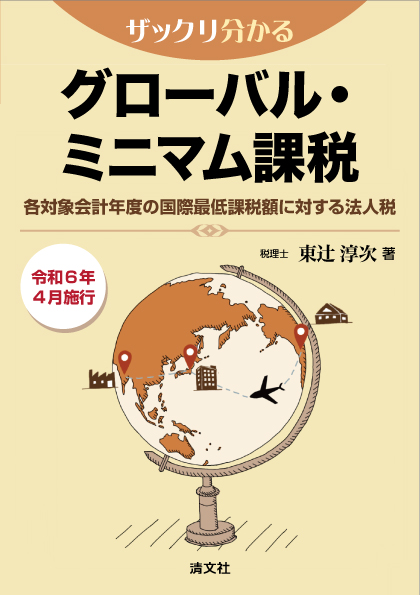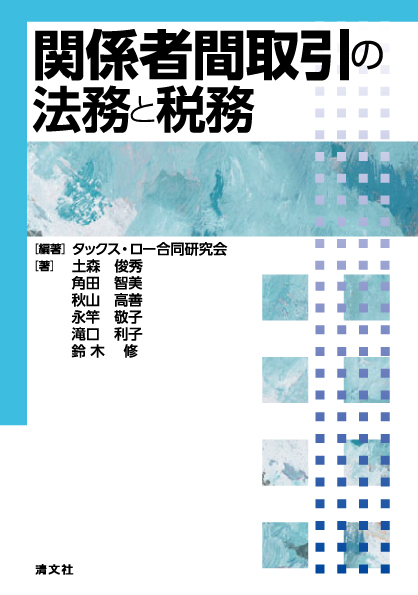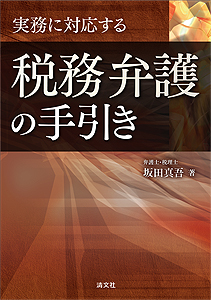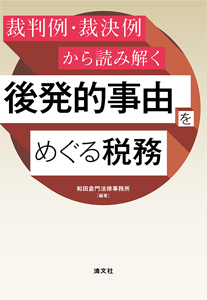包括的租税回避防止規定の
理論と解釈
【第1回】
「最近の税務訴訟の動き」
公認会計士 佐藤 信祐
連載の目次はこちら
なお、実際の検討としては、法人税法132条の2に規定する組織再編における包括的租税回避防止規定のみならず、法人税法132条に規定する同族会社等の行為計算の否認、その他の租税回避否認手法を含めたうえで、総合的な検討を行う予定である。
第1回目にあたる本稿では、最近の租税回避訴訟の動きについて総括したい。
1 最近の租税回避訴訟の動き
ヤフー・IDCF事件では、従来の学説と異なり、法人税法132条の2に規定する包括的租税回避防止規定が適用される場面として、以下のように判示した。
【控訴審判決抜粋】
法132条の2が設けられた趣旨、組織再編成の特性、個別規定の性格などに照らせば、同条が定める「法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるもの」とは、(ⅰ)法132条と同様に、取引が経済的取引として不自然・不合理である場合〔最高裁昭和50年(行ツ)第15号同52年7月12日第三小法廷判決・裁判集民事121号97頁、最高裁昭和55年(行ツ)第150号同59年10月25日第一小法廷判決・裁判集民事143号75頁参照〕のほか、(ⅱ)組織再編成に係る行為の一部が、組織再編成に係る個別規定の要件を形式的には充足し、当該行為を含む一連の組織再編成に係る税負担を減少させる効果を有するものの、当該効果を容認することが組織再編税制の趣旨・目的又は当該個別規定の趣旨・目的に反することが明らかであるものも含むと解することが相当である。このように解するときは、組織再編成を構成する個々の行為について個別にみると事業目的がないとはいえないような場合であっても、当該行為又は事実に個別規定を形式的に適用したときにもたらされる税負担減少効果が、組織再編成全体としてみた場合に組織再編税制の趣旨・目的に明らかに反し、又は個々の行為を規律する個別規定の趣旨・目的に明らかに反するときは、上記(ⅱ)に該当するものというべきこととなる。
そのため、これらの事件の影響から、行為計算否認規定についての解釈が見直されるのではないかという報道も存在する(※1)。
(※1) T&Amaster571号8頁(平成26年)
しかしながら、ヤフー・IDCF事件で国側の立場で書かれた朝長英樹氏の鑑定意見書は、その書かれている立案過程に疑念を示す声もあり(※2)、さらに、ヤフー控訴審判決では、同鑑定意見書に書かれている制度趣旨を一部否定していることから(※3)、制度趣旨を踏まえた解釈が重要になると言われながらも、結局は、立案当初に開示された立案担当者による解説が重要なものとなり、その後に語られたものを根拠とするのであれば、現役の課税当局の者が公式の場で語ったもののみが含まれることになる(※4)。すなわち、考慮すべき制度趣旨についても、組織再編税制の専門家の共通認識を超えることはあり得ない。その意味で、ヤフー控訴審判決は、一応のバランス感覚の取れた判決であったと評価できる。なお、これらの事件の詳細な評釈は、別の連載である「組織再編・資本等取引に関する最近の裁判例・裁決例について」に委ねることとしたい。
(※2) 大淵博義「『法人税法132条の2』の射程範囲と租税回避行為概念」税経通信69巻9号21-22頁(平成26年)
(※3) 佐藤信祐「ヤフー事件高裁判決からみる実務上の留意点」旬刊経理情報1404号37-38頁(平成27年)
(※4) むろん、個別事案によって解釈が異なる可能性があることから、その多くはリスクヘッジのために「私見」であるということになっているものの、税務業務に携わる者からすると、尊重すべきものとされているものは少なくない。
さて、筆者が平成21年に中央経済社より、『組織再編における包括的租税回避防止規定の実務』を出版したときは、包括的租税回避防止規定についての考え方はほとんど示されていなかった。
強いて言えば、平成20年当時税務大学校研究部教授であった清水一夫氏の論文において、行為計算否認(法法132、132の2、132の3)を適用するための要件として、①形式的要件、②税負担の減少、③税負担減少の不当性(本件取引の行為・計算が通常の経済人を基準として不自然・不合理であることの評価根拠事実)を挙げられており(※5)、財務省主税局OBであった佐々木浩氏も平成23年に行われた座談会において、包括的租税回避防止規定については経済合理性がキーワードになる旨を述べられた(※6)。
(※5) 清水一夫「課税減免規定の立法趣旨による『限定解釈』論の研究」税大論叢59号314頁(平成20年)
(※6) 仲谷修ほか『企業組織再編成税制及びグループ法人税制の現状と今後の展望』(佐々木浩発言)129頁(大蔵財務協会、平成24年)
しかしながら、平成24年になると、同じく財務省主税局OBであった朝長英樹氏が制度の濫用について適用されるものであるという見解を述べられるようになり(※7)、また、同年、税務大学校研究部教授であった斉木秀憲氏の論文でも、包括的租税回避防止規定が適用される場面について、①組織再編税制の基本的な考え方からの乖離、②組織再編成の濫用、③個別防止規定の潜脱の3つに類型化されるようになった(※8)。
(※7) 朝長英樹ほか「組織再編成税制を巡る否認が相次ぐ中、今明かされる『行為計算否認規定(法人税法132条の2)』の創設の経緯・目的と解釈」(朝長英樹発言)T&Amaster 449号9頁(平成24年)
(※8) 斉木秀憲「組織再編成に係る行為計算否認規定の適用について」税大論叢73号9頁(平成24年)
ヤフー・IDCF事件の第一審判決が公表された後には、多くの雑誌・書籍において、包括的租税回避防止規定についての分析がなされるようになってきているが、いまだ上告審判決が公表されていないことや、仮に公表された後であっても、判例の射程がどこまで及ぶのかについては、その後の租税法学者の研究を待つ必要がある。
しかしながら、包括的租税回避防止規定に対する租税法学者の研究が進んでいくのには時間を要するし、仮に研究が進んでいったとしても、実務上は、無批判にそれを受け入れることは妥当ではない。なぜならば、従前から指摘させていただいたように、租税回避を意図する納税者はそれほど多くなく、法律の範囲内で節税を行いたいという納税者が大半であるというのが実感であり、租税法のあるべき論に比べ、かなり保守的な分析をすることが一般的であるからである(※9)。
(※9) 佐藤信祐『組織再編における包括的租税回避防止規定の実務』中央経済社 はじめに(平成21年)
すなわち、学者と実務家はそもそも基本的な役割が異なる。具体的には、学者は真理を追究する立場にあるため、やや保守的に考えればよいという立場はとり得ないであろう。これに対し、実務家は、無難に税務調査が終わればよいのであって、わざわざ、節税と租税回避の限界点を探る必要性が乏しい。そのため、やや保守的に考えればよいという立場はむしろ健全な立場であるといえる。
この点も、従前から指摘させていただいた点であるが、租税回避に該当するか否かの判断は、様々な判例や論文が参考になることはいうまでもないが、多くの日本企業では、国税不服審判所や裁判所で争ってまで税負担の減少を図ることを想定しておらず、無難に税務調査が終わることを望んでおり、国税不服審判所や裁判所で納税者が勝訴した事件であっても、国税不服審判所や裁判所で争わざるを得なかったという点をもって否定的に考える傾向にある(※10)。
(※10) 佐藤信祐前掲書(※9)2頁
それでは、租税回避に対する研究や意見の表明に意味がないのかといえば、租税回避行為に該当するような提案をしないという自己牽制効果が働くということから、本来であれば、積極的に租税回避に該当するか否かの意見の表明を行っていくべきであろう(※11)。
(※11) 佐藤信祐前掲書(※9)はじめに
このように、本連載では、過去の判例や論文を参考にしながらも、節税と租税回避の限界点を探っていくことを目的とせず、どのような場合であれば、包括的租税回避防止規定が適用される可能性が少ないのかという分析を行うときの一助になることを目的に解説を行っていく予定である。そのため、やや学術的な分析とは異なる可能性もあり得るが、ご容赦いただきたい。
(了)
「包括的租税回避防止規定の理論と解釈」は、隔週で掲載されます。