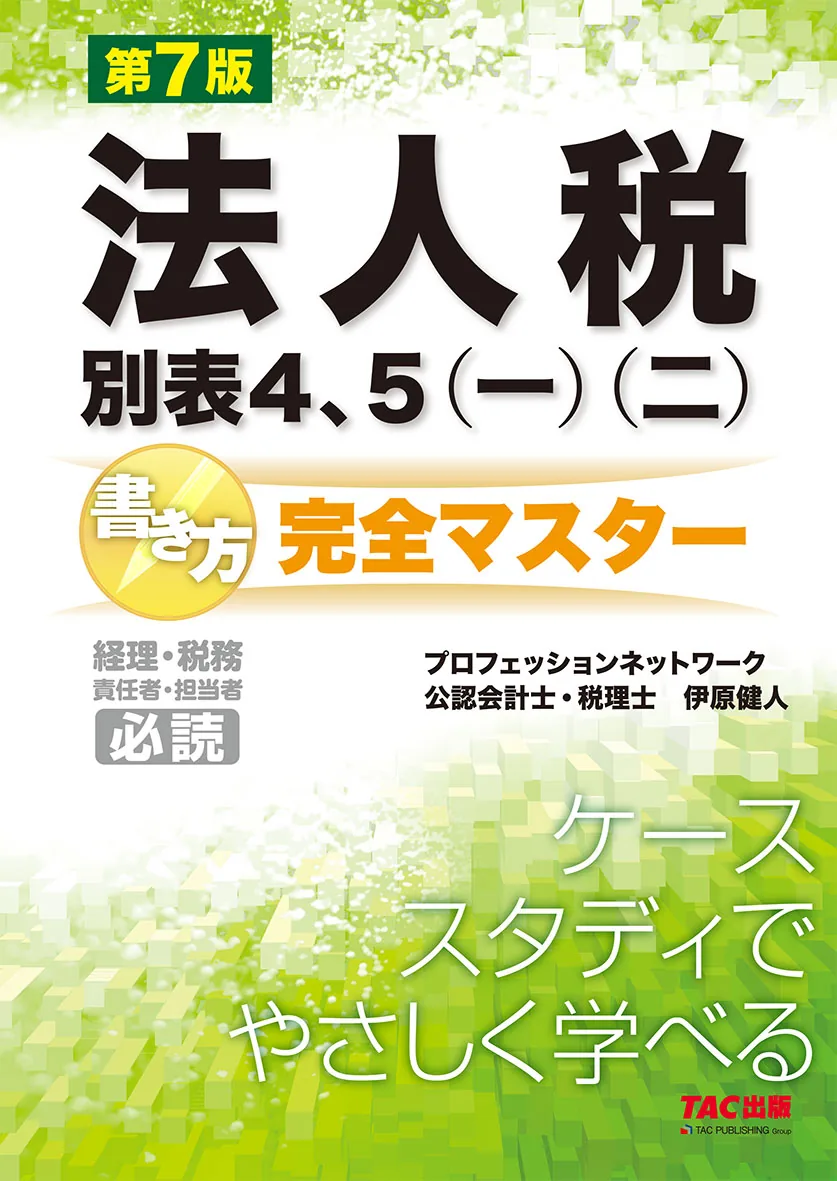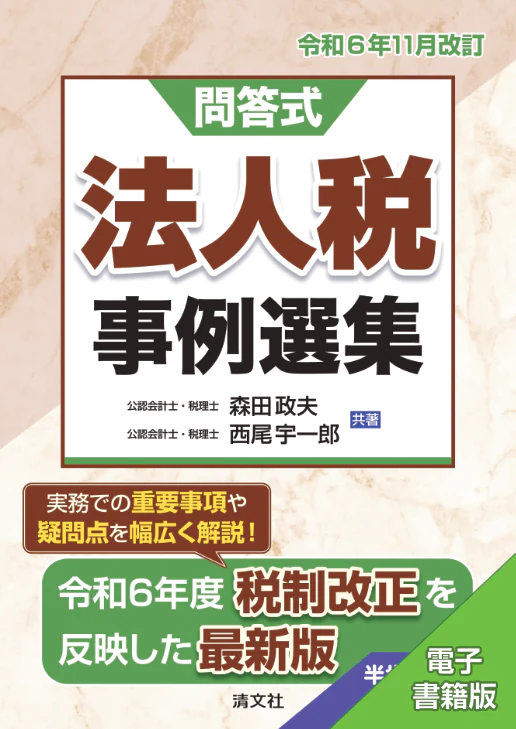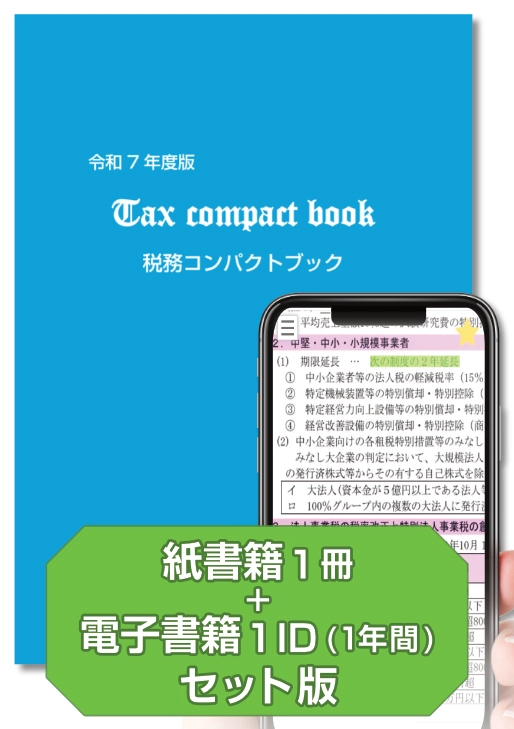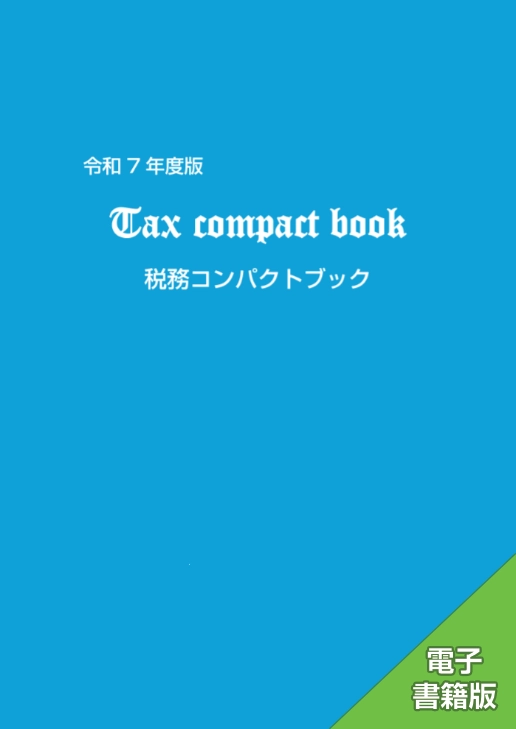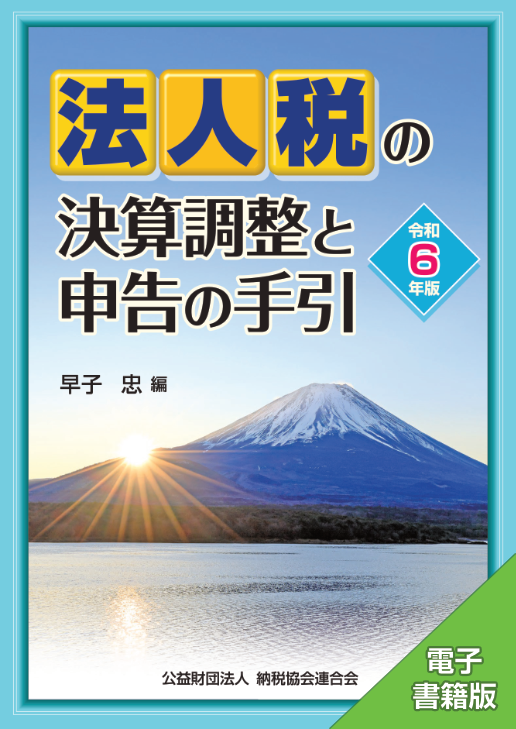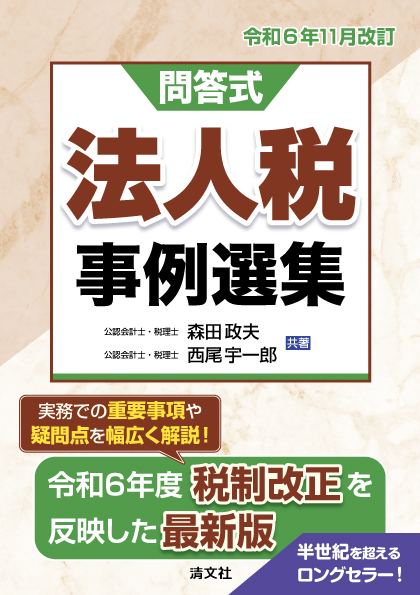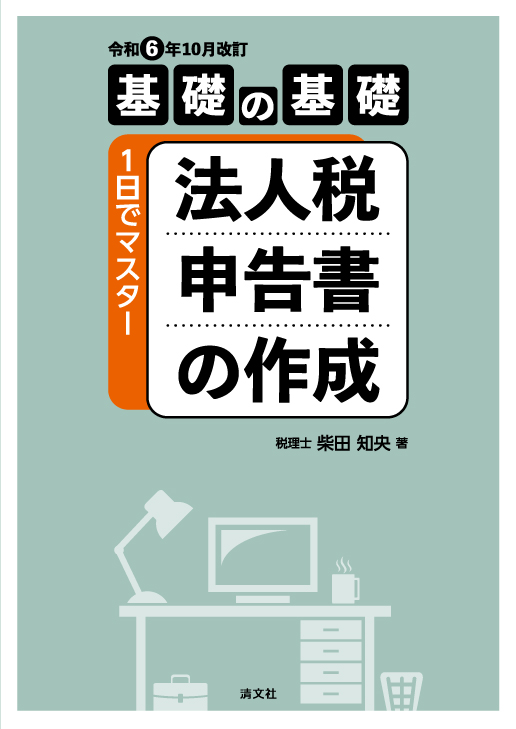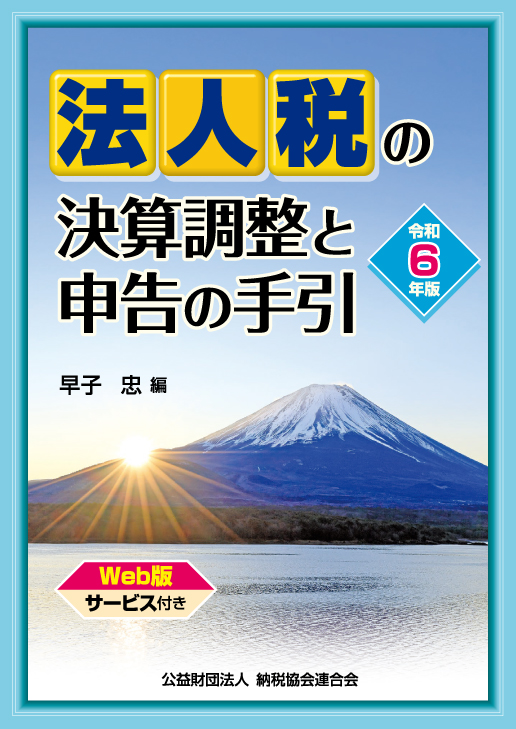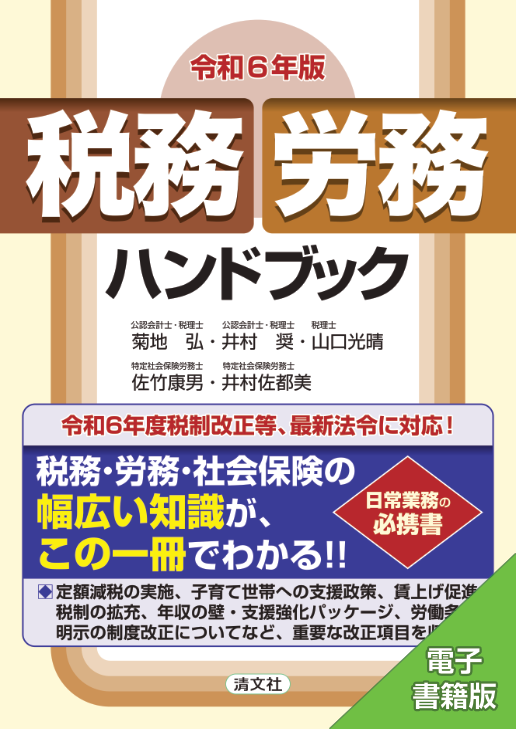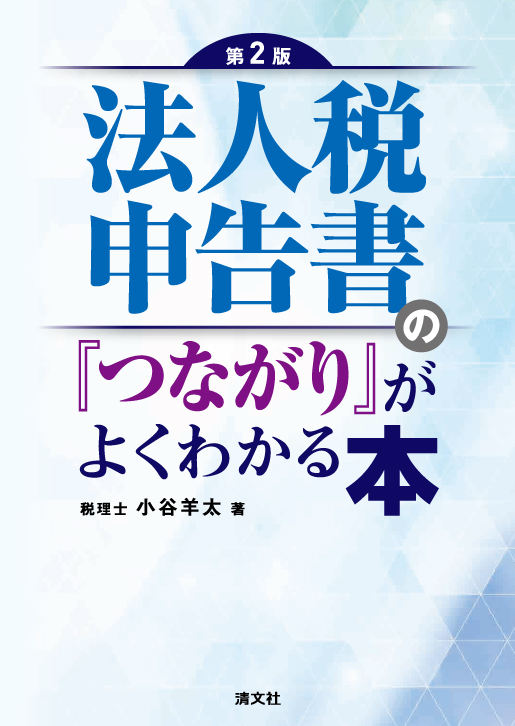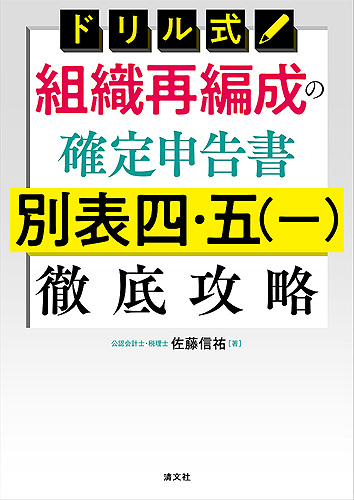〈事例で学ぶ〉
法人税申告書の書き方
【第33回】
「別表6(19) 特定の地域又は地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除に関する明細書」及び「別表6(19)付表 基準雇用者数等、給与等支給額及び比較給与等支給額の計算に関する明細書」
公認会計士・税理士
菊地 康夫
Ⅰ はじめに
本連載では、法人税申告書のうち、税制改正により変更もしくは新たに追加となった様式、実務書籍への掲載頻度が低い様式等を中心に、簡素な事例をもとに記載例と書き方のポイントを解説していく。
第31回目からは、平成29年度をもって終了する従来の雇用促進税制(地方拠点強化税制における雇用促進税制へ改組)、及び平成30年度の税制改正により見直しが行われたことによりその様式も改正された、地方拠点強化税制における雇用促進税制の別表をあらためて採り上げており(※)、改正点を踏まえながらその適用パターンごとに分けて順次解説している。
(※) 改正前の様式については【第10回】及び【第11回】を参照。
パターン①:平成30年4月1日以前に開始し、平成30年4月1日以後終了する事業年度の場合で従来の雇用促進税制の適用のみを受ける場合・・・「別表6(19) 特定の地域において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除に関する明細書」⇒【第31回】参照
パターン②:平成30年4月1日以前に開始し、平成30年4月1日以後終了する事業年度の場合で、従来の雇用促進税制とあわせて地方拠点強化税制における雇用促進税制の上乗せ適用を受ける場合・・・「別表6(19) 特定の地域において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除に関する明細書」⇒【第32回】参照
パターン③:平成30年4月1日以後に開始する事業年度の場合で、地方拠点強化税制における雇用促進税制の適用を受ける場合・・・「別表6(19) 特定の地域又は地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除に関する明細書」⇒【第33回】(本稿)参照
Ⅱ 概要
この別表は、青色申告書を提出する法人が租税特別措置法第42条の12第1項もしくは第2項(特定の地域又は地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除)の規定の適用を受ける場合に作成する。
この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員登録およびログインが必要です。
すでに会員登録をされている方は、下記ボタンからログインのうえ、ご覧ください。
Profession Journalのすべての記事をご覧いただくには、「プレミアム会員(有料)」へのご登録が必要となります。
なお、『速報解説』については「一般会員(無料)」へのご登録でも、ご覧いただけます。
※他にもWebセミナー受け放題のスーパープレミアム会員などがございます。
会員登録がお済みでない方は、下記会員登録のボタンより、ご登録のお手続きをお願いいたします。