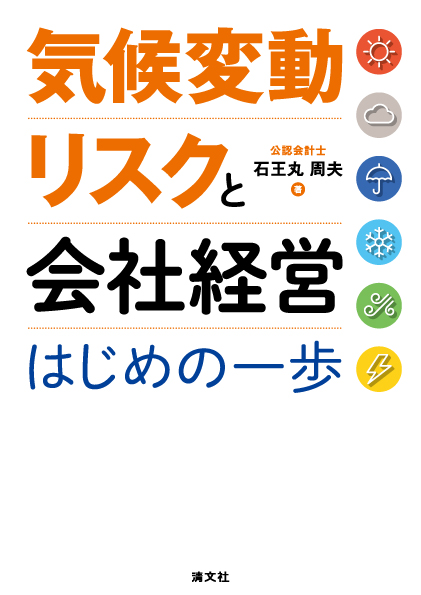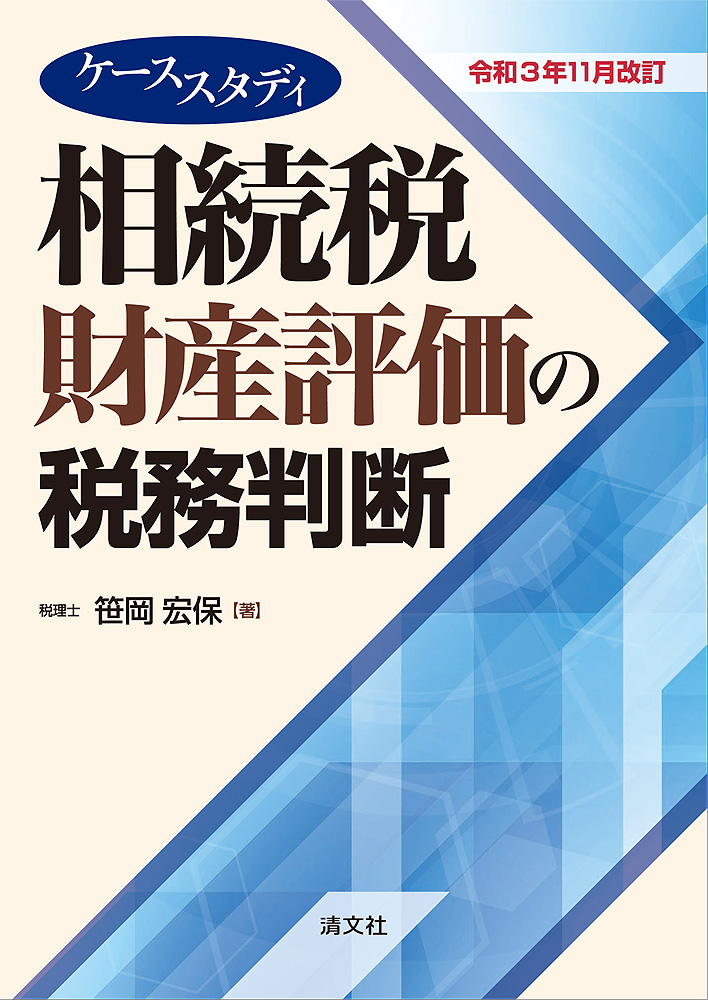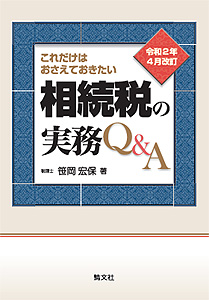各ステップに移動する場合はこちらをクリック
【STEP2】子会社株式及び関連会社株式の評価
(1) 時価の有無
(2) 時価の著しい低下の有無
(3) 時価のある程度以上の下落の有無
(4) 実質価額の著しい低下の有無
(5) 実質価額のある程度低下の有無
(6) 通常時の評価
(7) 減損
① 時価のある子会社株式等の減損
② 時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式等の減損
(8) 投資損失引当金
① 時価又は実質価額がある程度低下している場合の投資損失引当金
② 実質価額が著しく低下している場合の投資損失引当金

(1) 時価の有無
時価の有無により、この後の検討過程が異なる。そのため、時価のある子会社株式等の場合、「(2) 時価の著しい低下の有無」を検討する。時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式等の場合、「(4) 実質価額の著しい低下の有無」を検討する。
(2) 時価の著しい低下の有無
時価のある子会社株式等で、時価の著しい低下(【STEP1】(2)①(ⅰ)~(ⅲ)参照)がある場合、減損が必要かどうかの検討が必要となるため、(7)①を検討する。時価の著しい低下がない場合は、(3)を検討する。
(3) 時価のある程度以上の下落の有無
時価が著しく低下していないが、ある程度以上下落している場合、健全性の観点から時価の低下に相当する金額を投資損失引当金として計上することができる(監査委員会報告第71号「子会社株式等に対する投資損失引当金に係る監査上の取扱い(以下、「取扱い」という)」3.(1)、2.(2))。
時価がある程度以上下落している場合、投資損失引当金の計上の検討が必要となるため、(8)①を検討する。時価がある程度下落していない場合は、(6)を検討する。
なお、「ある程度以上の下落」の水準は「取扱い」で明らかになっていないため、各社で設定する必要がある。
(4) 実質価額の著しい低下の有無
実質価額とは、原則として、資産等の時価評価に基づく評価差額等を加味して算定した1株当たりの純資産額に所有株式数を乗じた金額をいう。
そして、実質価額が取得原価に比べて50%程度以上低下している場合、実質価額が著しく低下している状態である(実務指針92)。
実質価額が著しく低下している場合、(7)②を検討する。実質価額が著しく低下していない場合、(5)を検討する。
(5) 実質価額のある程度の低下の有無
実質価額は著しく低下していないが、ある程度低下している場合、健全性の観点から実質価額の低下に相当する金額を投資損失引当金として計上することができる(取扱い2.(1)①、(2))。
実質価額がある程度低下している場合、投資損失引当金の計上の検討が必要となるため、(8)①を検討する。実質価額がある程度低下していない場合は、(6)を検討する。
なお、「ある程度の低下」の水準は「取扱い」で明らかになっていないため、各社で設定する必要がある。
(6) 通常時の評価
減損処理が必要ではない子会社株式等は、取得原価をもって貸借対照表価額とする(基準17)。
(7) 減損
減損の検討は、時価のある子会社株式等と時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式等で検討過程が異なる。
① 時価のある子会社株式等の減損
時価のある子会社株式等における減損の検討は、時価のある満期保有目的の債券(【STEP1】(2)①参照)と同様である。
時価のある子会社株式等において、著しい時価の下落があり、かつ、回復可能性が認められない場合には、減損処理を行う必要があるため、著しい時価の下落に該当するか否かの判断が必要となる。具体的には、(ⅰ)50%程度以上の下落、(ⅱ)30%以上50%未満の下落、(ⅲ)30%未満の下落に分けて判断することになる。
(ⅰ) 50%程度以上の時価の下落がある場合
個々の銘柄の子会社株式等の時価が取得原価に比べて50%程度以上下落した場合には、時価が著しく下落したときに該当する。この場合、合理的な反証がない限り、時価が取得原価まで回復する見込みがあるとは認められないため、減損処理を行わなければならない(実務指針91)。
時価が50%程度以上下落した場合には、通常、合理的な反証を行うことはできず、減損処理することが多いと考えられる。
(ⅱ) 30%以上50%未満の時価の下落がある場合
時価の下落率が30%以上50%未満であっても、状況によっては時価の回復可能性がないとして減損処理が必要な場合があることから、時価の著しい下落があったものとして、回復可能性の判定の対象とされることがある。この場合、時価の著しい下落率についての固定的な数値基準を定めることはできないため、状況に応じて個々の企業において時価が「著しく下落した」と判定するための合理的な基準を設け、回復可能性がない場合には、減損処理をする(実務指針284)。
したがって、各社で、状況に応じて50%未満の時価の下落における、著しい時価の下落の合理的な基準を設定(例えば、2期連続して時価が30%以上低下している場合等)し、毎期、減損処理が必要かどうかを判断する必要がある。
【回復可能性を検討する際の留意事項】
株式の場合に、回復する見込みがあると認められるときとは、時価の下落が一時的なものであり、期末日後おおむね1年以内に時価が取得原価にほぼ近い水準にまで回復する見込みのあることを合理的な根拠をもって予測できる場合をいう。
この場合の合理的な根拠は、個別銘柄ごとに、株式の取得時点、期末日及び期末日後における市場価格の推移及び市場環境の動向、最高値・最安値と購入価格との乖離状況、発行会社の業況等の推移等、時価下落の内的・外的要因を総合的に勘案して検討することが必要である。
ただし、株式の時価が過去2年間にわたり著しく下落した状態にある場合や、株式の発行会社が債務超過の状態にある場合又は2期連続で損失を計上しており、翌期もそのように予想される場合には、通常は回復する見込みがあるとは認められない(実務指針91)。
(ⅲ) 30%未満の時価の下落がある場合
時価の下落率が30%未満の場合には、一般的には「著しく下落した」ときに該当しないと考えられるため、減損処理は不要である(実務指針91)。
なお、30%未満の時価の下落であっても、株式発行会社の業績の悪化や信用リスクの増大などによって時価の下落が生じていることもあるため、上記(ⅱ)において30%未満の時価の下落率を合理的な基準として設定することも認められる(実務指針284)。
② 時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式等の減損
時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式等は、子会社等の財政状態の悪化により実質価額が著しく低下したときは、減損処理を行う。ただし、回復可能性が十分な証拠によって裏付けられる場合には、減損処理をしないことも認められる。(実務指針92)。
したがって、(ⅰ)財状状態の悪化の判定、(ⅱ)実質価額の著しい低下の判定、(ⅲ)減損の判定を検討する必要がある。
(ⅰ) 財政状態の悪化の判定
財政状態とは、原則として資産等の時価評価に基づく評価差額等を加味して算定した1株当たりの純資産額をいう。「財政状態の悪化」とは、この1株当たりの純資産額が、当該株式を取得したときのそれと比較して相当程度下回っている場合をいう(実務指針92)。
「相当程度下回っている」とは、どの程度かが基準等で定められていないため、各社で相当程度下回っている場合を決定する必要がある。
なお、財政状態の悪化がなくても、減損処理が必要な場合(下記(ⅲ)参照)があるため、財政状態の悪化の有無にかかわらず、下記(ⅱ)、(ⅲ)実質価額の著しい低下を検討する必要がある。
(ⅱ) 実質価額の著しい低下の判定
上記(4)より、すでに実質価額の著しい低下があると判定されているため、ここで改めて判定する必要はない。
(ⅲ) 減損の判定
上記(ⅰ)、(ⅱ)より、財政状態の悪化により実質価額が著しく低下している場合には、減損処理を行う。なお、子会社等の実質ベースの財務諸表や事業計画等を入手し、回復可能性(取得原価までの回復)が十分な証拠によって裏付けられる場合には、減損処理をしないこともできる(Q&A Q33、実務指針92)。減損処理をしない場合は、(8)②を検討する。
また、財政状態の悪化がなくても、以下のような場合、実質価額の著しい低下のみで減損処理を行う。
企業買収においては、会社の超過収益力や経営権等を反映して、財務諸表から得られる1株当たり純資産額に比べて相当高い価額で当該会社の株式を取得することがある。その後、超過収益力等が減少したために実質価額が大幅に低下することがある。このような場合には、たとえ発行会社の財政状態の悪化がないとしても、将来の期間にわたってその状態が続くと予想され、超過収益力が見込めなくなった場合には、実質価額が取得原価の50%程度を下回っている限り、減損処理をしなければならない(Q&A Q33)。
(8) 投資損失引当金
投資損失引当金の検討は、実質価額の低下の程度により分けて検討する。時価のある子会社株式等の場合は、ある程度以上低下している場合のみ検討する。
① 時価又は実質価額がある程度低下している場合の投資損失引当金
時価又は実質価額がある程度低下している場合、健全性の観点から実質価額の低下に相当する金額を投資損失引当金として計上する必要があるかどうかを検討する(取扱い2.(1)①、(2)、3.(1))。
② 実質価額が著しく低下している場合の投資損失引当金
実質価額が著しく低下しているが、回復可能性が見込めるとして減損処理を行っていない場合、回復可能性の判断はあくまでも将来の予測に基づいて行われるものであり、その回復可能性の判断を万全に行うことは実務上困難なときがある。そのため、健全性の観点からこのリスクに備えて、実質価額の低下に相当する金額を投資損失引当金として計上する必要があるかどうかを検討する(取扱い2.(1)①、(2))。
【 投資損失引当金の取崩し(取扱い2.(3))】
- 上記(8)①において、子会社等の財政状態が悪化して子会社株式等の実質価額が著しく低下した場合、又は(8)②において、実質価額の回復可能性が見込めないこととなった場合、投資損失引当金を取り崩し、減損処理する。
(※) (8)①において時価が著しく低下した場合も同様と考えられる。
- 上記(8)①及び②において、子会社等の財政状態が改善し、子会社株式等の実質価額が回復した場合には、回復部分に見合う額の投資損失引当金を取り崩す。
(※) (8)①において時価が回復した場合も同様と考えられる。
ただし、子会社及び関連会社の事業計画等により財政状態の改善が一時的と認められる場合には、取り崩してはならない。