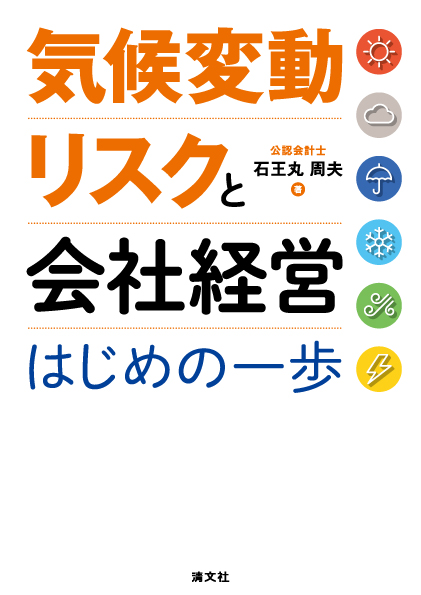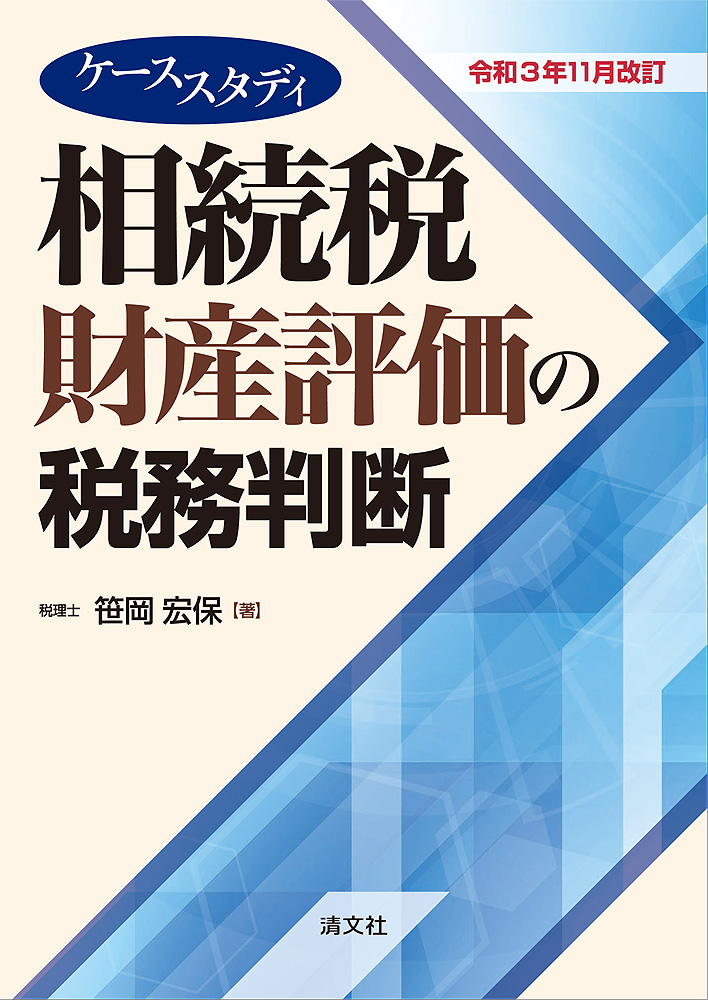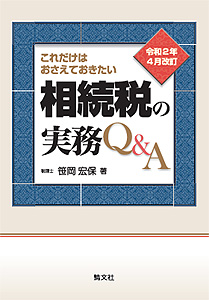各ステップに移動する場合はこちらをクリック
【STEP1】満期保有目的の債券の評価
(1) 通常時の評価
(2) 減損
① 時価のある満期保有目的の債券の減損
② 時価を把握することが極めて困難と認められる満期保有目的の債券の減損

(1) 通常時の評価
満期保有目的の債券は、原則として、取得原価をもって貸借対照表価額とする(企業会計基準第10号「金融商品に関する会計基準(以下、「基準」という)」16)。
ただし、債券を債券金額より低い価額又は高い価額で取得した場合において、取得価額と債券金額との差額の性格が金利の調整と認められるときは、償却原価法に基づいて算定された価額をもって貸借対照表価額としなければならない(基準16)。
したがって、時価のある債券であっても、時価評価することはない。
償却原価法とは、金融資産又は金融負債を債権額又は債務額と異なる金額で計上した場合において、当該差額に相当する金額を弁済期又は償還期に至るまで毎期一定の方法で取得価額に加減する方法をいう。この加減額は、受取利息又は支払利息で計上する(基準注5)。
〈満期保有目的の債券の通常時の評価〉
◆原則
・・・取得原価
◆債券を債券金額より低い価額又は高い価額で取得した場合において、取得価額と債券金額との差額の性格が金利の調整と認められるとき
・・・償却原価法
また、償却原価法には、利息法と定額法の2つの方法がある。原則として利息法によるものとされているが、継続適用を条件として、簡便法である定額法を採用することができる(会計制度委員会報告第14号「金融商品会計に関する実務指針(以下、「実務指針」という)」70)。
【利息法】
債券のクーポン受取総額と金利調整差額の合計額を、債券の帳簿価額に対し一定率(実効利子率)となるように、複利をもって各期の純損益に配分し、当該配分額とクーポン計上額(クーポンの現金受取額及びその既経過分の未収計上額の増減額の合計額)との差額を帳簿価額に加減する方法
【定額法】
債券の金利調整差額を取得日(又は受渡日)から償還日までの期間で除して各期の純損益に配分し、当該配分額を帳簿価額に加減する方法
《設例1》
【前提条件】
- X1年4月1日に額面10,000の社債を9,000で購入した。
- この社債は、満期まで所有する意図をもって保有する。
- 決算日は3月末日である。
- 利息法を採用している。
- 社債の条件は以下のとおりである。
満期日:X4年3月31日
クーポン利子率:年利2%
利払日:毎年3月末日
【会計処理】
【X1年4月1日】
![]()
【X2年3月31日】

(※1) 利息配分額
(※2) クーポン受取額
(※3) 利息配分額-クーポン受取額
- クーポン受取額=額面10,000×2%
- 利息配分額=直前帳簿価額×実効利子率
- 実効利子率の算定

(2) 減損
減損とは、著しい時価(又は実質価額)の下落があり、かつ、回復可能性が認められない場合に、時価(実質価額)と貸借対照表価額の差額を当期の損失として処理することである(基準20、21、実務指針91、92)。
満期保有目的の債券の減損においては、「時価のある満期保有目的の債券」と「時価を把握することが極めて困難と認められる債券」に分けて検討する。
なお、減損処理を行った満期保有目的の債券については、取得差額はもはや金利調整差額とは考えられないため、減損後は、償却原価法は適用しない(金融商品会計に関するQ&A (以下、「Q&A」という)Q25)。
① 時価のある満期保有目的の債券の減損
時価のある満期保有目的の債券において、著しい時価の下落があり、かつ、回復可能性が認められない場合には、減損処理を行う必要がある。そのため、著しい時価の下落に該当するか否かの判断が必要となる。具体的には、(ⅰ)50%程度以上の下落、(ⅱ)30%以上50%未満の下落、(ⅲ)30%未満の下落に分けて判断することになる。
(ⅰ) 50%程度以上の時価の下落がある場合
個々の銘柄の満期保有目的の債券の時価が取得原価に比べて50%程度以上下落した場合には、時価が「著しく下落した」ときに該当する。この場合、合理的な反証がない限り、時価が取得原価まで回復する見込みがあるとは認められないため、減損処理を行わなければならない(実務指針91)。
時価が50%程度以上下落した場合には、通常、合理的な反証を行うことはできず、減損処理することが多いと考えられる。
(ⅱ) 30%以上50%未満の時価の下落がある場合
時価の下落率が30%以上50%未満であっても、状況によっては時価の回復可能性がないとして減損処理が必要な場合があることから、時価の著しい下落があったものとして、回復可能性の判定の対象とされることがある。この場合、時価の著しい下落率についての固定的な数値基準を定めることはできないため、状況に応じて個々の企業において時価が「著しく下落した」と判定するための合理的な基準を設け、回復可能性がない場合には、減損処理をする(実務指針284)。
したがって、各社で、状況に応じて50%未満の時価の下落における、著しい時価の下落の合理的な基準を設定(例えば、2期連続して時価が30%以上低下している場合等)し、毎期、減損処理が必要かどうかを判断する必要がある。
【回復可能性を検討する際の留意事項】
債券の場合、単に一般市場金利の大幅な上昇によって時価が著しく下落した場合であっても、いずれ時価の下落が解消すると見込まれるときは、回復する可能性があるものと認められる。しかし、格付の著しい低下があった場合や、債券の発行会社が債務超過や連続して赤字決算の状態にある場合など、信用リスクの増大に起因して時価が著しく下落した場合には、通常は回復する見込みがあるとは認められない(実務指針91)。
(ⅲ) 30%未満の時価の下落がある場合
時価の下落率が30%未満の場合には、一般的には「著しく下落した」ときに該当しないと考えられるため、減損処理は不要である(実務指針91)。
なお、30%未満の時価の下落であっても、債券発行会社の業績の悪化や信用リスクの増大などによって時価の下落が生じていることもあるため、上記(ⅱ)において30%未満の時価の下落率を合理的な基準として設定することも認められる(実務指針284)。
② 時価を把握することが極めて困難と認められる満期保有目的の債券の減損
時価を把握することが極めて困難と認められる満期保有目的の債券の貸借対照表価額は、債権の貸借対照表価額に準ずるとされている(基準19(1))。したがって、償却原価法を適用した上で、債権の貸倒見積高の算定方法に準じて信用リスクに応じた償還不能見積高を算定し、会計処理を行う。また、償還不能見積高の算定は、原則として、個別の債券ごとに行う(実務指針93)。
償還不能額がなければ、貸借対照表価額は当然に(1)通常の評価の場合と同額になる。