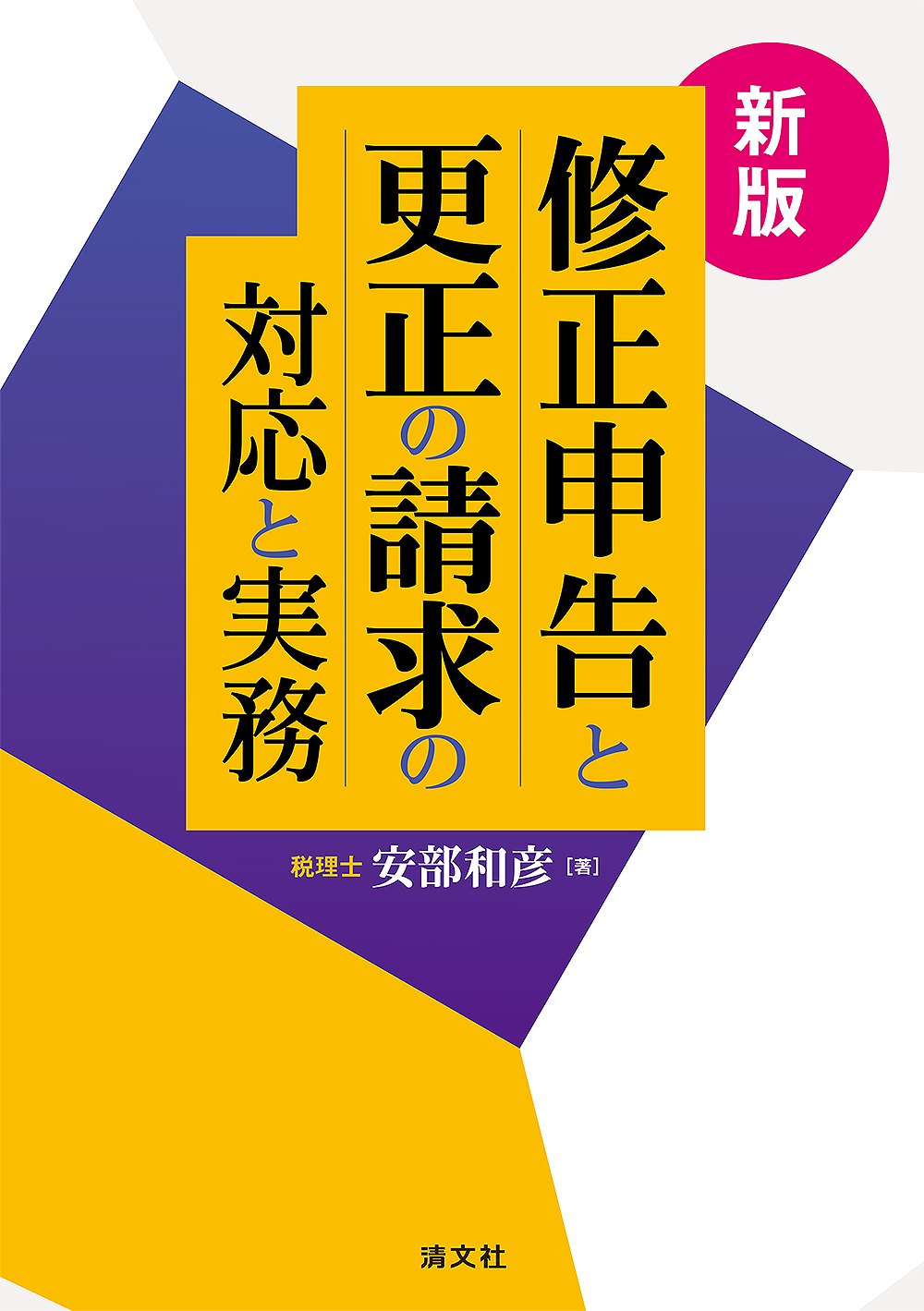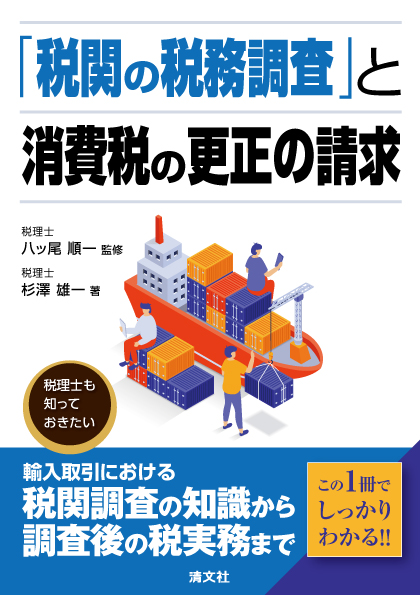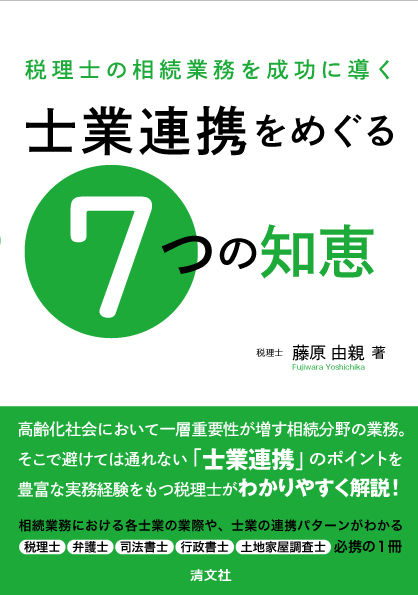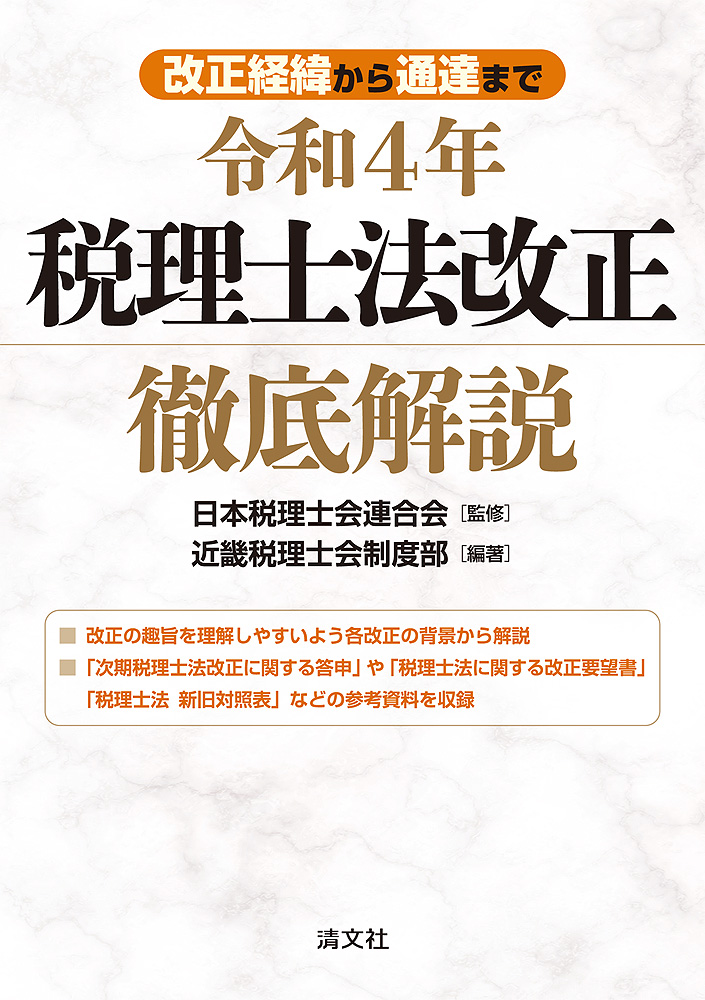〔顧問先を税務トラブルから救う〕
不服申立ての実務
【第20回】
(最終回)
「審判官経験者から見た税理士代理人の特徴」
公認会計士・税理士 大橋 誠一
1 自らが持てる武器を知らない
(1) 審査請求人に認められた権利を行使しない
これまでの回で解説したように、審査請求人には自らの主張立証活動に資するための各種権利が認められており、その行使をすれば、担当審判官は基本的にはそれを拒むことはできない。
しかし、これらの権利を経験上行使しない審査請求人の割合が高く、必要がないから敢えて行使しないのではなく、代理人も含めた不服申立制度の理解不足によって行使しないと思しきケースもある。
- 担当審判官による職権調査の申立て(第7回)
- 口頭意見陳述における発問権の行使(第10回)
- 原処分庁の主張に対する反論(第12回)
- 閲覧謄写請求(第13回)
- 自らに有利な証拠書類等の提出(第14回)
(2) 担当審判官の心証形成に敏感でない
また、審査請求人は、裁決までの一連の手続の中で、担当審判官の着眼点を推し量り、自らの主張が認容される可能性を占う場面がある。
この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員登録およびログインが必要です。
すでに会員登録をされている方は、下記ボタンからログインのうえ、ご覧ください。
Profession Journalのすべての記事をご覧いただくには、「プレミアム会員(有料)」へのご登録が必要となります。
なお、『速報解説』については「一般会員(無料)」へのご登録でも、ご覧いただけます。
※他にもWebセミナー受け放題のスーパープレミアム会員などがございます。
会員登録がお済みでない方は、下記会員登録のボタンより、ご登録のお手続きをお願いいたします。
〔顧問先を税務トラブルから救う〕
不服申立ての実務
【第20回】
(最終回)
「審判官経験者から見た税理士代理人の特徴」
公認会計士・税理士 大橋 誠一
1 自らが持てる武器を知らない
(1) 審査請求人に認められた権利を行使しない
これまでの回で解説したように、審査請求人には自らの主張立証活動に資するための各種権利が認められており、その行使をすれば、担当審判官は基本的にはそれを拒むことはできない。
しかし、これらの権利を経験上行使しない審査請求人の割合が高く、必要がないから敢えて行使しないのではなく、代理人も含めた不服申立制度の理解不足によって行使しないと思しきケースもある。
- 担当審判官による職権調査の申立て(第7回)
- 口頭意見陳述における発問権の行使(第10回)
- 原処分庁の主張に対する反論(第12回)
- 閲覧謄写請求(第13回)
- 自らに有利な証拠書類等の提出(第14回)
(2) 担当審判官の心証形成に敏感でない
また、審査請求人は、裁決までの一連の手続の中で、担当審判官の着眼点を推し量り、自らの主張が認容される可能性を占う場面がある。
この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員登録およびログインが必要です。
すでに会員登録をされている方は、下記ボタンからログインのうえ、ご覧ください。
Profession Journalのすべての記事をご覧いただくには、「プレミアム会員(有料)」へのご登録が必要となります。
なお、『速報解説』については「一般会員(無料)」へのご登録でも、ご覧いただけます。
※他にもWebセミナー受け放題のスーパープレミアム会員などがございます。
会員登録がお済みでない方は、下記会員登録のボタンより、ご登録のお手続きをお願いいたします。