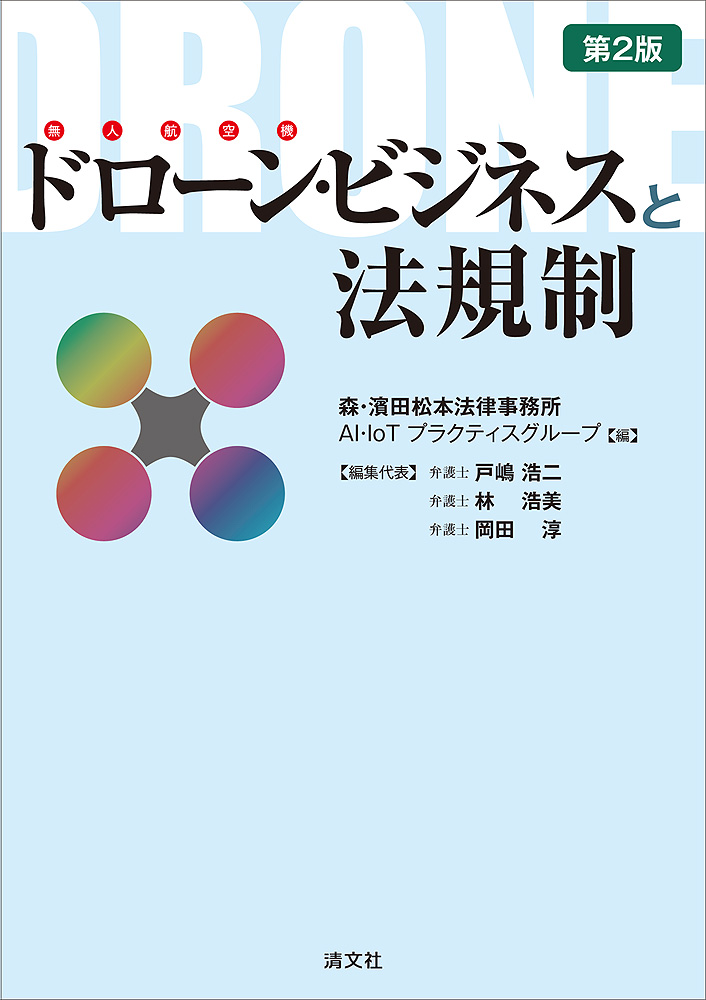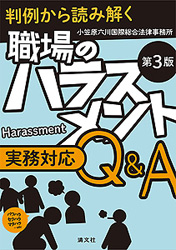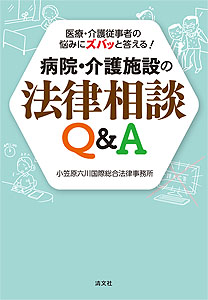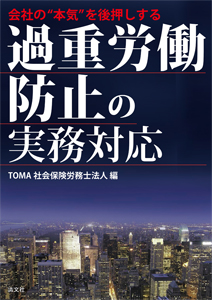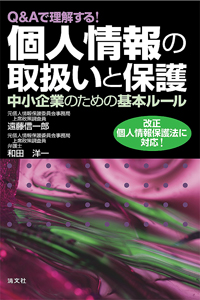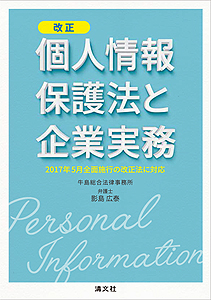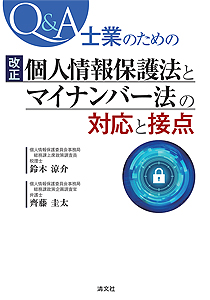ハラスメント発覚から紛争解決までの
企 業 対 応
【第36回】
「逆パワハラの申告があった場合の対応のポイント」
弁護士 柳田 忍
【Question】
当社の社員Bから、上司であるA部長からパワハラを受けているとの申告があったため、A部長のヒアリングを実施したところ、A部長はパワハラの事実を否定するとともに、むしろ自分が部下Bから逆パワハラを受けていると主張しました。逆パワハラとは、部下から上司に対するパワハラのことを意味すると理解していますが、A部長は自分にかかったパワハラの嫌疑をそらすため、逆パワハラにあっているなどと虚偽の主張をしているのではないかと疑っています。A部長の申告に対して、どのように対応するべきでしょうか。
この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員登録およびログインが必要です。
すでに会員登録をされている方は、下記ボタンからログインのうえ、ご覧ください。
Profession Journalのすべての記事をご覧いただくには、「プレミアム会員(有料)」へのご登録が必要となります。
なお、『速報解説』については「一般会員(無料)」へのご登録でも、ご覧いただけます。
※他にもWebセミナー受け放題のスーパープレミアム会員などがございます。
会員登録がお済みでない方は、下記会員登録のボタンより、ご登録のお手続きをお願いいたします。