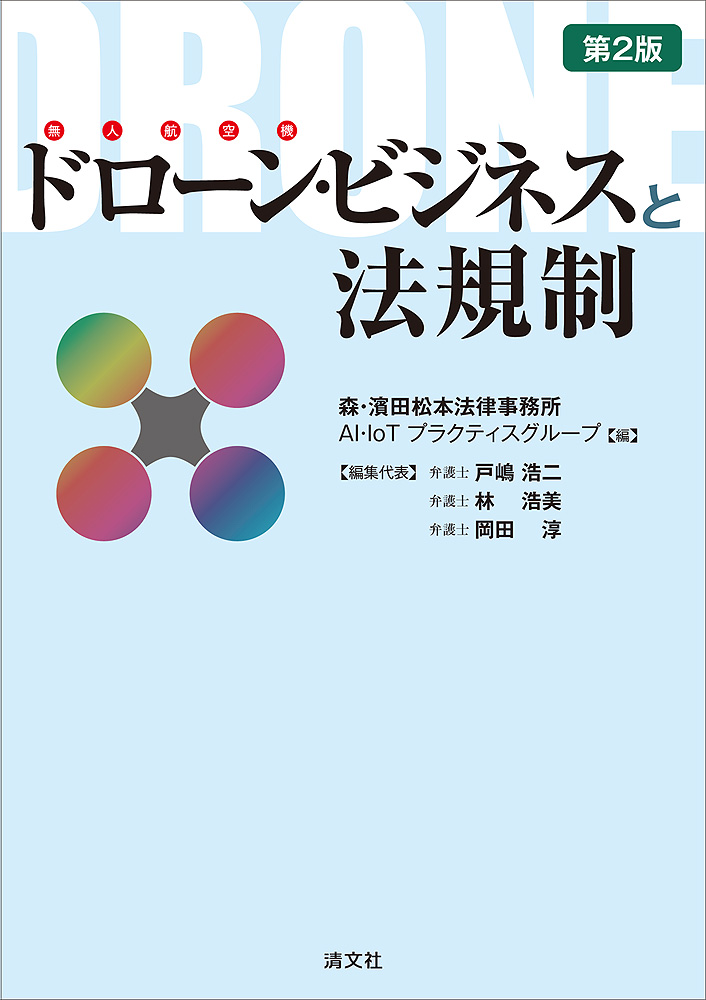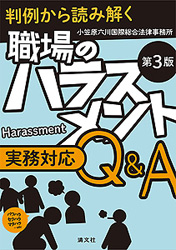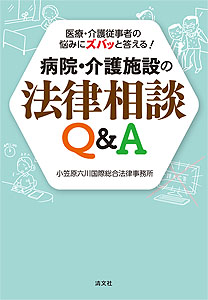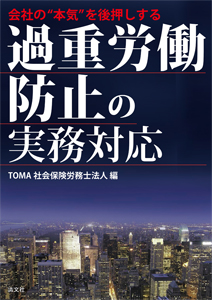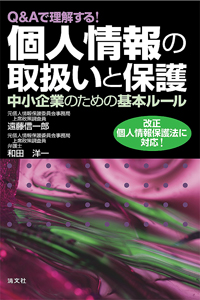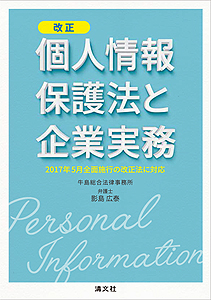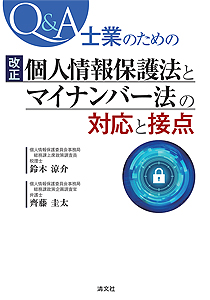ハラスメント発覚から紛争解決までの
企 業 対 応
【第31回】
「ハラスメントの懲戒処分の勘所」
弁護士 柳田 忍
【Question】
ハラスメント事案の行為者に対して、懲戒処分を科すべきか否か、懲戒処分を科すべきとしてどの種類の懲戒処分を科すべきかについて、判断に迷うことがよくありますが、判断のポイントなどはありますか。この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員登録およびログインが必要です。
すでに会員登録をされている方は、下記ボタンからログインのうえ、ご覧ください。
Profession Journalのすべての記事をご覧いただくには、「プレミアム会員(有料)」へのご登録が必要となります。
なお、『速報解説』については「一般会員(無料)」へのご登録でも、ご覧いただけます。
※他にもWebセミナー受け放題のスーパープレミアム会員などがございます。
会員登録がお済みでない方は、下記会員登録のボタンより、ご登録のお手続きをお願いいたします。