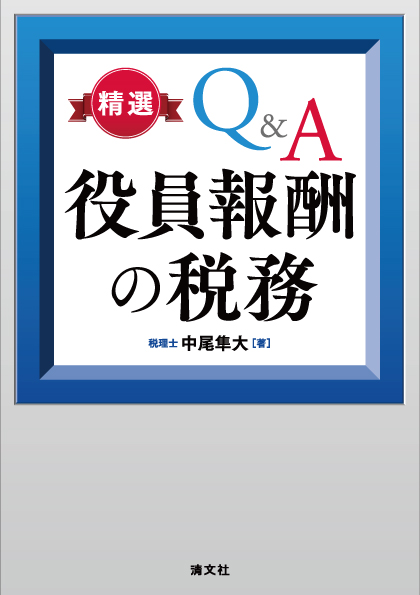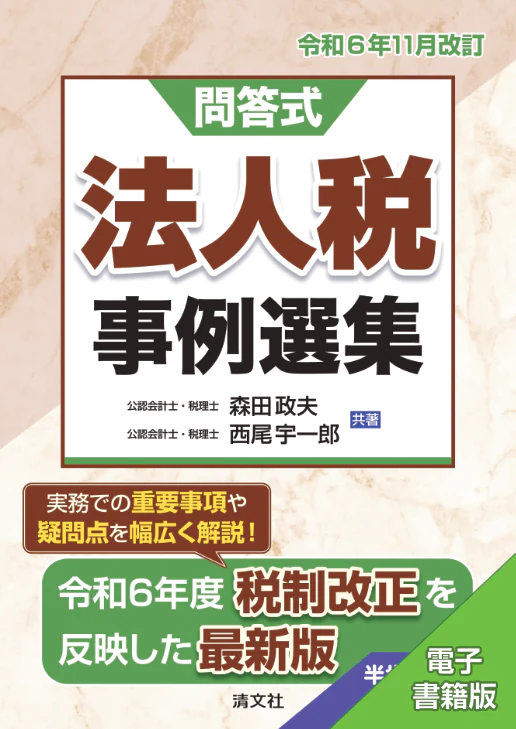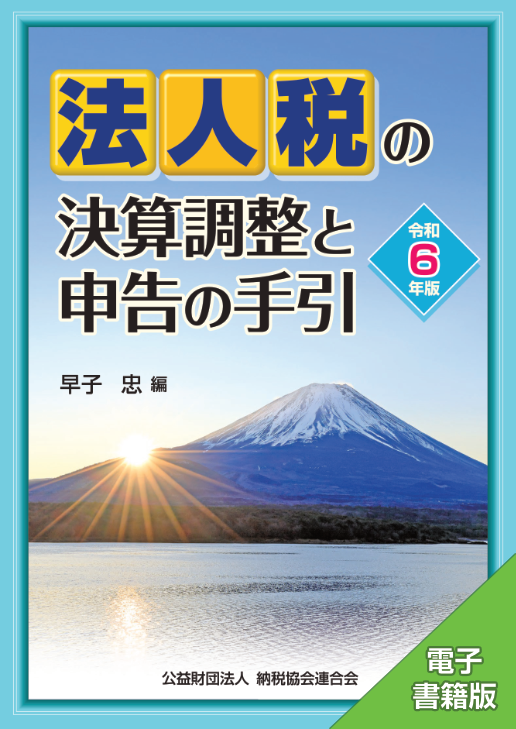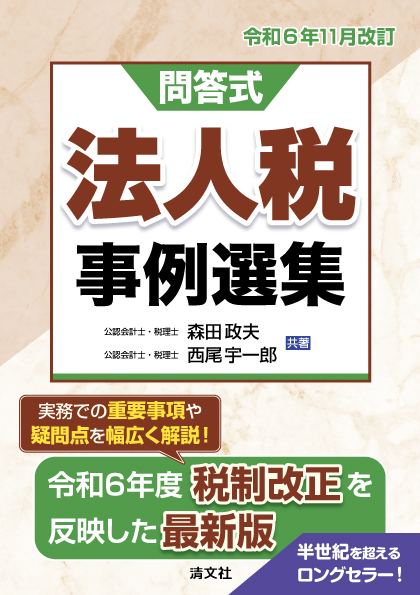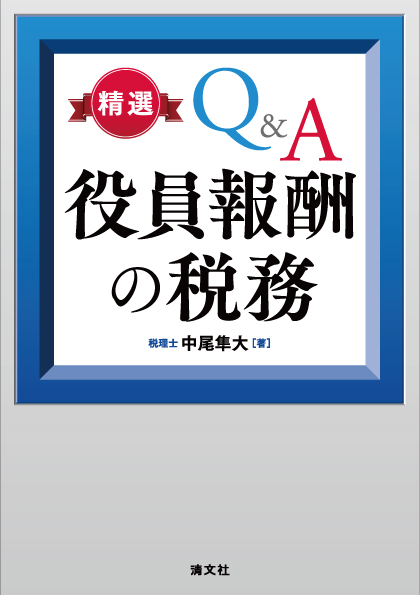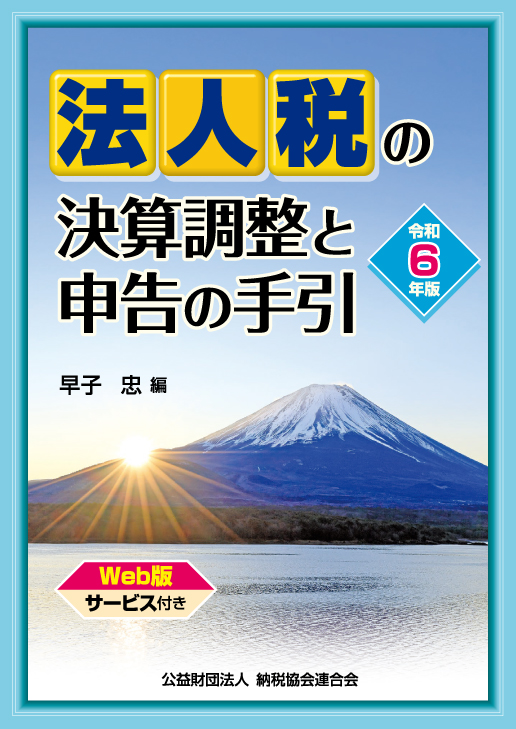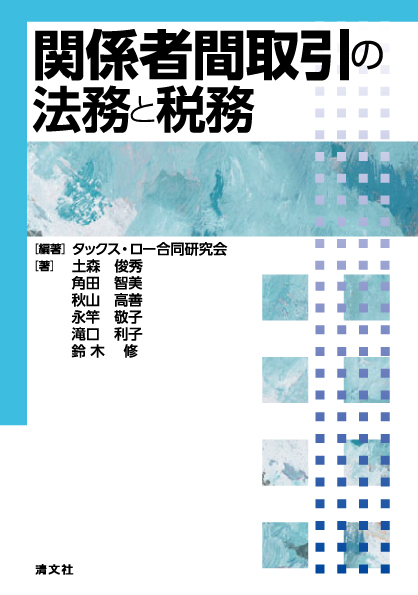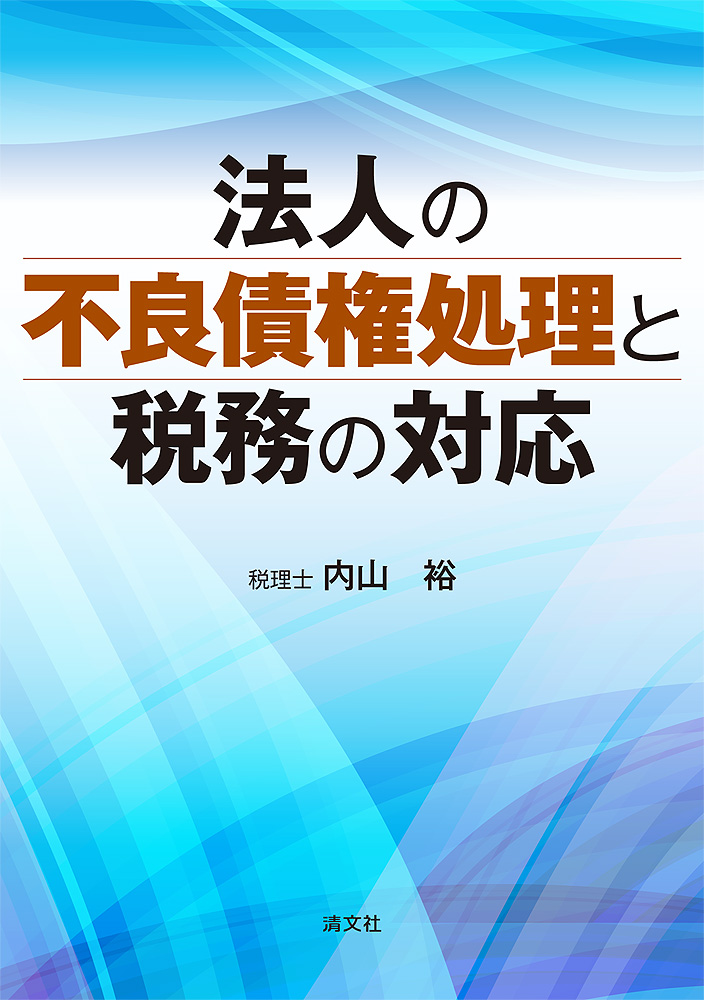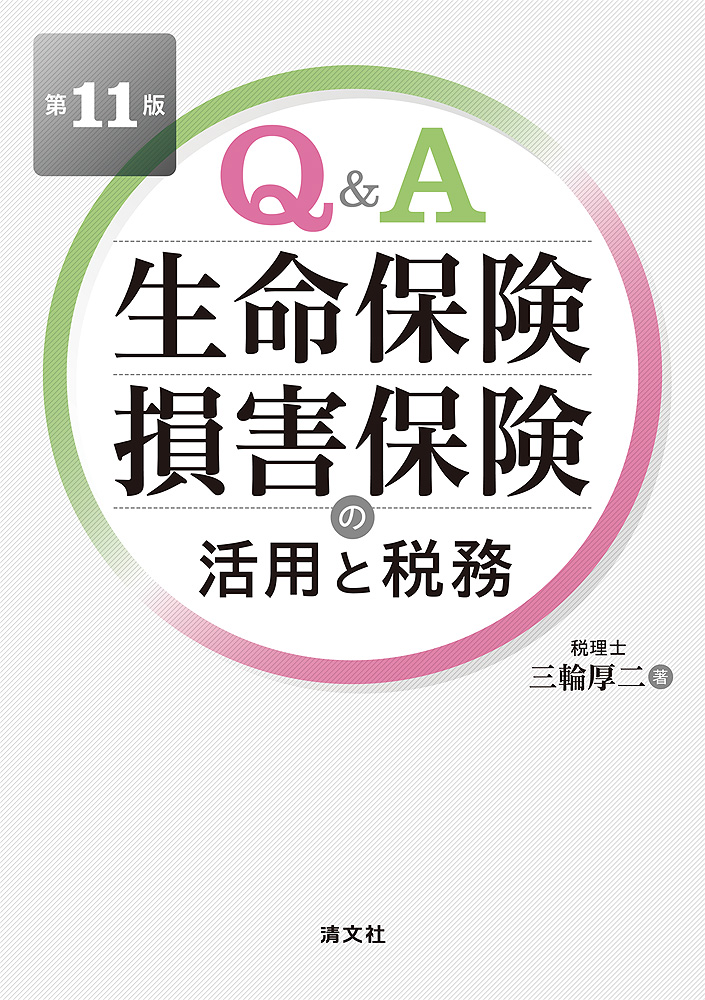〈ポイント解説〉
役員報酬の税務
【第31回】
「役員貸付金の解消方法としての貸倒損失」
税理士 中尾 隼大
【 質 問 】
私は中小企業の経理担当者です。当社は社長個人への役員貸付金が多額となっています。
近年、事業承継を控えているため役員貸付金の解消について検討していますが、社長個人は現時点で資力が芳しくないため、貸倒損失処理も選択肢に入っています。
この場合、何か留意点はありますか。
この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員登録およびログインが必要です。
すでに会員登録をされている方は、下記ボタンからログインのうえ、ご覧ください。
Profession Journalのすべての記事をご覧いただくには、「プレミアム会員(有料)」へのご登録が必要となります。
なお、『速報解説』については「一般会員(無料)」へのご登録でも、ご覧いただけます。
※他にもWebセミナー受け放題のスーパープレミアム会員などがございます。
会員登録がお済みでない方は、下記会員登録のボタンより、ご登録のお手続きをお願いいたします。