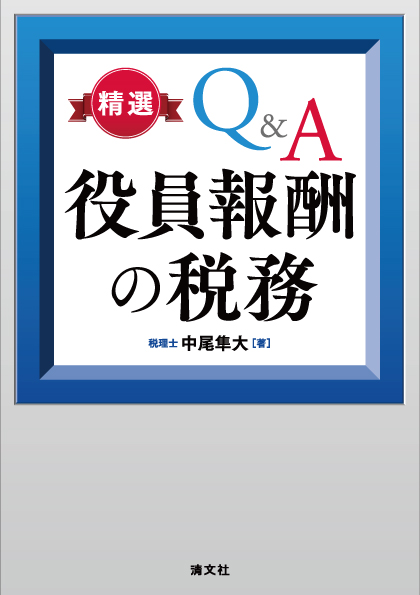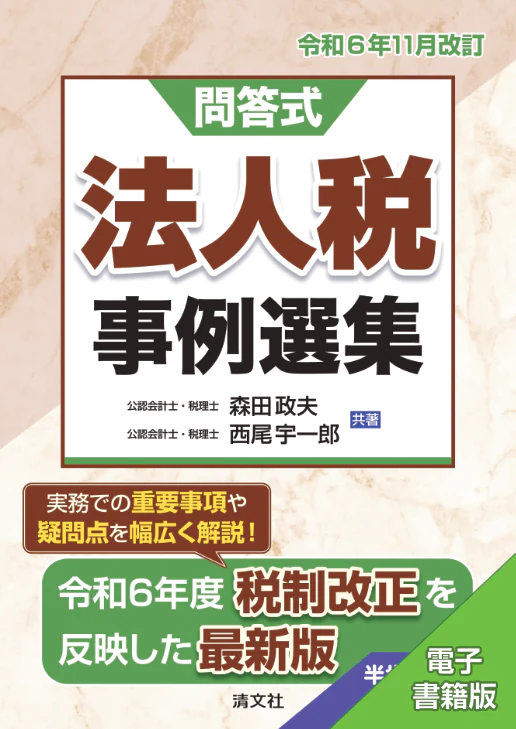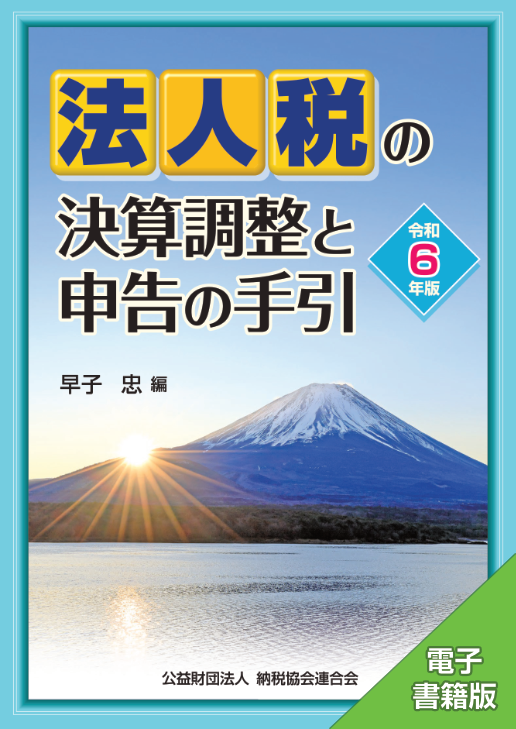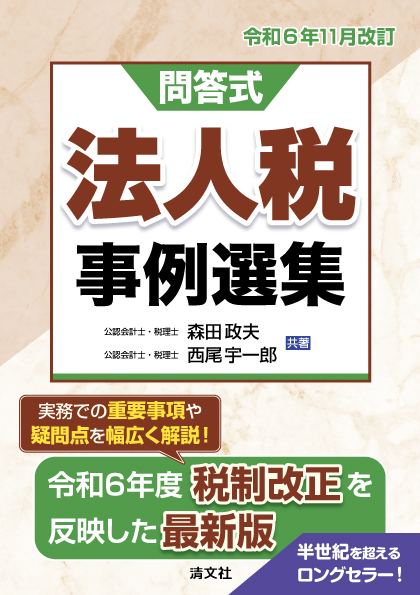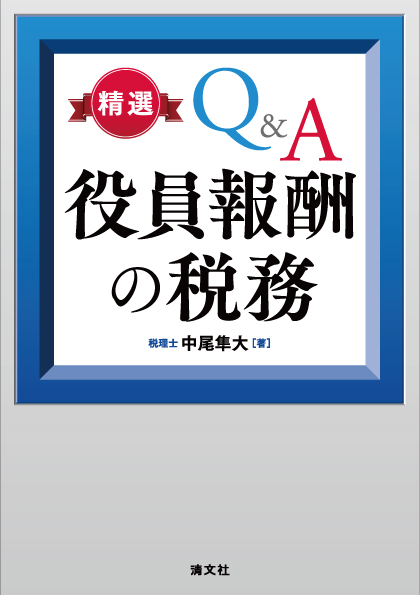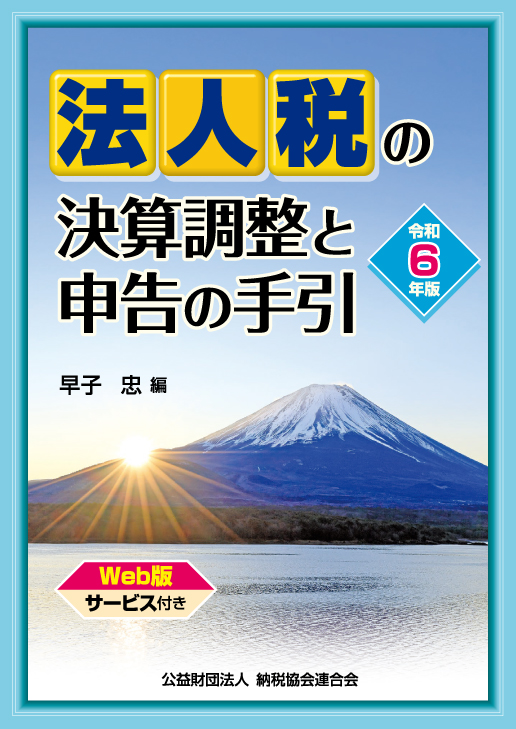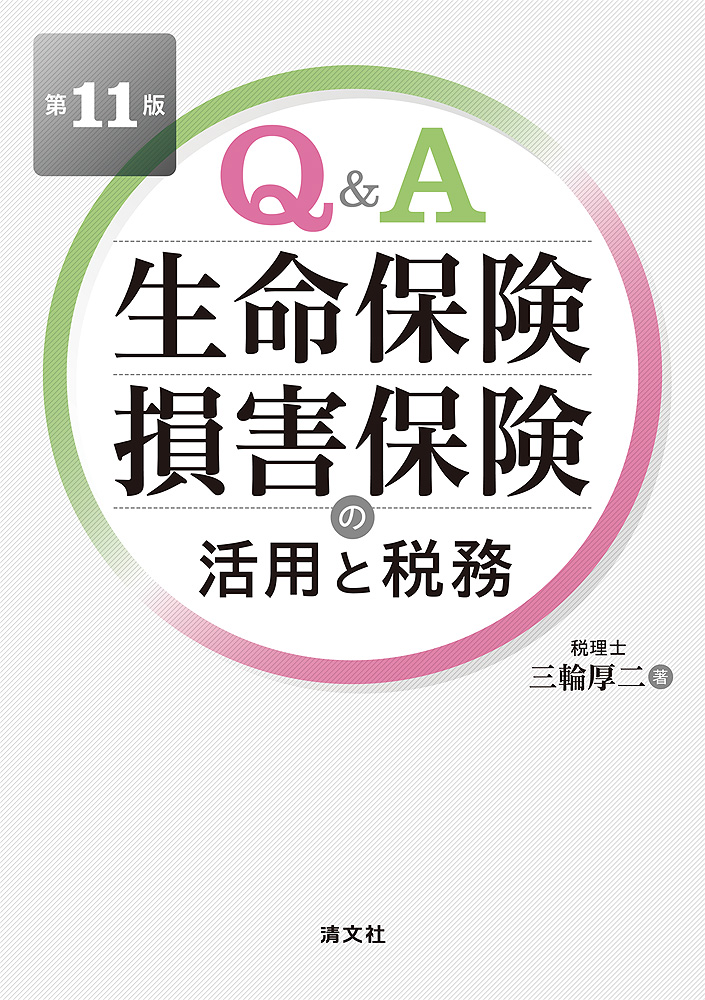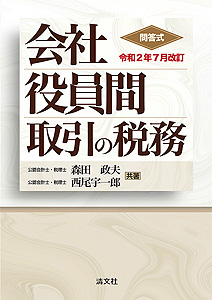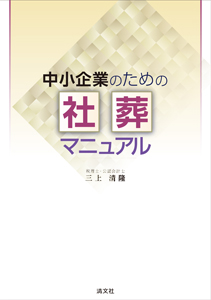〈ポイント解説〉
役員報酬の税務
【第19回】
「使用人兼務取締役に係る役員報酬と事業報告」
税理士 中尾 隼大
【 質 問 】
役員報酬は会社法上の役員に支給するものと理解しています。そうだとすれば、上場企業である当社の特定の人材を使用人兼務取締役とし、当該人材の総支給額のうち使用人部分としての給与部分の割合を高めることで、事業報告に反映させる役員報酬の総額を抑えることができるのかもしれないと思っています。
このような案につき、可能かどうかを含め、税務上や会社法上の論点を教えてください。
この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員登録およびログインが必要です。
すでに会員登録をされている方は、下記ボタンからログインのうえ、ご覧ください。
Profession Journalのすべての記事をご覧いただくには、「プレミアム会員(有料)」へのご登録が必要となります。
なお、『速報解説』については「一般会員(無料)」へのご登録でも、ご覧いただけます。
※他にもWebセミナー受け放題のスーパープレミアム会員などがございます。
会員登録がお済みでない方は、下記会員登録のボタンより、ご登録のお手続きをお願いいたします。