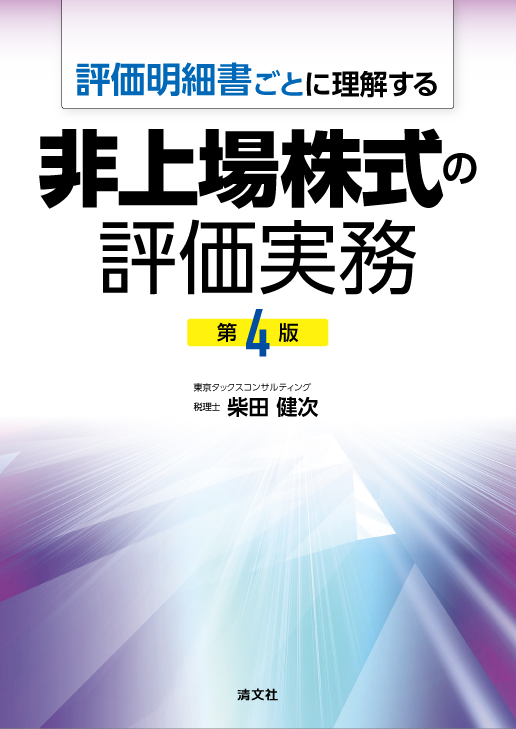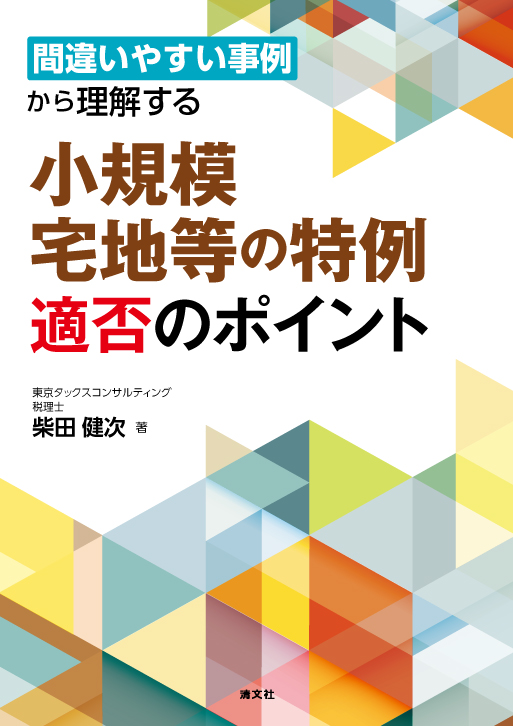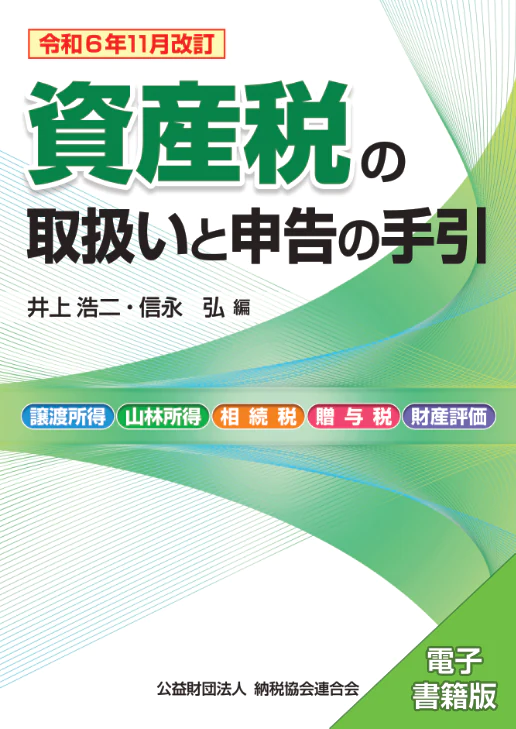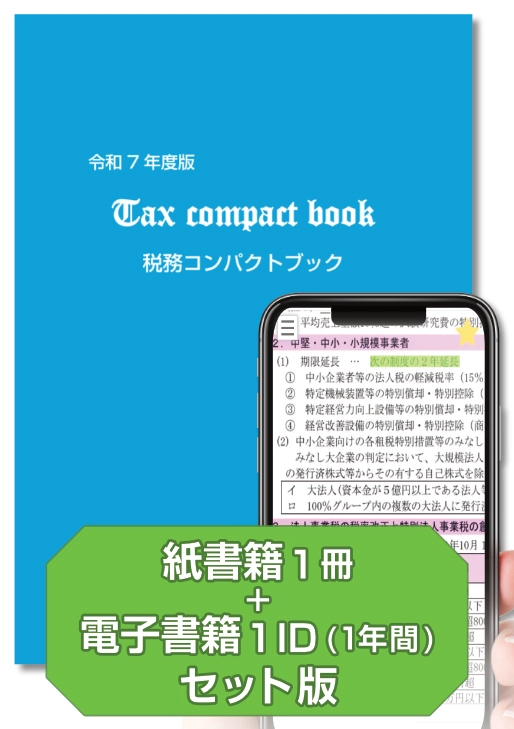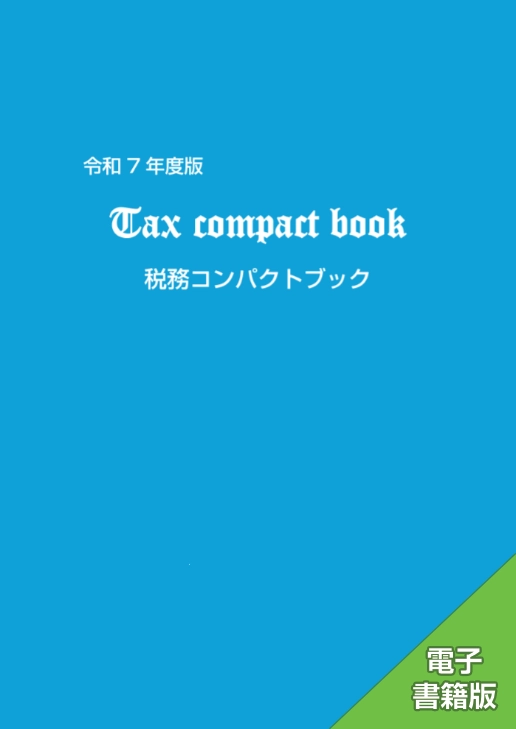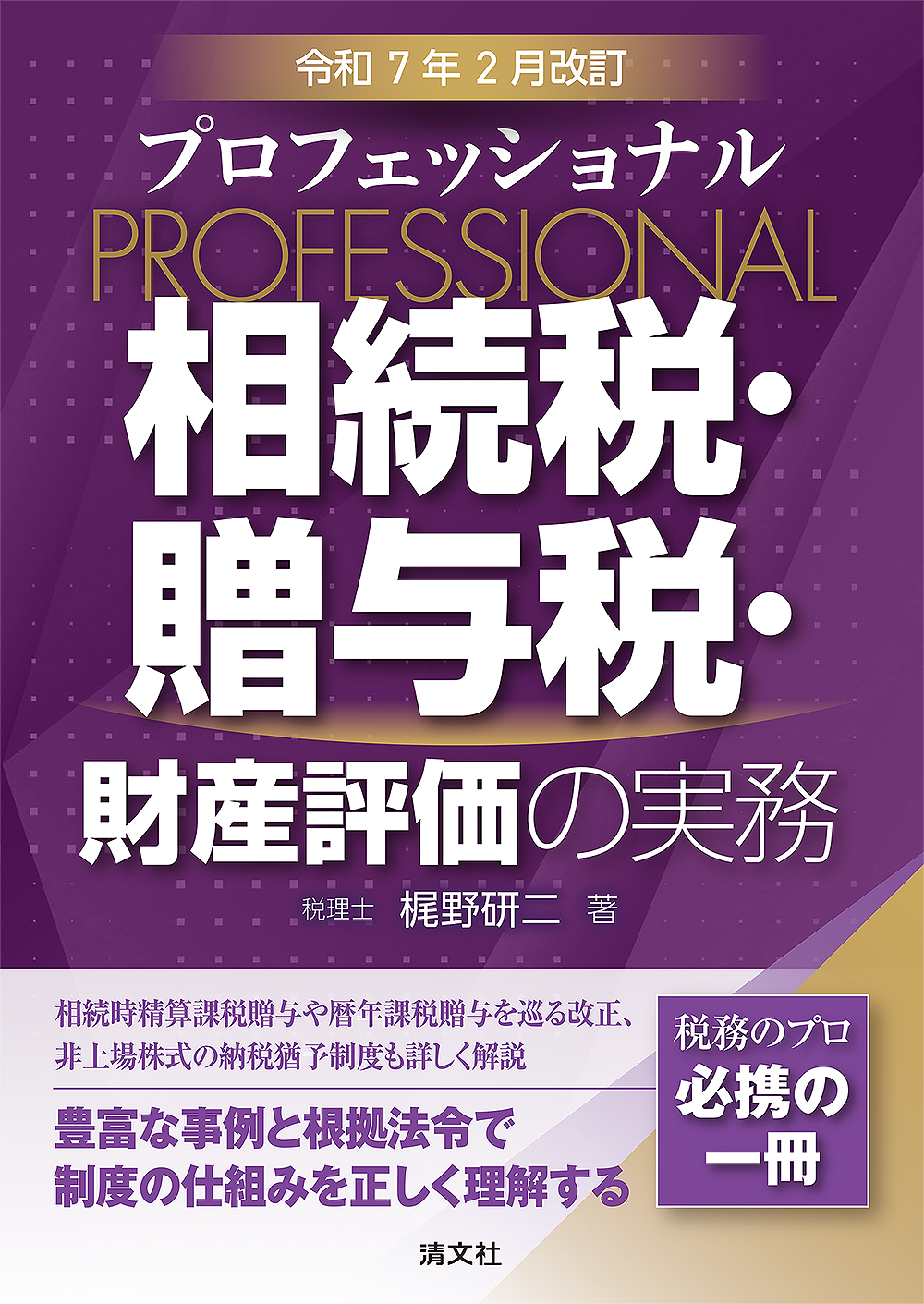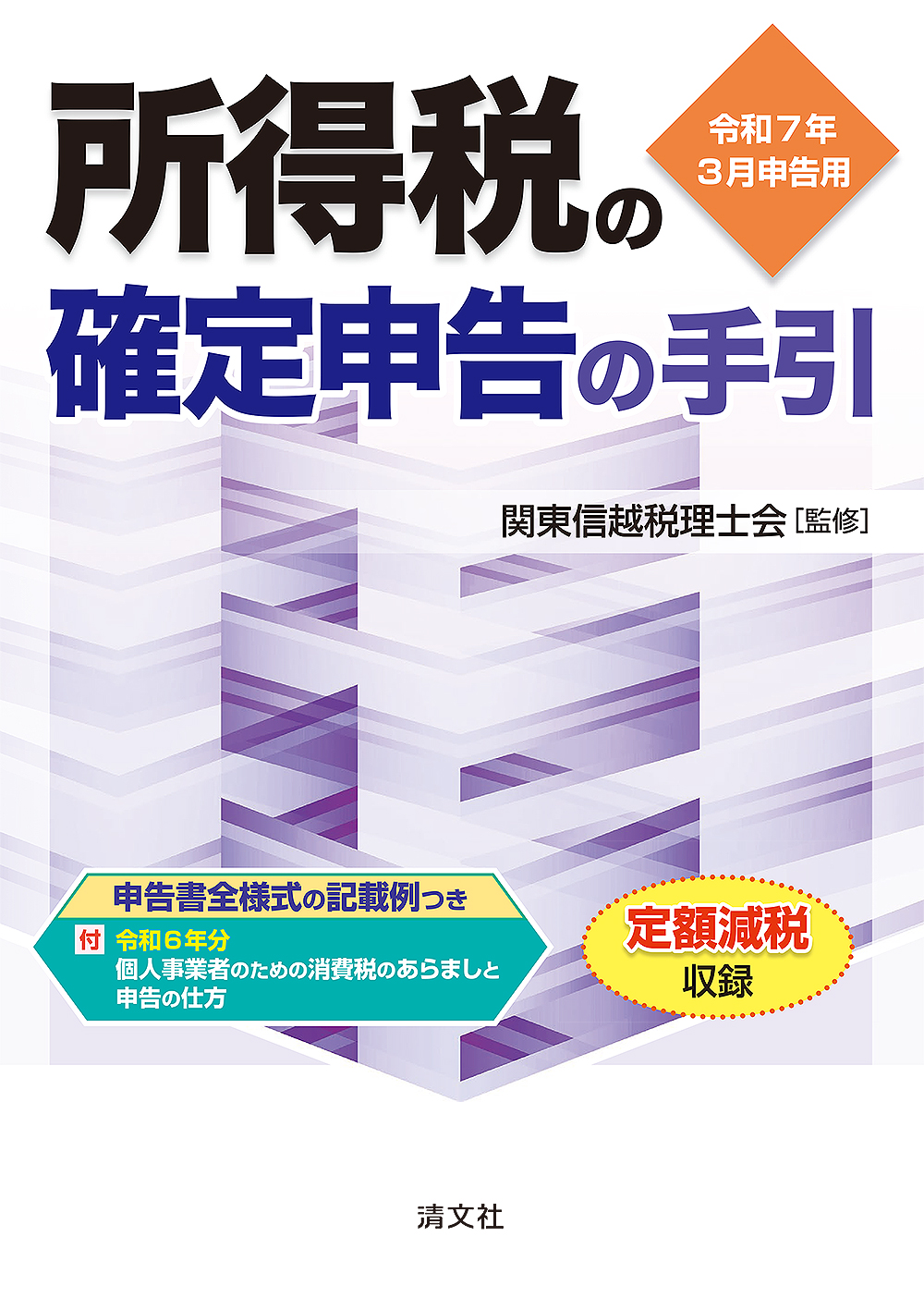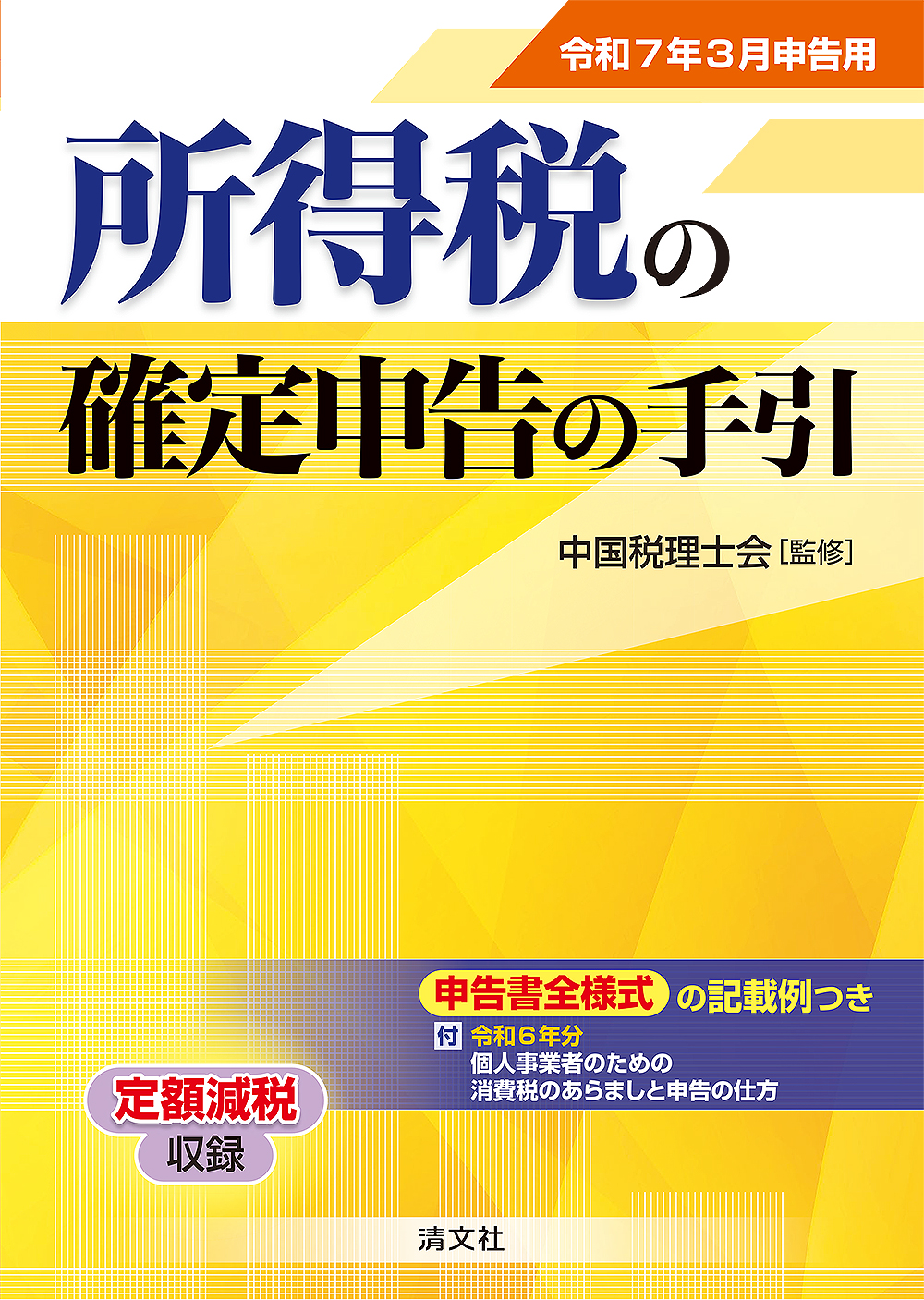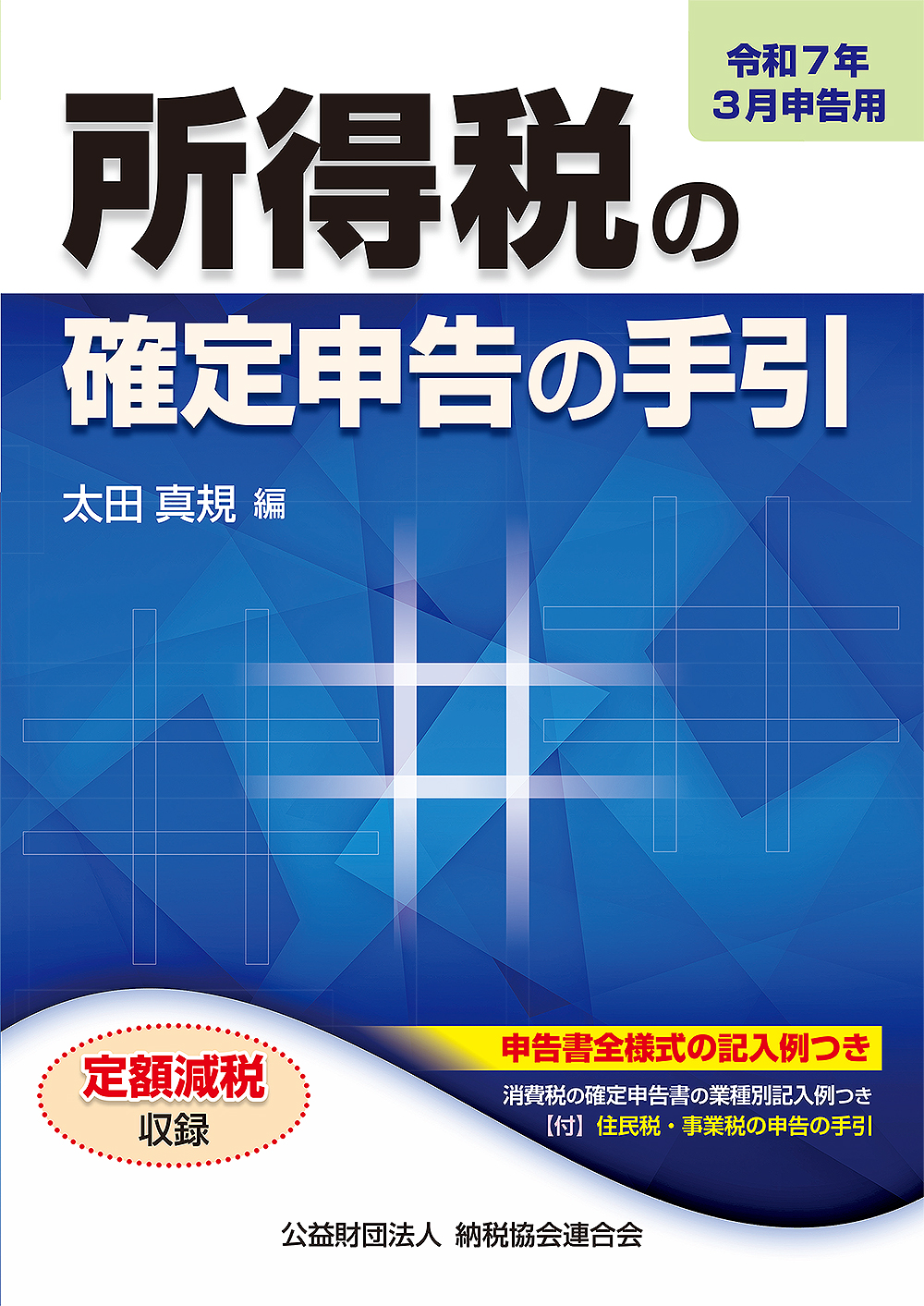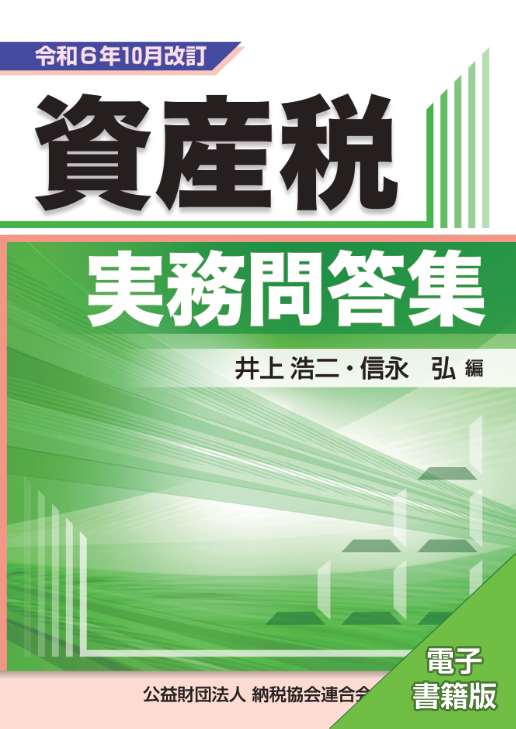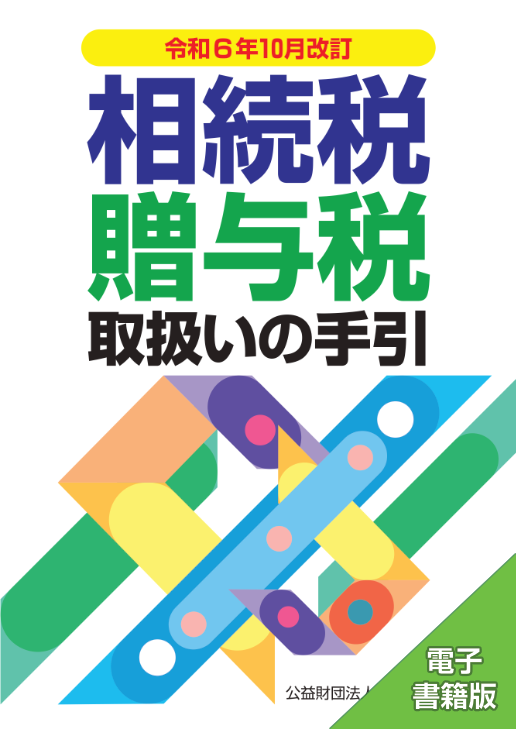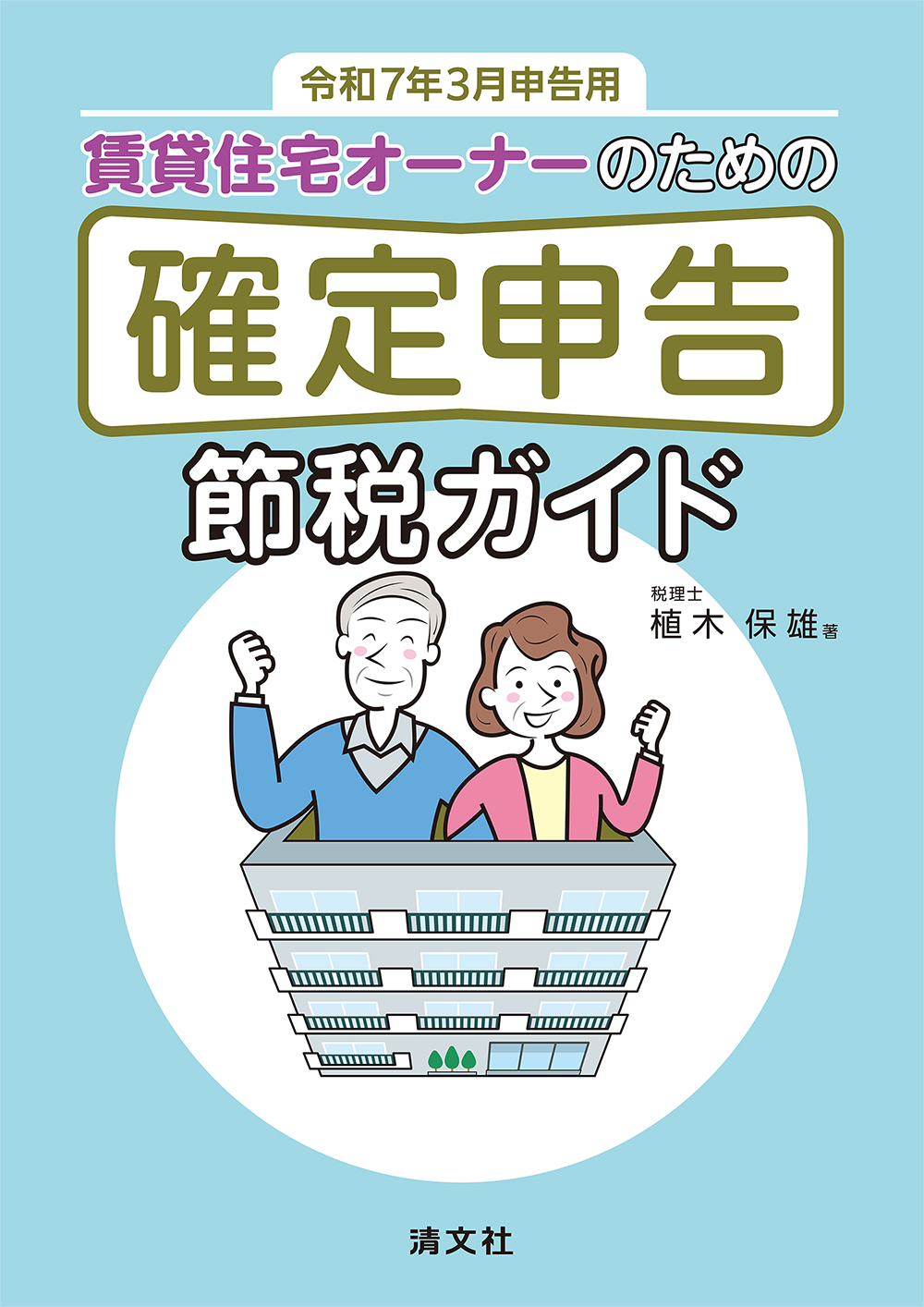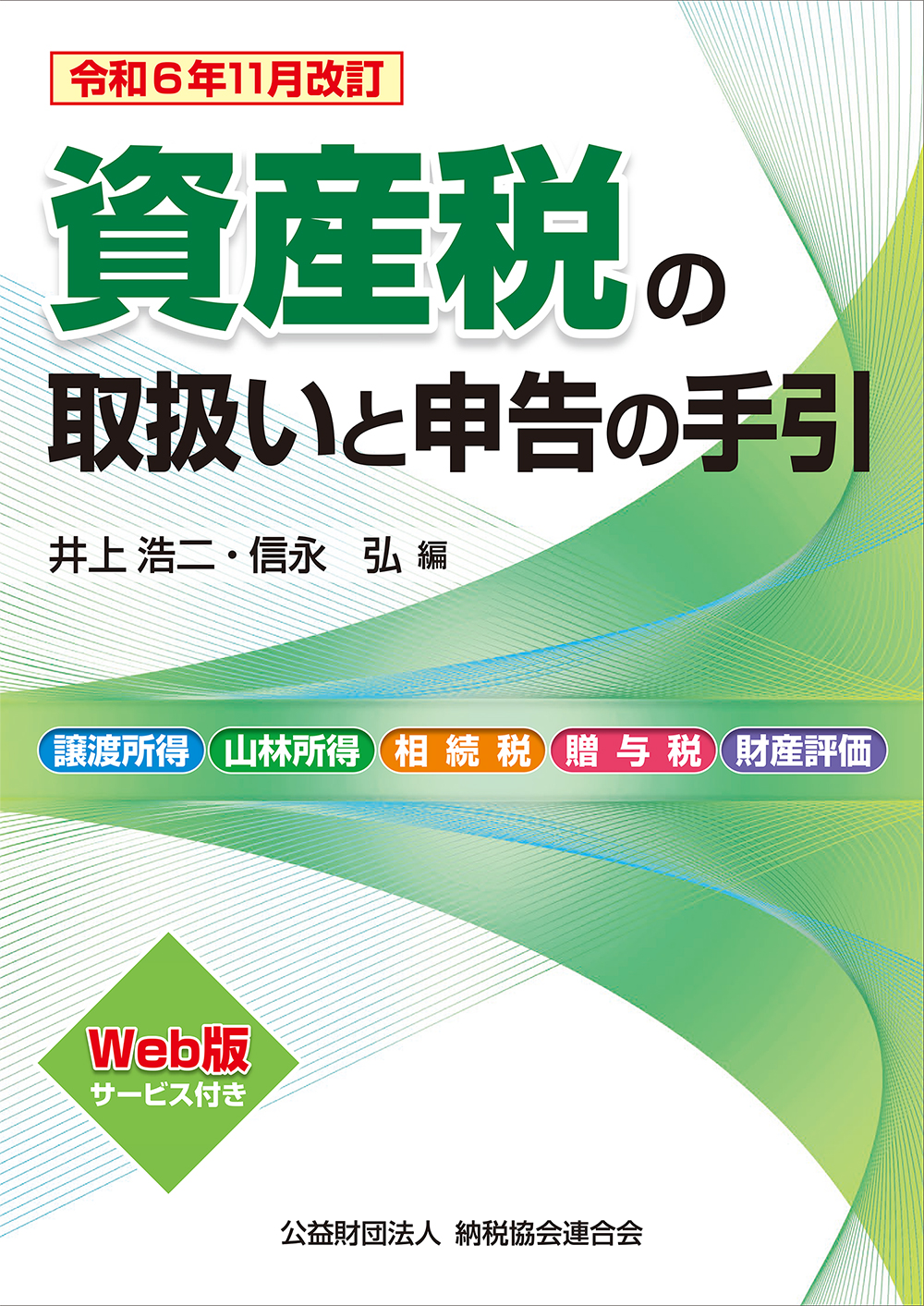〔事例で解決〕小規模宅地等特例Q&A
【第19回】
「2以上の居住用宅地等がある場合の特定居住用宅地等の特例」
税理士 柴田 健次
[Q]
被相続人である甲は、下記の通りAマンション、B宅地及び家屋、Cマンション、Dマンションを所有していましたが、このうち、特定居住用宅地等に係る小規模宅地等の特例を受けることができるのはどの宅地でしょうか。甲の相続人は、生計を一にしている配偶者である乙、生計を一にしている長男である丙(大学生)、生計を一にしている二男である丁(大学生)の3人です。土地及び家屋については、全て乙が相続で取得しています。
甲、乙、丙及び丁の宅地の利用状況は、下記の通りです。
① 甲は転勤中であり、平日は職場の近くである都内のAマンションで過ごし、週末はB宅地及び家屋で乙と過ごしていました。Aマンションは、都内のワンルームマンションで賃貸用として甲が購入したものですが、甲の転勤中に空き家となったため、転勤中の期間のみ使用する目的で利用しています。甲の転勤が終わった後は、第三者に賃貸する予定でしたが、転勤中に死亡しています。
② 乙は職場の近くであるB宅地及び家屋に居住しています。
③ 丙は、東京の大学の近くであるCマンションに居住していますが、週末の時間のある時にB宅地及び家屋で家族と過ごしています。丙は、大学4年で就職も決まっており、引き続き、Cマンションに居住する予定です。
④ 丁は、大学2年生であり京都の大学の近くであるDマンションに居住しています。年末年始のみB宅地及び家屋で家族と過ごしています。
この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員登録およびログインが必要です。
すでに会員登録をされている方は、下記ボタンからログインのうえ、ご覧ください。
Profession Journalのすべての記事をご覧いただくには、「プレミアム会員(有料)」へのご登録が必要となります。
なお、『速報解説』については「一般会員(無料)」へのご登録でも、ご覧いただけます。
※他にもWebセミナー受け放題のスーパープレミアム会員などがございます。
会員登録がお済みでない方は、下記会員登録のボタンより、ご登録のお手続きをお願いいたします。