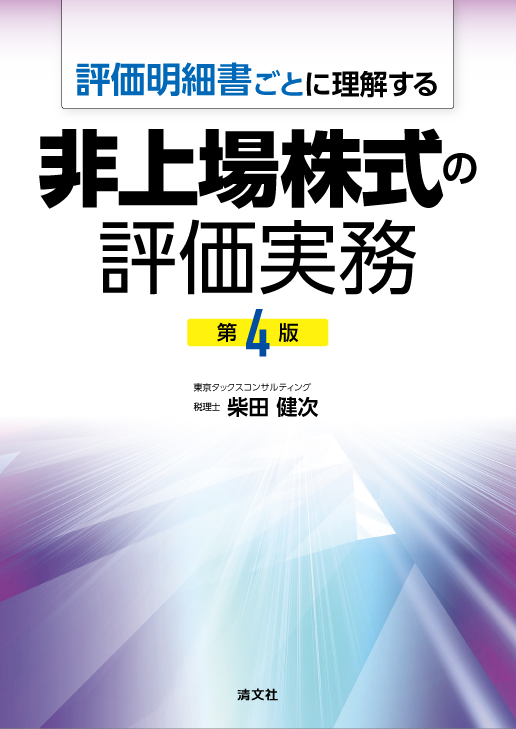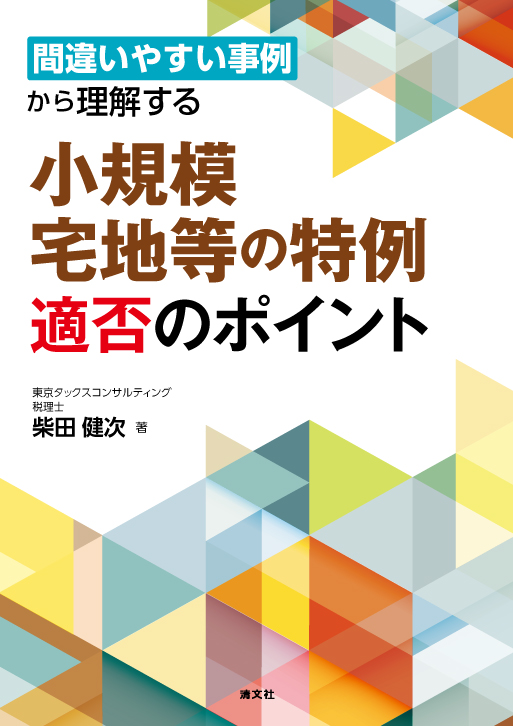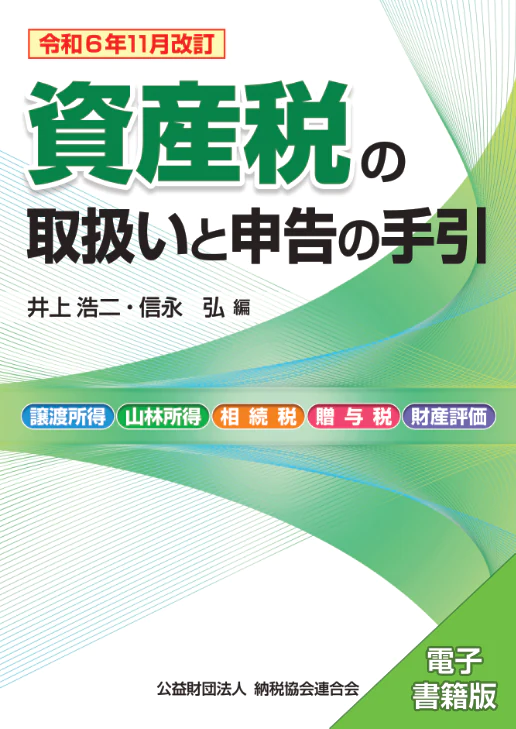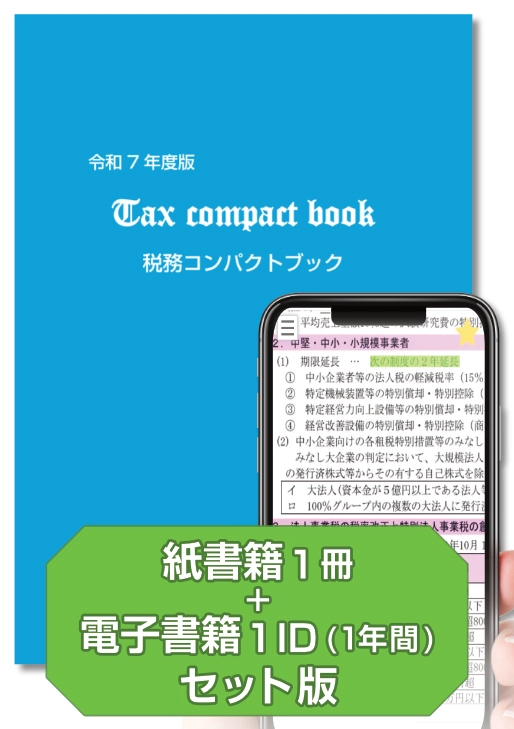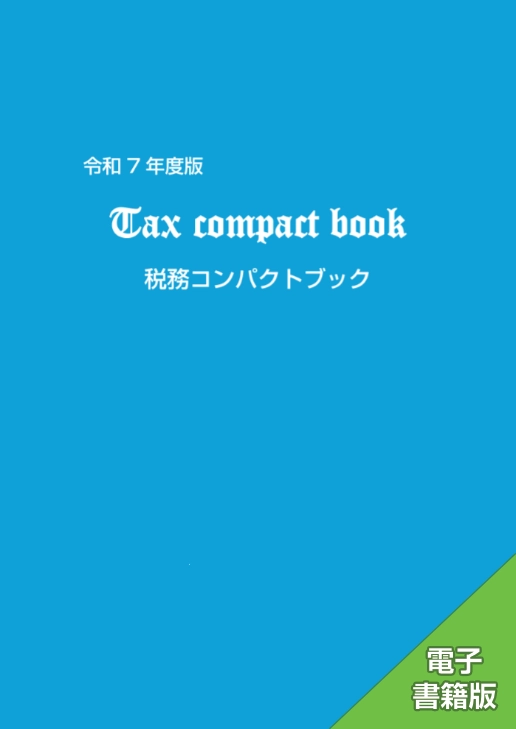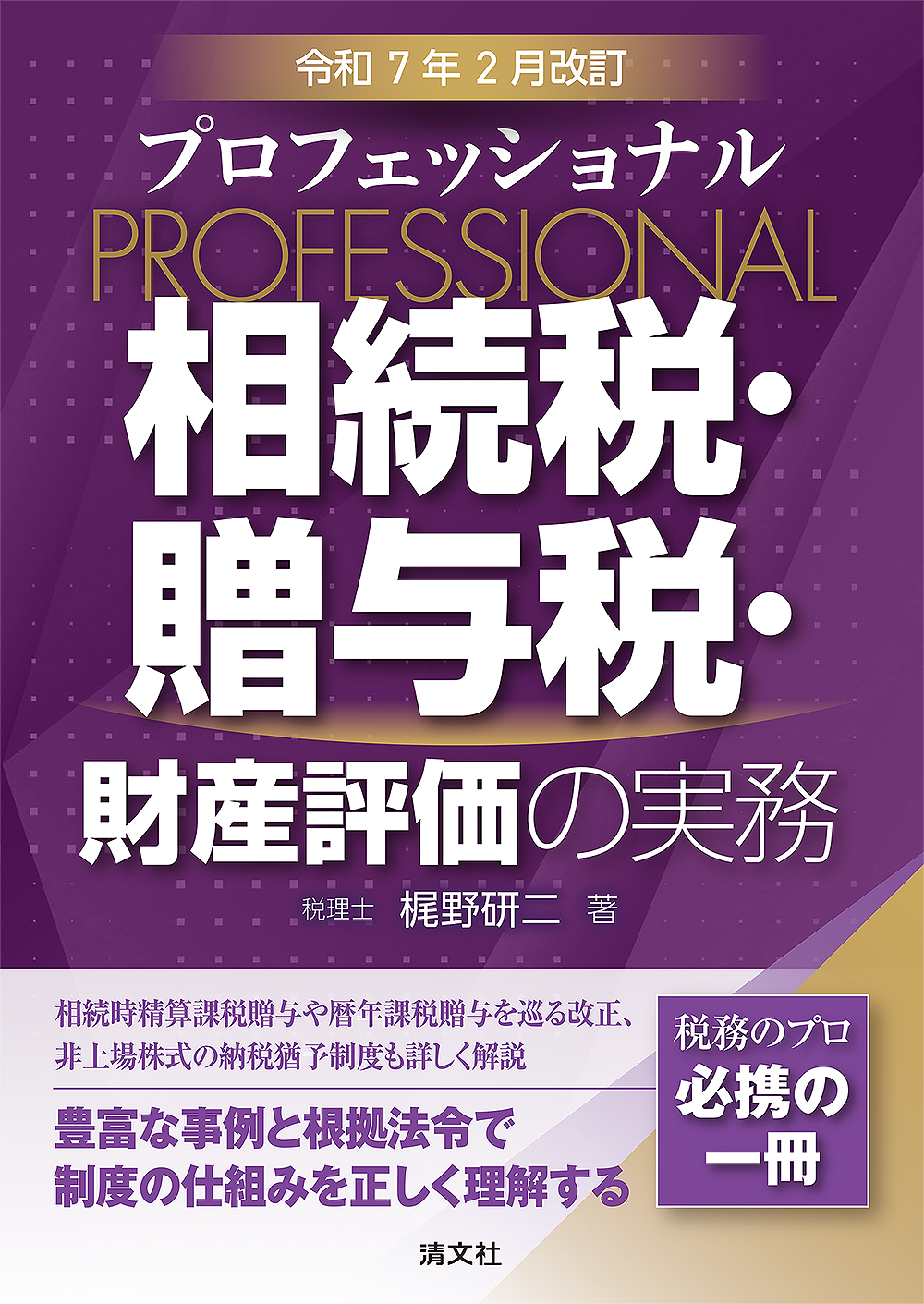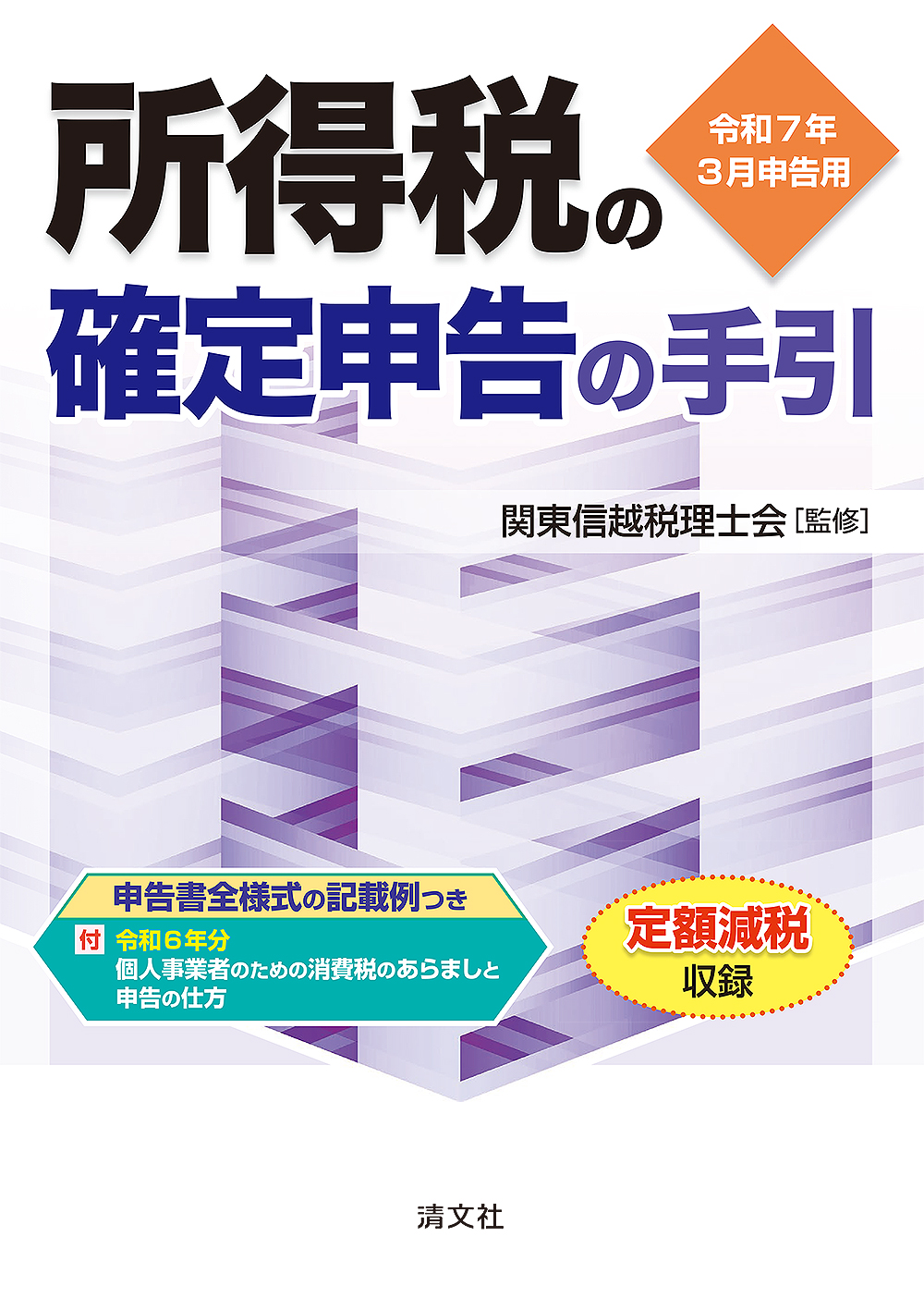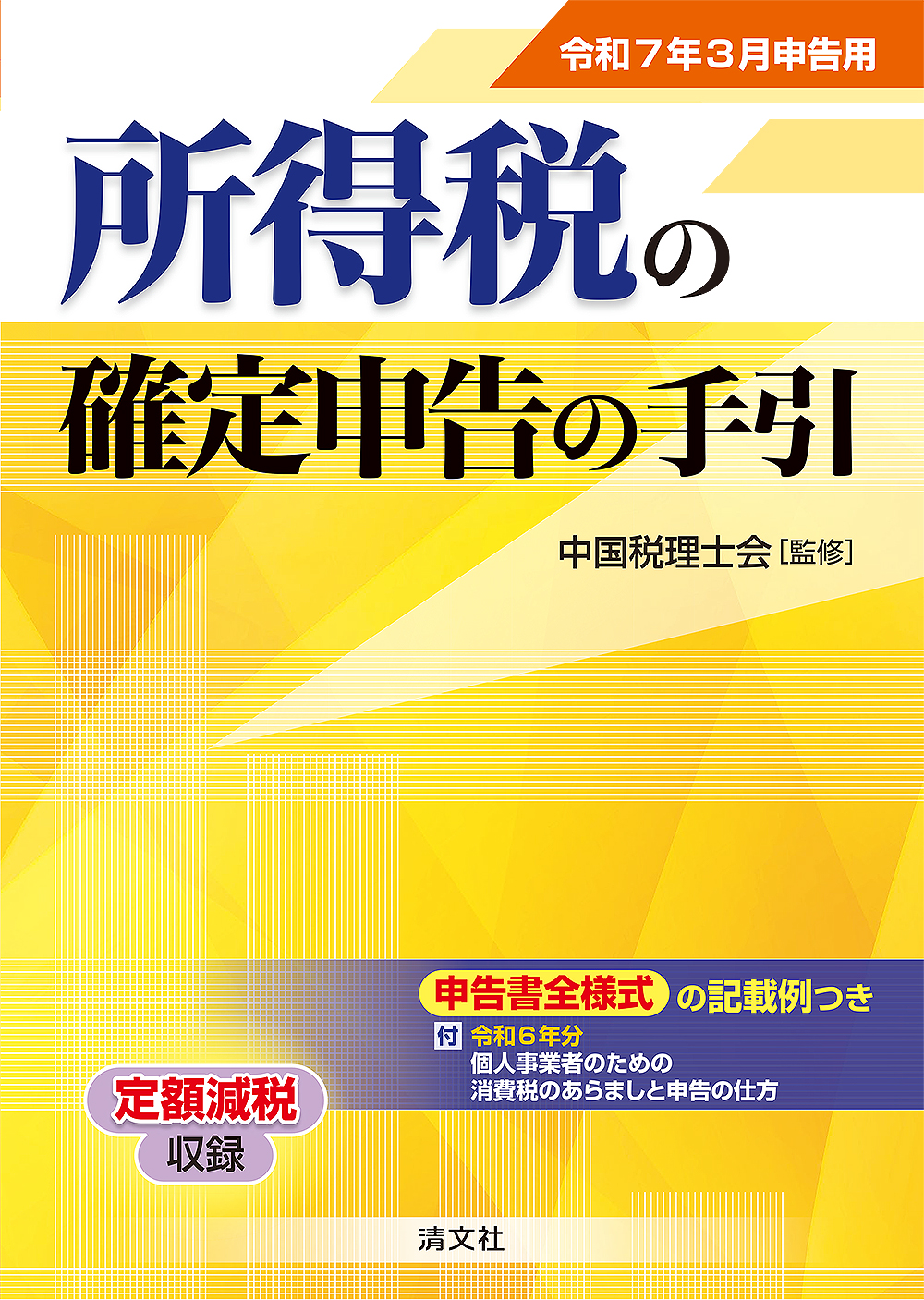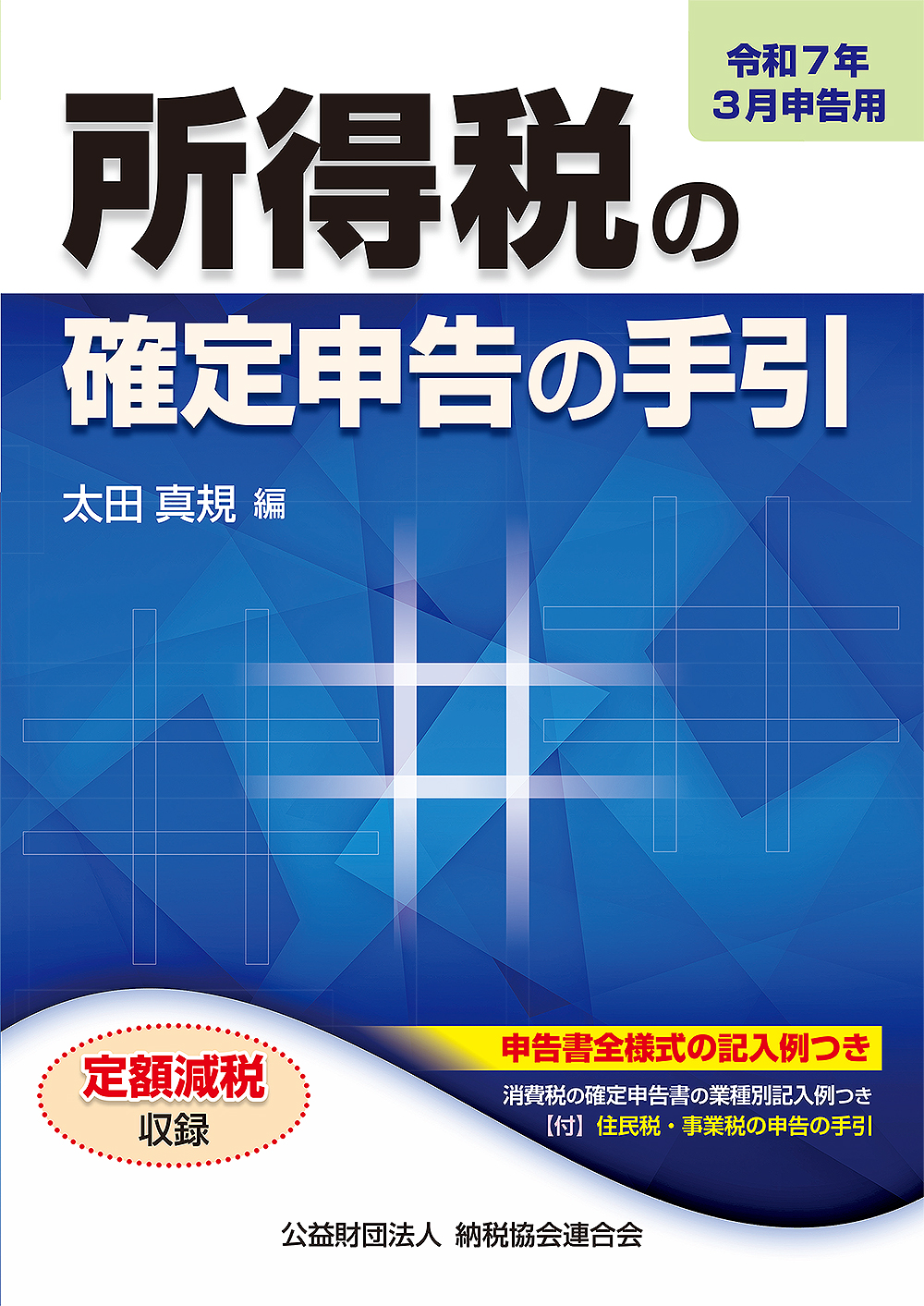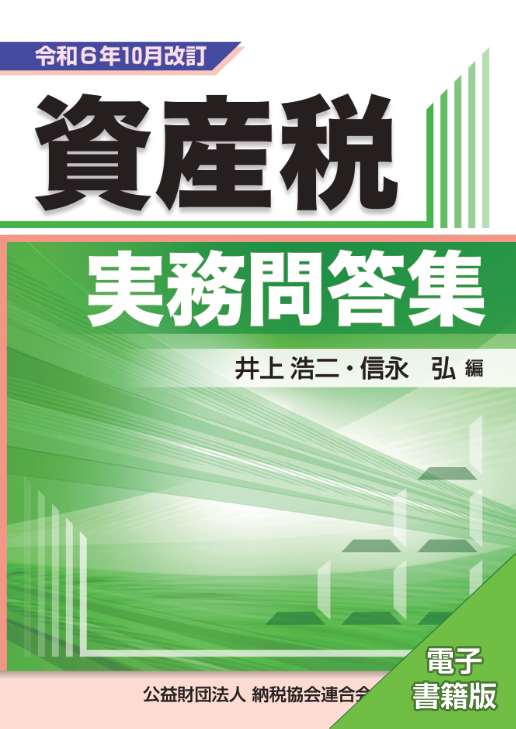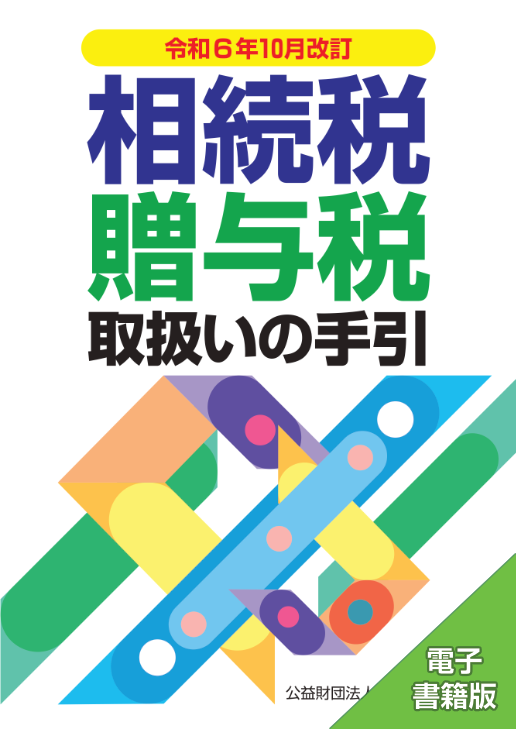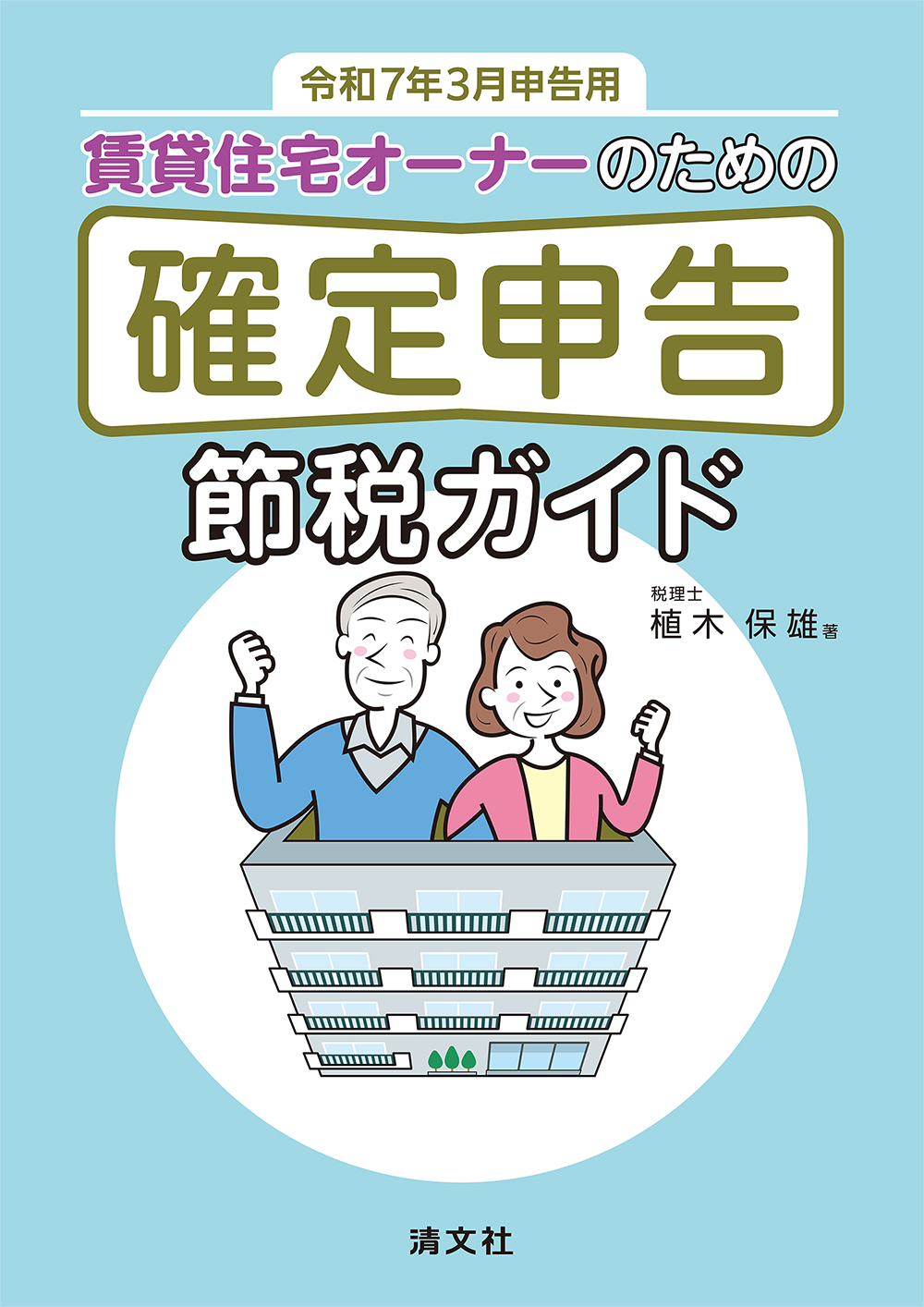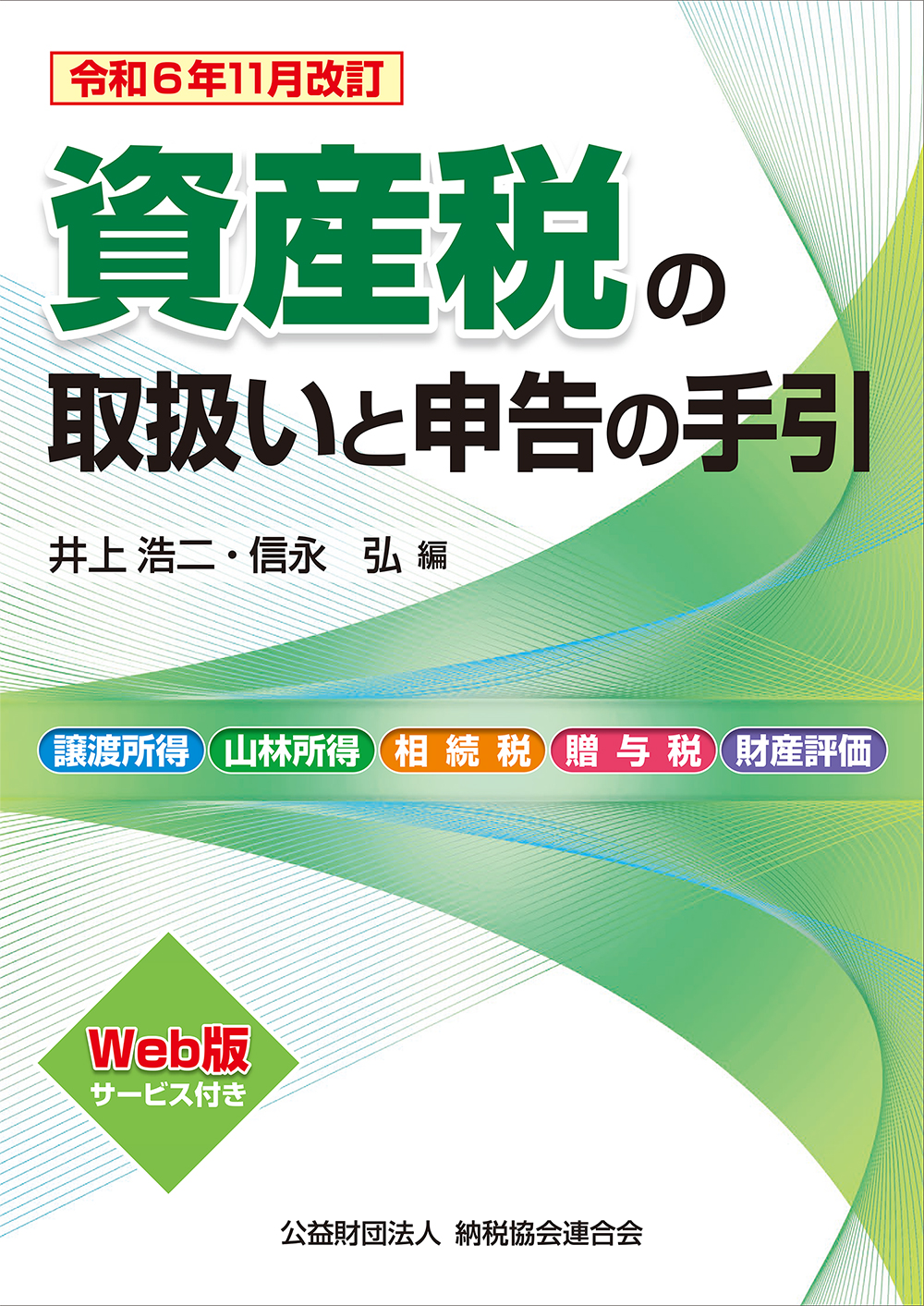〔事例で解決〕小規模宅地等特例Q&A
【第24回】
「主である建物と附属建物がある場合の特定居住用宅地等の特例の適否」
税理士 柴田 健次
[Q]
被相続人である甲(相続開始は令和4年2月1日)は、下記の宅地(330㎡)の上にA建物及びB建物を所有していました。A建物は主である建物120㎡、附属建物50㎡となっており、被相続人及びその配偶者乙が主である建物に居住し、附属建物は、離れ家のトイレと部屋のみであり、長男丙及び丙の配偶者の寝室として利用していました。B建物は丙と丙の配偶者及び子が居住の用に供していました。甲の推定相続人は、乙及び丙の2人であり、乙がA建物及び上記土地の2分の1を取得し、丙がB建物及び上記土地の2分の1を取得しています。丙は被相続人と生計を別にしている親族に該当します。
区分登記がされていない建物である場合には、被相続⼈⼜は被相続⼈の親族の居住の⽤に供されていた部分が被相続人の居住用宅地等として取り扱うこととされていますので、乙及び丙が取得した宅地等のうち、A建物の敷地部分は特例の対象になると考えていいでしょうか。
この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員登録およびログインが必要です。
すでに会員登録をされている方は、下記ボタンからログインのうえ、ご覧ください。
Profession Journalのすべての記事をご覧いただくには、「プレミアム会員(有料)」へのご登録が必要となります。
なお、『速報解説』については「一般会員(無料)」へのご登録でも、ご覧いただけます。
※他にもWebセミナー受け放題のスーパープレミアム会員などがございます。
会員登録がお済みでない方は、下記会員登録のボタンより、ご登録のお手続きをお願いいたします。