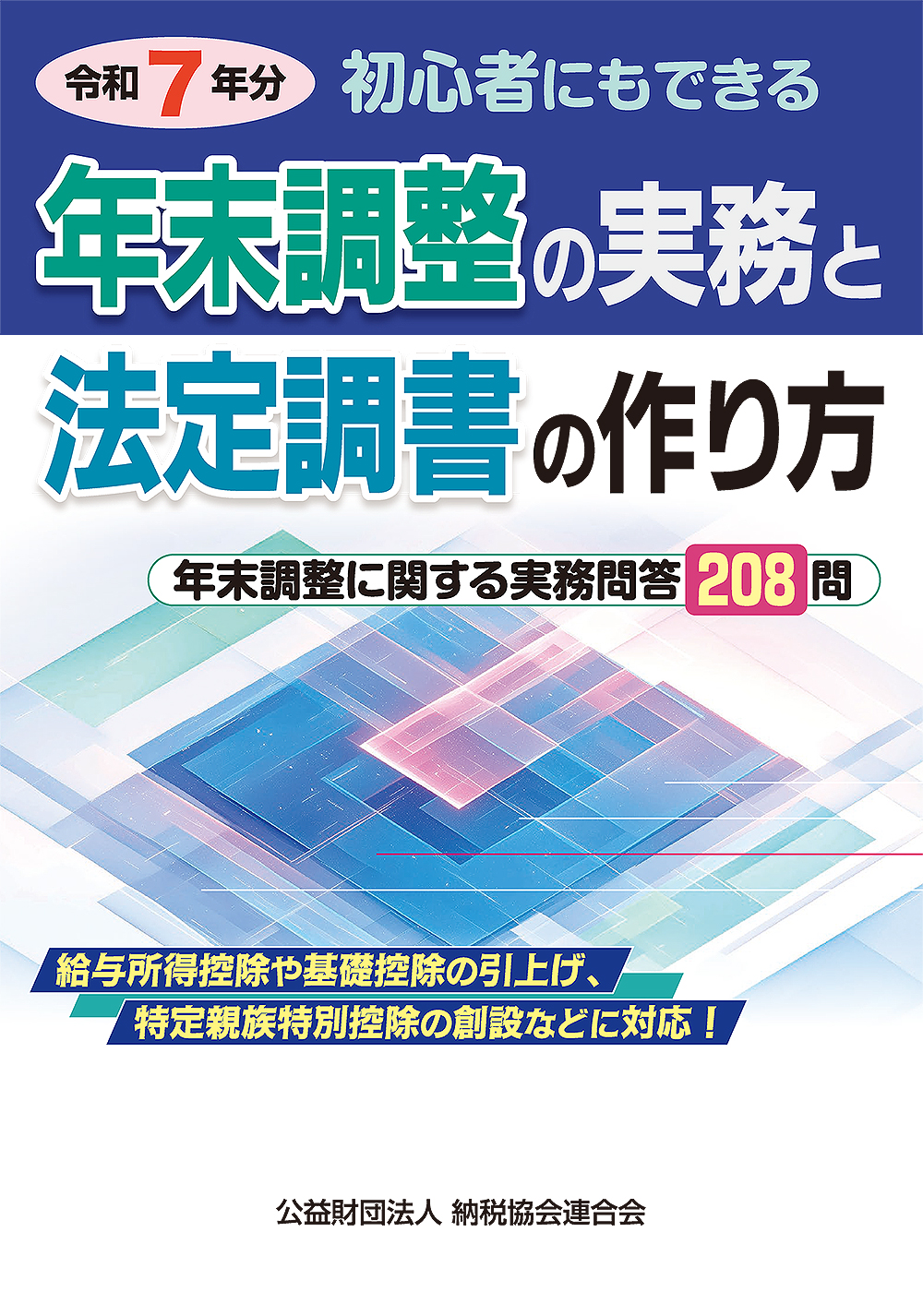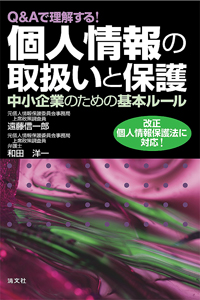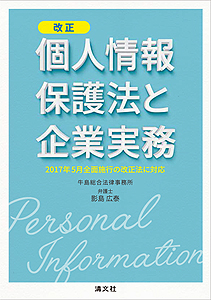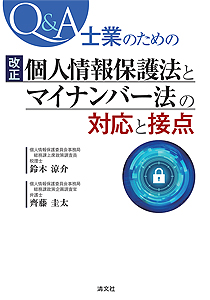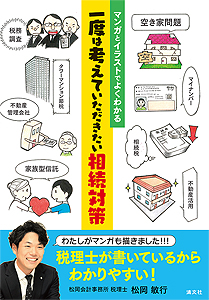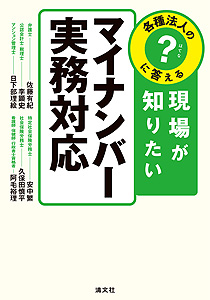〈平成27年分〉
おさえておきたい
年末調整のポイント
【第1回】
「注意しておきたい最近の改正事項」
公認会計士・税理士 篠藤 敦子
10月も下旬となり、年末調整に向けて準備を始める時期となった。年末調整の業務は、作業量が多く注意点も多岐にわたるため、早目に準備をしておきたい。
今回から3回シリーズで、年末調整における実務上の注意点やポイント等を解説する。
なお、各書類の記載方法や理解しておくべき用語の解説等については、過去の拙稿をご参照いただきたい。
【関連記事】
- 〈平成26年分〉おさえておきたい年末調整のポイント
【第3回】 『扶養控除等(異動)申告書』記載内容の検討
【第4回】 『保険料控除申告書 兼 配偶者特別控除申告書』記載内容の検討
【第5回】 『住宅借入金等特別控除申告書』記載内容の検討
- 〈平成25年分〉おさえておきたい年末調整のポイント
【第5回】 実務上、判断に迷うケースQ&A
- 〈平成24年分〉おさえておきたい年末調整のポイント
【第2回】 質問の多い事項を解説
今年から適用される税制改正事項のうち、今回の年末調整に大きな影響を及ぼすものはない。しかし、今年の年末調整事務と同時並行で行われることの多い「平成28年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の受理に際しては、2つの改正事項が影響する。
そこで、今回は、年末調整に関係する最近の主な改正事項と「平成28年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に影響のある改正事項についてまとめることとする。
(1) 注意が必要な最近の税制改正事項
最近の税制改正事項のうち、今年の年末調整に影響のあるものをまとめると次のとおりである。
▷給与所得控除額の上限設定(※)
〔コメント:2018/11/6〕
平成29年分~平成31年分までは220万円が上限となり、平成32年分以後は195万円が上限となる。
〔概要〕
給与等の収入金額が1,500万円を超える場合の給与所得控除額は、一律245万円とされた(所法28③六)。
〔適用開始年度〕
平成25年分
(※) 平成26年度の税制改正により、給与所得控除の上限をさらに段階的に引き下げることが決まっている。当該改正は、平成28年分以後の所得税に対して適用される。
【参考】 拙稿「《速報解説》 給与所得控除の見直し(縮小)~平成26年度税制改正大綱~」
▷復興特別所得税の創設
〔概要〕
平成25年1月1日から平成49年12月31日まで、所得税と併せて復興特別所得税が課される(復興財確法9①)。
〔適用開始年度〕
平成25年分
▷生命保険料控除の改組
〔概要〕
介護医療保険料控除が創設され、控除の適用限度額が12万円となった(所法76①②③④)。
〔適用開始年度〕
平成24年分
▷扶養控除の見直し
〔概要〕
16歳未満の扶養親族(年少扶養親族)に対する扶養控除及び16歳以上19歳未満の扶養親族に対する上乗せ額(25万円)が廃止された(所法2①三四の二・三、84①)。
〔適用開始年度〕
平成23年分
▷同居特別障害者加算措置の改組
〔概要〕
同居特別障害者の加算35万円が、扶養控除の額への上乗せから、障害者控除の額に上乗せする方法に変更された(所法79③)。
〔適用開始年度〕
平成23年分
各改正事項の詳細については、以下の拙稿をご参照いただきたい。
【関連記事】
- 〈平成26年分〉おさえておきたい年末調整のポイント
【第1回】 注意しておきたい最近の改正事項
- 〈平成25年分〉おさえておきたい年末調整のポイント
【第1回】 給与所得控除の上限設定
【第2回】 生命保険料控除について~改正による記載もれ・計算誤りに注意~
【第3回】 復興特別所得税(その1)~概要から源泉処理まで再確認~
【第4回】 復興特別所得税(その2)~年末調整の手順と設例~
- 〈平成24年分〉おさえておきたい年末調整のポイント
【第1回】 今年度適用となる改正事項 (生命保険料控除の改正)
(2) 「平成28年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に影響する改正事項
① マイナンバー制度への対応
いわゆるマイナンバー法の施行により、平成28年1月以降、国等へ税務関係書類を提出するときには個人番号の記載が求められる。
これに伴い、「平成28年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」については、給与所得者本人、控除対象配偶者、扶養親族の個人番号を記載することが必要となる。
源泉徴収義務者が従業員等から個人番号の提供を受ける場合には、本人確認を実施しなければならない。具体的には、提供を受ける番号が正しいことの確認(番号確認)と番号の提供者が正しい持ち主であることの確認(身元確認)の2つを実施する必要がある。
本人確認の方法には、次の2つがある。
(ア) 個人番号カードによる確認(番号確認と身元確認の両方を実施できる。)
(イ) 個人番号カード以外の書類等による確認(書類等を組合せることにより、番号確認と身元確認を実施する。)
従業員等が個人番号カードを取得するまでにはある程度の時間を要すると思われるため、しばらくは(イ)の方法で本人確認を行うケースが多くなると考えられる。
(イ)の方法の場合、さまざまな書類の組合せがある。一般的な組み合わせを挙げると次のとおりである。
なお、雇用関係にある者等から個人番号の提供を受ける場合には、実質的な身元確認はすでにできていると考えられるため、身元確認の書類は要しないものとされている。
◆番号確認:通知カード又は住民票の写し(番号付きのもの)
+
◆身元確認:顔写真付きの身分証明書である運転免許証又はパスポート
(※) 上記の方法によることが困難な場合には、国税庁から公表されている本人確認に関する告示が参考になる。
【参考】 国税庁ホームページ「国税庁告示について」
源泉徴収事務において、マイナンバーの取得は、必ずしも平成28年1月までに行う必要はない。中途退職者を除き、平成28年分の源泉徴収票(提出期限:平成29年1月末)からマイナンバーを記載することとなるため、それまでに取得していればよい。
なお、本人確認の詳しい解説については、本誌掲載の岡田健司公認会計士による以下の連載が参考になる。
「従業員等からの『マイナンバー』入手の手順」(岡田健司)
② 国外居住親族を扶養控除等の対象とするときの取扱い
平成28年分以後の所得税及び平成29年度分以後の個人住民税について、国外に居住する親族を扶養控除等の対象とするときには、「親族関係書類」と「送金関係書類」を扶養控除等申告書に添付等することが必要となった(所令316の2②③)。
このうち、「親族関係書類」については、「平成28年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出するときに提出又は提示しなければならない(※)。
(※) 配偶者特別控除の適用を受ける場合には、「平成28年分 給与所得者の配偶者特別控除申告書」を提出するときに提出又は提示する。
制度の詳細については、以下の拙稿をご参照いただきたい。
【関連記事】
なお、扶養控除等申告書に国外居住親族を記載しても「親族関係書類」を提出又は提示していない場合には、源泉徴収税額の計算上その親族は扶養親族等の数に反映されない。「親族関係書類」が提出又は提示された後、最初に支払われる給与等の計算から扶養親族等の数に加えることとなる。
* * *
次回は、海外転勤、外国人に関わる年末調整について解説を行う予定である。
〔凡例〕
所法・・・所得税法
所令・・・所得税法施行令
復興財確法・・・東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法
(例)所法28③六・・・所得税法28条3項6号
(了)