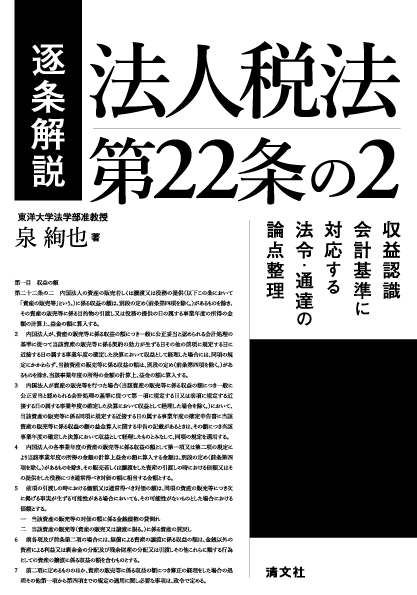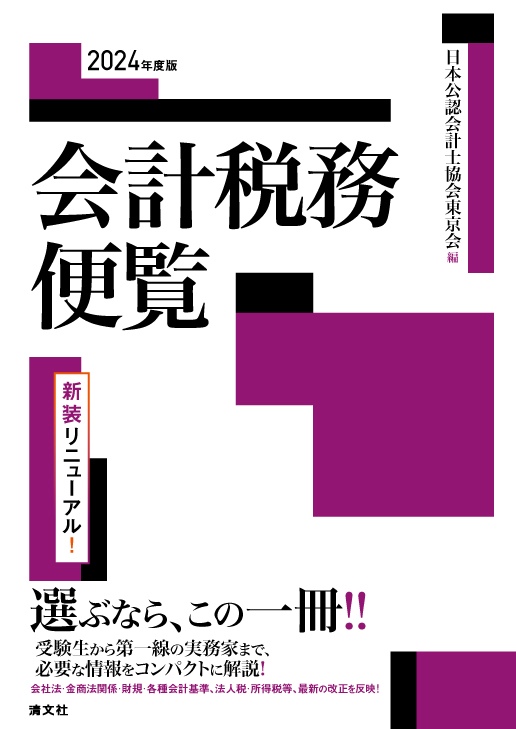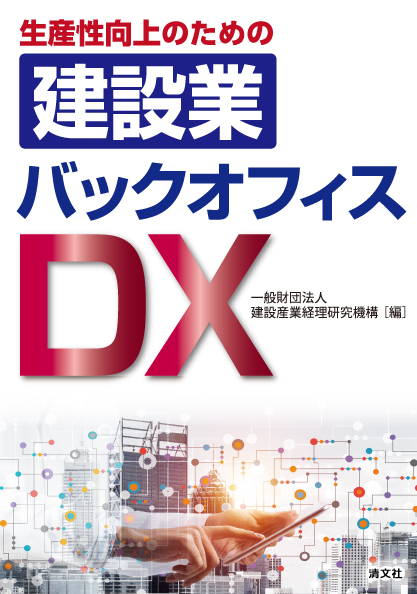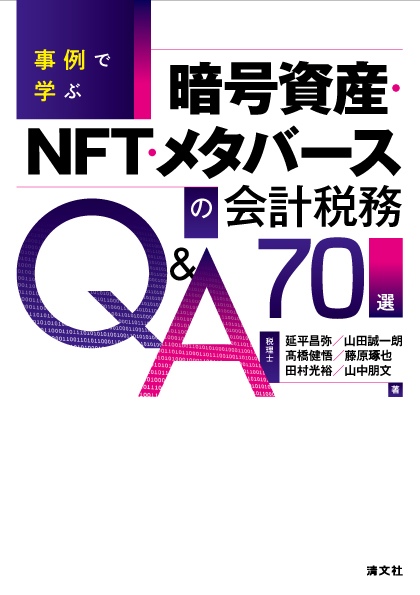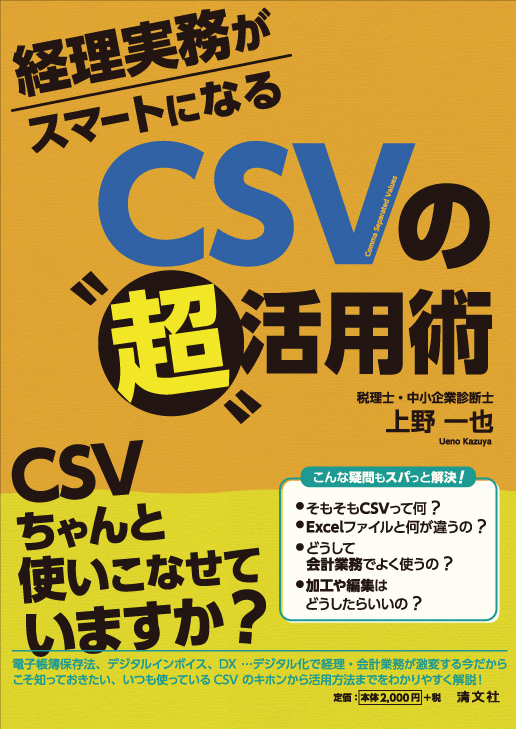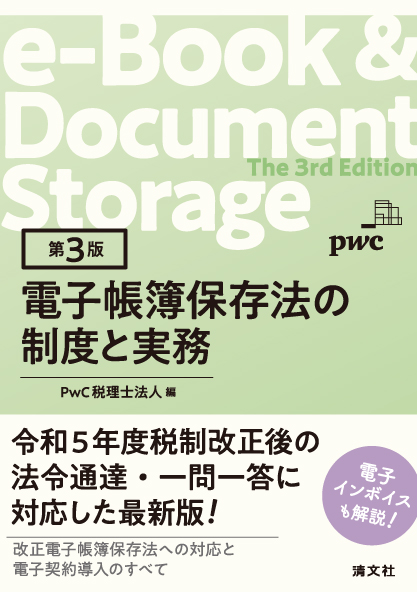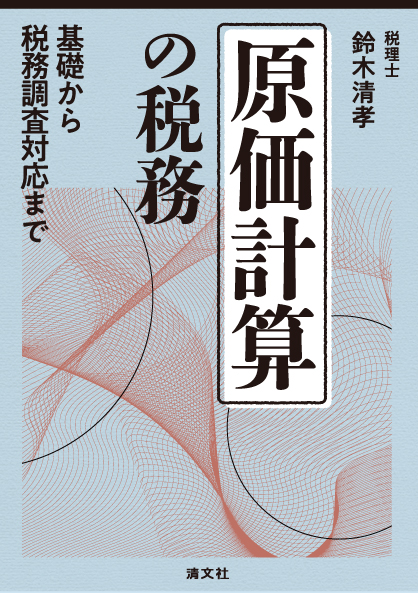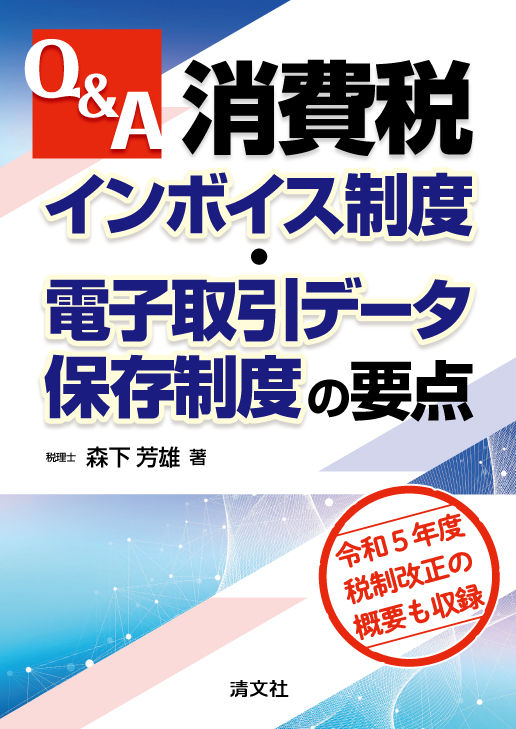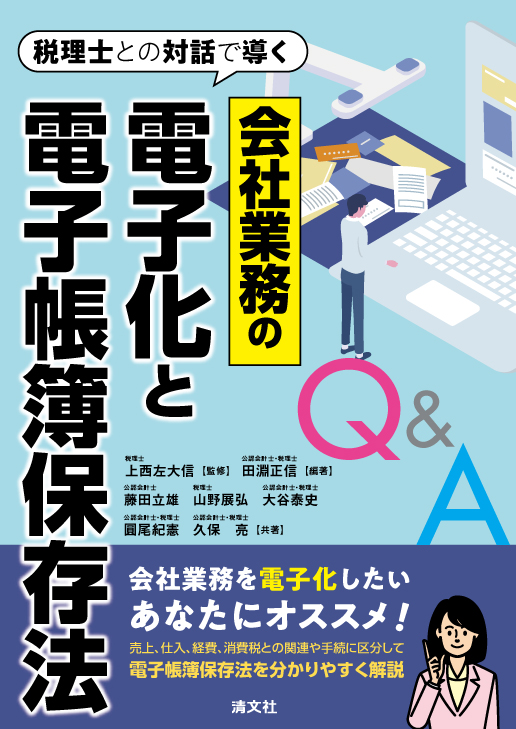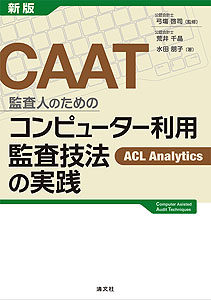暗号資産(トークン)・NFT をめぐる税務
【第1回】 ★一般会員公開中★
〔連載に当たって〕
【第2回】 ★一般会員公開中★
第1章 暗号資産の税務と課税問題
第1節 暗号資産とは
1 暗号資産の定義
2 通貨該当性・強制通用力の有無
【第3回】 ★一般会員公開中★
3 暗号資産の私法上の性質・位置付け
(1) 総論
(2) 各論
《更なる考察》 「占有=所有」構成
《更なる考察》 私法の議論から得られる示唆
【第4回】
第2節 所得税における暗号資産の税務と課税問題
1 所得税法の暗号資産関連規定
(1) 暗号資産の定義
【第5回】
(2) 暗号資産の贈与・低額譲渡に関する規定
【第6回】
(3) 暗号資産を譲渡した場合の計算に関する規定
ア 棚卸資産と売上原価の計算
イ 暗号資産の譲渡原価の計算
ウ 暗号資産の取得価額
【第7回】
エ 年末時点での1単位当たりの取得価額
(ア) 総平均法と移動平均法
(イ) 評価方法の選定・変更等
【第8回】
(ウ) 相続等により取得した暗号資産の取得価額
【第9回】
(エ) 暗号資産の取得価額がわからない場合と5%通達の問題
NFTに関する税務上の取扱いに係るFAQ詳解
【第10回】
◆本連載の今後の進め方について◆
問1 NFTを組成して第三者に譲渡した場合(一次流通)
1 所得の定義
2 「デジタルアートの閲覧に関する権利」が前提とされたことに伴うリスク
3 NFT取引の着眼点とNFTに係る権利の設定という構成
4 一次流通の場合の所得区分
5 法人税の取扱い
【第11回】
問2 NFTを組成して知人に贈与した場合(一次流通)
1 贈与した個人の取扱い
2 贈与した法人の取扱い
問3 非居住者がNFTを組成して、日本のマーケットプレイスで譲渡した場合(一次流通)
【第12回】
問4 購入したNFTを第三者に転売した場合(二次流通)
1 二次流通の場合の所得区分
2 譲渡所得金額の計算
3 「デジタルアートの閲覧に関する権利」という前提
4 法人税の取扱い
【第13回】
問5 第三者の不正アクセスにより購入したNFTが消失した場合
問6 役務提供の対価として取引先が発行するトークンを取得した場合
【第14回】
問7 商品の購入の際に購入先が発行するトークンを取得した場合
【第15回】
問8 ブロックチェーンゲームの報酬としてゲーム内通貨を取得した場合
【第16回】
問9 NFTを贈与又は相続により取得した場合
【第17回】
問10 NFT取引に係る源泉所得税の取扱い
【第18回】
問11 NFT取引に係る消費税の取扱い①(デジタルアートの制作者)
【第19回】
問12 NFT取引に係る消費税の取扱い②(デジタルアートに係るNFTの転売者)
【第20回】
問13 財産債務調書への記載の要否
問14 財産債務調書へのNFTの価額の記載方法
問15 国外財産調書への記載の要否
【第21回】
2 暗号資産取引と所得区分(所得の種類)
(1) 暗号資産取引と所得区分の概要
【第22回】
(2) 譲渡所得該当性を否定する国税庁の根拠
【第23回】
(3) 国会における議論①:譲渡所得該当性を否定する根拠
【第24回】
(4) 国会における議論②:資産ではあるが、譲渡所得の基因となる資産ではない?
【第25回】
(5) 国会における議論③:譲渡所得を肯定する学説と外貨の取扱い
【第26回】
(6) 国税庁の見解に対する疑問
ア 「①清算課税説」
【第27回】
イ 「②支払手段性」
【第28回】
ウ 「③暗号資産の譲渡益の性質」と「④結論」
【第29回】
《更なる考察》邦貨と外貨の交換(両替)と所得税法33条の「譲渡」
【第30回】
3 所得税における暗号資産の信用取引
【第31回】
4 その他雑所得と必要経費
(1) 必要経費の問題
【第32回】
(2) 業務に係る雑所得とその他雑所得の区分とその判断基準
【第33回】
5 マイニング所得と雑所得
(1) マイニングとは
(2) 事案の概要
(3) 基礎事実(請求人による仮想通貨のマイニングについて)
(4) 当事者の主張と争点
(5) 審判所の判断
ア 審判所の判断枠組み
イ 結論と理由
【第34回】
6 異なる種類の暗号資産同士の交換は課税イベントか
【第35回】
7 暗号資産同士の交換時に課税しないという改正要望
【第36回】
8 暗号資産の所得は誰に帰属するか
【第37回】
9 暗号資産の節税コンサルティングの被害と損害賠償
(1) 事案の概要
(2) 事実関係
(3) 裁判所の判断
(4) 類似事案における重加算税の賦課
【第38回】
10 暗号資産に係る所得を分離課税にしてほしいという改正要望
【第39回】
11 詐欺・盗難等による暗号資産の損失①(譲渡原価等と現金類似の取扱い)
【第40回】
12 詐欺・盗難等による暗号資産の損失②(雑所得の基因となる資産の損失)
【第41回】
13 詐欺・盗難等による暗号資産の損失③(雑損控除)
【第42回】
14 秘密鍵を紛失した場合
【第43回】
15 暗号資産交換業者から暗号資産に代えて金銭の補償を受けた場合
(1) 国税庁の見解
(2) 損害賠償金の課税関係
【第44回】
(3) 補償金の非課税所得該当性
(4) タックスアンサーの回答の検討
【第45回】
16 暗号資産の損失と立証責任
(1) 事案の概要
(2) 基礎事実
(3) 争点
(4) 争点についての当事者の主張
【第46回】
(5) 審判所の判断
(6) コメント
【第47回】
17 ビットコインETFと分離課税(その1):概要
(1) SECによるビットコインETFの承認
(2) ETFとは
(3) ビットコインETFの特徴
【第48回】
18 ビットコインETFと分離課税(その2):問題意識①
【第49回】
19 ビットコインETFと分離課税(その3):問題意識②
【第50回】
20 ビットコインETFと分離課税(その4):本信託の概要
(1) 本信託と本件持分
(2) 本信託の設立
(3) 本信託の投資目的等
(4) 本信託とビットコイン等
(5) その他
【第51回】
21 ビットコインETFと分離課税(その5):本信託のスキーム図と主な関係者
(1) スキーム図
(2) 主な関係者
ア スポンサー(Sponsor)
イ 受託者(Trustee)
ウ 管理者(Administrator)
エ 名義書換代理人(Transfer Agent)
オ ビットコインカストディアン(Bitcoin Custodian)
カ キャッシュカストディアン(Cash Custodian)
キ 指定参加者(Authorized Participant)
ク 持分所有者(Shareholder)
ケ その他の関係者
【第52回】
22 ビットコインETFと分離課税(その6):本信託の仕組み
(1) 設定と償還(指定参加者による買注文と売注文)
ア バスケット単位による設定と償還
イ 発行プロセス
ウ 償還プロセス
(2) 資金の使途
(3) ハードフォークによって生ずる付随的権利等の取扱い
(4) 持分所有者に対する分配
(5) 本信託の終了
【第53回】
(6) 受益権と本件持分
ア 概要
イ 本件持分の発行方式等
ウ 本件持分の譲渡方式等
(7) 米国連邦所得税の課税関係
ア スポンサーの意図
イ 信託課税
ウ 米国持分所有者に対する課税
(8) 非米国持分所有者への課税
(9) 米国における情報申告とバックアップ源泉徴収
【第54回】
23 ビットコインETFと分離課税(その7):本件分離課税特例「株式等」及び「上場株式等」
(1) 本件分離課税特例における「株式等」及び「上場株式等」の意義
(2) 「投資信託の受益権」該当性
ア 特定資産の意義と「投信法上の投資信託」該当性①
【第55回】
イ 特定資産の意義と「投信法上の投資信託」該当性②
ウ 「外国投資信託」該当性
【第56回】
エ 外国信託が投信法上の投資信託に類するものといえるかどうかは種々の事情を総合勘案すべきという見解
(3) 「特定受益証券発行信託の受益権」該当性
【第57回】
(4) 「法人課税信託」該当性
ア 「受益権を表示する証券を発行する旨の定めのある信託」該当性
(ア) 受益権を表示する「紙片」を発行する旨の定めがない信託は含まれないとする見解
【第58回】
(イ) 特定受益証券発行信託とそれ以外の受益証券発行信託で異なる課税方式を採用した趣旨
【第59回】
イ 紙片を発行せずに振替式を利用する定めのある外国信託も含まれるとする見解①(規定の趣旨との関係)
【第60回】
ウ 紙片を発行せずに振替式を利用する定めのある外国信託も含まれるとする見解②(社債等振替法に係る振替受益権との関係)
(ア) 信託法と社債等振替法
(イ) 法人税法
【第61回】
エ 「集団投資信託」該当性
(ア) 合同運用信託と紙片を発行する旨の定めがない外国投資信託
(イ) 「信託会社」該当性
【第62回】
(ウ) 「金銭信託で、共同しない多数の委託者の信託財産を合同して運用するもの」及び「信託」等該当性
オ 「信託」該当性
カ 本信託の法人課税信託該当性とその効果
(5) 「株式等で金融商品取引所に上場されているものに類するもの」
(6) 本件分離課税特例(分離課税)の適用の可否
【第63回】
24 ビットコインETFと分離課税(その8):まとめ
【第64回】
25 ビットコインETFと分離課税(その9):国税庁の回答
【第65回】
26 DeFi取引と課税①:DeFiとDEX
(1) DeFiとは
(2) スマートコントラクトとは
(3) DEXとは
【第66回】
(4) Uniswap
【第67回】
27 DeFi取引と課税②:流動性供給開始は課税イベントか
(1) 課税イベントになるという見解
(2) 課税イベントと実現
【第68回】
(3) 暗号資産(トークン)の含み損益の課税イベント
【第69回】
(4) 権利義務の帰属主体の不存在
(5) 課税イベントの候補
【第70回】
28 DeFi取引と課税③:トークンのラップは課税イベントか
(1) ラップとブリッジ
【第71回】 7/10公開
(2) BTCからWBTCへのラップ
(3) ラップは課税イベントか
ア 課税イベントと捉える見解
【第72回】 7/24公開
イ カストディアンがいるケース
ウ カストディアンがいないケース
・・・ 以下、順次公開 ・・・