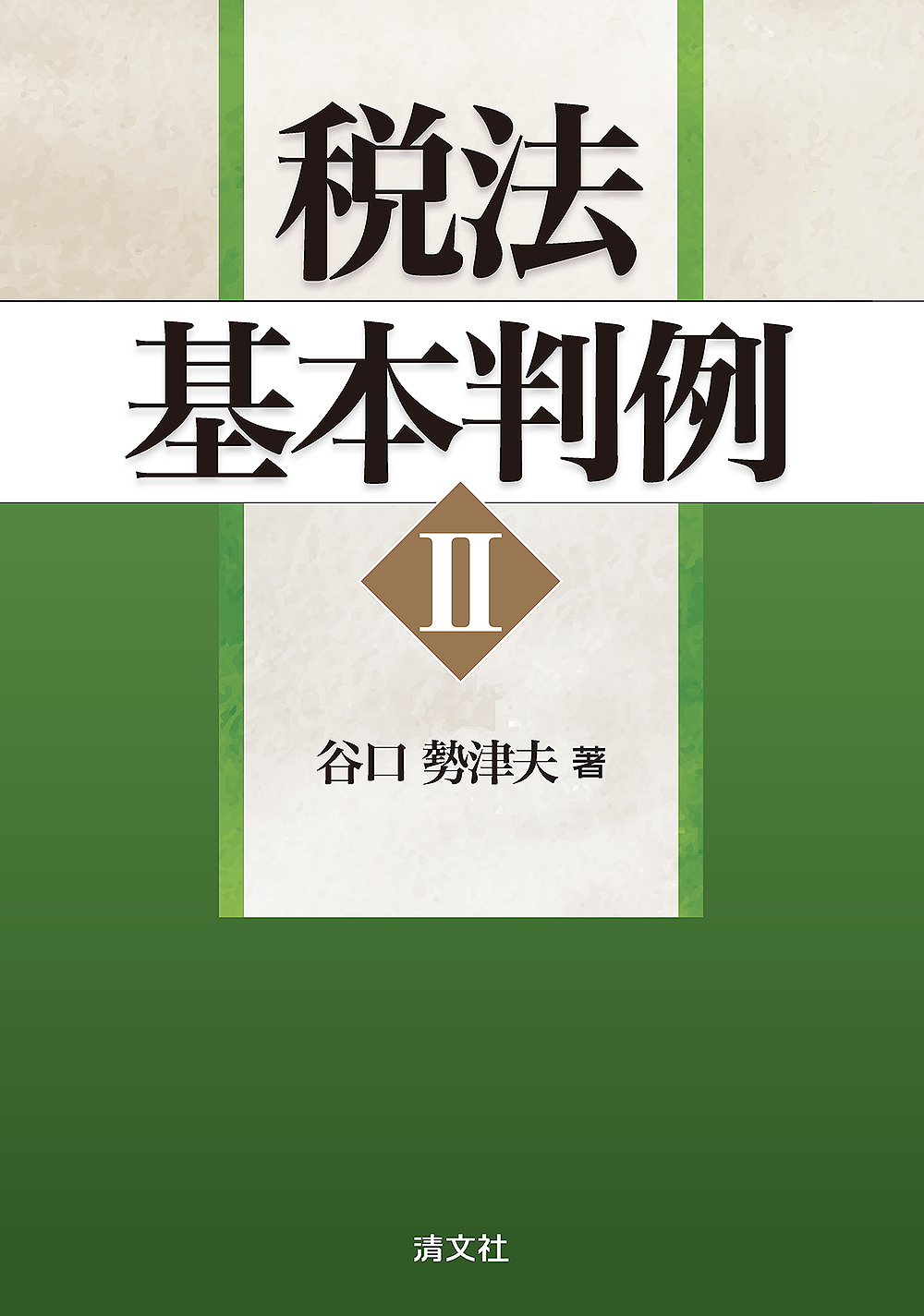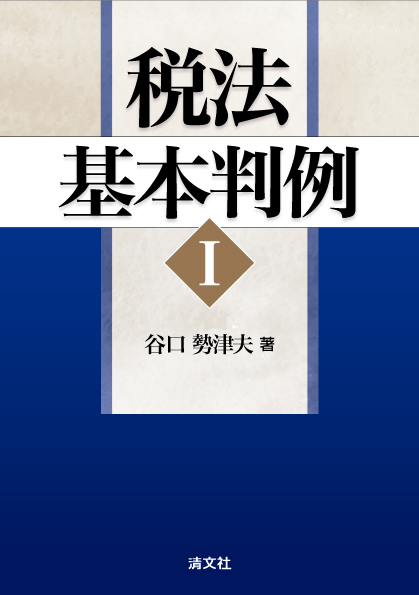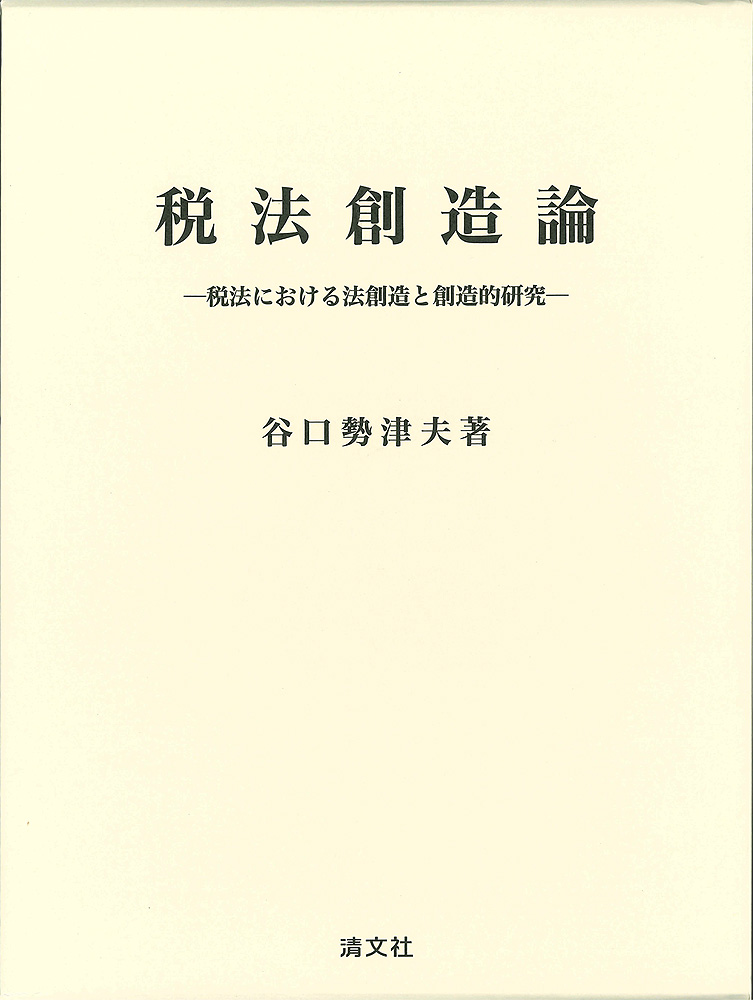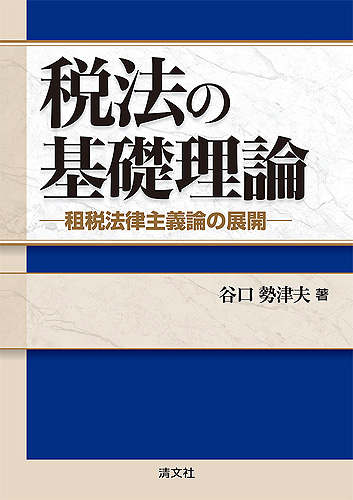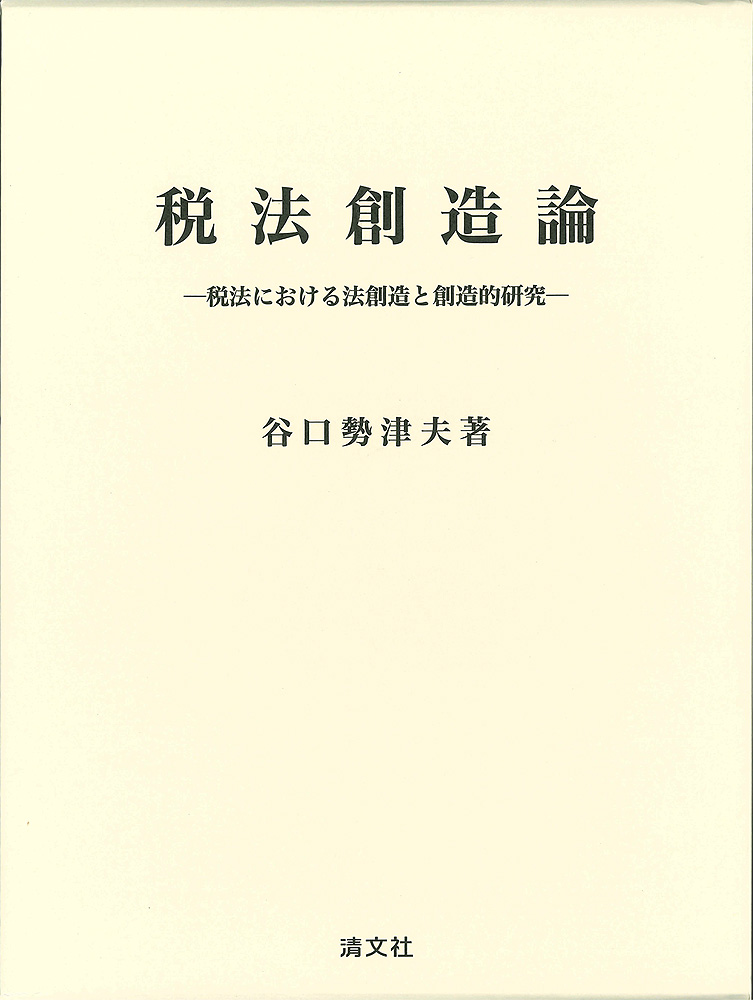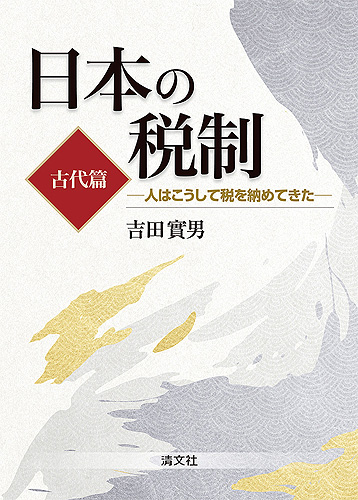谷口教授と学ぶ
税法基本判例
【第52回】
「事業所得と給与所得との区分に関する「判断の一応の基準」の意味」
-弁護士顧問料事件・最判昭和56年4月24日民集35巻3号672頁-
大阪学院大学法学部教授
谷口 勢津夫
Ⅰ はじめに
今回は、弁護士の顧問料の給与所得該当性が争われたいわゆる弁護士顧問料事件に関する最判昭和56年4月24日民集35巻3号672頁(以下「本判決」という)において示された、事業所得と給与所得の区分に関する「判断の一応の基準」の意味について検討する。
なお、本判決は、民集35巻3号672頁の「判示事項」でも、「いわゆる減額再更正処分の取消を求める訴の利益の有無」が取り上げられ、これに関する判断を示した判決としても(むしろ当時はそのような判決として)注目を集めたが(この問題については園部逸夫「判解」最判解民事篇(昭和56年度)275頁ほか多くの判例評釈がある)、この問題は第39回(特にⅡ2)で検討した。
また、事業所得と給与所得との区分が争われるのは、「所得を得るために必要な支出」という意味での必要経費(理論的意味における必要経費)の控除が実額控除とされるか(事業所得)又は概算控除とされるか(給与所得)という取扱いの違いによるものであるが(理論的意味における必要経費、実額控除、概算控除については拙著『税法基本講義〔第8版〕』(弘文堂・2025年)【312】、【262】、【267】参照)、その争いの実質的な原因は、多くの場合、大嶋訴訟(第2回参照)に典型的にみられたように当該事案における給与所得に係る必要経費の概算控除(給与所得控除)の額が必要経費の実額控除の額を下回る点にあったところ、本件では、確定申告における顧問料収入に係る必要経費については概算控除の方が上回っていたものと思われる(本件における確定申告、更正及び再更正に係る給与所得及び事業所得の収入金額、所得金額等の内訳については原審・東京高判昭和51年10月18日民集35巻3号686頁、687頁以下参照)。
この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員登録およびログインが必要です。
すでに会員登録をされている方は、下記ボタンからログインのうえ、ご覧ください。
Profession Journalのすべての記事をご覧いただくには、「プレミアム会員(有料)」へのご登録が必要となります。
なお、『速報解説』については「一般会員(無料)」へのご登録でも、ご覧いただけます。
※他にもWebセミナー受け放題のスーパープレミアム会員などがございます。
会員登録がお済みでない方は、下記会員登録のボタンより、ご登録のお手続きをお願いいたします。