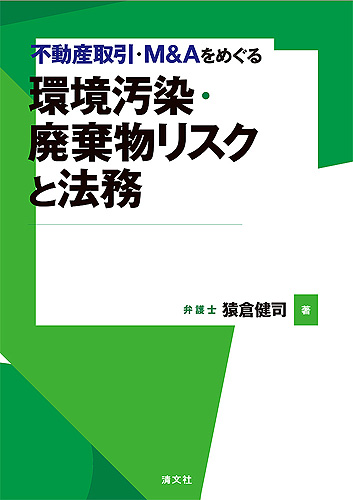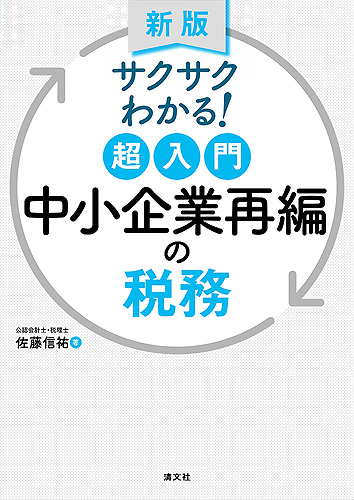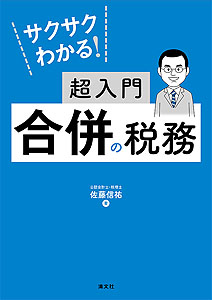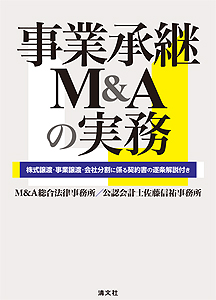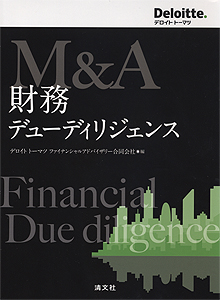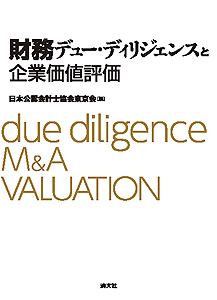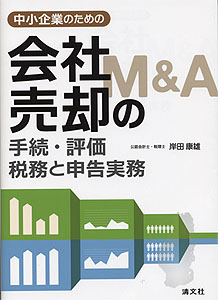M&Aに必要な
デューデリジェンスの基本と実務
弁護士法人ほくと総合法律事務所 パートナー
弁護士 石毛 和夫
◆むすびに代えて◆
~「財務・税務と法務との対話と協働」再び~
【前編】
「弁護士はなぜ『計算書類の適正』を表明保証させるのか?」
長きにわたった本連載も、今回からいよいよ最終コーナーに入る。
本連載ではこれまで、「財務・税務デューデリジェンス編」と「法務デューデリジェンス編」とを姉妹編として、両者の協働の重要性、そして両者を繋ぐものとしての依頼者=当事者との協働の重要性をたびたび強調してきた。
そこで本連載の最終テーマとして、こうした協働が、「買収契約書」という1つの「締めくくり」の場面でどう機能するのか、いささか風変わりな趣向ではあるが、「会社担当者と専門家たちとの架空の対話」という形で紹介したいと思う。
* * *
〔登場人物〕
《高橋氏》
X社の法務部所属。今回の買収案件の担当者の1人。やがては法科大学院に通い、弁護士資格を取ろうという野望を抱いている。今回初めてのM&Aに挑戦し、いつにも増して気合十分である。
《石毛先生》
法務デューデリジェンス担当弁護士の1人。
《松澤先生》
財務・税務デューデリジェンス担当公認会計士の1人。
(あらすじ)
X社はZ社の発行済全株式をY社から買収することを検討しており、財務・税務アドバイザーとして外部の公認会計士を、法務アドバイザーとして外部の弁護士を起用した。
両事務所はそれぞれZ社の財務・税務デューデリジェンス/法務デューデリジェンスを実施、X社に報告を済ませ、石毛先生が株式譲渡契約書をドラフトしてY社との条件交渉に入ろうという段階である。
そんな折に、どうしたことか高橋氏が、松澤先生の会計事務所に駆け込んできた。
《高橋氏》
松澤先生!
石毛先生がドラフトしたこの契約書を見てください。ひどいんですよ。
《松澤先生》
どうしたんですか。まあ、落ちついてください。
ほう、これは「売主の表明保証」の条項(※)ですね。
(※) 「表明保証条項」については、法務編【第8回】を参照。
第●条
売主は、本契約締結日及びクロージング日(但し、別途時点が明示される場合にはその時点)において、買主に対し、下記各号が真実かつ正確であることを表明し、かつ保証する。
(中略)
第●号(財務諸表等)
対象会社が売主に開示した2019年3月31日(以下「前決算期日」という。)現在の対象会社貸借対照表並びに前決算期日に終了した事業年度の損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表並びにそれらの附属明細書(以下「本財務諸表」と総称する。)は、対象会社に対して継続的に適用され、一般に公正妥当と認められた会計基準に従い、対象会社の前決算期日現在の財政状態及び前決算期日に終了した事業年度の経営成績を、それぞれ正確かつ適正に示している。本財務諸表は、虚偽の記載を含まず、また、記載すべき事項若しくは誤解を生じさせないために必要な事実の記載を欠いていない。
(後略)
《松澤先生》
よくある条文ですね。
特におかしいとは思いませんが。
《高橋氏》
松澤先生までそんなことをおっしゃるなんて・・・。
だって先生、私は松澤先生の財務デューデリジェンスレポートをちゃんと読みましたよ。
《松澤先生》
法務部員として、法務デューデリジェンスの結果だけでなく、財務・税務デューデリジェンスの結果もきちんと知っておくのは、良いことだと思います。X社も部署間で役割があるかと思いますが、意外とこの当然のことができていない方もいらっしゃるのですよ。それどころか、弁護士さんの中にさえ、財務デューデリジェンスレポートをろくに読まずにM&Aアドバイザリーを務めようという人もいるのですから・・・。
それはそうと、この条文の何が問題なのでしょう?
《高橋氏》
先生の財務デューデリジェンスレポートを読んだら、Z社の計算書類等には要修正項目だらけだったじゃないですか。貸借対照表なんか、純資産が半分くらいに修正されていましたよ。
それがわかっているのに、「対象会社の前決算期日現在の財政状態及び前決算期日に終了した事業年度の経営成績を、それぞれ正確かつ適正に示している」ことを表明保証させるなんて、おかしいじゃないですか。
《松澤先生》
ああ、そこは別におかしくないですよ。
この条文は、対象会社が開示した財務諸表が、「一般に公正妥当と認められた会計基準に従い」、つまり、一般に公正妥当と認められた会計基準(GAAP)の範囲内で、正確かつ適正に財政状態や経営成績を示している、ということを言っているにすぎません。
これに対し、財務デューデリジェンスは、財務諸表がGAAPに即しているかどうかということの検証をするものではありません。具体的なM&A取引を前提として、より実態に即した財政状態、実態に即したキャッシュフロー稼得能力を把握しようとするものなのです。だから、対象会社が作成した計算書類等からみれば、「修正」が加わっているのは当然ですね。
《高橋氏》
むむっ。では、この条文それ自体はおかしくないのですね。
しかし、そうであればですよ、買主は財務デューデリジェンスによって、「より実態に即した」対象会社の財政状態・キャッシュフロー稼得能力を、すでに把握していることが前提ですよね。であれば、そのうえ、計算書類が「GAAPに即している」ことの表明保証をさせても「実は意味がない」ということになりませんか?
《松澤先生》
そうでもないでしょう。
第一に、財務デューデリジェンスも、対象会社作成の計算書類が「GAAPベースのものとして正しいこと」を前提としている、あるいは少なくとも調査の出発点にしている部分があるので、大前提としての「GAAPベース」に不適正があっては困ります。
第二に、買主としては、買収後も、対象会社が作成した計算書類を利用するわけであり、その計算書類は当然、「財務デューデリジェンスベース」ではなく「GAAPベース」です。そうである以上、過去の計算書類が「GAAPベース」のものとして正しいことを保証させることには大いに意味があると思います。
《高橋氏》
なるほど・・・。
石毛先生も適当にドラフトしていたわけじゃなかったんですね。
《松澤先生》
それはそうですよ。なにしろ石毛先生ですからね。
それから、たしかに財務デューデリジェンスの過程で、そもそもGAAPに即していないという事象が発見されることもありますよ。そういうときはその旨も財務デューデリジェンスレポートに記載して報告しますが、そのような修正項目は、他の修正項目とは質的に異なりますから、財務デューデリジェンスレポート上も、他の修正項目とは区別して記載しています。
高橋さんのお仕事である法務の観点からいえば、買収契約書上の表明保証条項の文言にも一工夫必要になると思いますが、これは法務の実務上、どうやっているのでしょうか?
《高橋氏》
この間、石毛先生に教わりました。
「・・・の点を除き、GAAPに従って作成されており」といったふうに、カーブアウトすると思います。
《松澤先生》
なるほどね。しかし、そういうカーブアウトを漏れなくできるようにするためには、弁護士も法務担当者も、財務デューデリジェンスレポートを隅から隅まで読んで理解していないといけませんよね。もし、法務部の担当者も弁護士も財務デューデリジェンスレポートを読み飛ばしていて、カーブアウトすべき事象をカーブアウトし忘れたらどうなるのでしょうか。
《高橋氏》
つまり、「GAAPに合致していないところが現にあり、そのことを買主は財務デューデリジェンスによって知った。しかし、売主に対して、『すべてGAAPに合致している』という表明保証をさせて、後から『表明保証違反があるじゃないか!』と咎めることが可能か」ということでしょうか。さすがにそれは無理だと思いますが・・・。
・・・自信はないので、石毛先生に聞いてみます。
(つづく)
次回は10/3の掲載となります。