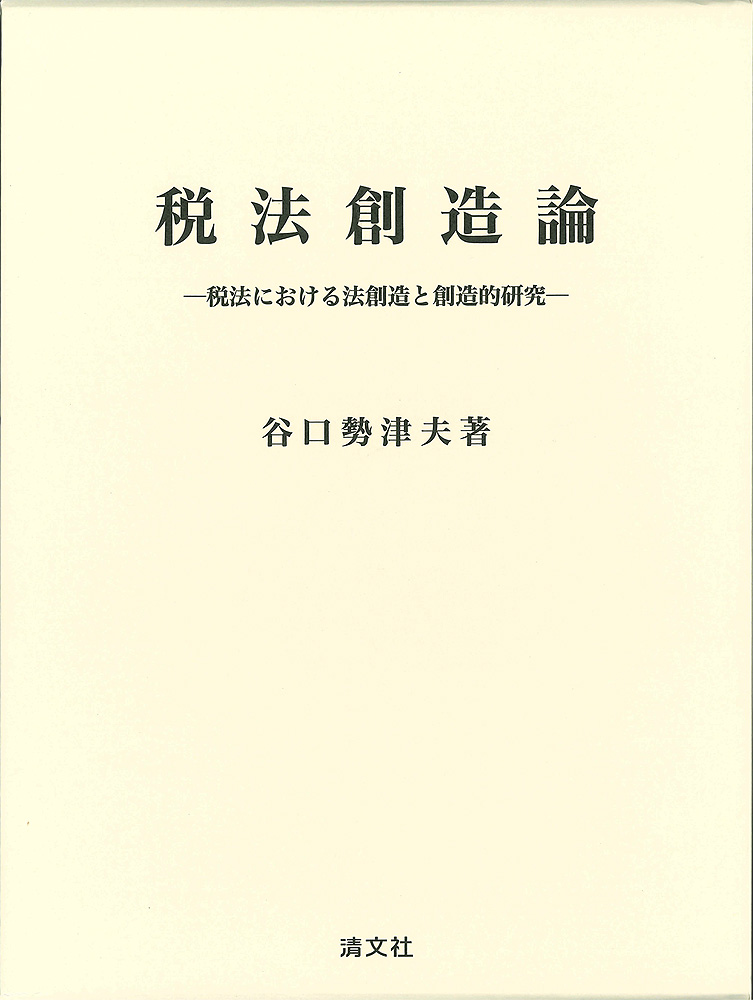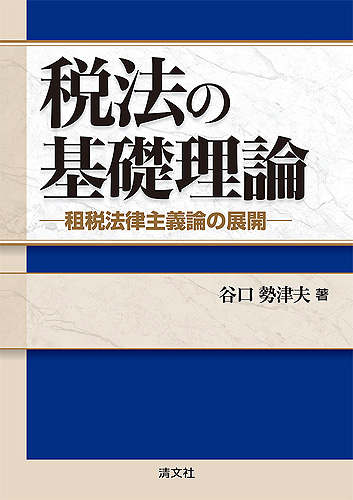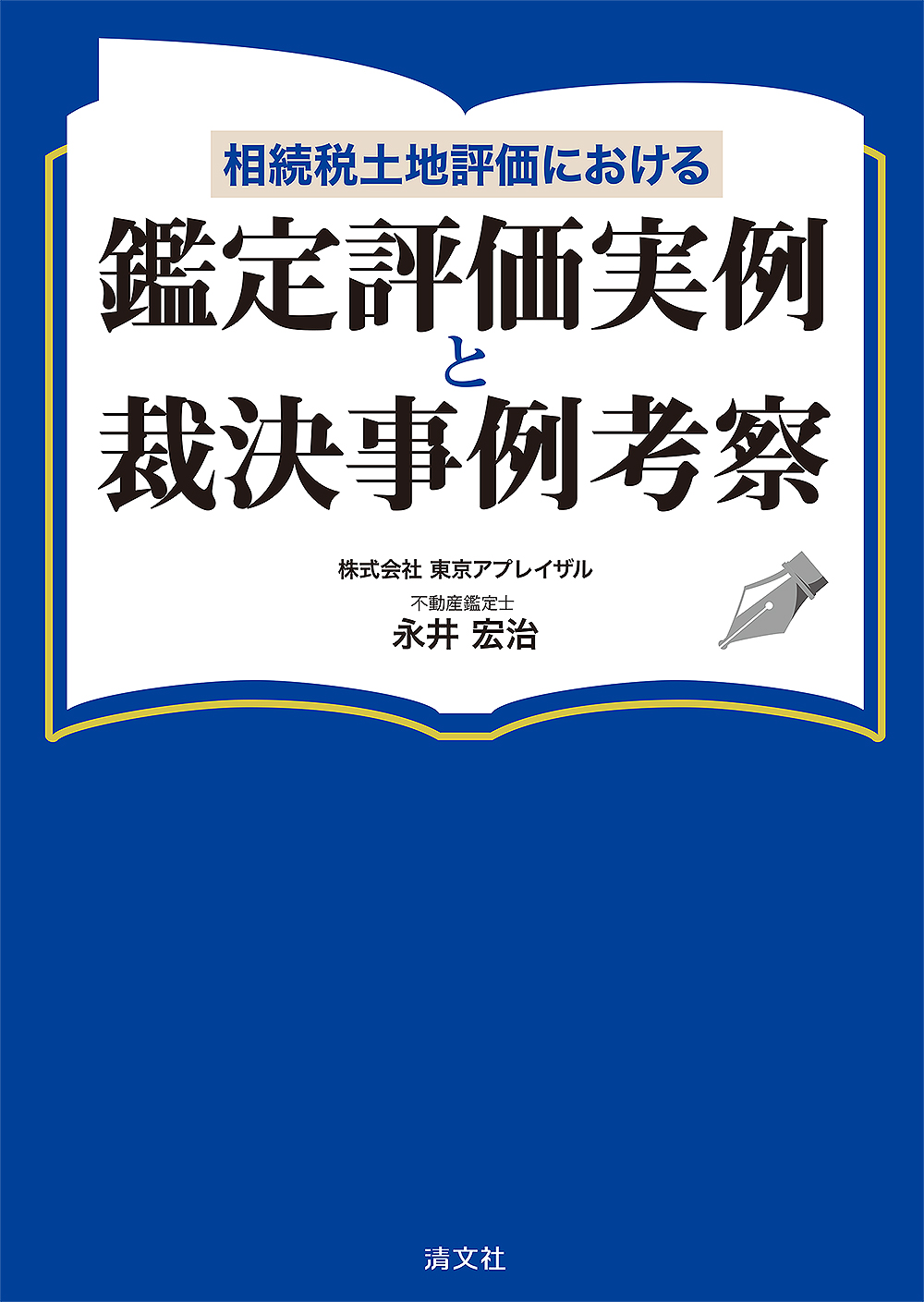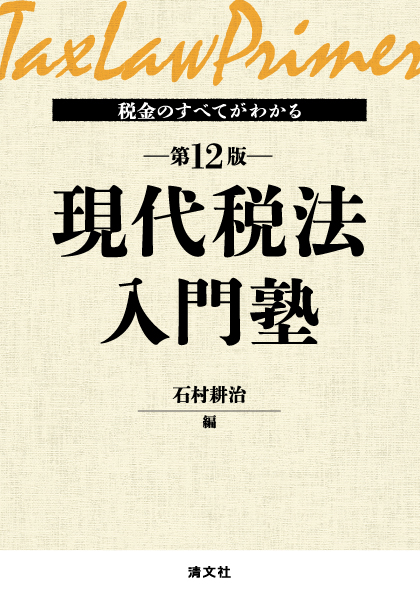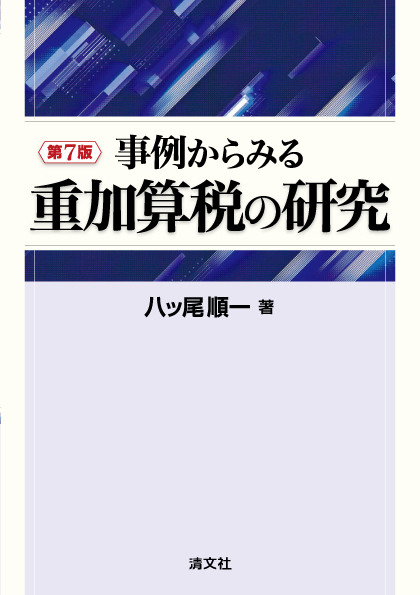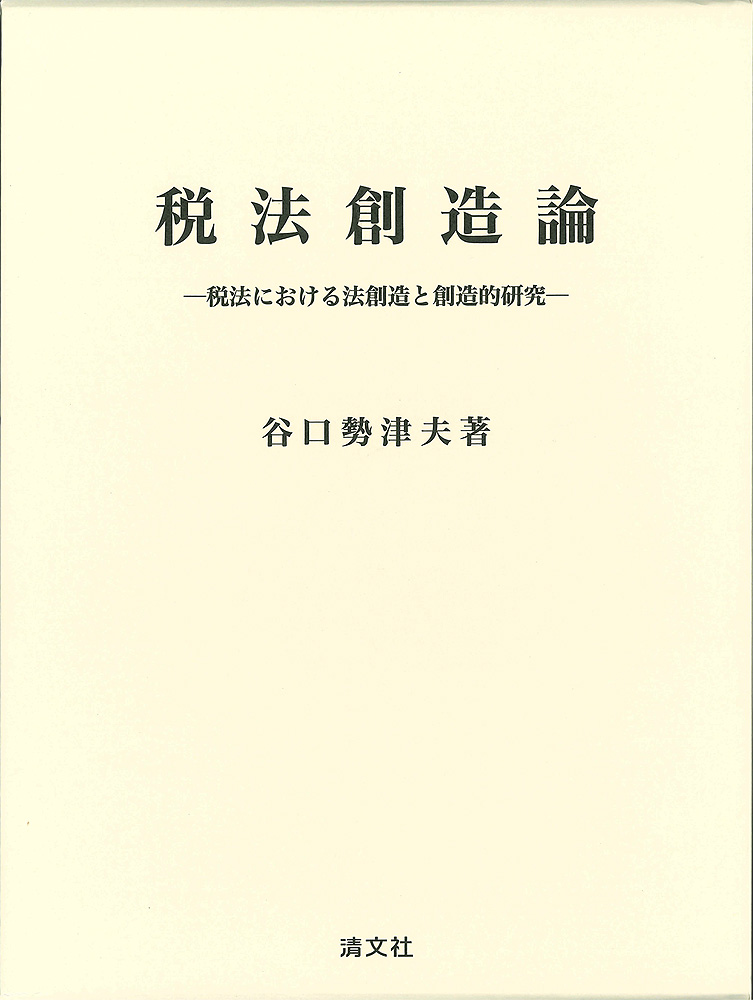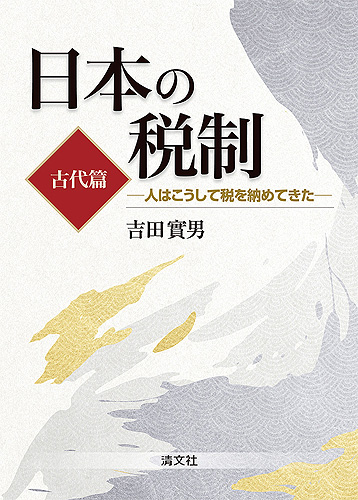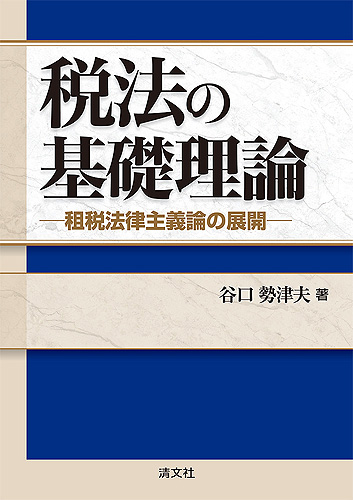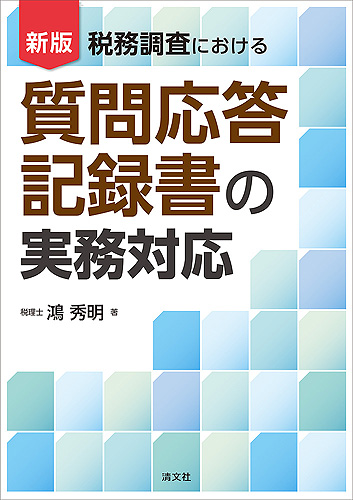谷口教授と学ぶ
税法基本判例
【第13回】
「借用概念論の実践的意図とその実現」
-株主優待金事件に関する最判昭和35年10月7日民集14巻12号2420頁と最大判昭和43年11月13日民集22巻12号2449頁-
大阪学院大学法学部教授
谷口 勢津夫
Ⅰ はじめに
前回Ⅱで、借用概念論は、「税法と私法」論との密接な関連において、私法関係準拠主義(拙著『税法基本講義〔第7版〕』(弘文堂・2021年)【60】)を実質的基盤として、借用概念を税法独自の概念(固有概念)と区別することによって「租税法の解釈に関する錯綜した議論を多少とも整理し、またいわゆる実質課税の原則を根拠として租税法に自由な解釈をもち込むことに対して歯止めをかけること」(金子宏『租税法理論の形成と解明 上巻』(有斐閣・2010年)386頁)という、税法解釈論上の実践的意図をもって展開されてきたものとみてよいと述べた。
今回は、借用概念論のそのような実践的意図とその実現について、いわゆる株主相互金融会社における株主優待金の税法上の取扱いに関する昭和35年10月7日民集14巻12号2420頁(以下「昭和35年最判」という)と最大判昭和43年11月13日民集22巻12号2449頁(以下「昭和43年最大判」という)を素材にして、検討することにする。
昭和35年最判では、株主優待金が所得税法上の利益配当(「法人から受ける利益の配当」)に該当するか否かが争われたのに対して、昭和43年最大判では、株主優待金が法人税法の課税所得の計算上損金に算入されるか否かが争われたところ、「両者はいちおう別個の問題ではあるが、株主優待金の法的構造ないし性質をいかに把握するかという点では、両者に共通する問題が横たわっているといえる。」(後者に関する調査官解説である可部恒雄「判解」最判解民事篇(昭和43年度)1432頁、1440頁)ことから、以下では、両者を比較しながら、借用概念論の実践的意図とその実現について検討していくことにする。
この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員登録およびログインが必要です。
すでに会員登録をされている方は、下記ボタンからログインのうえ、ご覧ください。
Profession Journalのすべての記事をご覧いただくには、「プレミアム会員(有料)」へのご登録が必要となります。
なお、『速報解説』については「一般会員(無料)」へのご登録でも、ご覧いただけます。
※他にもWebセミナー受け放題のスーパープレミアム会員などがございます。
会員登録がお済みでない方は、下記会員登録のボタンより、ご登録のお手続きをお願いいたします。