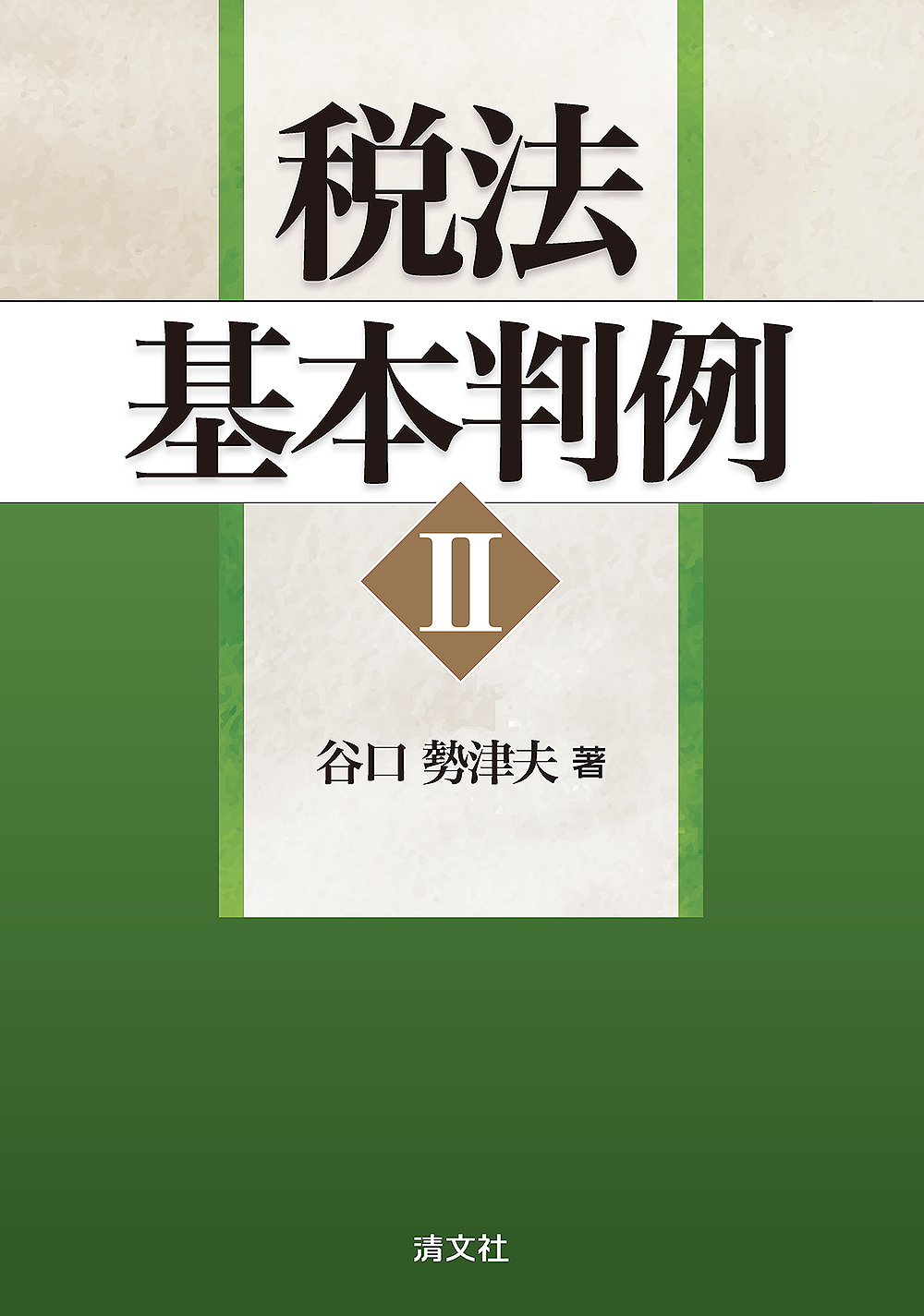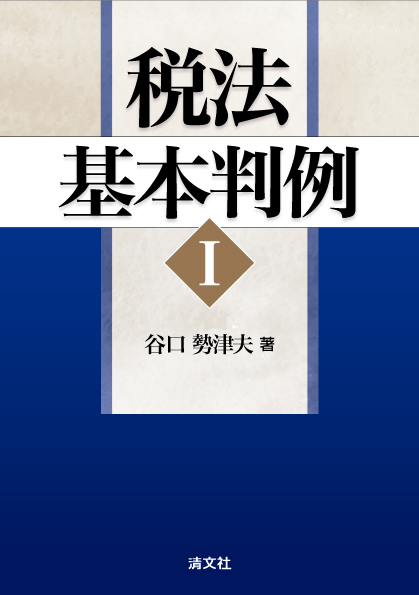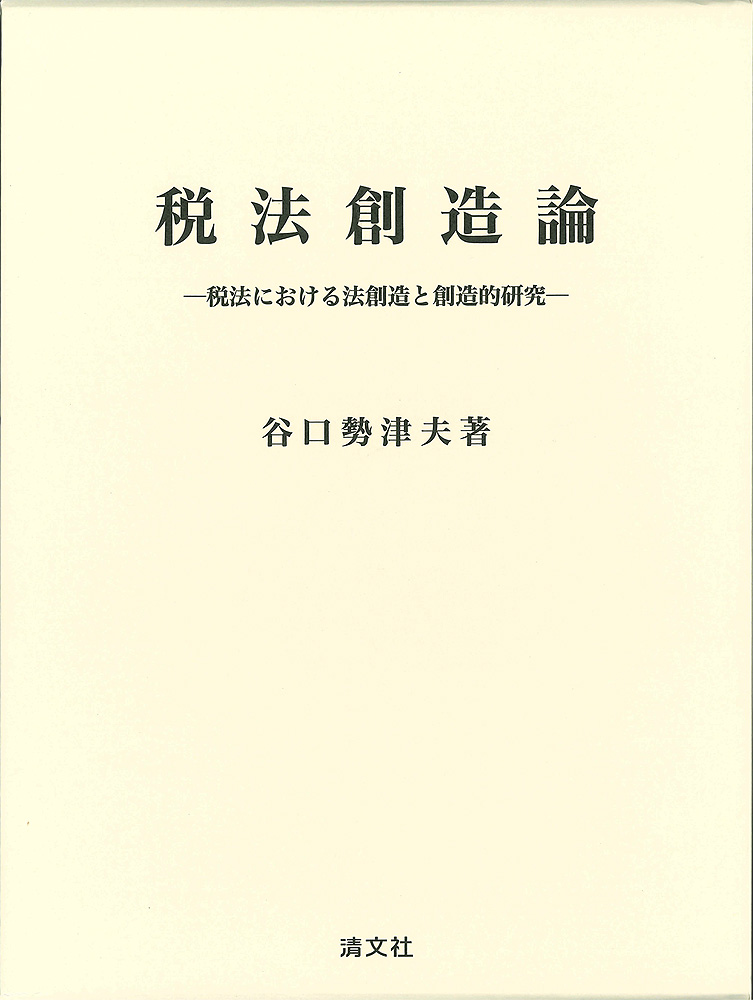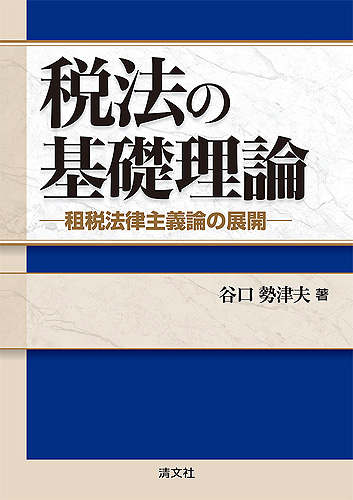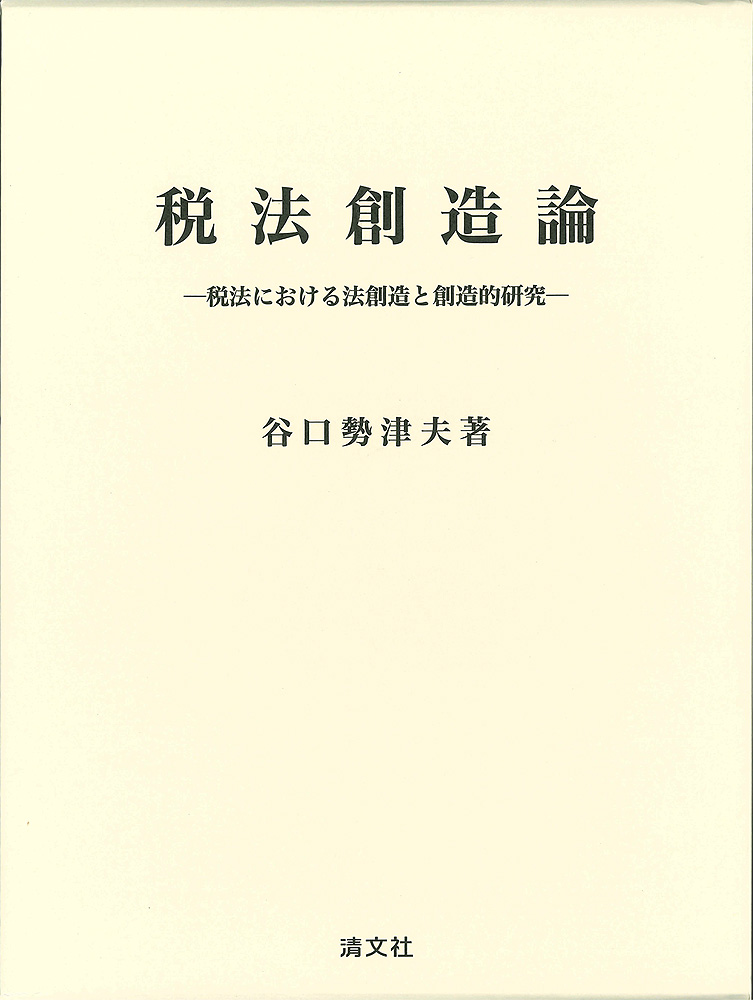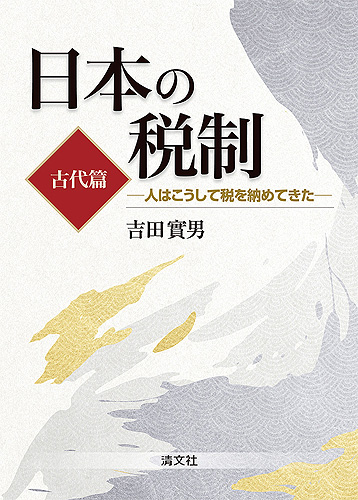谷口教授と学ぶ
税法基本判例
【第31回】
「私人の公法行為に対する私法の適用の可否」
-家督相続「錯誤」申告事件・最判昭和39年10月22日民集18巻8号1762頁-
大阪学院大学法学部教授
谷口 勢津夫
Ⅰ はじめに
前回までは租税実体法の領域(拙著『税法基本講義〔第7版〕』(弘文堂・2021年)第2編第1章)における税法基本判例を3回にわたって取り上げ検討したが、今回からは租税手続法の領域(同編第2章以下)における税法基本判例を取り上げ検討することにする。
租税手続法は、租税実体法における課税要件の充足による納税義務の成立を前提にして、その成立した納税義務(抽象的納税義務)の具体的内容(税額等)を確認する納税義務の確定並びにその確定した納税義務(具体的納税義務)の履行のための租税の納付及び徴収に関する行政手続を定める法(租税行政法)とそこでの納税者の権利救済に関する法(租税争訟法ないし租税救済法)とで構成されるが(前掲拙著【86】参照)、今回から、租税行政法の領域における手続の流れに即して税法基本判例を検討することにしよう。
この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員登録およびログインが必要です。
すでに会員登録をされている方は、下記ボタンからログインのうえ、ご覧ください。
Profession Journalのすべての記事をご覧いただくには、「プレミアム会員(有料)」へのご登録が必要となります。
なお、『速報解説』については「一般会員(無料)」へのご登録でも、ご覧いただけます。
※他にもWebセミナー受け放題のスーパープレミアム会員などがございます。
会員登録がお済みでない方は、下記会員登録のボタンより、ご登録のお手続きをお願いいたします。