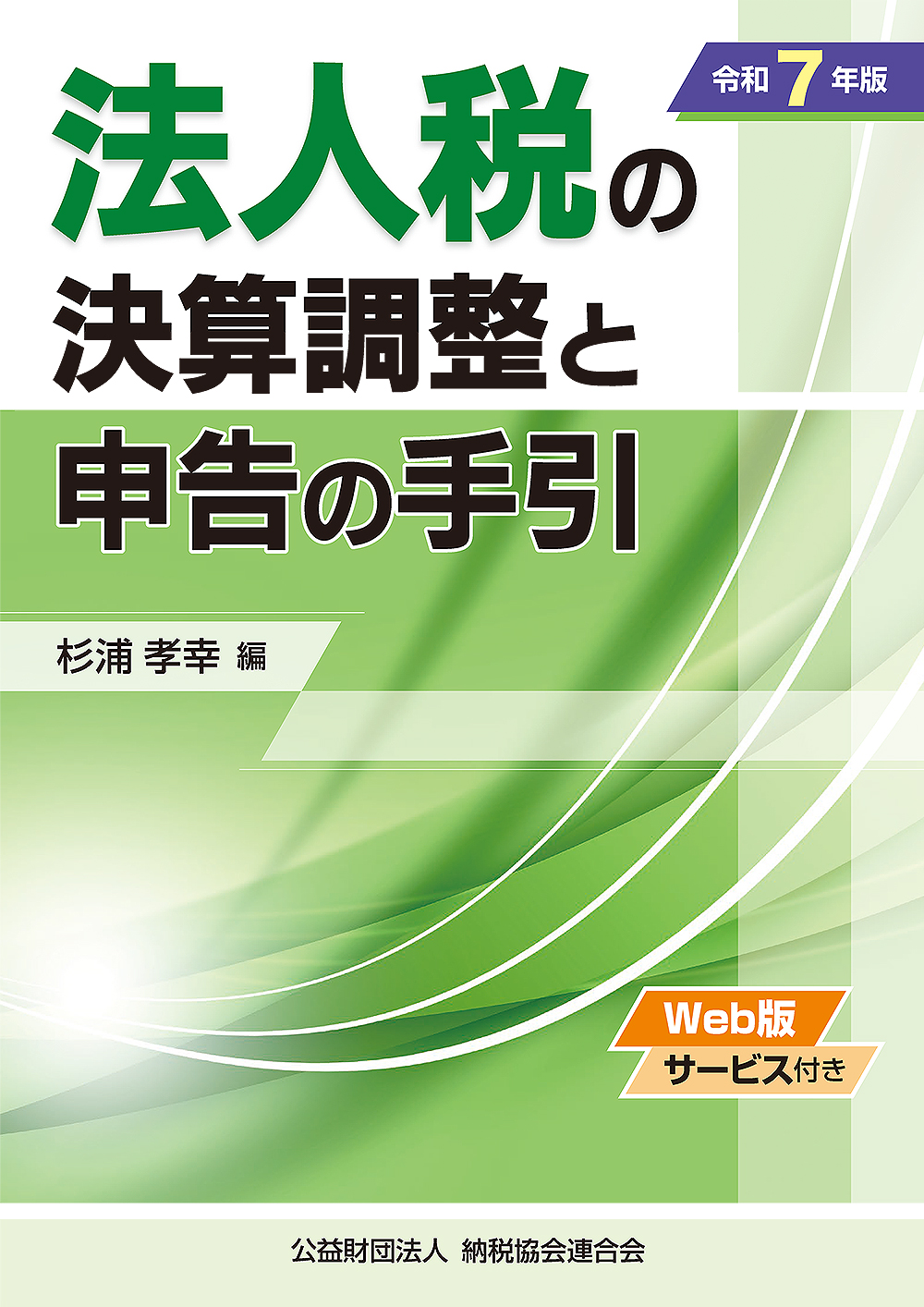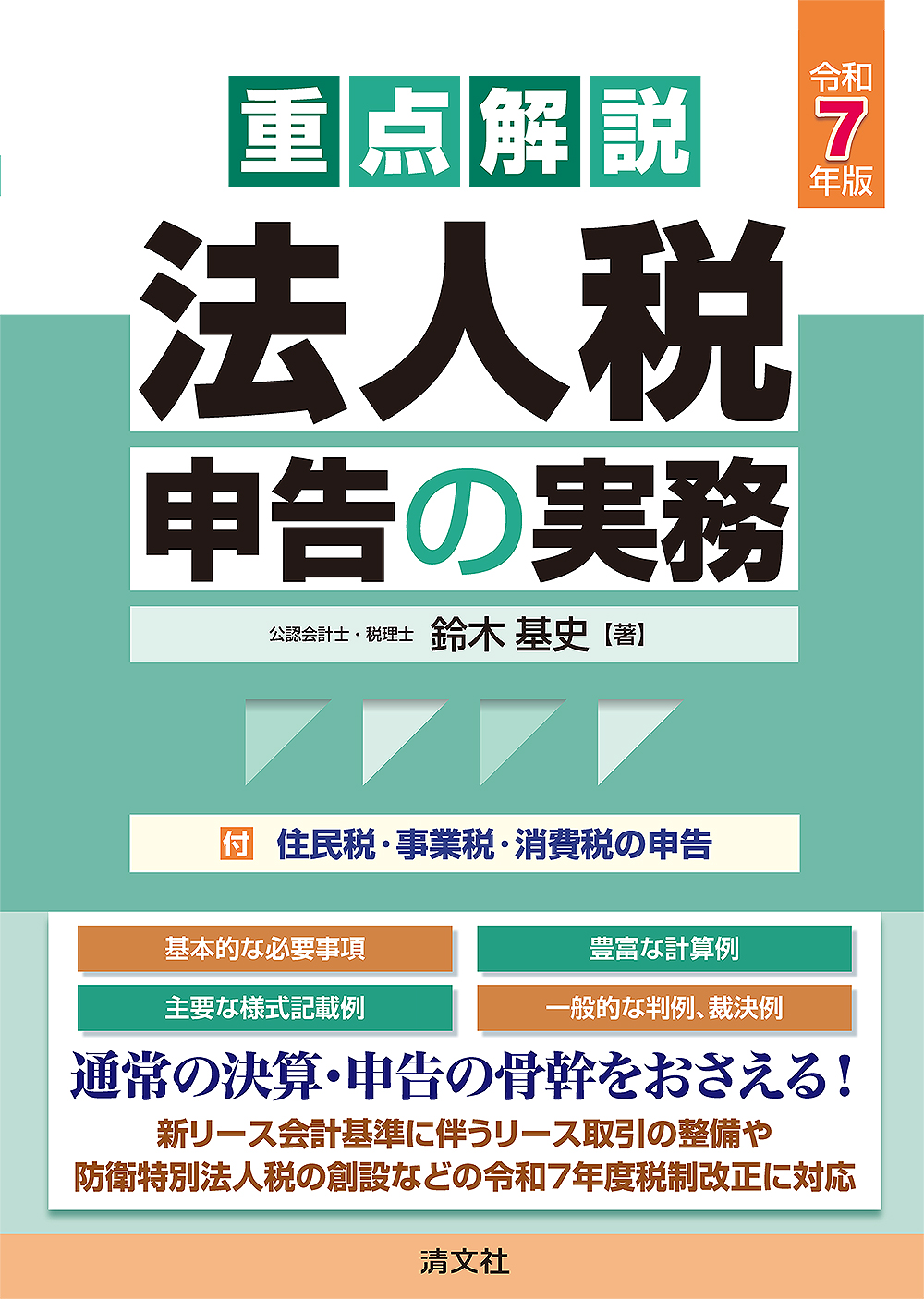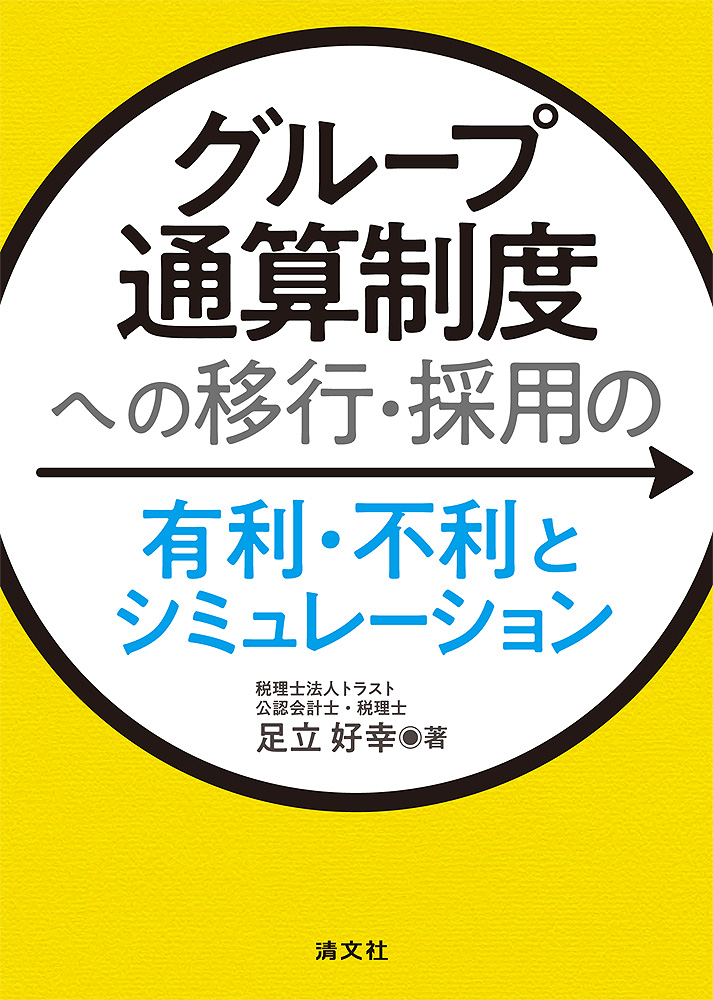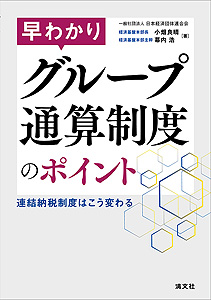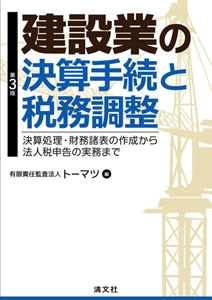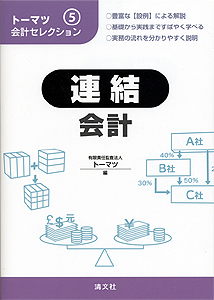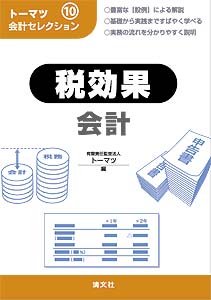各ステップに移動する場合はこちらをクリック
【STEP4】個別財務諸表/回収可能性の検討
連結納税における繰延税金資産(個別財務諸表)の回収可能性の検討は、基本的には【第35回】「個別財務諸表における税効果会計(回収指針対応版)」と同様である。しかし、単体納税における回収可能性の検討とは、以下の点で異なる(実報7号Q3)。
Ⅰ 法人税は連結納税主体で計算し、住民税・事業税は各連結納税会社単位で計算するため、税効果においても、法人税・住民税・事業税それぞれに区分して検討する。
Ⅱ 法人税部分の繰延税金資産の回収可能性の判断は、個別所得見積額だけでなく、他の連結納税会社の個別所得見積額も考慮する。
Ⅲ 特定連結欠損金は個別所得見積額を限度に連結所得から控除する。そのため、特定連結欠損金の場合、各連結納税会社の個別所得見積額及び連結所得見積額の両方を考慮する。
Ⅳ 非特定連結欠損金は連結所得から控除するため、連結所得見積額を考慮する。
上記のⅠ~Ⅳを踏まえて、連結納税における繰延税金資産(個別財務諸表)の回収可能性の検討は、以下の順に行う。
(1) 企業分類の決定
① 将来減算一時差異
② 非特定連結欠損金個別帰属額
③ 特定連結欠損金個別帰属額
④ 地方税部分
(2) 回収可能性の検討
① 一時差異等の解消のスケジューリング
② 法人税部分の繰延税金資産の回収可能性の検討
③ 住民税部分の繰延税金資産の回収可能性の検討
④ 事業税部分の繰延税金資産の回収可能性の検討
(3) 支払可能性の検討
(1) 企業分類の決定
連結納税における税効果では、法人税部分の繰延税金資産は、連結納税主体(連結全体)で回収可能性を検討し、地方税部分の繰延税金資産は連結納税会社(各社)ごとに回収可能性を検討する。
そのため、各連結納税会社の企業分類のみならず、連結納税主体の企業分類を決定する必要がある。連結納税主体の企業分類の決定方法も各連結納税会社の企業分類の決定方法と同様である。詳細は【第35回】「個別財務諸表における税効果会計(回収指針対応版)」の【STEP4】(1)参照。
また、連結納税における税効果では、法人税部分の将来減算一時差異・繰越欠損金の種類、地方税部分それぞれで用いる企業分類が異なるので留意が必要である。
① 将来減算一時差異(法人税部分)
将来減算一時差異(法人税部分)は連結納税においては連結所得をベースに解消されるため、将来減算一時差異に係る繰延税金資産の回収可能性を判断する場合、連結納税主体の企業分類が、連結納税会社の企業分類と同じか上位にあるときは、連結納税主体の例示区分を用いる。ただし、ここでの検討は個別財務諸表であることから、連結納税会社の企業分類が連結納税主体の企業分類の上位にあるときは、まず自己の個別所得見積額をベースに判断するため、当該連結納税会社の企業分類を用いる(実報7号Q3)。
② 特定連結欠損金個別帰属額(法人税の繰越欠損金)
特定連結欠損金個別帰属額は、連結納税会社の個別所得を限度として、連結所得より繰越控除できる。言い換えると、連結所得の発生が少ない(しない)場合や個別所得の発生が少ない(しない)場合は、繰越控除ができない部分が発生する。したがって、連結納税主体と連結納税会社の例示区分のうち、より下位の例示区分を用いる。
③ 非特定連結欠損金個別帰属額(法人税の繰越欠損金)
非特定連結欠損金個別帰属額は連結所得と相殺されることで解消するため、連結納税主体の企業分類を用いる。
④ 地方税部分
連結納税においても地方税は単体納税と同様に単体のみで税額計算するため、連結納税会社の企業分類を用いる。
以上の①から④をまとめると以下のとおりとなる。
※画像をクリックすると、別ページで拡大表示されます。

(2) 回収可能性の検討
回収可能性の検討は、法人税部分・住民税分・事業税分それぞれ別に行う。
① 一時差異等のスケジューリング
スケジューリングは、個別財務諸表における税効果と同様である。そのため、詳細は、【第35回】「個別財務諸表における税効果会計(回収指針対応版)」の【STEP4】を参照。
ただし、スケジューリングにおいて留意する点が1つある。
連結納税における税効果では、全ての企業分類が「1」又は「5(スケジューリング可能な将来加算一時差異がない場合を想定)」でない限り、必ずスケジューリングを行う必要がある(連結財務諸表でも同様)。
例えば、連結納税会社Aの企業分類が「1」で、他の連結納税会社の企業分類が「3」で、かつ、連結納税主体の企業分類が「3」であったとする。この場合、単体納税であれば、連結納税会社Aはスケジューリングに関係なく繰延税金資産を計上できるが、連結納税の場合、法人税部分の税効果は連結納税会社Aのスケジューリングが他の連結納税会社の一時差異等の解消に影響する。そのため、企業分類「1」である連結納税会社Aにおいてもスケジューリングを行う必要がある。
② 法人税部分の繰延税金資産の回収可能性の検討
法人税部分の繰延税金資産の回収可能性の検討は「将来減算一時差異」、「特定連結欠損金個別帰属額」、「非特定連結欠損金個別帰属額」それぞれにおいて、以下の順に行う(実報7号Q3)。
(ⅰ) 将来減算一時差異
(イ) スケジューリングに基づき、将来減算一時差異の解消見込額と個別所得見積額を解消年度ごとに相殺する。相殺された金額に係る繰延税金資産は回収可能性があると判断する。
![]()
(ロ) 上記(イ)で相殺できなかった将来減算一時差異は、その解消見込年度ごとの受取個別帰属法人税額(連結納税会社が損益通算により他の連結納税会社の所得と相殺できる金額の法人税相当額)の見積額を課税所得に換算した金額(当該年度の個別所得見積額がマイナスの場合には、マイナスの個別所得見積額に充当後の残額)と相殺する。相殺された金額に係る繰延税金資産は、回収可能性があると判断する。
![]()
(ハ) 上記(ロ)においても相殺できなかった将来減算一時差異は、連結納税における税効果会計上、解消年度に発生した非特定連結欠損金個別帰属額と同様に取り扱われる。この非特定連結欠損金個別帰属額と同様に取り扱うこととなる繰延税金資産の回収可能性の判断は、下記(ⅲ)により行う。
(ⅱ) 特定連結欠損金個別帰属額
特定連結欠損金個別帰属額は、税務上認められる繰越期間内に上記(ⅰ)控除後の個別所得見積額を限度に連結所得見積額(各連結納税会社の上記(ⅰ)控除後の連結所得見積額)と相殺する。相殺された金額に係る繰延税金資産は回収可能性があると判断する。相殺できなかった金額は、回収可能性がないと判断し、繰延税金資産を計上することはできない。
(ⅲ) 非特定連結欠損金個別帰属額
非特定連結欠損金個別帰属額は、税務上認められる繰越期間内に連結所得見積額(各連結納税会社の上記(ⅰ)及び(ⅱ)控除後の連結所得見積額)と相殺する。相殺された金額に係る繰延税金資産は回収可能性があると判断する。相殺できなかった金額は、回収可能性がないと判断し、繰延税金資産を計上することはできない。
③ 住民税部分の繰延税金資産の回収可能性の検討
住民税部分の繰延税金資産の回収可能性の検討は「将来減算一時差異」、「連結欠損金個別帰属額」、「控除対象個別帰属調整額・控除対象個別帰属税額」それぞれにおいて、以下の順に行う(実報7号Q3)。
(ⅰ) 将来減算一時差異
(イ) スケジューリングに基づき、将来減算一時差異の解消見込額を個別所得見積額と解消見込年度ごとに相殺する。相殺された金額に係る繰延税金資産は回収可能性があると判断する。
![]()
(ロ) 上記(イ)で相殺できなかった将来減算一時差異の解消見込額は、以下のように取り扱う。
(a) 受取個別帰属法人税額が見込まれる場合、当該受取個別帰属法人税額の見積額を課税所得に換算した金額(当該年度の個別所得見積額がマイナスの場合には、マイナスの個別所得見積額に充当後の残額)に法人税率を乗じた金額は、解消年度に発生した控除対象個別帰属税額と同様に取り扱う。この控除対象個別帰属税額と同様に取り扱うこととなる繰延税金資産の回収可能性の判断は、下記(ⅲ)により行う。
(b) 上記(イ)で相殺できなかった将来減算一時差異の解消見込額のうち、上記の受取個別帰属法人税額の見積額を課税所得に換算した金額以外の金額は、連結欠損金個別帰属額と同様に取り扱う。この連結欠損金個別帰属額と同様に取り扱うこととなる繰延税金資産の回収可能性の判断は、下記(ⅱ)により行う。
(ⅱ) 連結欠損金個別帰属額
(イ) 当期末において存在する連結欠損金個別帰属額のうち、税務上認められる繰越期間内における連結欠損金個別帰属額の繰越控除額(当該事業年度に損金算入される連結欠損金のうち、各連結納税会社に帰属する金額)の見積額を超える部分の金額に係る繰延税金資産については、回収可能性がないと判断し、繰延税金資産を計上することはできない。
![]()
(ロ) 上記(イ)における連結欠損金個別帰属額の繰越控除額の見積額のうち、将来減算一時差異の解消額控除後の個別所得見積額に達するまでの金額に係る繰延税金資産は、回収可能性があると判断する。
![]()
(ハ) 上記(ロ)において連結欠損金個別帰属額の繰越控除額の見積額のうち、回収可能性があると判断された部分以外の金額は、その繰越控除された事業年度に発生した控除対象個別帰属税額と同様に取り扱う。その回収可能性の判断については、下記(ⅲ)により行う。
(ⅲ) 控除対象個別帰属調整額・控除対象個別帰属税額
(イ) 当期末において存在する控除対象個別帰属調整額及び控除対象個別帰属税額を、税務上認められる繰越期間内に、その連結納税会社が支払うと見込まれる個別帰属法人税額と相殺する。相殺された金額に係る繰延税金資産は、回収可能性があると判断する。
![]()
(ロ) 上記(イ)で相殺できなかった控除対象個別帰属調整額及び控除対象個別帰属税額に係る繰延税金資産は、回収可能性がないと判断し、繰延税金資産を計上することはできない。
④ 事業税部分の繰延税金資産の回収可能性の検討
事業税部分の繰延税金資産の回収可能性の検討は「将来減算一時差異」、「繰越欠損金」それぞれにおいて、以下の順に行う(実報7号Q3)。
(ⅰ) 将来減算一時差異
スケジューリングに基づき、将来減算一時差異の解消見込額を個別所得見積額と解消見込年度ごとに相殺する。相殺された金額に係る繰延税金資産は回収可能性があると判断される。相殺できなかった将来減算一時差異は、連結納税における税効果会計上、解消年度に発生した繰越欠損金と同様に取り扱う。この繰越欠損金と同様に取り扱う繰延税金資産の回収可能性の判断は、下記(ⅱ)により行う。
(ⅱ) 繰越欠損金
(イ) 当期末において存在する繰越欠損金を、税務上認められる繰越期間内に、(上記(ⅰ)控除後の)個別所得見積額と相殺する。相殺された金額に係る繰延税金資産は、回収可能性があると判断する。
![]()
(ロ) 上記(イ)で相殺できなかった繰越欠損金に係る繰延税金資産は、回収可能性がないと判断し、繰延税金資産を計上することはできない。
なお、以上の②~④では将来減算一時差異等と将来加算一時差異との相殺について解説していないが、回収可能性の検討においては当然に考慮する(連結財務諸表でも同様)。
(3) 支払可能性の検討
将来加算一時差異は、将来の課税所得(税金)を増加させるものである。したがって、理論上は将来の税金の支払が見込まれる(支払可能性のある)将来加算一時差異に係る繰延税金負債のみを貸借対照表に計上するために、繰延税金負債について支払可能性の検討が必要である。
しかし、会計制度委員会報告第10号「個別財務諸表における税効果会計に関する実務指針」(以下、「個別指針」という)では、事業休止等により、会社が清算するまでに明らかに将来加算一時差異を上回る損失が発生し、課税所得が発生しないことが合理的に見込まれる場合のみ支払可能性がないと判断することになっている(個別指針24)。そのため、事業休止等の状況でない限り、支払可能性はあるとし、会社が事業を行っている状況では支払可能性を検討せずに、(スケジューリング不能な将来加算一時差異も含む)全ての将来加算一時差異に係る繰延税金負債を貸借対照表に計上する。