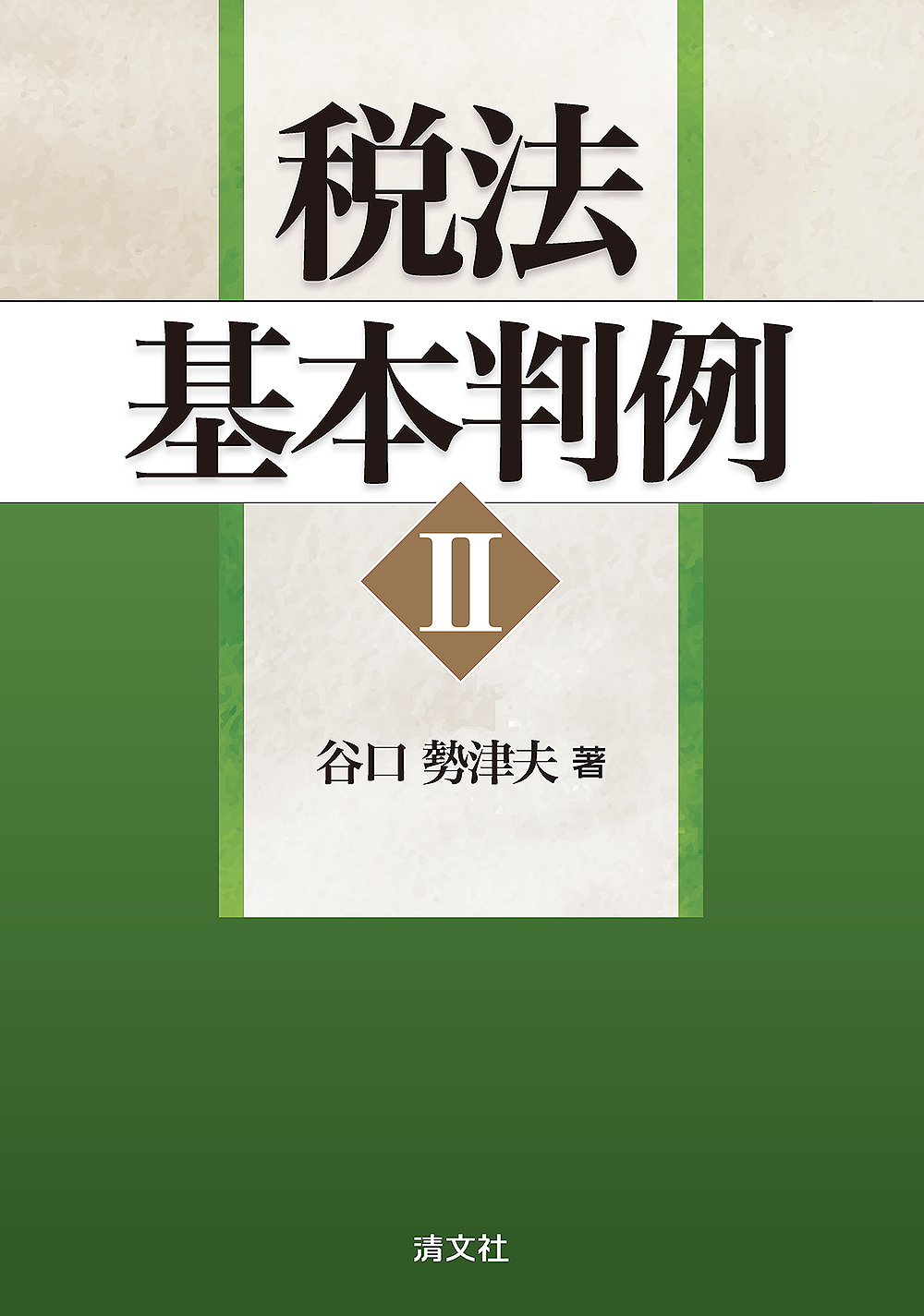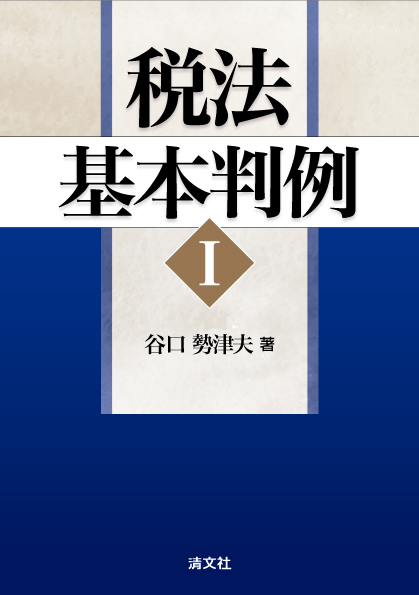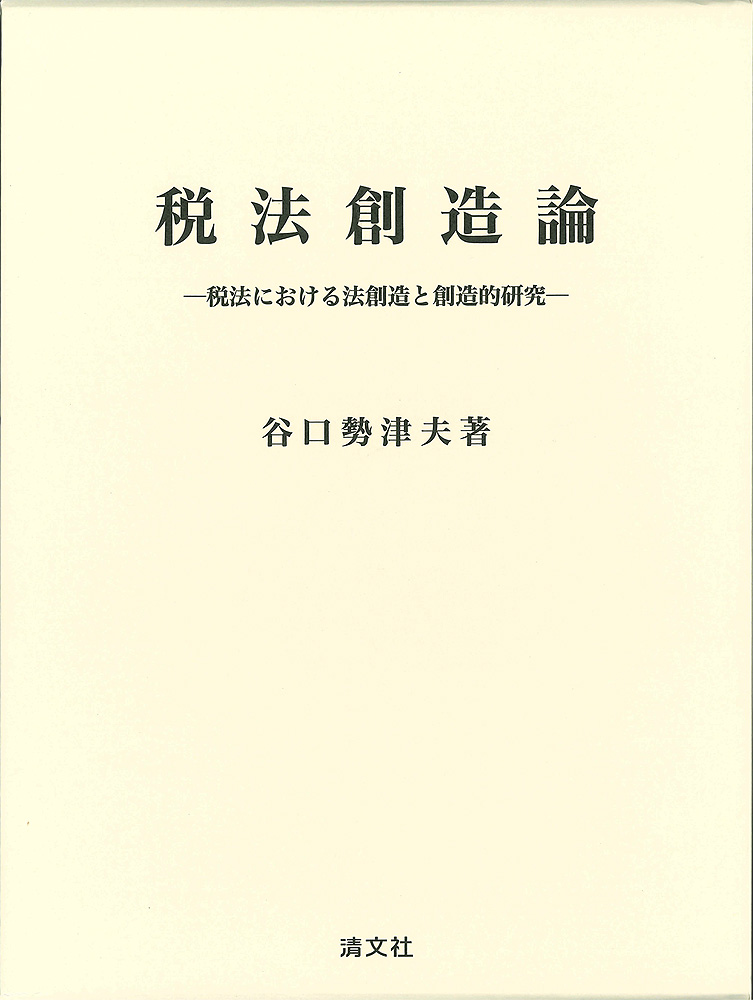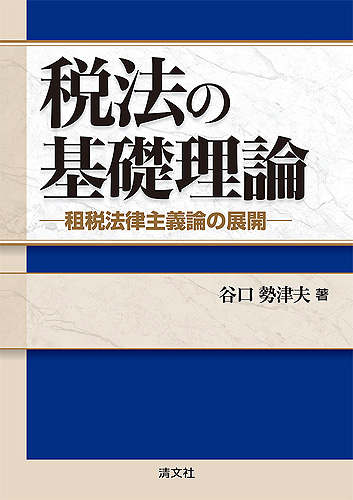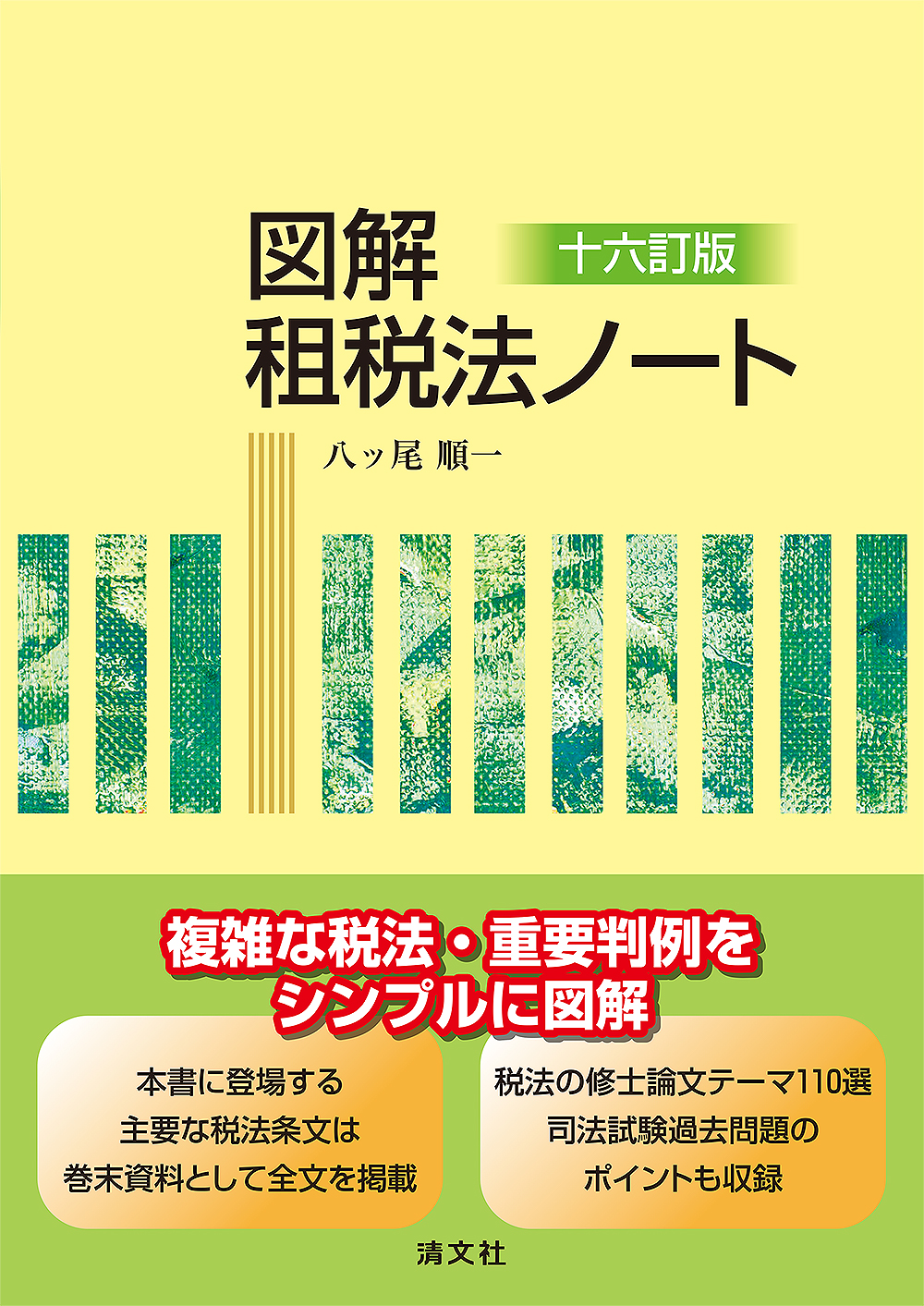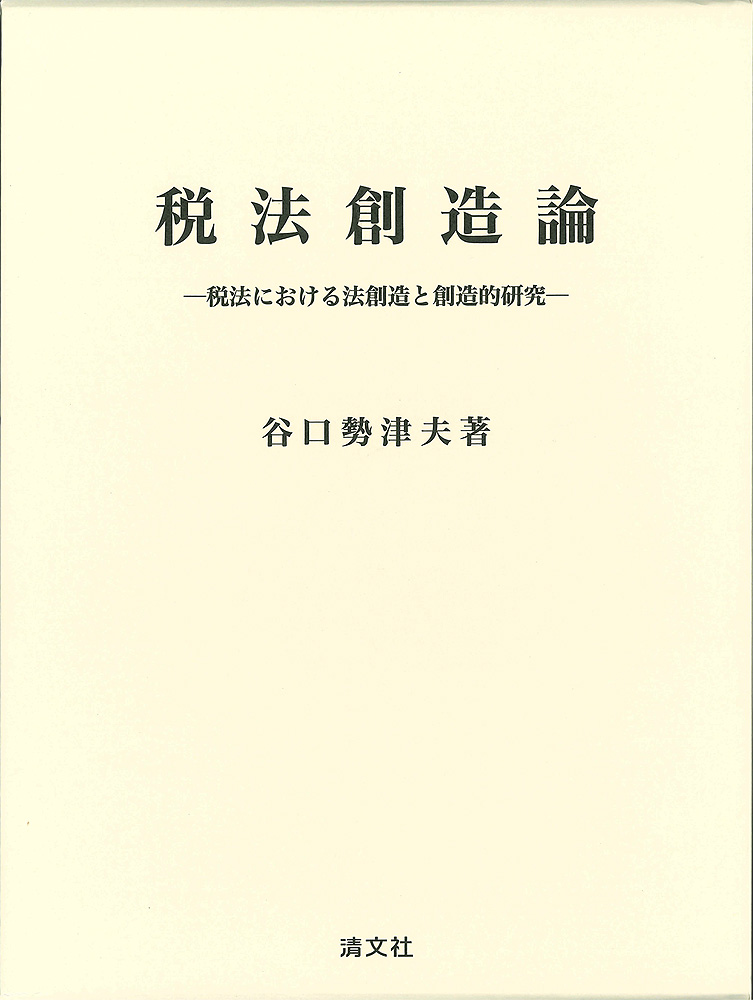谷口教授と学ぶ
税法基本判例
【第53回】
「給与所得該当性判断に関する「判断の一応の基準」の意味と展開」
-外国親会社ストック・オプション[所得分類]事件・最判平成17年1月25日民集59巻1号64頁-
大阪学院大学法学部教授
谷口 勢津夫
Ⅰ はじめに
前回は、弁護士顧問料事件・最判昭和56年4月24日民集35巻3号672頁(以下「昭和56年最判」という)において示された、事業所得と給与所得の区分に関する「判断の一応の基準」の意味について検討した結果、「自己の計算と危険において独立して営まれ、営利性、有償性を有し、かつ反覆継続して遂行する意思と社会的地位とが客観的に認められる業務から生ずる所得」という事業所得の定義で示された基準は「判断の完全な基準」である(したがって、弁護士の顧問料が事業所得に該当すると判断した同判決については、この基準がレイシオ・デシデンダイである)のに対して、「雇傭契約又はこれに類する原因に基づき使用者の指揮命令に服して提供した労務の対価として使用者から受ける給付」という給与所得の定義で示された基準は「判断の一応の基準」にとどまるという見解を述べた(そこでは前者の基準を「労務の提供等の独立性」基準、後者の基準を「労務の提供等の従属性」基準と呼んだ)。
今回は、米国親会社がその100%子会社である内国法人の代表取締役に対して付与したストック・オプションに係る権利行使益(以下「本件権利行使益」という)の給与所得該当性を認めた外国親会社ストック・オプション[所得分類]事件・最判平成17年1月25日民集59巻1号64頁(以下「本判決」という)が「所論引用の判例[=昭和56年最判]は本件に適切でない。」と判断したことの意味を検討しながら、昭和56年最判が示した給与所得該当性の判断基準(「労務の提供等の従属性」基準)が「判断の一応の基準」であることの意味をもう一度確認し、本判決におけるその基準の展開を検討することにしたい。
なお、過少申告加算税の賦課以外は本件と類似の事実関係の下で過少加算税につき「正当な理由」が認められるか否かが争われた外国親会社ストック・オプション[加算税]事件については最判平成18年10月24日民集60巻8号3128頁がある(第34回Ⅱ参照)。
この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員登録およびログインが必要です。
すでに会員登録をされている方は、下記ボタンからログインのうえ、ご覧ください。
Profession Journalのすべての記事をご覧いただくには、「プレミアム会員(有料)」へのご登録が必要となります。
なお、『速報解説』については「一般会員(無料)」へのご登録でも、ご覧いただけます。
※他にもWebセミナー受け放題のスーパープレミアム会員などがございます。
会員登録がお済みでない方は、下記会員登録のボタンより、ご登録のお手続きをお願いいたします。