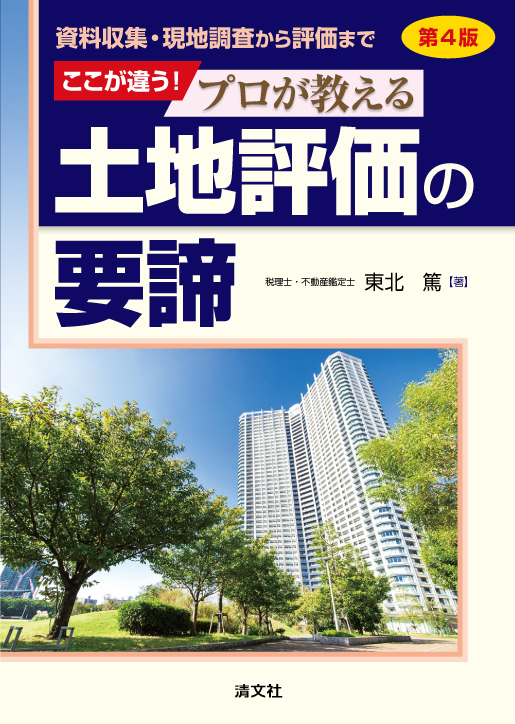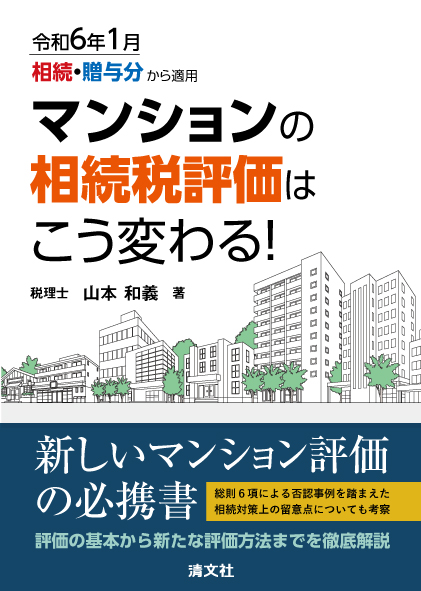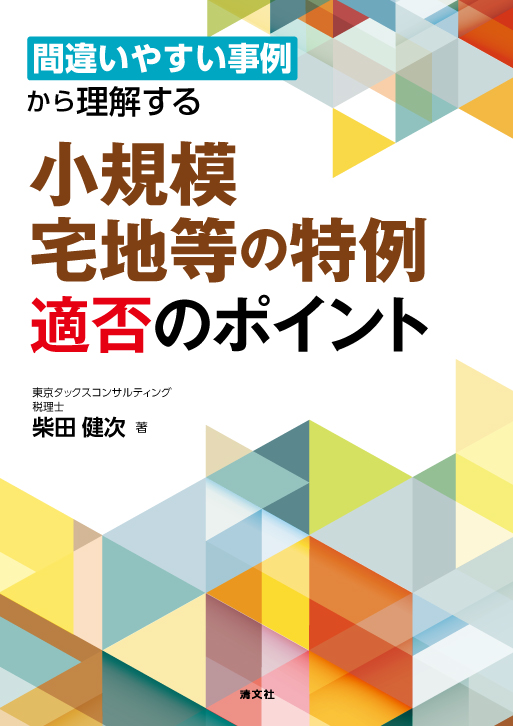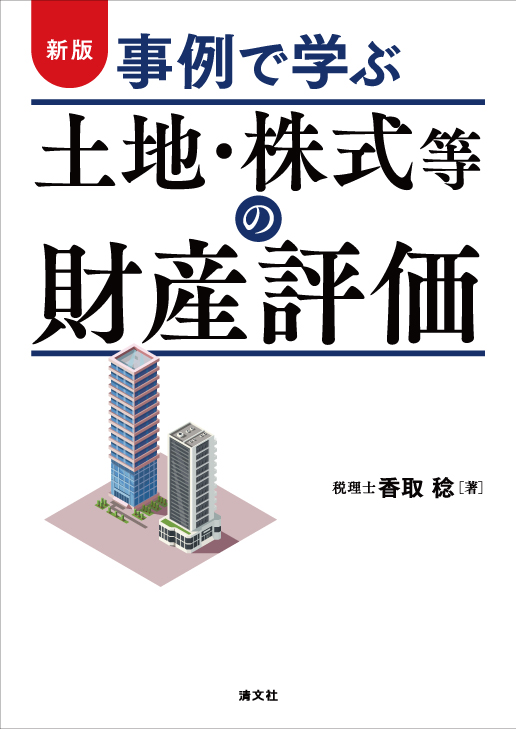空き家をめぐる法律問題
【事例1】
「立木の侵入や擁壁の崩壊等した場合の法的責任」
弁護士 羽柴 研吾
- 事 例 -
私は、現在、関西で暮らしていますが、東北の実家で一人暮らしであった母が亡くなったため、母名義の実家の土地と建物を相続しました。実家は、現在は空き家となっています。
私の実家の土地は、隣家より少し高い位置にあるため、隣家との法面をブロック塀で補強しており、ブロック塀に沿って木を植えています。ある日、私が実家に立ち寄った際に、ポストに隣家の方からの手紙が届いていました。手紙には、主として次の2つの事項が書かれていました。
【1】 昨年の大雪で一部崩れたブロック塀の間から木の根が出ており、枝も成長して侵入しているので、枝と根を切除すること
【2】 ブロック塀が崩れて土砂が流入しているので、除去すること
このような場合、どのように対応すればよいでしょうか。
1 空き家の類型と管理責任について
近年、空き家に関する議論は、空き家の取壊し関するものから有効活用に関するものまで、広がりを見せている。
もっとも、ひと言に「空き家」と言っても、
① 建物自体の管理が放棄されており、周囲に危険を及ぼすおそれがあるもの
② 周囲に危険を及ぼすおそれは低いが、適切な管理が行われていないもの
③ 有効活用できる状態のもの
など様々な状態の空き家がある。
このため、空き家の管理に関する法律問題を考えるに当たっては、その空き家がどのような状態の空き家であるかを意識して検討することが有益である。
本件のように、空き家に関する相続が発生した場合、相続人が被相続人から遠方で生活しており、時間的・距離的制約のため、相続人による空き家の管理が適切に行われず、隣家とトラブルになることがある。上記①~③の空き家の類型でいえば、②の類型に生じやすい法律問題である。
2 隣地の権利関係の調整
一般に、所有権者は、自由に、その所有物の使用、収益及び処分をすることができる(民法第206条)。一方で、土地は物理的には連続しているため、土地の所有権者間の相互の利用を調整する必要が生じる。
そこで、民法は、第209条から第238条において、各種の利用調整に係る条項を規定している。これらの規定は「相隣関係」と呼ばれている。
土地の所有権は、その土地を十分に利用する範囲で上下に及び、境界付近に樹木を植えることは可能である。しかしながら、成長した樹木の枝や根が空中や地中を経て隣地に侵入することがあるため、隣地との権利関係を調整する必要が生じる。
このような場合を想定して規定されたのが、民法第233条(竹木の枝の切除及び根の切取り)である。
民法第233条 隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
2 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。
上記のとおり、民法は、隣地から枝が侵入してきた場合と、根が侵入してきた場合とで、侵入された所有権者がとりうる手段に差を設けている。
このような差があるのは、①枝の方が根よりも高価であることや、②枝が侵入した場合は、竹木の所有権者が自らの土地の中からその枝を切除できるのに対して、根が侵入した場合は、隣地に入らなければ切除できないことによるものと考えられている。
まず、竹木の枝が境界線を越えた場合は、所有権者は隣地の所有権者に対して、その枝を切除することを請求することができ、この請求に応じない場合は、裁判所を通じて、隣地の所有者の負担において、第三者に枝の伐採を実現させることができる。
もっとも、このような請求が無制限に認められるわけではなく、何らの害悪も生じていない状況において、枝の切除を請求することは、権利の濫用と評価されることもある。
また、侵入してきた根を自らの判断で切除する場合でも、枝の場合と同様に、根の侵入による影響がほとんどないにもかかわらず、根を切除して高価な竹木を枯らしてしまったような場合は、権利の濫用と評価される可能性があるため、留意が必要である。
3 流出した土砂の処理について
所有権者は、物権を侵害されたり、そのおそれがある場合に、所有権に基づく物権的請求権を行使することができる。
物権的請求権は、侵害の態様に応じて、
① 返還請求権
② 妨害排除請求権
③ 妨害予防請求権
の3種類が認められている。
この物権的請求権の法的性質は、積極的行為請求権、すなわち、その相手方が侵害状態を作出したか否かにかかわらず、費用を負担させて、侵害状態やそのおそれがある状態を取り除くことを請求する権利と解されている。
しかしながら、過去の大審院判決によれば、不可抗力によって第三者の土地を侵害する状態が生じているような場合には、物権的請求権の発生や行使が制限されると解する余地がある。また、学説においても、所有権者は、自らの費用負担で侵害状態を除去することができ、これを相手方に認容させることができるに留まるとする見解など、積極的行為請求権を修正する見解が有力に主張されている。
その他、裁判例の中には、妨害予防請求権が行使された事案において、隣地所有者間双方に便益が生じることや、工事に多額の費用が生じること等を理由に、費用の分担を命じているものもあり、このような場合には個別の検討を要する。
4 本件の対応
(1) 隣家からの要望【1】について
空き家の敷地所有者は、枝を切除するなど適宜対処し、根の切除については、隣地に入って作業をする必要がある場合には、隣地の所有者と協議をして隣地に入る同意を得たうえで切除を行うことになろう。
(2) 隣家からの要望【2】について
ブロック塀が崩れて、その隙間から土砂が流出しており、隣地の所有権を侵害することになるため、原則として、空き家の敷地所有者は、自らの負担で土砂を除去し、ブロック塀を補修する等適宜工事を行う必要がある。この場合も、隣地に入って作業をする必要があるときは、事前に隣地の所有者から同意を得ておく必要がある。
(3) その他留意事項
ブロック塀が崩れて土砂が流出した先に、隣家の花壇等があり、これらを損壊したような場合には、別途不法行為に基づく損害賠償請求をされる可能性があるので留意が必要である。
(了)
「空き家をめぐる法律問題」は、毎月第1週に掲載します。次回は5/10の掲載となります。