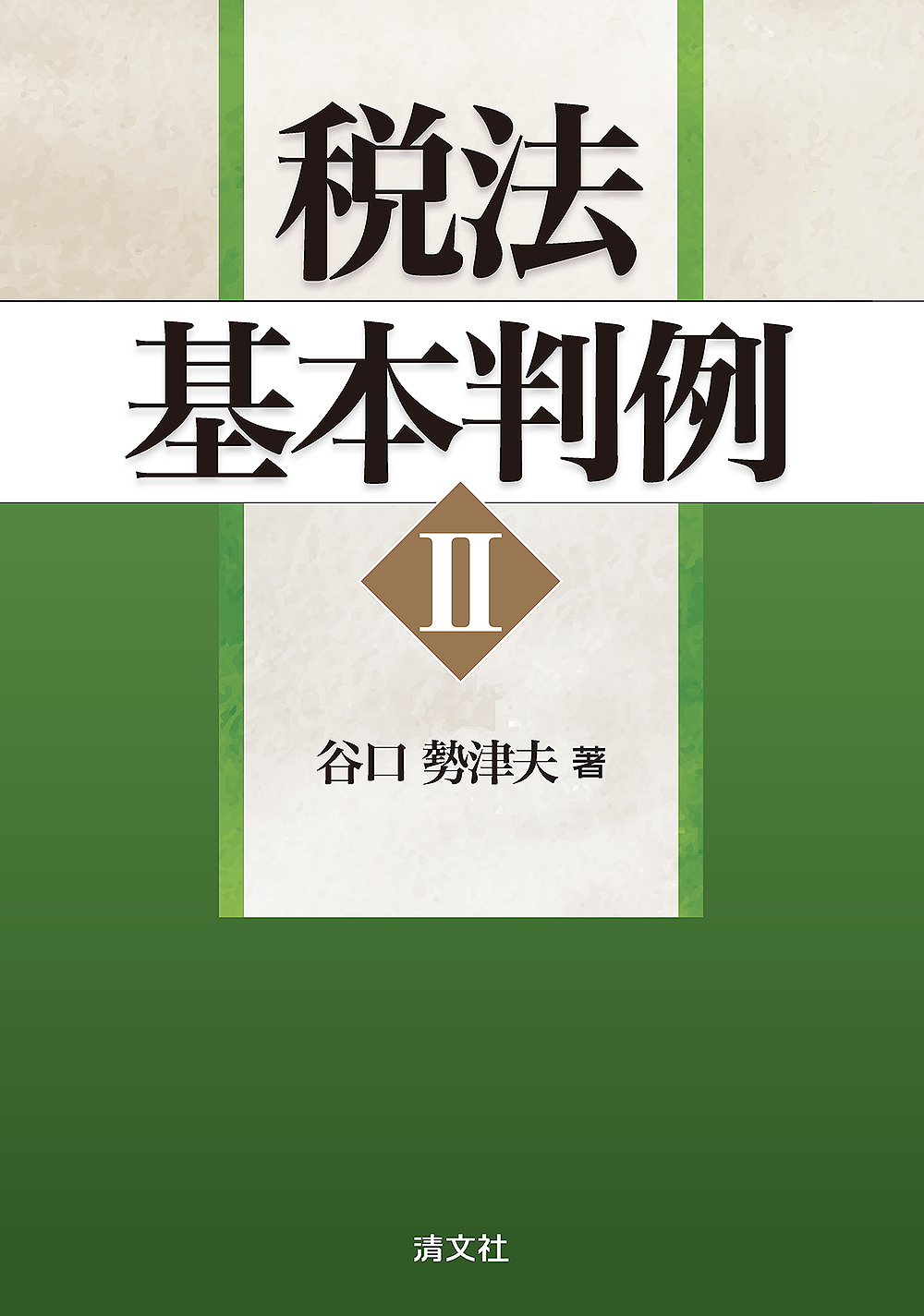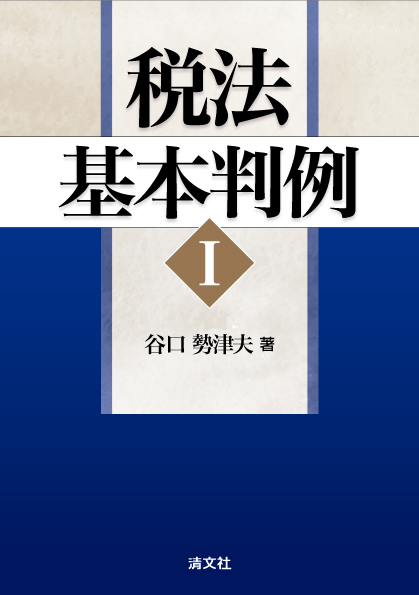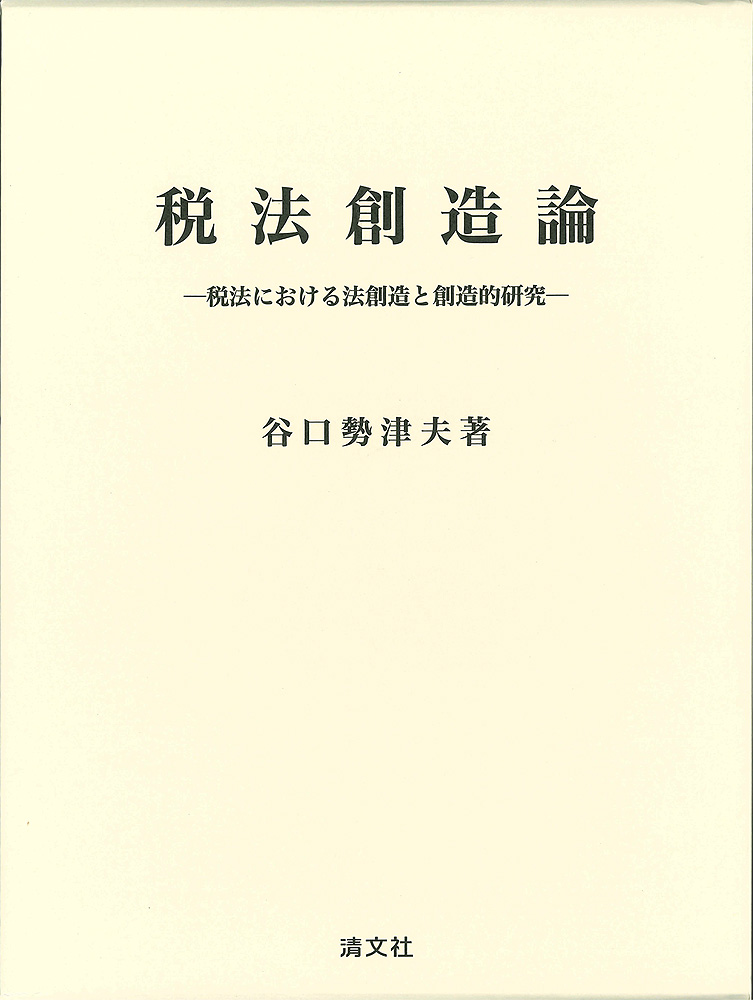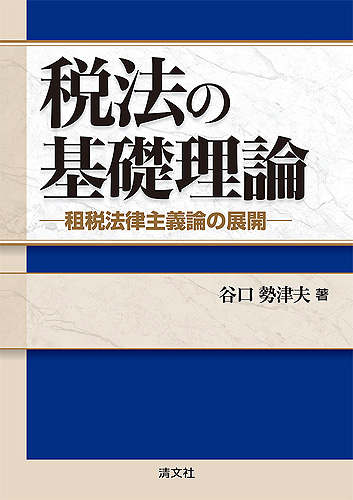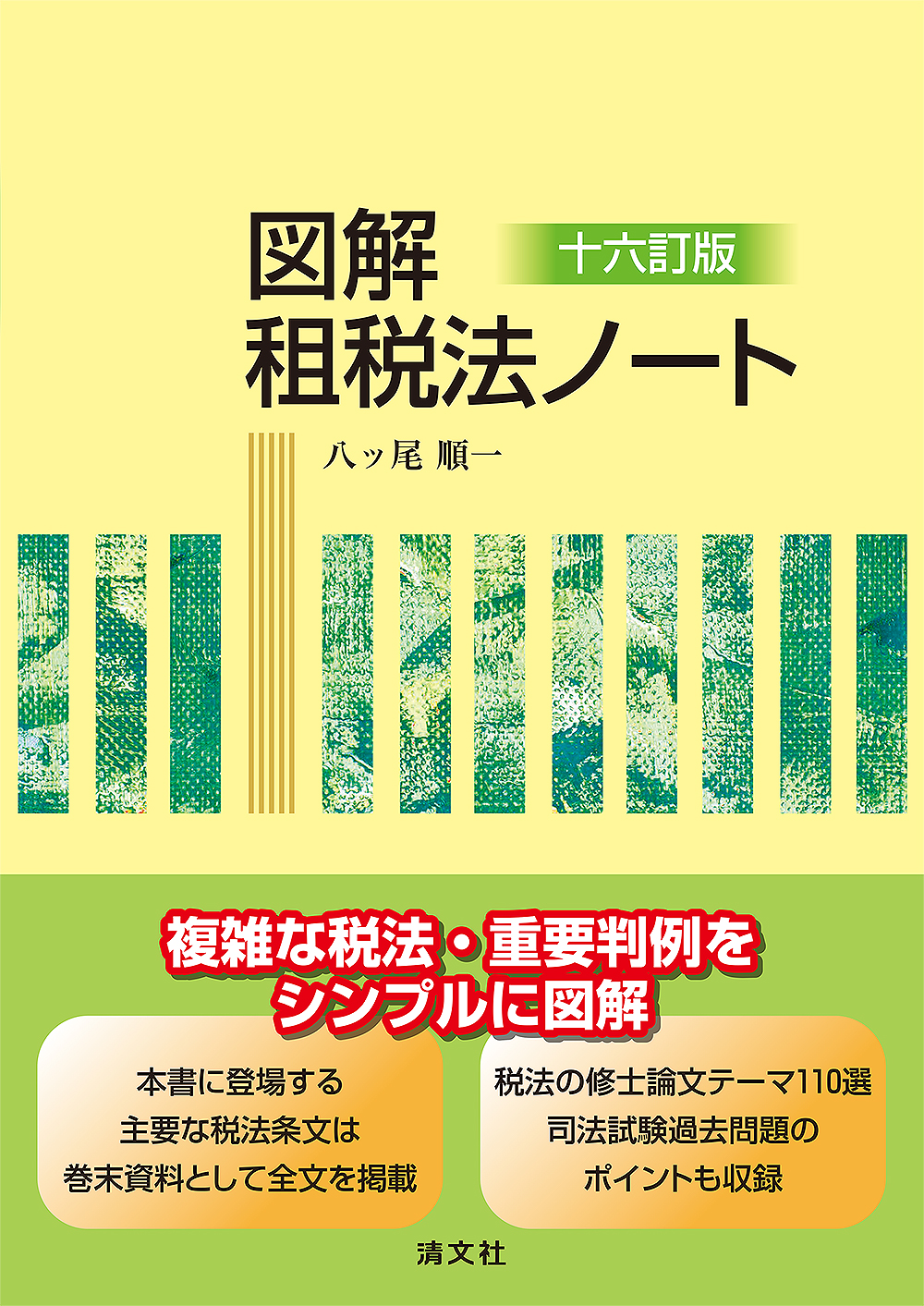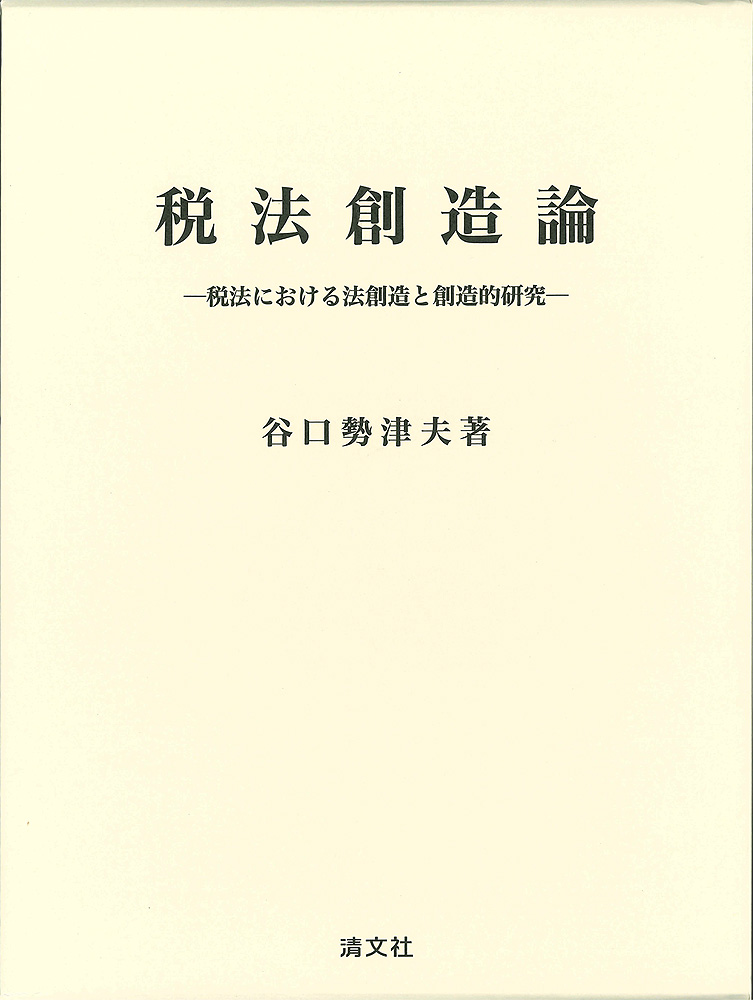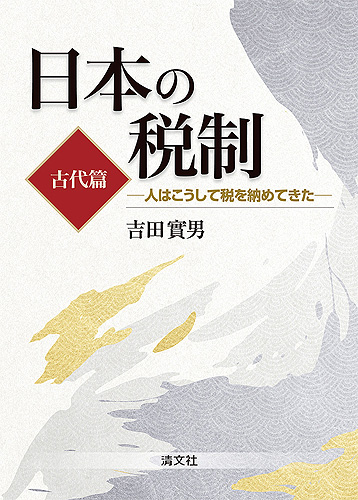谷口教授と学ぶ
税法基本判例
【第1回】
「憲法上の租税概念」
-旭川市国民健康保険条例事件・最[大]判平成18年3月1日民集60巻2号587頁-
大阪大学大学院高等司法研究科教授
谷口 勢津夫
Ⅰ はじめに
本連載は、「谷口教授と学ぶ」シリーズとして、昨年(2020年)12月に第50回をもって連載を終了した「税法の基礎理論」に続くものであり、「税法基本判例」と題して税法判例を検討するものである。
とはいえ、通常行われるような判例評釈や判例研究を主たる目的とするものではなく、「税法の基礎理論」と同じく原則1回読み切りの「読み物」として税法判例を検討しようとするものであることから、検討対象の判例が取り扱った論点を網羅的に検討するのではなく、むしろ筆者の問題関心により論点を絞って(内容的には「税法の基礎理論」的思考を重視しながら)検討しようとするものであることを、連載を始めるに当たって予めお断りしておく。
本連載で検討の対象とする判例は、基本的には、拙著『税法基本講義〔第6版〕』(弘文堂・2018年)で参照している判例の中から、同書における叙述の順に従って取り上げていくことにする。
今回は、旭川市国民健康保険条例事件・最[大]判平成18年3月1日民集60巻2号587頁(前掲拙著・欄外番号【9】【12】。以下「本判決」という)を取り上げることにしよう。
この事件は、平成6年4月12日にY1(旭川市-被告・控訴人・被上告人)を保険者とする国民健康保険の一般被保険者(全被保険者から退職被保険者及びその被扶養者を除いた被保険者)の資格を取得した世帯主であるX(旭川市民-原告・被控訴人・上告人)が、平成6年度から同8年度までの各年度分の国民健康保険の保険料について、Y1から賦課処分を受け、また、Y2(旭川市長-被告・控訴人・被控訴人)から所定の減免事由に該当しないとして減免しない旨の通知処分を受けたことから、Y1に対し上記各賦課処分の取消し及び無効確認を、Y2に対し上記各通知処分の取消し及び無効確認をそれぞれ求めた事案である。
この事件における争点は、国民健康保険料に対して憲法84条による規律(租税法律主義)が適用されるか否かであるが、その出発点として、憲法84条に規定する「租税」の意義が問題となる。以下では、この問題を中心に検討することにする。
Ⅱ 講学上の租税概念
1 租税概念の要素
本判決は、前記の争点について判断するに当たり、その冒頭において、憲法84条に規定する「租税」の意義について次のとおり判示している。
国又は地方公共団体が、課税権に基づき、その経費に充てるための資金を調達する目的をもって、特別の給付に対する反対給付としてでなく、一定の要件に該当するすべての者に対して課する金銭給付は、その形式のいかんにかかわらず、憲法84条に規定する租税に当たるというべきである。
本判決は、いわゆる保育料の租税該当性を否定した最判平成2年7月20日集民160号343頁とは異なり、大嶋訴訟・最[大]判昭和60年3月27日民集39巻2号247頁を引用してはいないものの、前記の判示は、同判決における「租税」の意義に関する判示、すなわち、「租税は、国家が、その課税権に基づき、特別の給付に対する反対給付としてでなく、その経費に充てるための資金を調達する目的をもつて、一定の要件に該当するすべての者に課する金銭給付である」という判示を踏襲したものと解される。
これらの判示にいう「租税」は、講学上の租税概念と基本的には同じものであると一般に解されている(差し当たり、講学上の租税概念を「固有の意義の租税」として同様の理解を示すものとして阪本勝「判解」最判解民事篇平成18年度(上)(法曹会・2009年)312頁、324頁参照)。講学上の租税概念については代表的な学説において下記のとおり概ね見解の一致がみられるところである(①=田中二郎『租税法〔第3版〕』(有斐閣・1990年)1-2頁、②=清永敬次『税法〔新装版〕』(ミネルヴァ書房・2013年)2頁、③=金子宏『租税法〔第23版〕』(弘文堂・2019年)9頁)。
【①】
租税とは、国又は地方公共団体が、その課税権に基づき、特別の給付に対する反対給付としてでなく、これらの団体の経費に充てるための財力調整の目的をもって、法律の定める課税要件に該当するすべての者に対し、一般的標準により、均等に賦課する金銭給付である[。]
【②】
租税とは、国又は地方公共団体が、収入を得ることを目的にして、法令に基づく一方的義務として課す、無償の金銭的給付である。
【③】
国家が、特別の給付に対する反対給付としてではなく、公共サービスを提供するための資金を調達する目的で、法律の定めに基づいて私人に課する金銭給付である[。]
租税の意義について、本判決による前記の定義も含め以上の定義に共通すると考えられる基本的要素は、相互に重なり合う部分もあるが、一応、㋑国家ないし国・地方公共団体、㋺課税権、㋩非対価性ないし無償性、㊁収入目的ないし資金調達目的、㋭権力性ないし一方性(強制性)、㋬金銭給付の6つに整理することができるように思われる(田中・前掲書2頁、清永・前掲書3頁、金子・前掲書10-11頁参照)。
2 課税権の意義
本判決は、租税の意義に関する前記の判示に続けて、「市町村が行う国民健康保険の保険料は、これ[=憲法84条に規定する租税]と異なり、被保険者において保険給付を受け得ることに対する反対給付として徴収されるものである。」と判示し、前記の㋩非対価性という要素を基準にして国民健康保険料の租税該当性を否定した。
この判断についてまず疑問に思われるのは、本判決がなぜ㋺課税権という要素を援用しなかったのかという点である。租税概念の前記の各要素のうち㋑、㊁、㋭及び㋬は、全く同一の意味においてではないにしても、国民健康保険料の要素でもある。すなわち、国民健康保険料は、市町村(㋑)が国民健康保健事業に要する経費を調達する目的(㊁)で強制加入制に基づき強制徴収(㋭)を行う金銭給付(㋬)である。しかし、国民健康保険料が㋺課税権に基づき課されるものでないことは明らかである。そうである以上、本判決が㋺課税権という要素を援用せず㋩非対価性という要素のみを援用して国民健康保険料の租税該当性を否定したのはなぜか、疑問に思われるのである。
この疑問を検討するに当たって、以下では、本判決は㋺課税権と㋩非対価性とを一体的に結びつけて判断したのではないかとの仮説を立て、その論証を行うことにしたい。
その論証を始めるに当たって、まず、課税権の意味を明らかにしておこう。「課税権」という語は、論者によって、また、文脈・場面によって、異なる意味で用いられる。例えば田中・前掲書によれば、ⓐ「国又は地方公共団体が統治権の主体として有する課税権」(2頁)という場合における「統治権の一環」(3頁)、ⓑ「行政権の一環としての課税権」(56頁)、Ⓒ「主権の発現としての租税高権」(106頁)、ⓓ「税務行政庁が租税債権の具体的確定のためにする処分、すなわち、更正若しくは決定(申告納税方式の場合)又は賦課決定(賦課課税方式の場合)をすることができる権利(公法上の一種の形成権)」(159頁。198頁も参照)というような意味が示されているが、田中・前掲書がⓓの意味での「課税権」(賦課権)と区別する「徴収権」すなわち「すでに確定した租税債務の履行として納付された税額を収納し、又はその履行を請求し、その収納をはかることができる権利」(159-160頁)も、見方によっては、次に述べるように、「課税権」に含めて理解することができるように思われる。
租税法律関係を租税債務関係とみる場合(租税債務関係説)には、「租税債権者としての国または地方団体の権利は、確定権と徴収権とに大別することができ」、「納税義務の内容を確定する権利」を確定権といい、「内容の確定した納税義務の履行を求め、その徴収を図る権利」を徴収権ということができる(金子・前掲書154頁)。この場合、確定権について、「従来は、賦課権という言葉が一般的に用いられてきたが、納税義務は法律の定める課税要件の充足によって成立し、更正・決定・賦課決定は租税を賦課する行為ではなく、納税義務の内容を確定する行為であるから、賦課権とか賦課処分という言葉を用いるのは不適当であると考える。」(同頁)といわれるが、この考え方は、田中・前掲書にみられる前記の用語法に租税権力関係説のいわば「残滓」を認めるものと解される。
ともかく、金子・前掲書の上記の考え方からすれば、確定権も徴収権も国又は地方公共団体の権利である以上、それらの権利を「課税権」に含めて理解することができ、さらには、それらの権利において確定や行使の対象となるⓔ租税債権それ自体も「課税権」に含めて理解することができるように思われる(前掲拙著【24】参照)。
この点について(そして、次のⅢ1における検討についても)、次の考え方は示唆に富むものである。それは、「課税権は公法的なものであるが、その結果生ずる租税債権には私法的性格が濃厚に残っているのである。」(中里実『財政と金融の法的構造』(有斐閣・2018年)57頁[初出・2014年])として、「租税は、主権と財産権の狭間に位置する存在といえるのではなかろうか。」(同58頁)と述べるものである。
Ⅲ 憲法上の租税概念の2つの側面
1 租税債権の目的としての租税
本判決が租税の意義に関してその要素として判示する「課税権」を、前述のようにⓔ租税債権の意味に理解する場合、㋺課税権と㋩非対価性とは一体的に結びつけて捉えることができると考えられる。その理由は以下のとおりである。
ここでは、まず、国家がなぜ租税債権を有するのかという問題から考えることにしよう。この問題は、国民がなぜ租税債務すなわち「納税の義務」(憲法30条)を負うのかという憲法上の租税根拠の問題を、国家の側からみたものである。
憲法上の租税根拠論について、筆者は、従来から次のとおり(前掲拙著【24】)、「憲法30条=29条『4項』論」を説いてきた。
憲法は、国家の存在を前提にして、その体制として社会主義体制ではなく、自由主義体制を選択した上で、財産権を基本的人権の1つとして保障している。そのため、国家資金の調達方法として国有財産および国家の営利活動による資金調達を予定することは、原則としてできない。そうすると、国家体制の選択の段階で既に、租税による国家資金の調達が、憲法上予定されていることになる(現行憲法による課税権の正統根拠論 ⇒【15】)。したがって、国家によって保障される私有財産制には、租税侵害が、その中核的内容として予め組み込まれている(内在している)、と考えられるのである。この点に関して、憲法による財産権保障規定(29条)と、納税の義務規定(30条)との位置関係は、多分に歴史的偶然の所産とはいえ、暗示的である。後者はいわば憲法29条「4項」の如く位置づけられるべきであろう(憲法30条=29条「4項」論)。ともかく、憲法上、租税は「民主主義の対価」(民主主義的租税観 ⇒【14】)であると同時に、自由主義(基本的人権尊重主義)の下、「自由(基本的人権保障)の対価」(自由主義的租税観)でもあり、両者の不可分一体的連関によって根拠づけられ正当化されるべき負担である(憲法上の租税根拠論[課税の正当根拠論]における両者の関係については ⇒【15】)。
この考え方によれば、ⓔ租税債権という意味での「課税権」は、国家が自由主義体制を選択し私有財産制を保障することといわば「引き換えに」私人に対して有する権利であると考えることができる。比喩的にいえば、いずれが「卵」か「鶏」かはともかく、租税債権(課税権)があるから私有財産制があるといってもよいし、私有財産制があるから租税債権(課税権)があるといってもよかろう。いずれにせよ、両者がこのような関係にあるが故に、租税は財産権にとって「内在的制約」であるといえるのである。
このことは、私有財産制に基礎を置く私人の自由な経済活動の「場」である市場には、租税はそれ自体としては登場しないことを意味する。換言すれば、租税は、市場を基礎づける私有財産制の中核的内容を構成するとはいえ、市場外の事象である。
そうすると、租税には、市場における交換経済の構成要素である対価性(給付に対する反対給付)は観念できないことになる。このことが、㋩非対価性が租税概念の要素とされる所以である。
以上により、「課税権」をⓔ租税債権の意味で理解する場合、㋺課税権(租税債権)に基づき課される租税、すなわち、租税債権の目的としての租税については、㋩非対価性がその属性として観念されることになるのである。この意味で、㋺課税権と㋩非対価性とは一体的に結びつけて捉えることができよう。
要するに、本判決は、憲法84条に規定する租税について租税債権の目的としての側面を問題にし、その属性としての㋩非対価性を基準にして、国民健康保険料の租税該当性を否定したものと解されるのである。
なお、本判決は、「Y1における国民健康保険事業に要する経費の約3分の2は公的資金によって賄われているが、これによって、保険料と保険給付を受け得る地位とのけん連性が断ち切られるものではない。」と判示する。ここでいう「けん連性」は対価性と言い換えてもよかろうが、それは、国民健康保険が、社会保険の一種として「国民の生活保障という社会政策目的に沿った扶助原理(扶養原理ともいわれる)によって修正」(加藤智章ほか『社会保障法〔第7版〕』(有斐閣・2019年)22頁[倉田聡執筆])を受けてはいるが、基本的には保険原理(給付反対給付均等の原則及び収支相等の原則)という市場原理に従って構想されており、その意味では市場内の事象であるからである。
この点に関連して、本判決が括弧書の中で「国民健康保険税は、前記のとおり目的税であって、上記の反対給付として徴収されるものであるが、形式が税である以上は、憲法84条の規定が適用されることとなる。」と判示したことにつき、「判旨全体との整合性には疑問がある」(藤谷武史「判批」租税判例百選〔第6版・2016年〕9頁)と指摘されることがある。理論的には成り立つ疑問であるが、その判示は、「日本国憲法の下では、租税を創設し、改廃するのはもとより、納税義務者、課税標準、徴税の手続はすべて前示のとおり法律に基いて定められなければならないと同時に法律に基いて定めるところに委せられていると解すべきである。」(下線筆者)という判例(最[大]判昭和30年3月23日民集9巻3号336頁。前掲大嶋訴訟・最[大]判も同旨)の立場を踏襲し、租税の創設を含め租税立法につき広範な裁量を認めたものと解される。
2 統治権の手段としての租税
ところで、本判決は、国民健康保険料に対して憲法84条が直接適用されるとはしなかったが、次のとおり判示して(下線筆者)、同条の趣旨が適用されることは認めた(憲法84条「趣旨」適用説。同説については拙稿「租税法律主義(憲法84条)」日税研論集77号(2020年)243頁、255頁参照)。
もっとも、憲法84条は、課税要件及び租税の賦課徴収の手続が法律で明確に定められるべきことを規定するものであり、直接的には、租税について法律による規律の在り方を定めるものであるが、同条は、国民に対して義務を課し又は権利を制限するには法律の根拠を要するという法原則を租税について厳格化した形で明文化したものというべきである。したがって、国、地方公共団体等が賦課徴収する租税以外の公課であっても、その性質に応じて、法律又は法律の範囲内で制定された条例によって適正な規律がされるべきものと解すべきであり、憲法84条に規定する租税ではないという理由だけから、そのすべてが当然に同条に現れた上記のような法原則のらち外にあると判断することは相当ではない。そして、租税以外の公課であっても、賦課徴収の強制の度合い等の点において租税に類似する性質を有するものについては、憲法84条の趣旨が及ぶと解すべきであるが、その場合であっても、租税以外の公課は、租税とその性質が共通する点や異なる点があり、また、賦課徴収の目的に応じて多種多様であるから、賦課要件が法律又は条例にどの程度明確に定められるべきかなどその規律の在り方については、当該公課の性質、賦課徴収の目的、その強制の度合い等を総合考慮して判断すべきものである。
ここでいう「国民に対して義務を課し又は権利を制限するには法律の根拠を要するという法原則」は、法律による行政の原理の内容の1つである法律の留保について妥当する「侵害留保の原則」(塩野宏『行政法Ⅰ〔第6版〕』(有斐閣・2015年)80頁)を意味することからすると、「[憲法84条は侵害留保の原則を]租税について厳格化した形で明文化したものというべきである」という判示では、「課税権」のうちⓐ統治権やⓑ行政権の一環としての課税権(前記Ⅱ2参照)に基づき課される「租税」が問題にされていると解される。
この意味での「租税」は、国家がⓐ統治権に基づき㊁資金調達目的でⓑ行政権によって㋭一方的に(強制的に)賦課徴収する㋬金銭給付であり、「統治権の手段としての租税」(目的は㊁)ということができるが、国民健康保険料はこれに「類似する性質を有する」公課といえる。本判決はこのような性質を有する国民健康保険料について「憲法84条の趣旨」が及ぶと判示したのである。
本判決のいう「憲法84条の趣旨」は、憲法84条が83条の財政民主主義を租税について具体化するものであること(前掲拙稿251頁参照)からすると、租税の賦課徴収に対する民主的コントロールの要請を意味するものと解されるので、その趣旨が国民健康保険料について及ぶということは、同保険料の賦課徴収に対する民主的コントロールを租税法律主義が要請することを意味すると解される。本判決は、その民主的コントロール(「賦課要件が法律又は条例にどの程度明確に定められるべきかなどその規律」)の在り方(規律密度)については、「当該公課の性質、賦課徴収の目的、その強制の度合い等を総合考慮して判断すべきものである。」と判示している。
本判決は、前述のとおり、「[憲法84条は侵害留保の原則を]租税について厳格化した形で明文化したものというべきである」と判示したが、この判示は、憲法84条は租税の賦課徴収に対する民主的コントロールを「法律」にのみ委ねるという原則を明らかにしたものと解される。その原則が租税法律主義であるが、憲法84条は、明治憲法下では基本的には自由主義的な法律による行政の原理として性格づけられていた租税法律主義を、財政民主主義の具体化として民主主義的に再構成したものと解される。このような租税法律主義の民主主義的再構成によって、課税要件法定主義が、そしてこれと「一体」をなす要請として課税要件明確主義が、租税法律主義の内容として確立されたのである(前掲拙稿250-254頁、275-279頁、谷口教授と学ぶ「税法の基礎理論」【第34回】Ⅱ3・4、【第45回】参照)。これらは、租税法律の規律密度を高めることを立法者に命じるものである。
Ⅳ おわりに
以上を要するに、本判決は、憲法84条に規定する租税について、一方では、租税債権の目的としての側面では、非対価性・無償性を基準にして国民健康保険料との区別を行うことによって、租税法律主義の適用範囲を明確にし、他方では、統治権の手段としての側面では、賦課徴収に対する民主的コントロールを国民健康保険料その他の公課の場合に比べて厳格化することによって、租税法律主義の規律内容を明確にしたものと解される。
このように、租税法律主義については、その適用範囲を検討する場合とその規律内容を検討する場合とで、憲法上の租税概念の異なる側面にそれぞれ着目する必要があると考えられる。前者の場合には、租税債権の目的としての側面に着目すべきであるが、その租税概念から非対価性・無償性の要素を導き出すためには、憲法上の租税根拠論にまで立ち返って検討する必要があると考えるところである。
なお、本判決が示した憲法上の租税の意義は、実定税法上の租税の意義についても基本的に妥当するものと解されている(ガーンジー島法人所得税制事件最判平成21年12月3日民集63巻10号2283頁参照。この判決については、谷口教授と学ぶ「税法の基礎理論」【第9回】Ⅱ1参照)。
(了)
この連載の公開日程は、下記の連載目次をご覧ください。