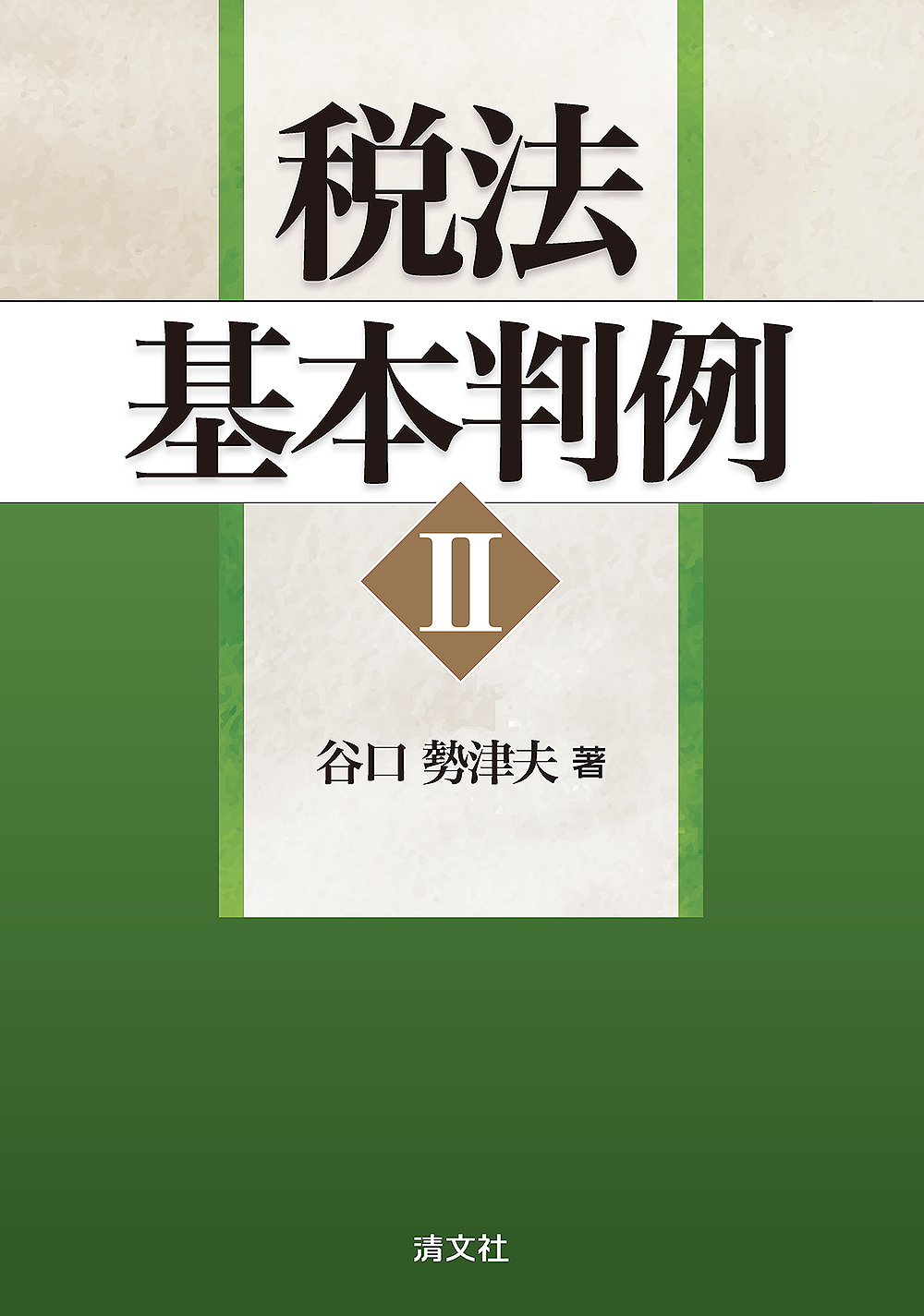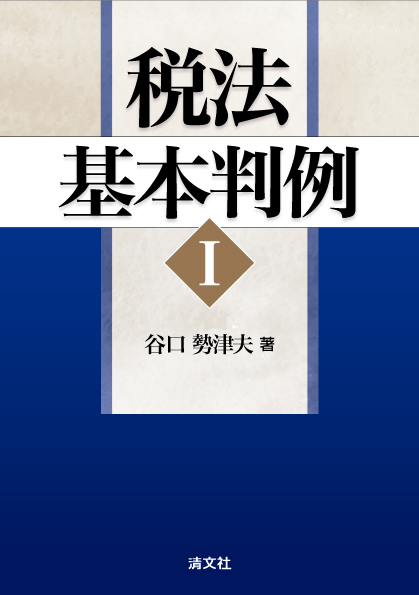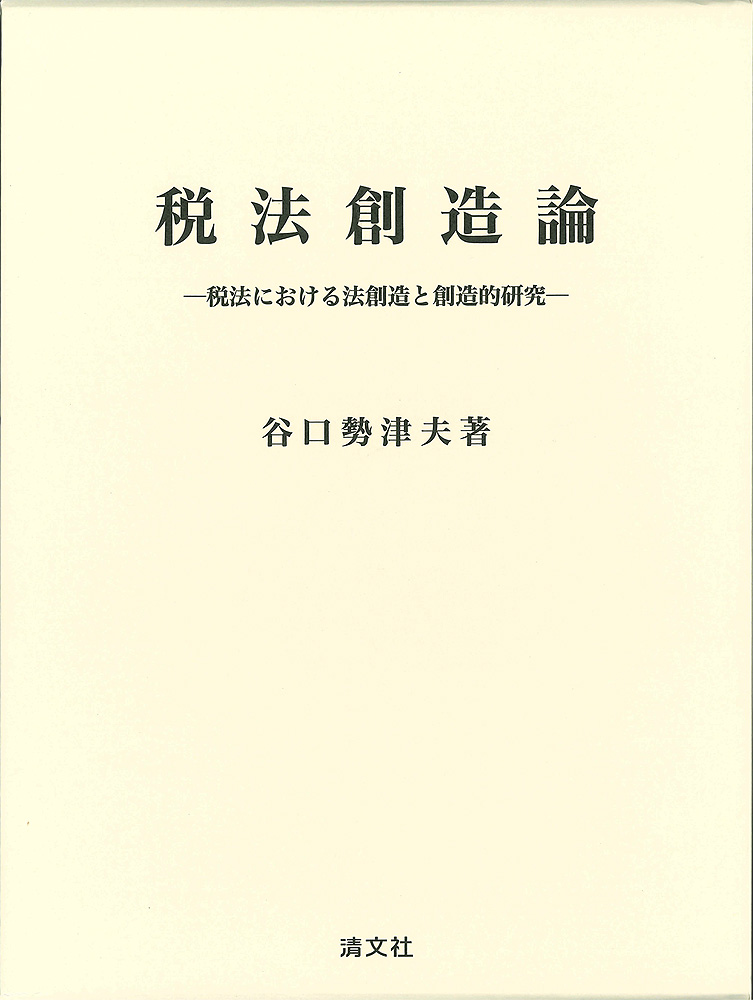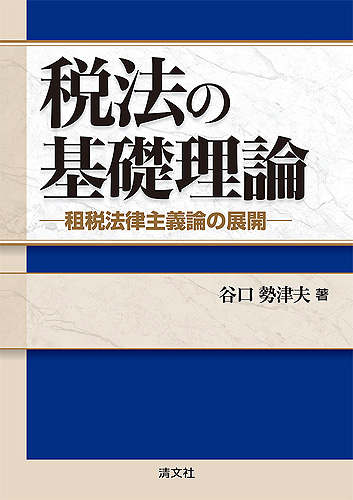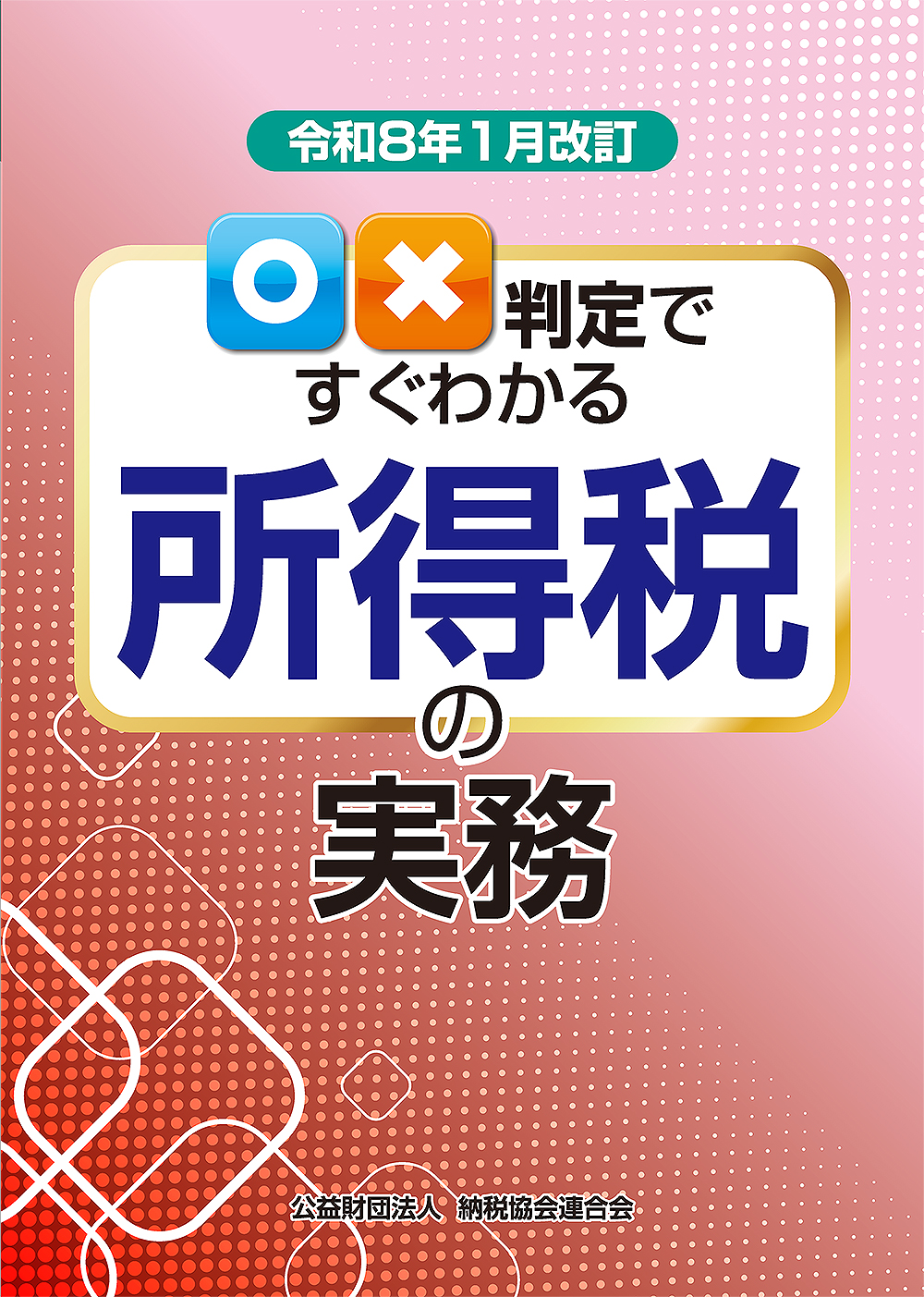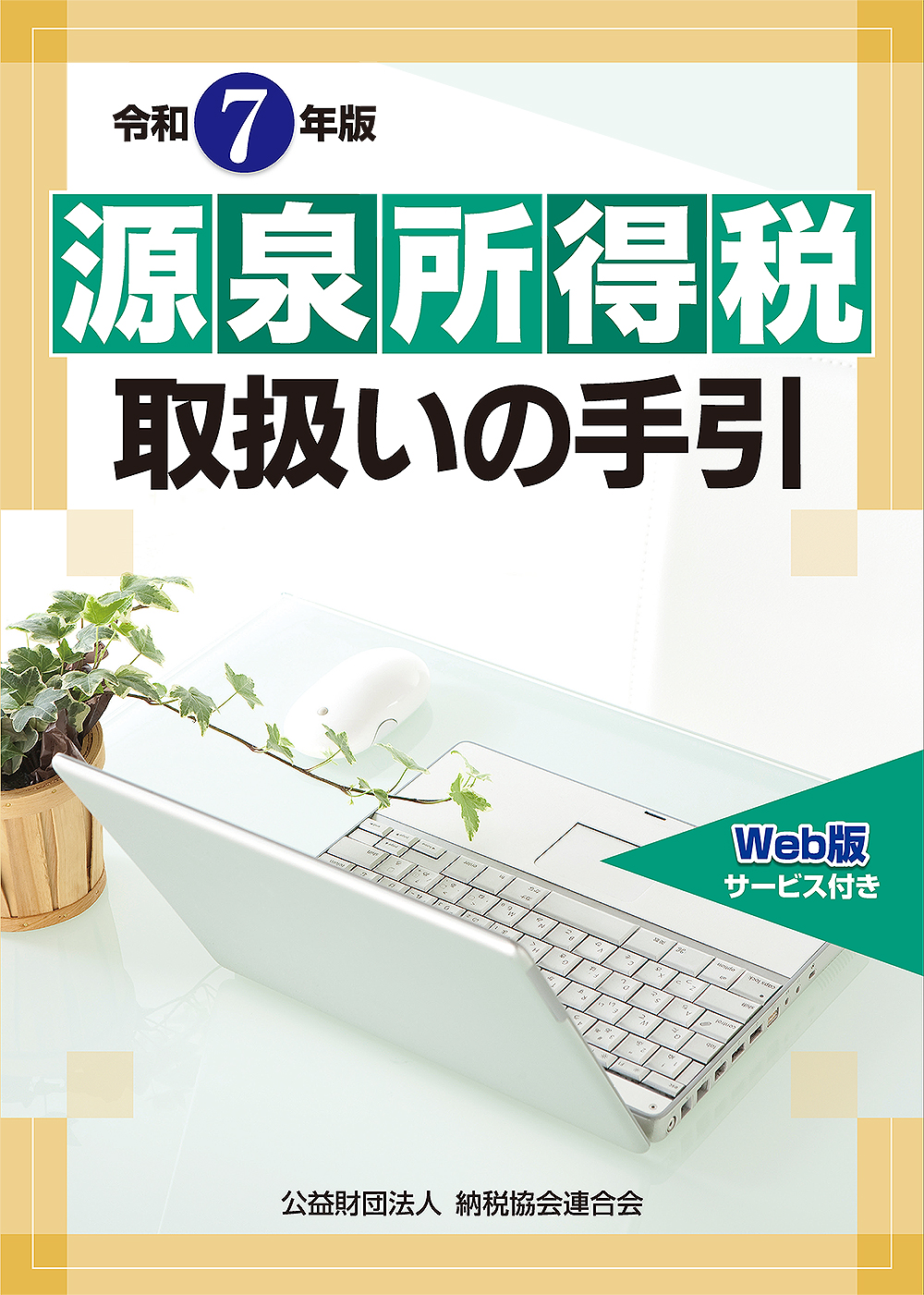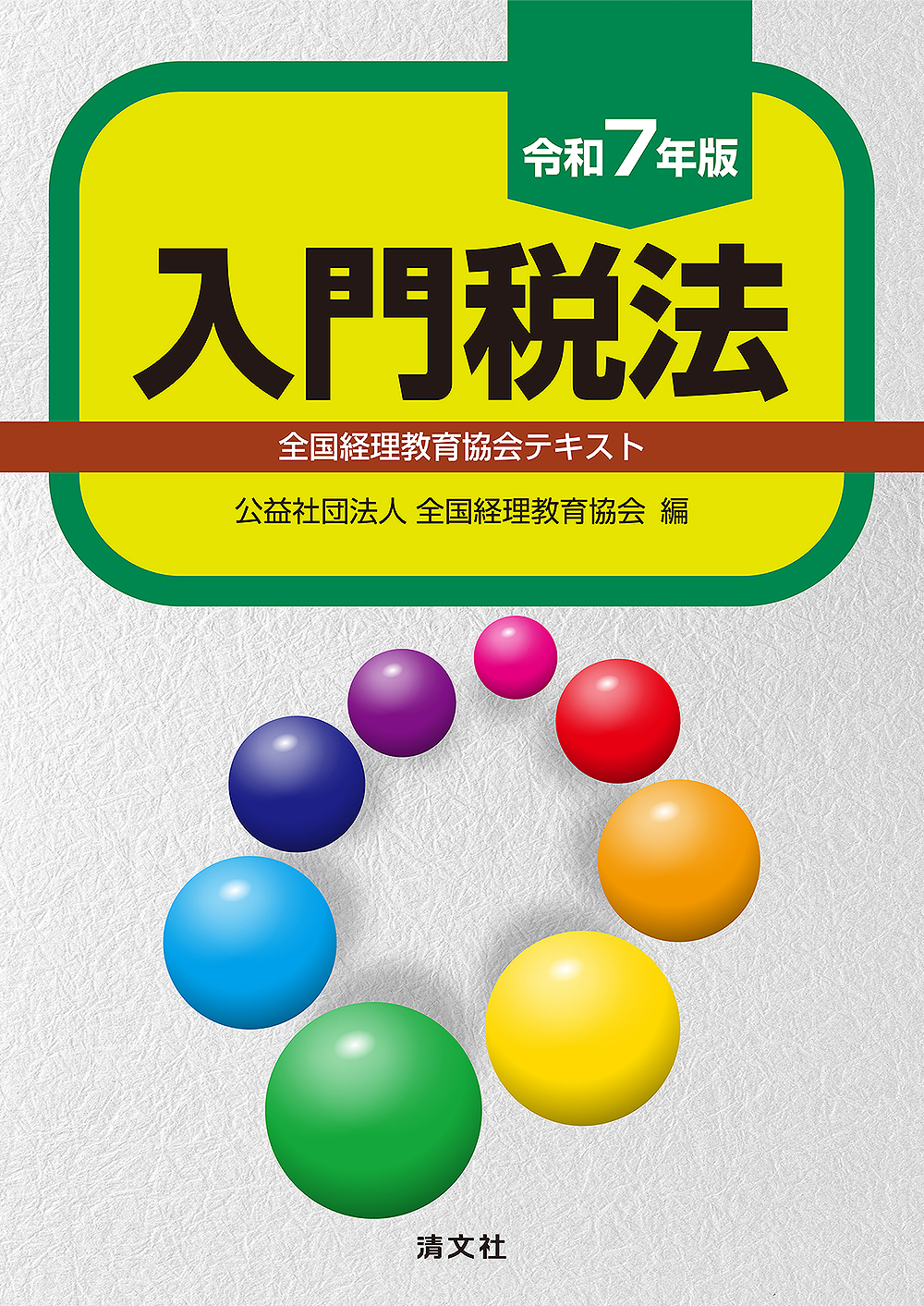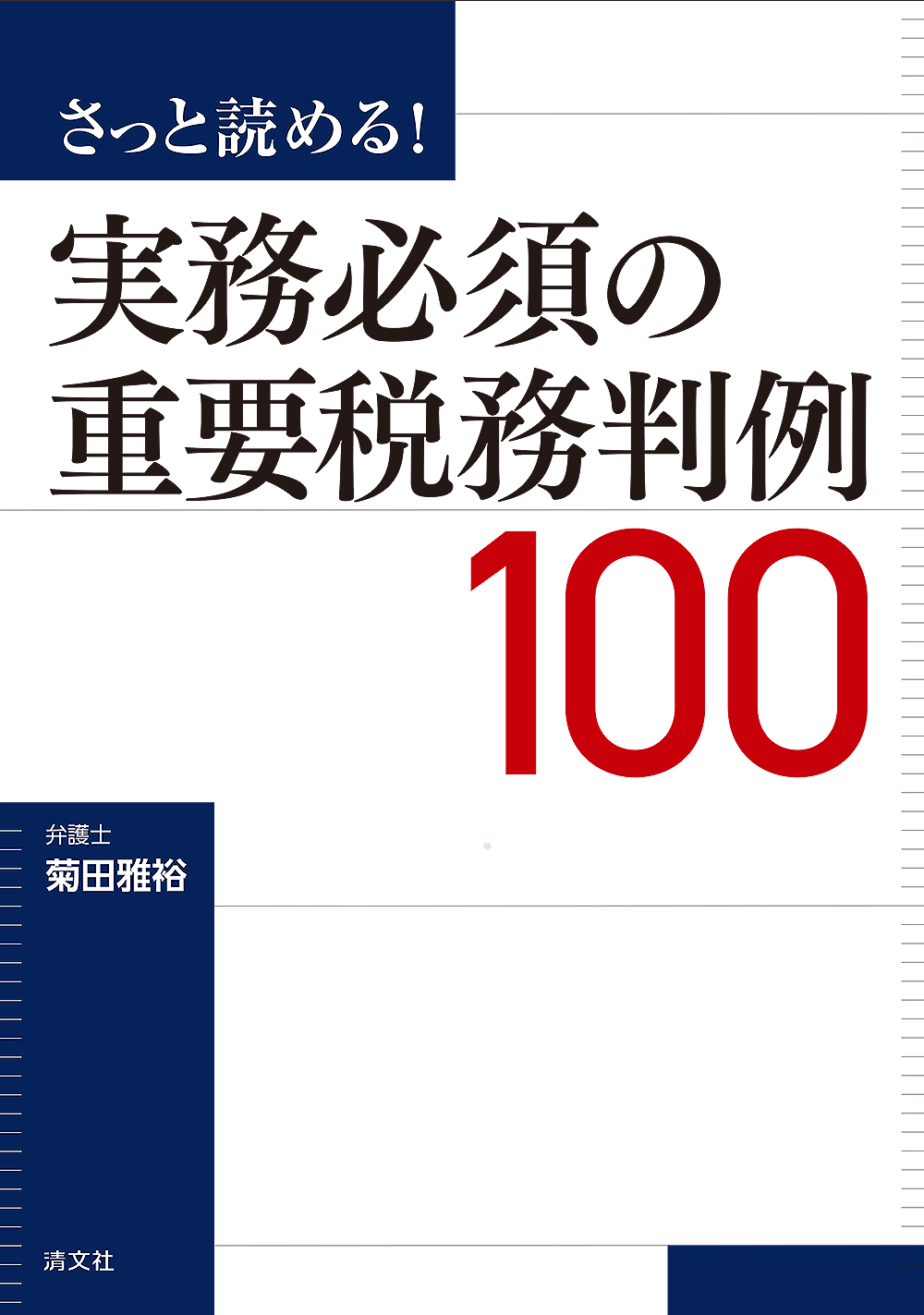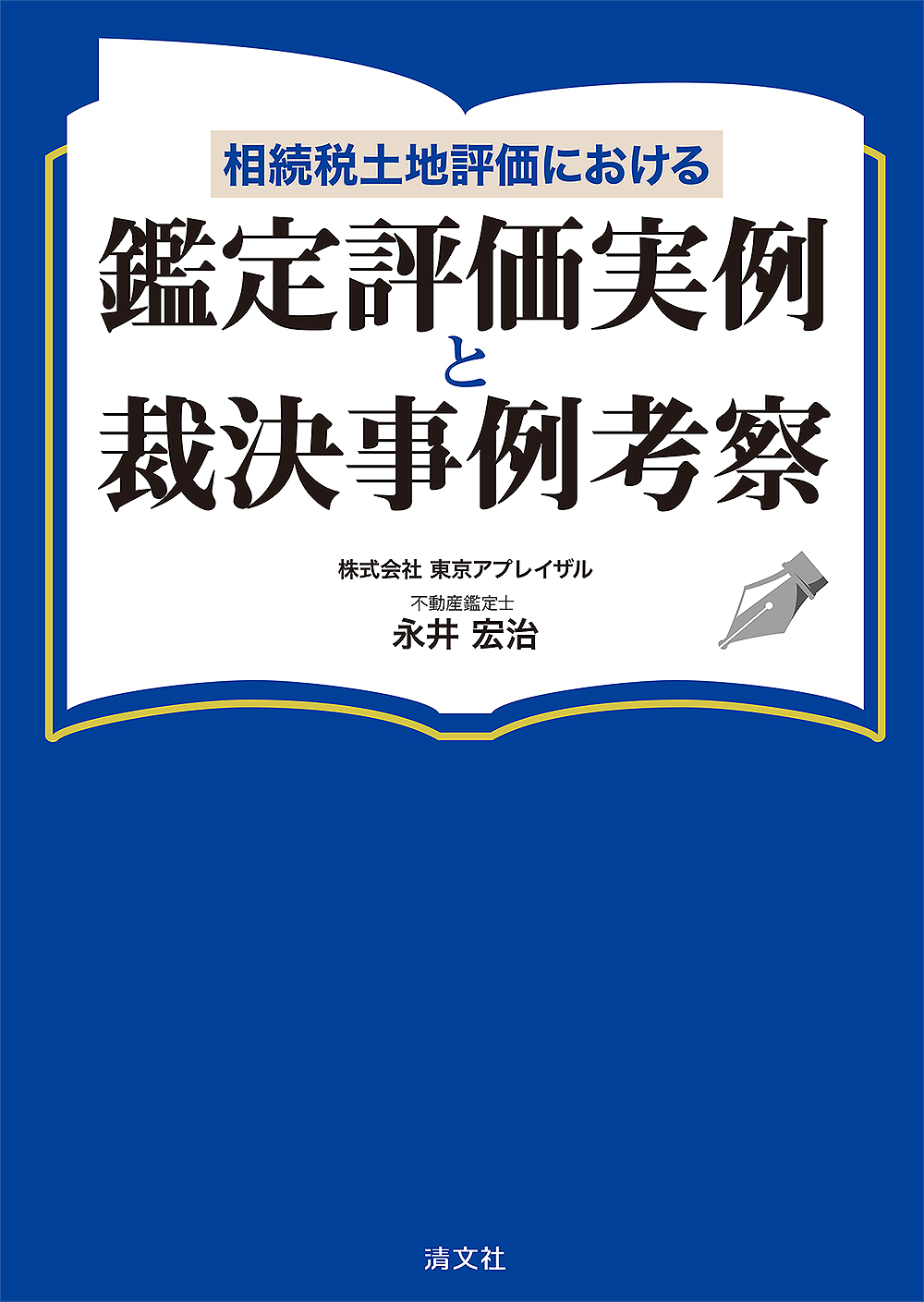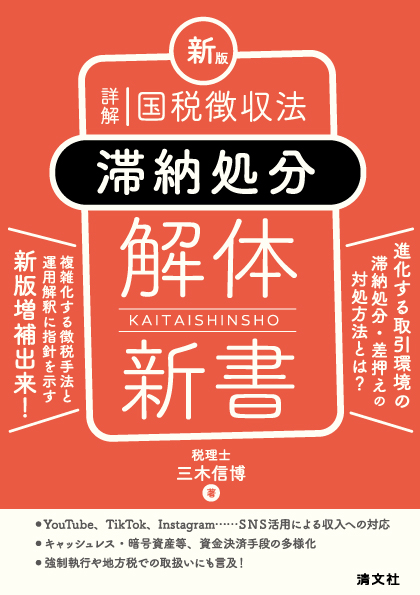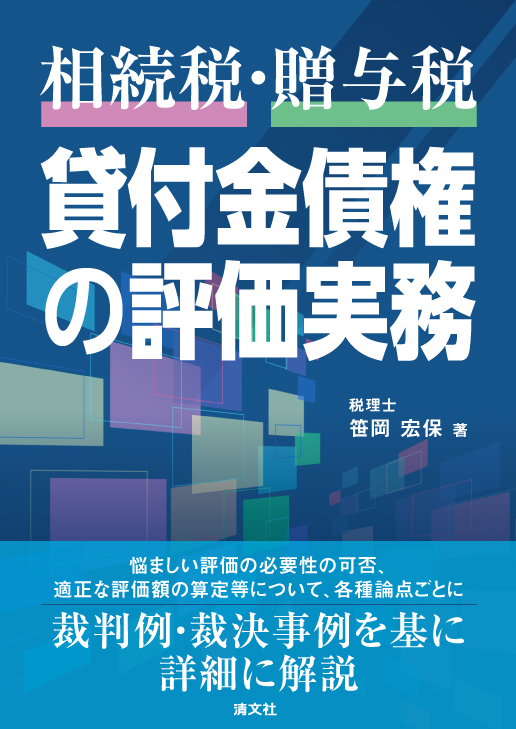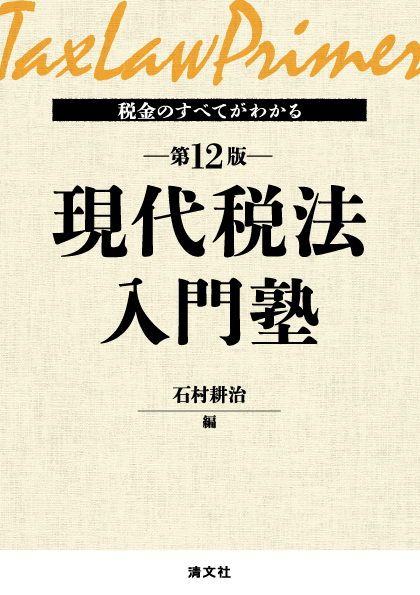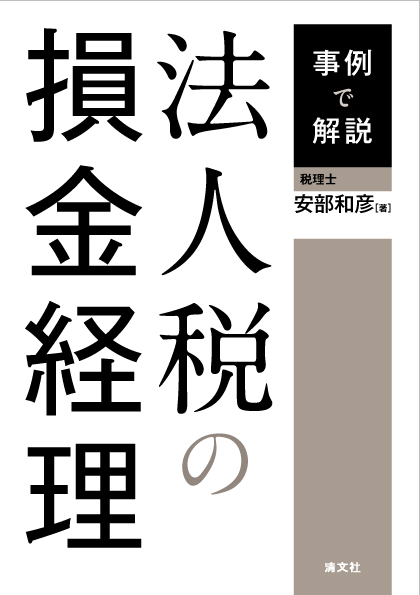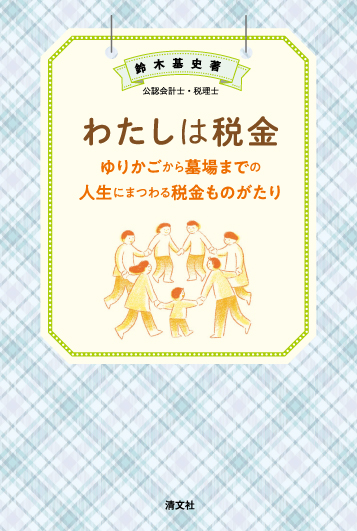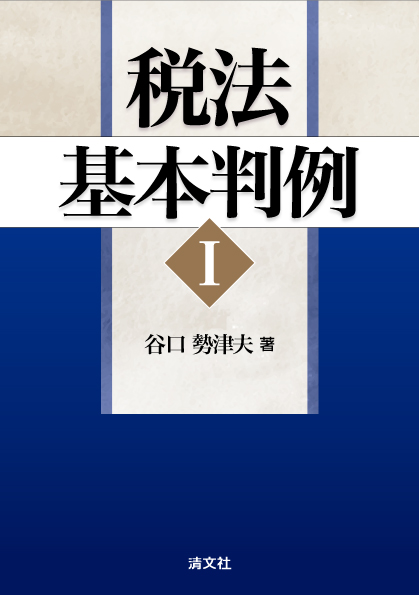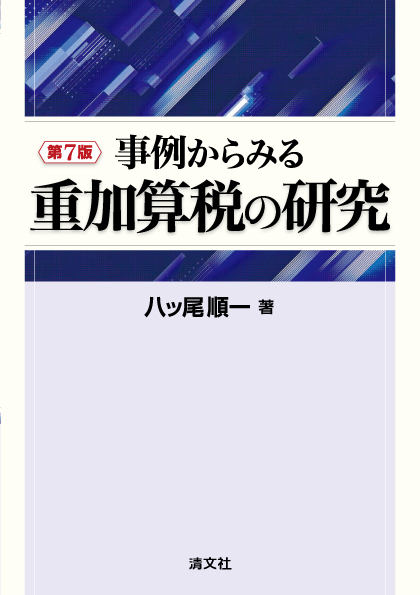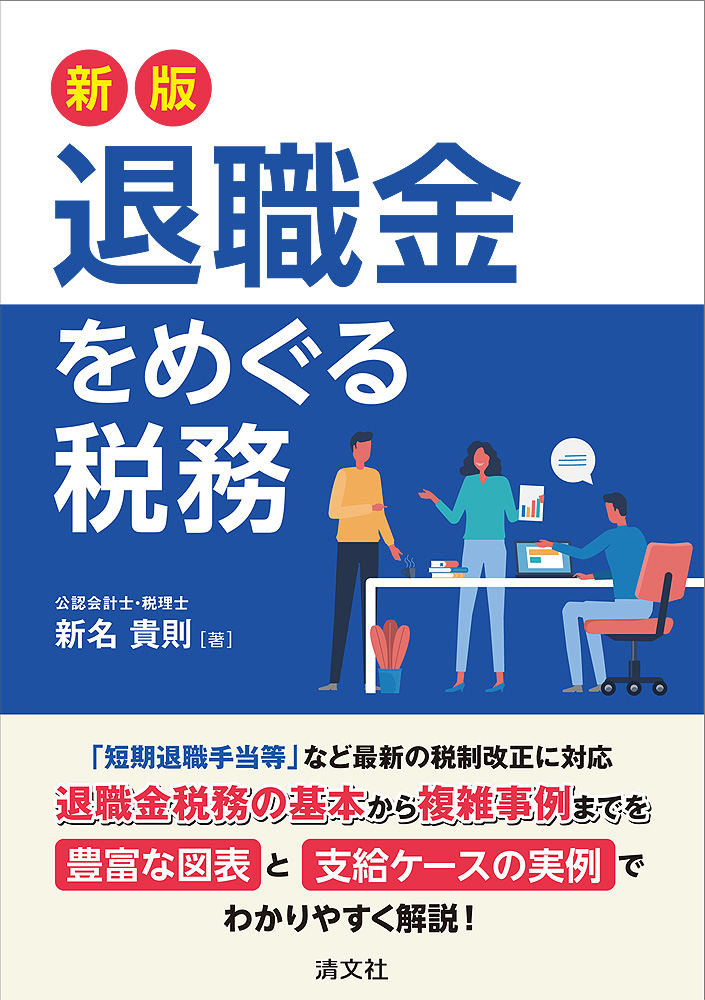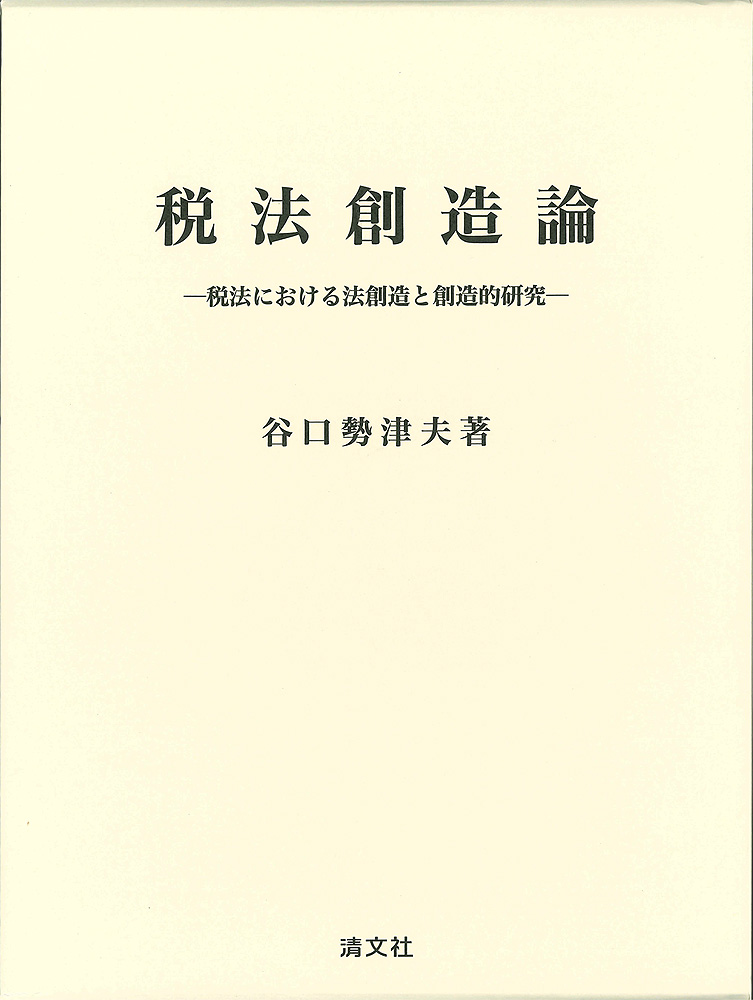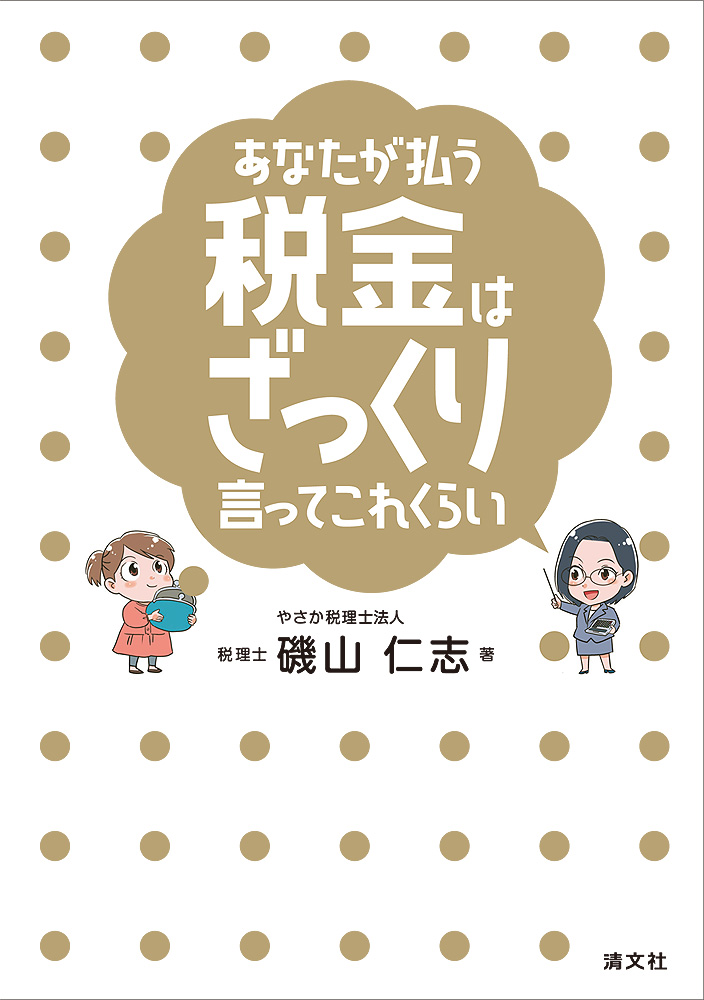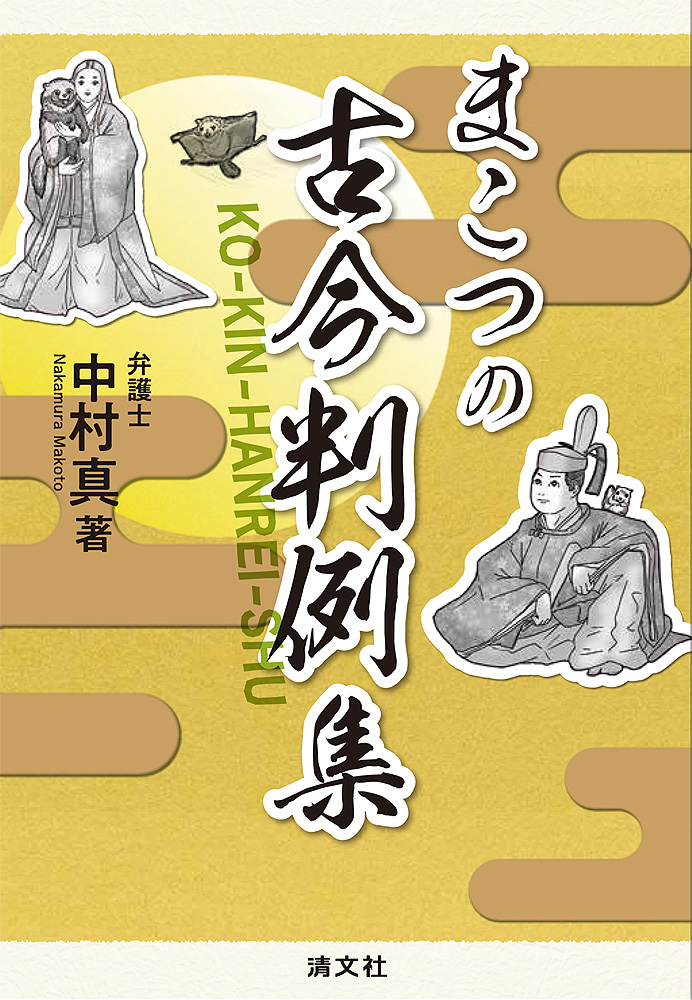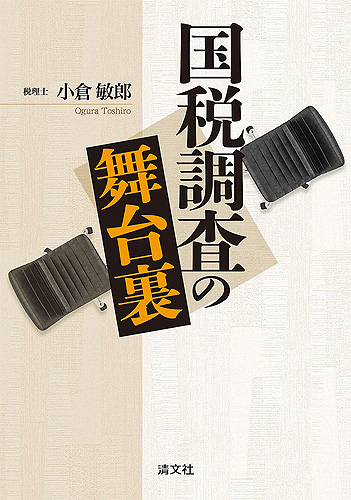谷口教授と学ぶ
税法基本判例
【第54回】
「定年延長と退職所得課税」
-10年退職金事件・最判昭和58年12月6日訟月30巻6号1065頁の今日的意義と「雇用継続税制」-
大阪学院大学法学部教授
谷口 勢津夫
Ⅰ はじめに
近時、退職所得課税の見直しが盛んに議論されるようになってきた。政府税制調査会では比較的早くから退職所得課税について「支給形態の多様化」、「雇用の流動化」、「課税の中立性」を主たる課題として検討がされてきたところである(油井雅志「退職金制度等における課税上の諸問題について―定年延長等における打切支給の取扱いを中心に―」税務大学校論叢110号(2023年)79頁、125頁以下参照。税制調査会「我が国税制の現状と課題―令和時代の構造変化と税制のあり方―」(令和5年6月)96頁も参照)。今回の原稿執筆中にも、「退職金課税の改正見送り」という見出しで「政府・与党は退職金課税の改正を2026年度は実施しない方針だ。政府で本格的な議論に上がって以降、見送りは3年連続となる。」旨が報じられた(日本経済新聞2025年11月15日朝刊5面)。
そのような議論状況の下、「近年における少子・高齢化の進展や公的年金等の支給開始年齢の段階的な引上げ等に伴い、高齢者雇用に関する就業機会の確保が求められることになり、企業において定年延長等の雇用制度の変更による労働環境の整備がなされている」(油井・前掲論文140頁)昨今、「定年延長等に伴い、退職手当を定年延長前の旧定年で支給する、いわゆる打切支給の退職金が支給されるケースも増えていると想定される」(同100-101頁)ところ、今回は、かつていわゆる短期定年制の下での打切支給退職金の退職所得該当性が争われた10年退職金事件に関する最判昭和58年12月6日訟月30巻6号1065頁(以下「本判決」という)の判断内容を検討し、その今日的意義に関連して若干の立法論的提言を述べることにする。
この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員登録およびログインが必要です。
すでに会員登録をされている方は、下記ボタンからログインのうえ、ご覧ください。
Profession Journalのすべての記事をご覧いただくには、「プレミアム会員(有料)」へのご登録が必要となります。
なお、『速報解説』については「一般会員(無料)」へのご登録でも、ご覧いただけます。
※他にもWebセミナー受け放題のスーパープレミアム会員などがございます。
会員登録がお済みでない方は、下記会員登録のボタンより、ご登録のお手続きをお願いいたします。