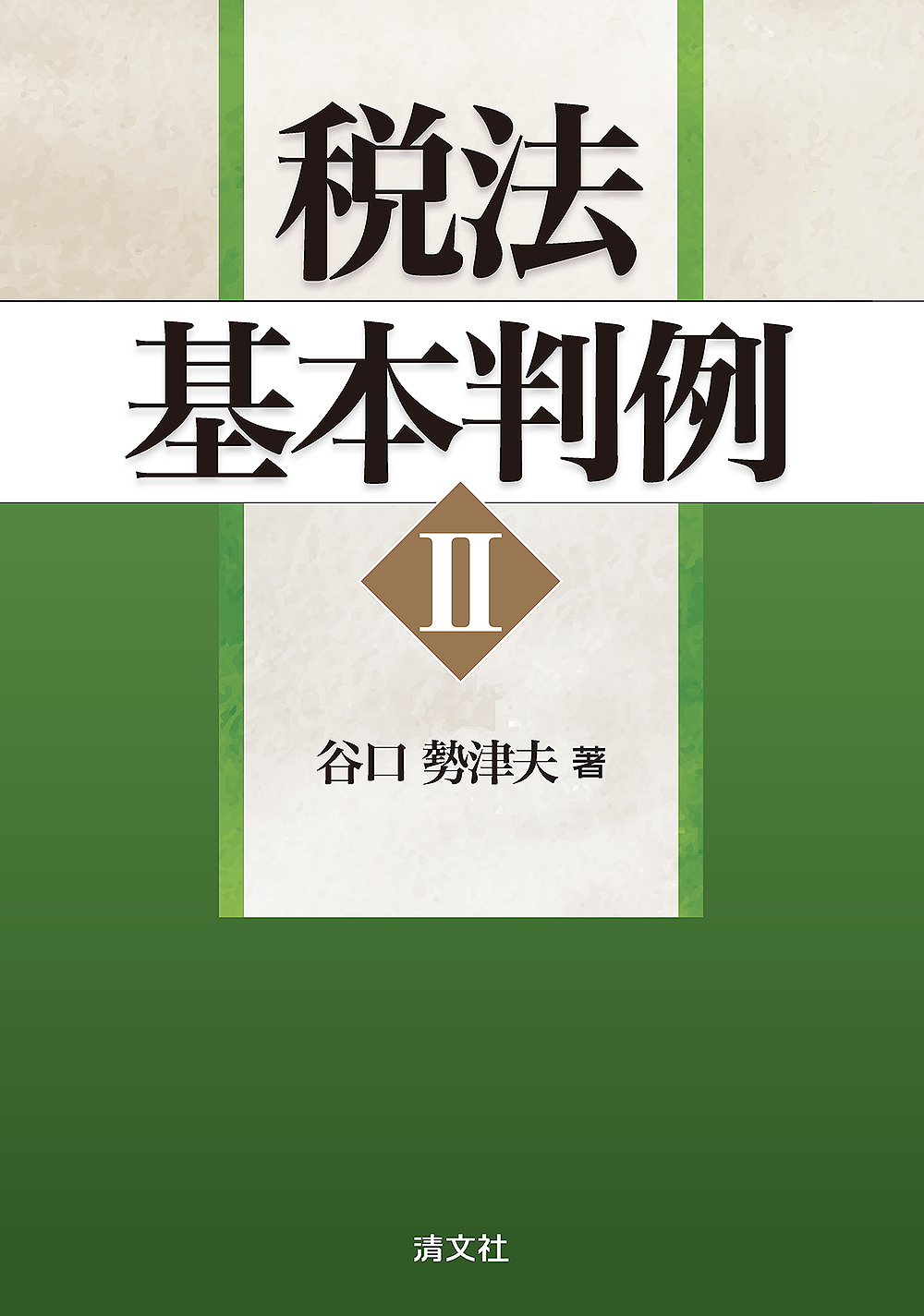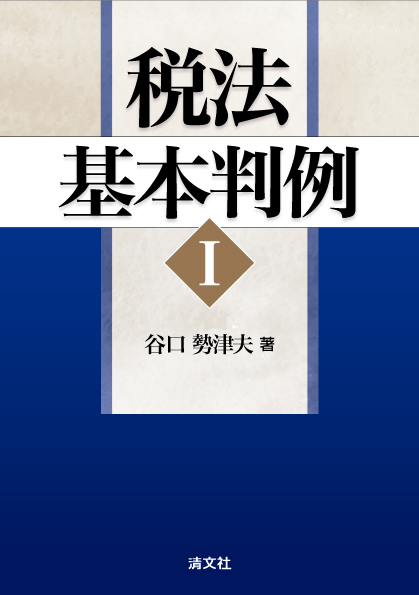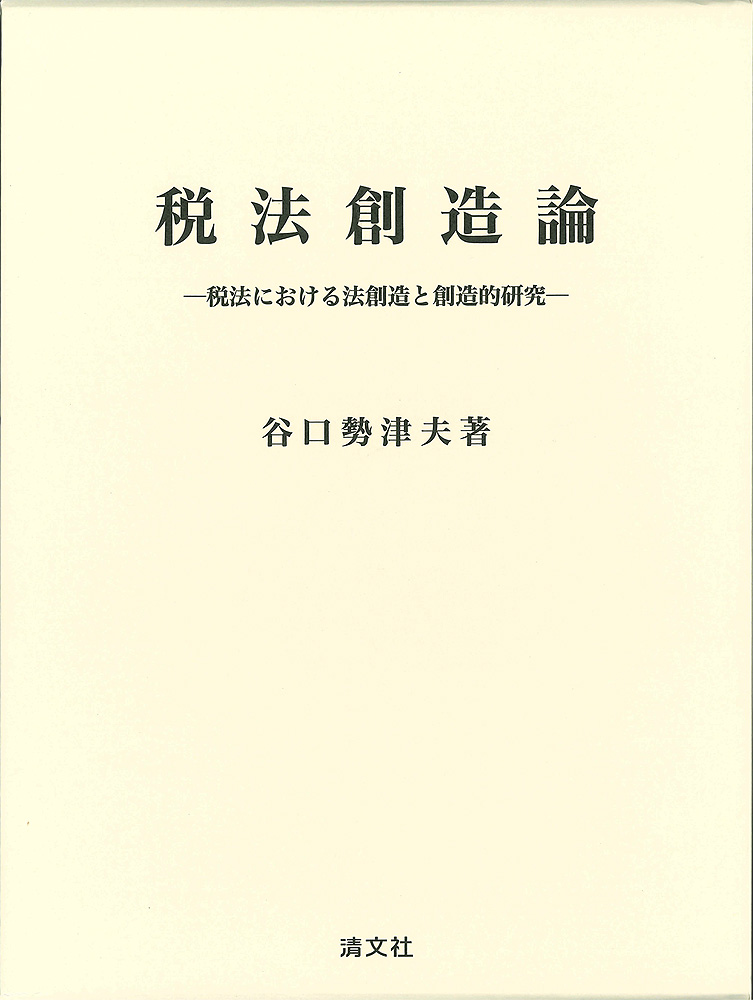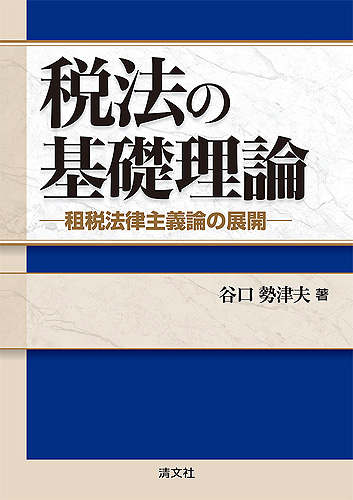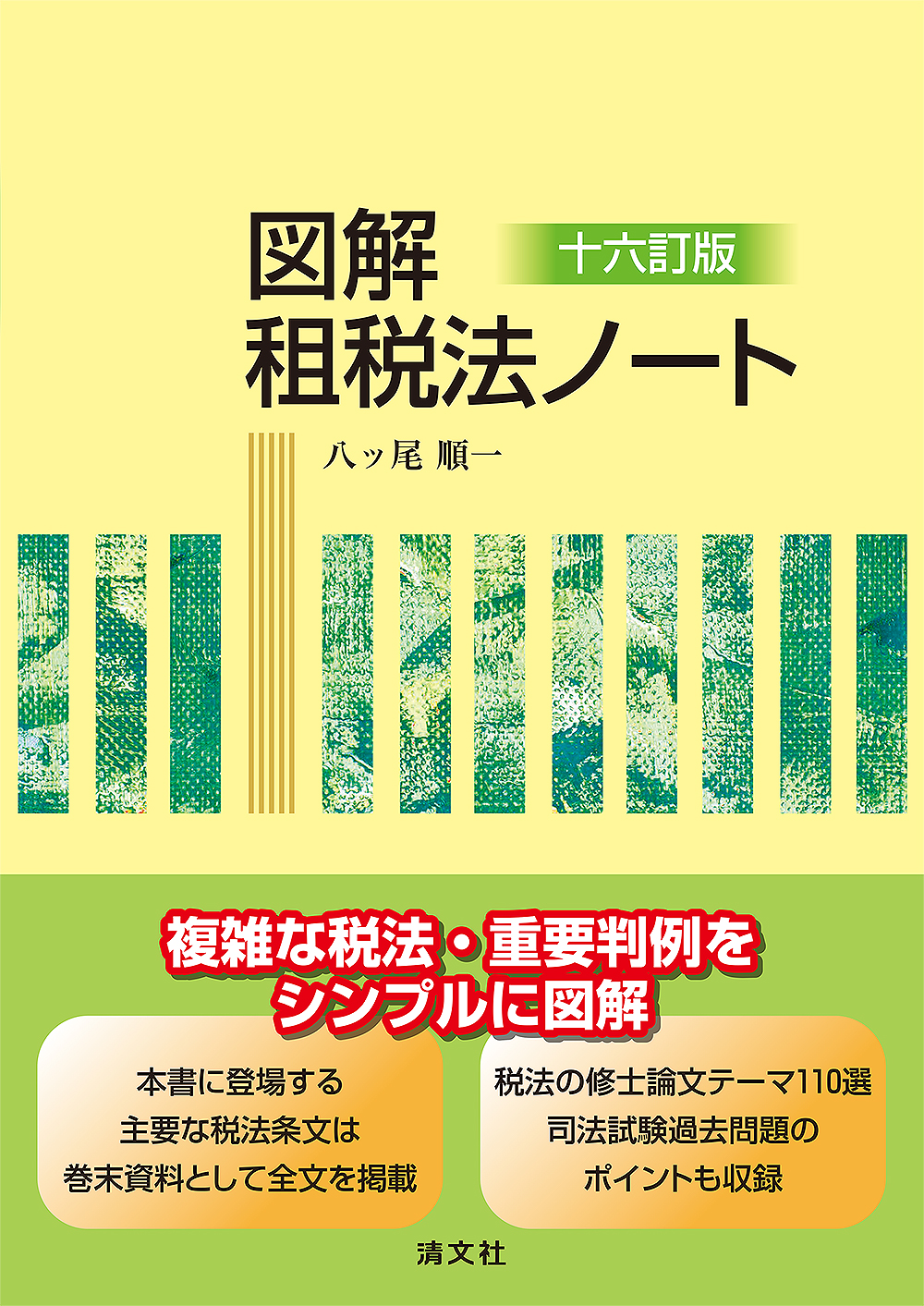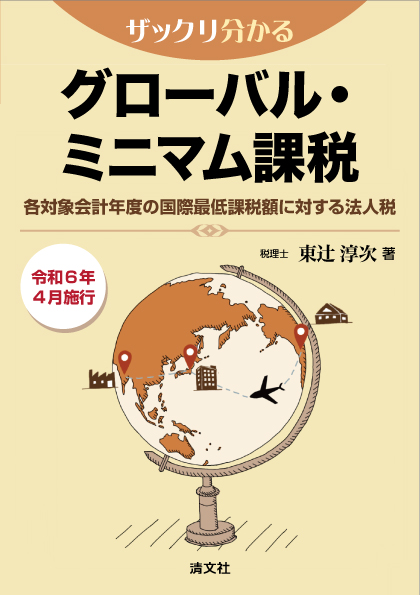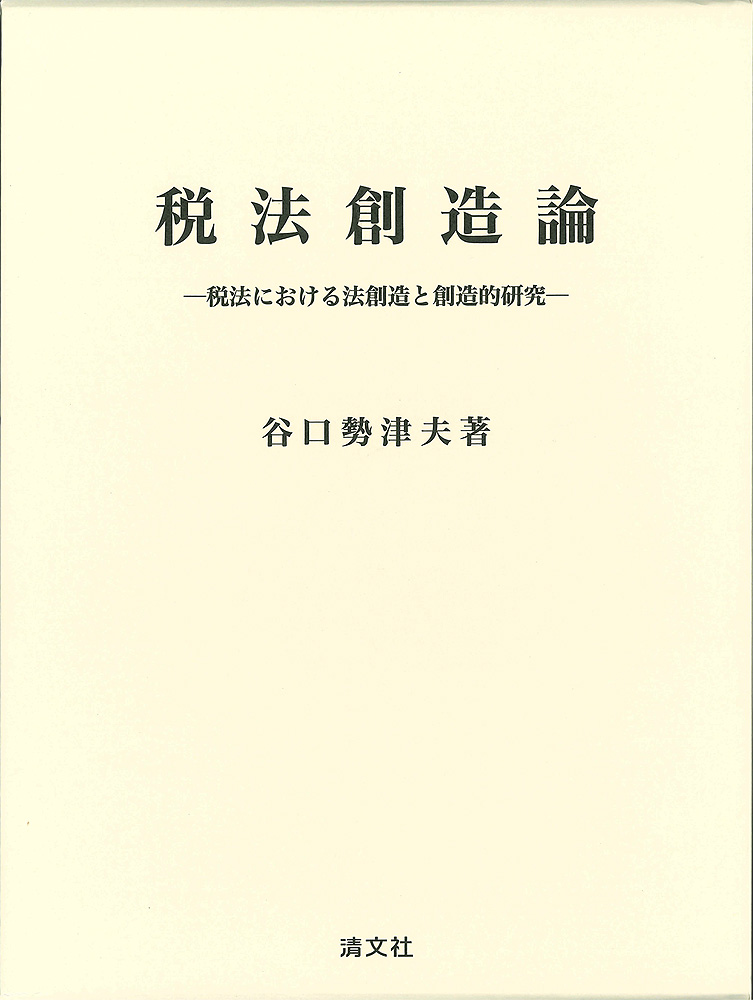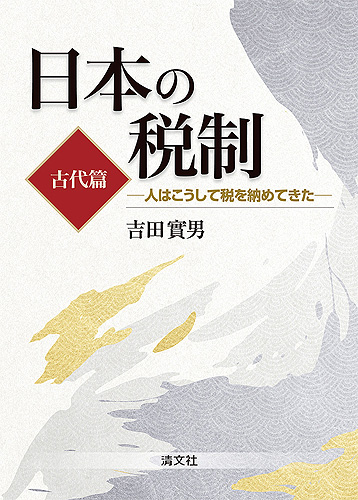谷口教授と学ぶ
税法基本判例
【第48回】
「所得税法56条の解釈適用に関する2つのアプローチ」
-所得税法56条弁護士「夫」税理士「妻」事件に係る各審級裁判所の判断の比較検討-
大阪学院大学法学部教授
谷口 勢津夫
Ⅰ はじめに
今回は、所得税法56条弁護士「夫」税理士「妻」事件を取り上げ、所得税法56条の解釈適用について、同事件の第一審・東京地判平成15年7月16日判時1891号44頁(以下「平成15年東京地判」という。なお、同判決は「国破山河在」(杜甫)に擬えて「国敗れて[東京地裁民事]三部あり」といわれた藤山判決(藤山雅行裁判官)の1つである)と、控訴審・東京高判平成16年6月9日判時1891号18頁(以下「平成16年東京高判」という)及びこれを是認した上告審・最判平成17年7月5日税資255号順号10070(以下「平成17年最判」という)とを比較検討することにする。平成17年最判は、所得税法56条の解釈適用については所得税法56条弁護士「夫婦」事件・最判平成16年11月2日訟月51巻10号2615頁(以下「別件平成16年最判」という)を参照しているので、この判決も上記の比較検討において考察の対象とすることにする。
上記の2つの事件で争点となったのは、所得税法56条が「居住者と生計を一にする配偶者その他の親族」として定める要件(以下「家族同一生計要件」という)と、「その居住者の営む不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業に従事したことその他の事由により当該事業から対価の支払を受ける場合」として定める要件(以下「家族事業稼得要件」という)という2つの要件の解釈適用である。
これらの要件は所得税の課税単位とも関連する内容をもつので、前記各判決の比較検討に入る前に、ここで、課税単位に関して家族同一生計要件と家族事業稼得要件の位置づけを行っておくことにする。
この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員登録およびログインが必要です。
すでに会員登録をされている方は、下記ボタンからログインのうえ、ご覧ください。
Profession Journalのすべての記事をご覧いただくには、「プレミアム会員(有料)」へのご登録が必要となります。
なお、『速報解説』については「一般会員(無料)」へのご登録でも、ご覧いただけます。
※他にもWebセミナー受け放題のスーパープレミアム会員などがございます。
会員登録がお済みでない方は、下記会員登録のボタンより、ご登録のお手続きをお願いいたします。