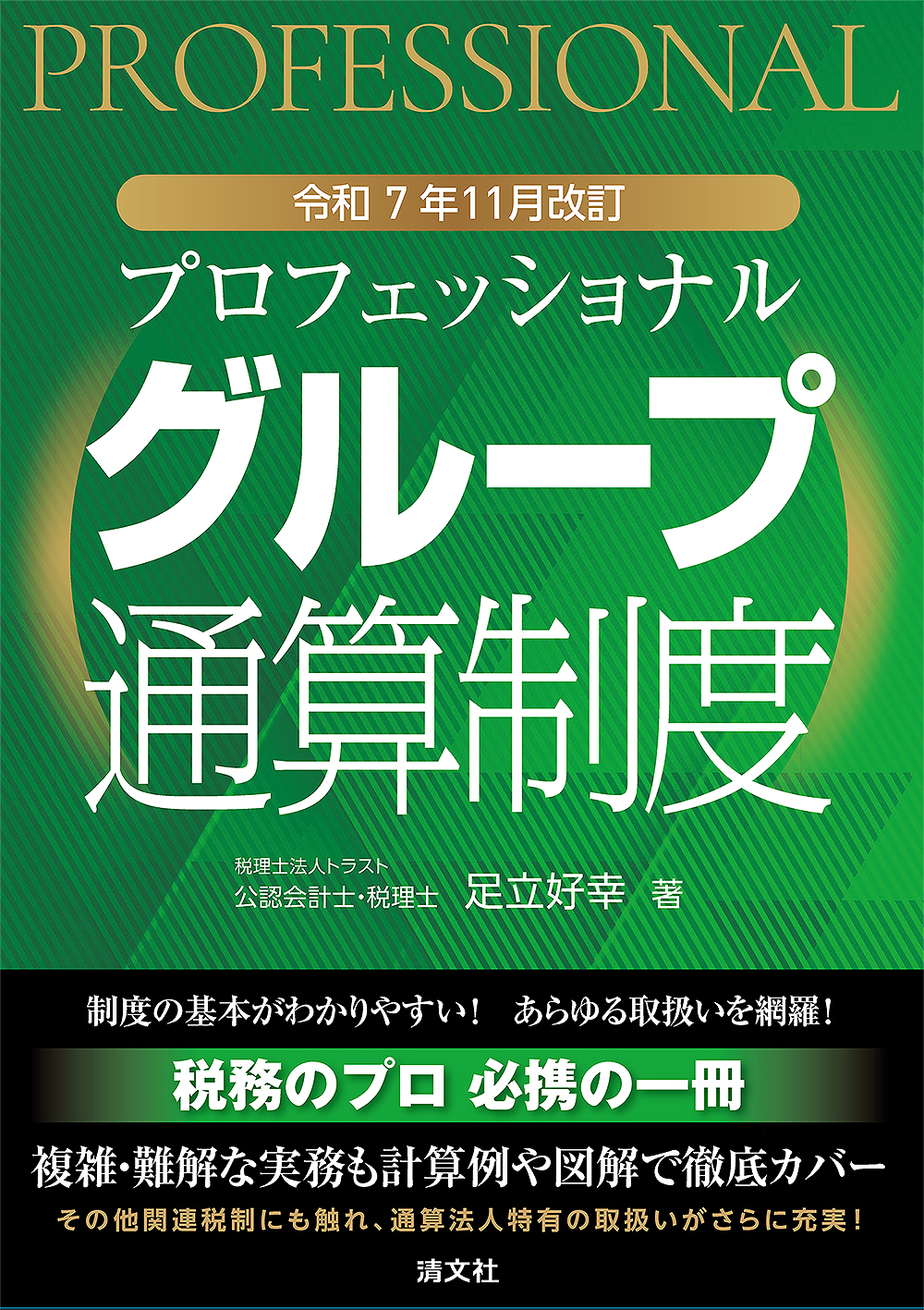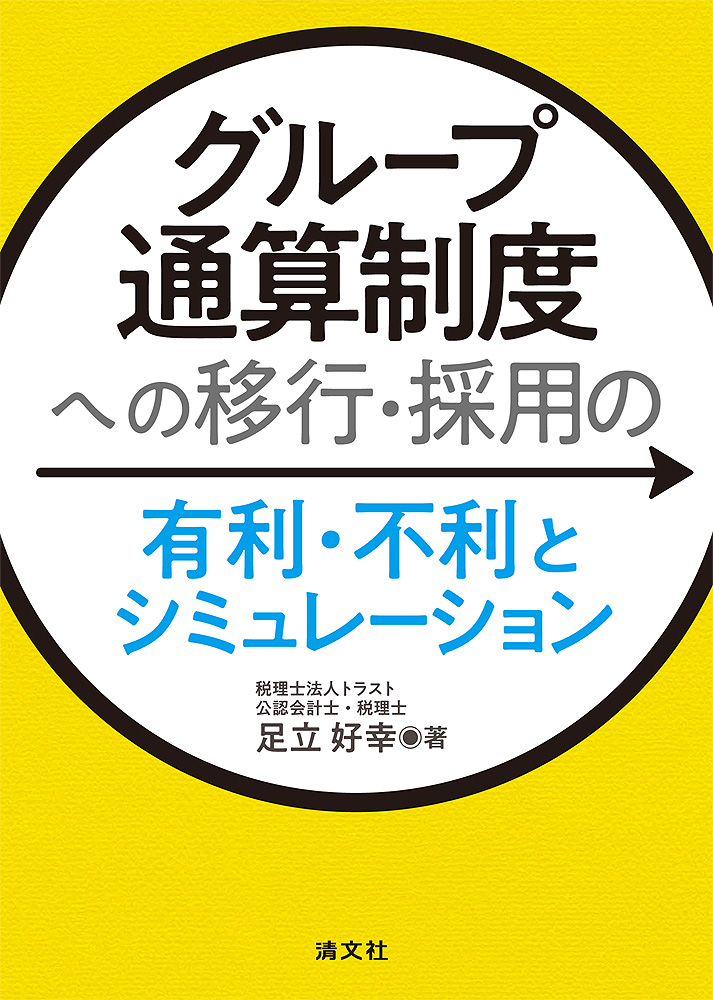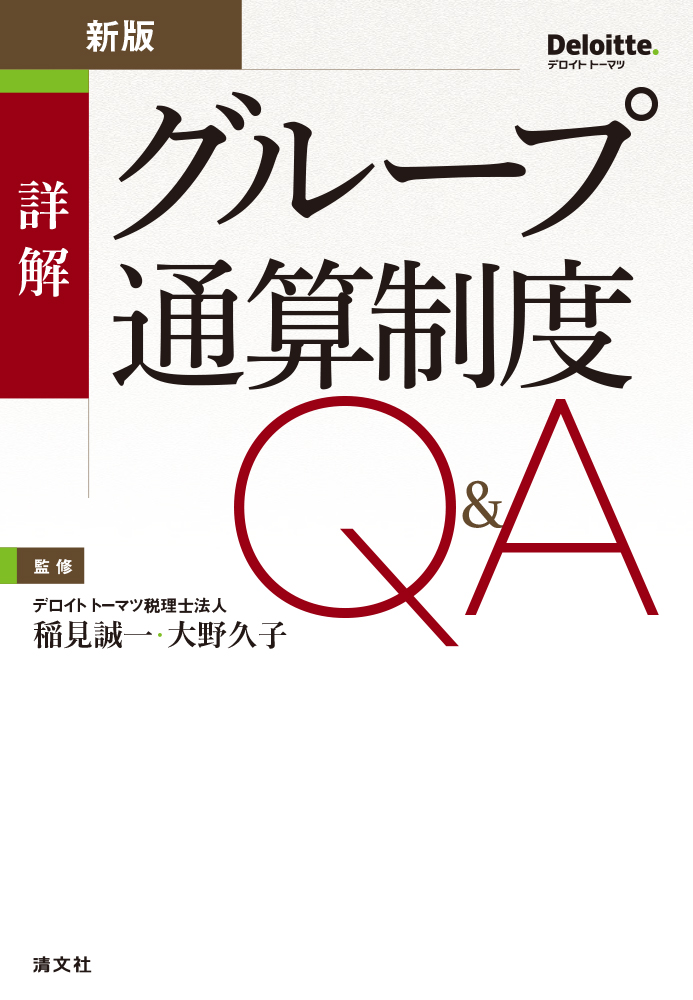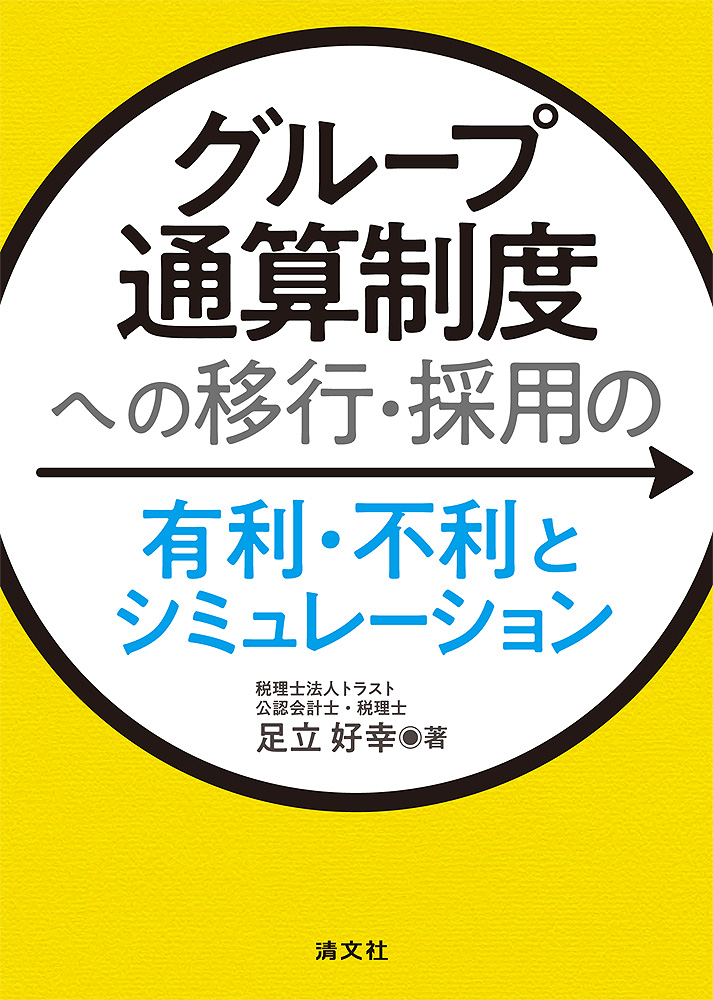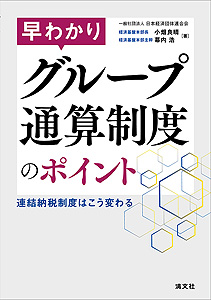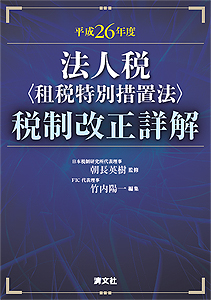《速報解説》
国税庁、令和4年度改正に係る「法人税基本通達等の一部改正について」等を公表
~通算制度への移行に対応し、グループ通算通達は法人税基本通達等へ移管~
公認会計士・税理士
税理士法人トラスト
足立 好幸
令和4年6月29日に国税庁から令和4年度税制改正に係る「法人税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)」が公表された。また、グループ通算制度への移行に対応するため「「法人の青色申告の承認の取消しについて」の一部改正について(事務運営指針)」等も公表された。
Ⅰ 法人税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)
1 グループ通算制度の見直し
(1) グループ通算制度に関する取扱通達(グループ通算通達)の基本通達等への移管
グループ通算制度の施行に伴い「グループ通算制度に関する取扱通達の制定について」(法令解釈通達、以下「グループ通算通達」という)に定める各通達を、法人税基本通達、租税特別措置法関係通達(法人税編)等に移管し、グループ通算通達が廃止されている。
(2) グループ通算制度の投資簿価修正の加算措置
〇 資産調整勘定対応金額等の計算が困難な場合の取扱い(法通2-3-21の4[新設])
その取得後におけるその対象株式の保有割合が低い又はその取得の時期が古いなどの理由により、その取得の時における資産調整勘定対応金額等の計算が困難であると認められる場合において、その取得の時において計算される資産調整勘定対応金額等を0とし、その後に追加取得した対象株式について各追加取得の時における資産調整勘定対応金額等を計算し、その計算の基礎となる事項を記載した書類を保存しているときは、課税上弊害がない限り、加算措置の適用を受けることができることを明らかにしている。
この場合、負債調整勘定対応金額が計算されることが見込まれる場合は、課税上弊害があるため、この取扱いの適用がないことも明らかにしている。
〇 資産調整勘定対応金額等の計算における負債調整勘定の金額の取扱い(法通2-3-21の6[新設])
資産調整勘定対応金額等の金額の計算上、時価純資産価額の計算の基礎となる負債の額には、退職給与債務引受額及び短期重要債務見込額の金額を含まないことを明らかにしている。
〇 資産調整勘定対応金額等の計算の基礎となる資産及び負債(法通2-3-21の7[新設])
時価純資産価額の金額の計算上、対象株式を取得した時の直前の月次決算期間又は会計期間の終了の日に当該他の通算法人が有する資産及び負債の同日における価額を基礎として計算している場合には、課税上弊害がない限り、その計算が認められることを明らかにしている。
〇 資産調整勘定対応金額等の計算の基礎となる対象株式の取得価額(法通2-3-21の8[新設])
資産調整勘定対応金額等の計算の基礎となる対象株式の取得価額は、付随費用を含めて計算し、この場合において、その対象株式の取得の時期が古いなどの理由により、付随費用の把握が困難なときには、その購入の代価をその対象株式の取得価額として資産調整勘定対応金額等を計算することができることを明らかにしている。
(3) 通算法人が1項括弧書適用除外法人又は2項適用除外法人であるかどうかの判定の時期(措通61の4(2)-8[新設])
通算グループ内のいずれかの通算法人の資本金の額又は出資金の額が100億円を超えるかどうかの判定(接待飲食費の50%の損金算入の可否判定=1項括弧書適用除外法人の判定)は、他の通算法人(その通算法人の適用年度終了の日においてその通算法人との間に通算完全支配関係がある法人に限る)の同日の現況によるのであるが、通算親法人の事業年度の中途において通算承認の効力を失った通算法人のその効力を失った日の前日に終了する事業年度の1項括弧書適用除外法人の判定についても、同様であることが明らかにされている。この取扱いは、通算グループ内の通算法人のすべてが中小法人に該当するかどうかの判定(定額控除限度額の適用可否の判定=2項適用除外法人の判定)についても、同様とすることが明らかにされている。
2 子会社株式簿価減額特例の見直し
〇 対象期間内に利益剰余金の額が増加した場合のその増加額を証する書類(法通2-3-22の6[新設])
他の法人の対象配当等の額を受ける直前の当該他の法人の利益剰余金の額から当該他の法人のその対象配当等の額に係る決議日等前に最後に終了した事業年度の貸借対照表に計上されている利益剰余金の額を減算した金額を証する書類とは、他の法人の決議日等前に最後に終了した事業年度終了の日現在の利益剰余金の額及び対象配当等の額を受ける直前の時の利益剰余金の額がそれぞれ明らかとなる書類をいうので、当該他の法人のその最後に終了した事業年度の貸借対照表の写しのほか、例えば、当該他の法人の対象期間における利益の額を計算した書類の写しが、これに該当することを明らかにしています。
3 少額の減価償却資産の取得価額の損金算入制度等の見直し
〇 一時的に貸付けの用に供した減価償却資産(法通7-1-11の2、措通67の5-2の2[新設])
各制度の適用上、法人が減価償却資産を貸付けの用に供したかどうかはその減価償却資産の使用目的、使用状況等を総合勘案して判定されるものであるので、例えば、一時的に貸付けの用に供したような場合において、その貸付けの用に供した事実のみをもって、その減価償却資産が貸付けの用に供したものに該当するとはいえないことを明らかにしている。
〇 主要な事業として行われる貸付けの例示(法通7-1-11の3、措通67の5-2の3[新設])
それぞれ次に定めるような行為は、その主要な事業として行われる貸付け(一括損金算入が制限されない貸付け)に該当することを例示的に明らかにしている。
① 企業グループ内の各法人の営む事業の管理運営を行っている中小企業者等がその各法人で事業の用に供する減価償却資産の調達を一括して行い、その企業グループ内の他の法人に対してその調達した減価償却資産を貸し付ける行為
② 中小企業者等が自己の下請業者に対して、その下請業者の専らその中小企業者等のためにする製品の加工等の用に供される減価償却資産を貸し付ける行為
③ 小売業を営む中小企業者等がその小売店の駐車場の遊休スペースを活用して自転車その他の減価償却資産を貸し付ける行為
④ 不動産貸付業を営む中小企業者等がその貸し付ける建物の賃借人に対して、家具、電気機器その他の減価償却資産を貸し付ける行為
4 所得拡大促進税制の見直し
〇 常時使用する従業員の範囲(措通42の12の5-1[新設])
ステークホルダー要件が課される資本金の額が10億円以上、かつ、常時使用する従業員の数が1,000人以上である場合において、常時使用する従業員の数は、常用であると日々雇い入れるものであるとを問わず、事務所又は事業所に常時就労している職員、工員等(役員を除く)の総数によって判定することを明らかにしている。この場合において、法人が繁忙期に数ヶ月程度の期間その労務に従事する者を使用するときは、その従事する者の数を「常時使用する従業員の数」に含めることを明らかにしている。
Ⅱ 「法人の青色申告の承認の取消しについて」の一部改正について(事務運営指針)
通算法人の青色申告の承認の取消しについても、グループ通算制度を適用していない場合と同様の取扱基準によることが明らかにされている(7 通算法人等に係る取扱いの適用)。
Ⅲ 「国税通則法第7章の2(国税の調査)等関係通達の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)
通算法人では個別申告を行い、各法人が納税義務者となるため、グループ通算制度を適用していない法人と同様の税務調査手続となることから、連結親法人を納税義務者とする連結納税制度の税務調査手続に係る取扱いが削除されるとともに、連結法人の令和4年4月1日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する税務調査手続については、改正前の取扱いが適用されることが明らかにされている(第6章 経過措置に関する事項10-5)。
Ⅳ 「法人税の重加算税の取扱いについて」等の一部改正について(事務運営指針)
1 法人税の重加算税の取扱いについて
国税通則法第68条第1項又は第2項に規定する「国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し」に該当する不正事実は、その通算法人の行為に係る不正事実をいい、他の通算法人の行為に係る不正事実はこれに該当しないことが明らかにされている(第4 通算法人等に係る取扱いの適用)。
また、「不正事実に基づく所得金額」(重加対象所得)は、その通算法人の行為に係る不正事実に基づく所得金額をいうことが明らかにされている(第4 通算法人等に係る取扱いの適用)。
2 法人税の過少申告加算税及び無申告加算税の取扱いについて
「通算規定に係る金額の計算の基礎とされた他の通算法人の有する金額等が異動したことに伴い、その通算法人に国税通則法第35条第2項の規定により納付すべき税額が生じたこと」は、他の通算法人及びその通算法人のいずれについてもその責めに帰すべき事由のない場合を除いて、国税通則法第65条第4項第1号に規定する正当な理由があると認められる事実に該当しないことが明らかにされている(第4 通算法人等に係る取扱いの適用)。
また、他の通算法人の通算適用事業年度(通算規定を適用した事業年度)に係る調査により、当該他の通算法人に対して、通算規定に係る金額の計算の基礎とされた当該他の通算法人の有する金額等に関する非違事項の指摘等があったことは、原則として、その通算法人の国税通則法第65条第1項又は第5項に規定する「更正があるべきことを予知してされたもの」に該当しないことが明らかにされている。
〔凡例〕
法通・・・法人税基本通達
措通・・・租税特別措置法関係通達
(了)