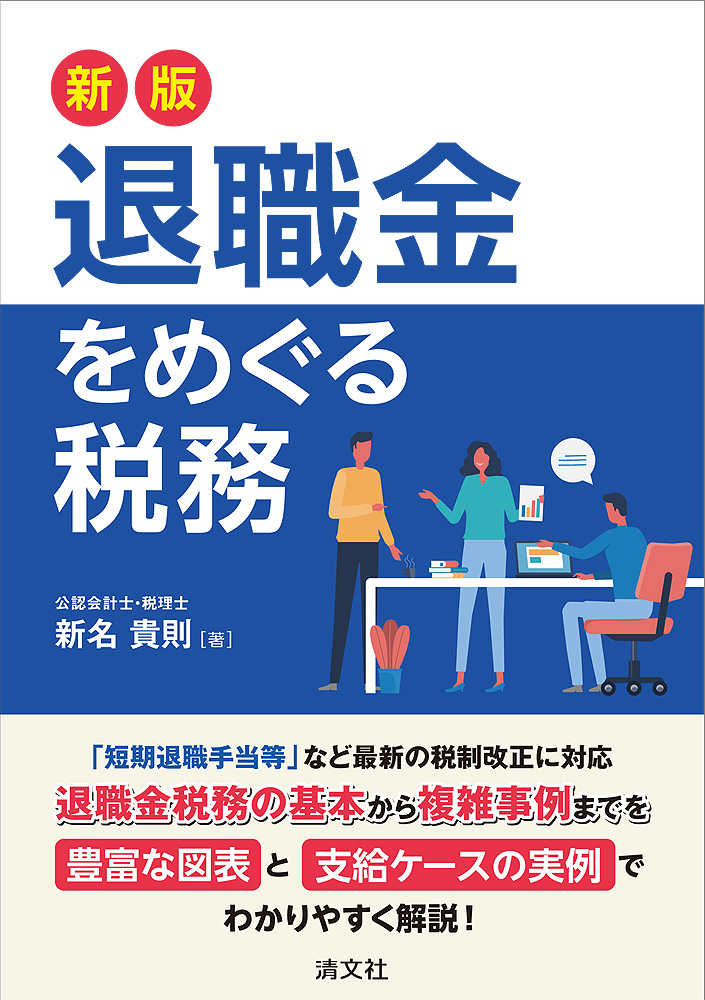(前ページ【STEP6】へ戻る)
期待運用収益とは、年金資産の運用により生じると合理的に期待される計算上の収益をいう(基準10)。期待運用収益の計算では、以下の2つを検討する。
(1) 長期期待運用収益率の設定
(2) 期待運用収益の計算
※画像をクリックすると、大きい画像が開きます。

(1) 長期期待運用収益率の設定
長期期待運用収益率とは、合理的に期待される収益率をいう(基準23)。長期期待運用収益率は、年金資産が退職給付の支払に充てられるまでの時期、保有している年金資産のポートフォリオ、過去の運用実績、運用方針及び市場の動向等を考慮して、各社で前期末(又は、当期首)に設定する(適用指針25)。例えば、過去3年から5年等の運用実績をもとに設定することが考えられる。
なお、当年度の退職給付費用の計算に用いられる長期期待運用収益率は、当期損益に重要な影響があると認められる場合のほかは、見直さないことができる(適用指針31)。
(2) 期待運用収益の計算
期待運用収益は、期首の年金資産の額に(1)で設定した長期期待運用収益率を乗じて計算する。ただし、期中に年金資産の重要な変動があった場合には、これを期首の年金資産に反映させて、期待運用収益を計算する(適用指針21)。
(次ページ【STEP8】へ進む)
フロー・チャートを使って学ぶ会計実務
【第14回】
「退職給付引当金(原則法)」
仰星監査法人
公認会計士 西田 友洋
【はじめに】
今回は、退職給付引当金(原則法)の会計処理について解説する。原則法とは、数理計算により退職給付引当金を算定する方法である。なお、簡便法による退職給付引当金、複数の事業主により設立された確定給付型企業年金制度及び確定拠出制度については、解説していない。
退職給付引当金(原則法)は、個別財務諸表と連結財務諸表で会計処理が異なるため、【STEP1】から【STEP9】で個別財務諸表における会計処理を解説してから、【STEP10】で連結財務諸表における会計処理を解説する。
また、解説の都合上、個別財務諸表における会計処理については、期末での会計処理(【STEP1】から【STEP4】)を解説してから、期中での会計処理(【STEP5】から【STEP9】)を解説する。過去勤務費用の算定については、期中で会計処理を行う可能性もあるが、【STEP4】で数理計算上の差異とともに解説している。
この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員登録およびログインが必要です。
すでに会員登録をされている方は、下記ボタンからログインのうえ、ご覧ください。
Profession Journalのすべての記事をご覧いただくには、「プレミアム会員(有料)」へのご登録が必要となります。
なお、『速報解説』については「一般会員(無料)」へのご登録でも、ご覧いただけます。
※他にもWebセミナー受け放題のスーパープレミアム会員などがございます。
会員登録がお済みでない方は、下記会員登録のボタンより、ご登録のお手続きをお願いいたします。