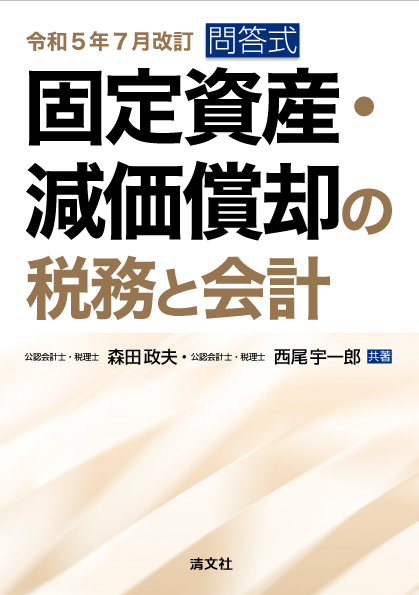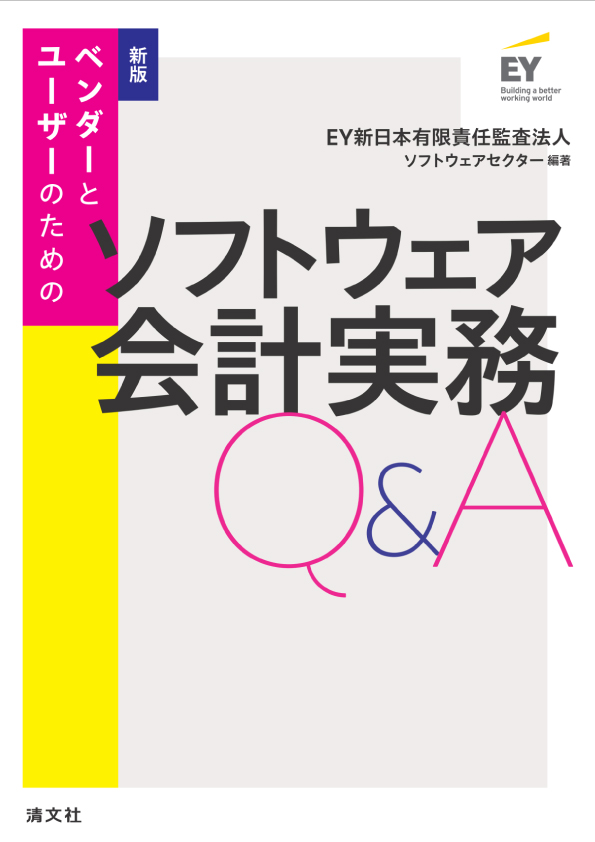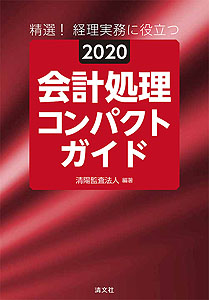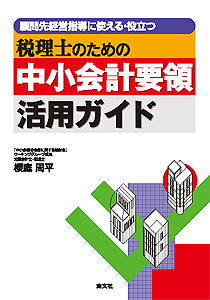〔事例で使える〕
中小企業会計指針・会計要領
《固定資産(その2)-ソフトウェア》編
【第1回】
「ソフトウェアの取得価額(1)~自社制作した場合」
公認会計士・税理士 前原 啓二
連載の目次はこちら
本連載の趣旨
「中小企業の会計に関する指針」(以下「中小企業会計指針」とします)は、中小企業が計算書類の作成に当たり拠ることが望ましい会計処理等を示すもので、一定の水準を保ったものとされています。これに比べ簡単な会計処理をすることが適切と考えられる中小企業を対象に「中小企業の会計に関する基本要領」も公表されました。
しかし、これらは簡潔に文章で記載されており、概念的には理解できても、実際にはどのように会計処理するのかがわからないため、仕方なく旧来どおりの決算処理を続けている中小企業が散見されます。
そこで、本連載では、実際の中小企業で行われている基本的かつ重要な会計処理の事例をテーマごとに選び出し、「中小企業会計指針」等に基づく会計処理の一例について数値例を用いて具体的に示して、実務上のモデルとなるように解説します。
連載の第16弾として、固定資産の中からソフトウェアを取り上げます。
本連載が、「中小企業会計指針」等のより一層の普及、さらに、中小企業の経営実態の正確な把握や適切な経営管理への発展に、少しでもつながれば幸いです。
▷《固定資産(その2)-ソフトウェア》編のラインナップ
- 【第1回】 ソフトウェアの取得価額(1)~自社制作した場合(本稿)
- 【第2回】 ソフトウェアの取得価額(2)~他の者から購入した場合
- 【第3回】 ソフトウェアの償却方法
はじめに
「中小企業会計指針」では、研究開発に該当しないソフトウェアの制作費について、社内利用のソフトウェアと市場販売目的のソフトウェアに分けて、それぞれの会計処理を簡単に説明しています。今回は、無形固定資産としてのソフトウェアの取得原価について、社内利用のソフトウェアを自社制作した場合をご紹介します。【設例1】
当社(3月31日決算)は、当期(X1年4月1日~X2年3月31日)において、社内の業務効率改善(従来と比べて事務部署の人件費を数人分削減)を目的として、2種類の自社制作ソフトウェア(「Xソフト」と「Yソフト」)を制作するために、下記の支出を行い、そのうち1種類のソフトウェア(「Xソフト」)を完成させ、稼働を開始しました。
(1) ソフトウェア制作に使用した特別な消耗品代280,000円。
(2) 当社の情報システム部署の担当社員であるシステムエンジニア2名が、ソフトウェア制作期間内に携わった実績時間に係る人件費15,000,000円。
(3) ソフトウェア制作に使用したパソコン等備品のリース料250,000円。
(4) ソフトウェア制作の一部をB社に委託外注した支払報酬9,000,000円。
(5) このソフトウェアを実際に稼働させるために、当社の情報システム部署の担当社員であるシステムエンジニア2名が調整等に携わった実績時間に係る人件費1,000,000円、さらに、B社に応援を依頼した支払報酬800,000円。
(6) ソフトウェア制作の場所となった情報システム部署エリアに係る光熱水費の配賦金額などソフトウェア制作に要した間接費600,000円。
(7) 制作途中において、自社制作ソフトウェアのうち1種類(「Xソフト」)の制作計画の変更により、もう1種類のソフトウェア(「Yソフト」)が明らかに不要となり制作を中止しました。この不要となった「Yソフト」のそれまでの制作費用は、(1)から(4)の合計で4,500,000円であり、すべて「Xソフト」の制作にはまったく関連のない費用です。「Xソフト」の完成・稼働により、当初の目的通り、従来と比べて事務部署の人件費が数人分削減できました。
このソフトウェア(無形固定資産)の取得原価はいくらでしょうか。
〈ソフトウェア(無形固定資産)の取得原価〉
⇒ 21,830,000円
「中小企業会計指針」によると、社内利用のソフトウェアは、その利用により将来の収益獲得又は費用削減が確実であると認められる場合には、取得に要した費用を無形固定資産として計上します。この無形固定資産の減価償却方法について、税法上の取扱いは、定額法により、耐用年数が「複写して販売するための原本」以外のソフトウェアとして5年とされています(耐令別表第三)。ソフトウェアの取得原価について、税務上の取扱いは、特に規定されておらず、自己の建設等に係る減価償却資産の取得原価の規定(法令54①二)に従って、次に掲げる金額の合計額となります。
① ソフトウェアの制作のために要した原材料費、労務費及び経費の額
② ソフトウェアを事業の用に供するために直接要した費用の額
この設例では、上記①の原材料費が「(1)ソフトウェア制作に使用した特別な消耗品代280,000円」、労務費は「(2)当社の情報システム部署の担当社員であるシステムエンジニア2名がソフトウェア制作期間内に携わった実績時間に係る人件費15,000,000円」、経費は「(3)ソフトウェア制作に使用したパソコン等備品のリース料250,000円」と「(4)ソフトウェア制作の一部をB社に委託外注した支払報酬9,000,000円」と「(6)ソフトウェア制作の場所となった情報システム部署エリアに係る光熱水費の配賦金額などソフトウェア制作に要した間接費600,000円」が該当します。
また、上記②は、「(5)このソフトウェアを実際に稼働させるために、当社の情報システム部署の担当社員であるシステムエンジニア2名が調整等に携わった実績時間に係る人件費1,000,000円、さらに、B社に応援を依頼した支払報酬800,000円」が該当します。
以上を集計すると、下記となります。
原材料費(1)280,000円 + 労務費(2)15,000,000円 +{直接経費(3)250,000円+(4)9,000,000円}+ 間接経費(6)600,000円+{事業の用に供するために直接要した費用(5)1,000,000円 + 800,000円}= 26,930,000円
このうち、制作費等のために要した間接費、付随費用等で、その制作原価のおおむね3%以内の金額であるものは、重要性の原則等の観点から取得原価に算入しないことができます(法基通7-3-15の3)。この設例では、間接経費(6)600,000円がこれに該当するので、これを取得原価から除くことにしています。
また、自社制作に係るソフトウェアの制作計画の変更等により、仕損じがあったため不要となったことが明らかなものに係る費用の額は、まったくのロスであることから、取得原価に含めなくてよいとされます(法基通7-3-15の3)。この設例では、(7)(制作途中において、自社制作ソフトウェアのうち1種類(「Xソフト」)の制作計画の変更により、もう1種類のソフトウェア(「Yソフト」)が明らかに不要となり、この不要となったソフトウェアの制作費用は、(1)から(4)の合計で4,500,000円)がこれに該当します。
これらを取得原価から除いて計算すると、ソフトウェアの取得原価は、下記のとおりです。
26,930,000円 -(6)600,000円 -(7)4,500,000 = 21,830,000円
[凡例]
- 中小企業会計指針・・・中小企業の会計に関する指針
- 中小企業会計要領・・・中小企業の会計に関する基本要領
- 法令・・・法人税法施行令
- 法基通・・・法人税基本通達
- 耐令・・・減価償却資産の耐用年数等に関する省令
(例)法令54①二・・・法人税法施行令第54条第1項第2号
[参考]
「中小企業の会計に関する指針・中小企業の会計に関する基本要領」(日本税理士会連合会ホームページ)
(了)
この連載の公開日程は、下記の連載目次をご覧ください。