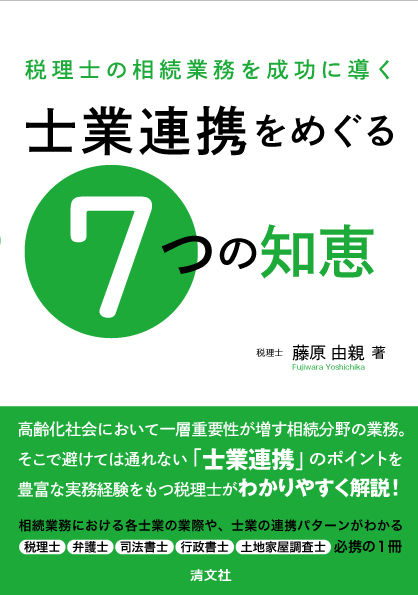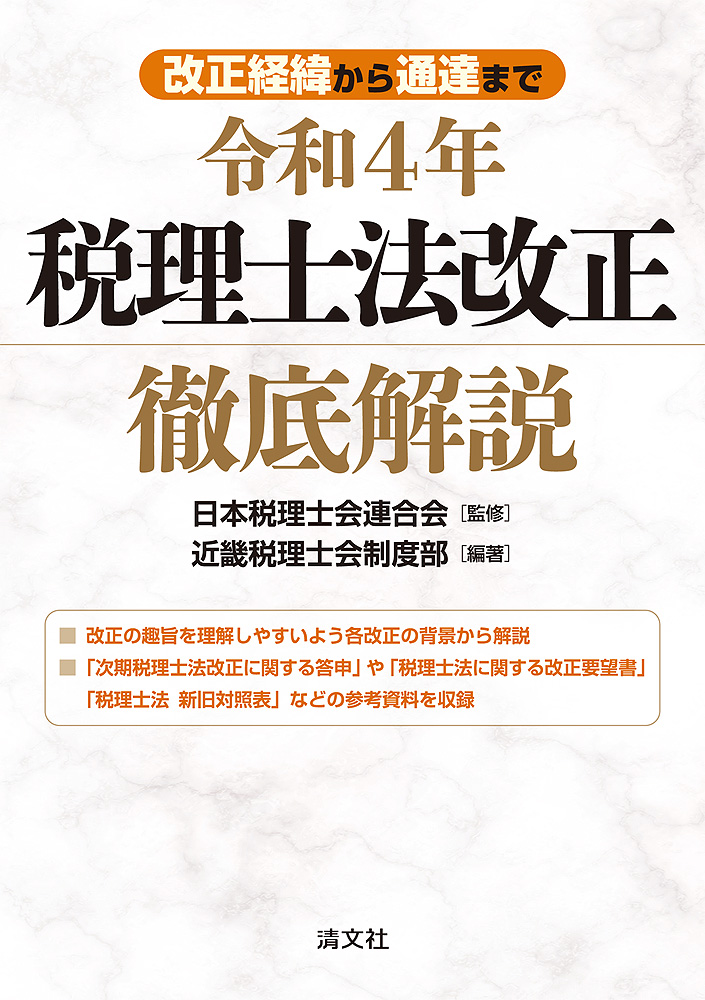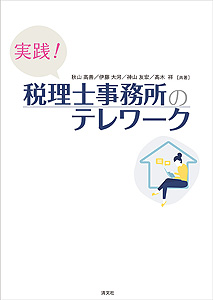〈事例から理解する〉
税法上の不確定概念の具体的な判断基準
【第1回】
「国税通則法第65条第4項第1号の過少申告加算税が課されない「正当な理由」のハードル」
公認会計士・税理士 大橋 誠一
連載に当たって
筆者は、税理士・公認会計士出身の専門家として国税不服審判所に勤務し、国税審判官として審査請求事件の調査審理に従事していたが、有り体に言えば、「納税者(審査請求人)に係る各種の事実関係が、この税法のこの課税要件に該当するか否か」を判断し、それを裁決書に取りまとめることであった。
例えば、何らかの事情によって修正申告に至り、当初申告よりも税額が増加した場合、通常は「過少申告加算税」が賦課される(国税通則法第65条第1項)が、同時に、「正当な理由」があれば、その事実に基づく税額については賦課されない(同条第4項第1号)。
そこで、納税者(審査請求人)は、「私を取り巻く事情は『正当な理由』に該当する」という主張をもって不服申立てに及ぶことになり、国税不服審判所はその主張が認容されるか否かを審理することになるが、その判断のためには、一定の判断基準を設定しているはずであり、それが「法令解釈」と言われるものである。
そうすると、納税者としては、税法に規定されている「課税要件」についての判断基準、すなわち「法令解釈」をあらかじめ把握しておくことで、不服申立ての際、又はその前段階である税務調査の際、更にはその前段階である当初申告の際において、自らの主張が認容されそうか否かをあらかじめ占うことができ、想定していなかった税務トラブルが自らに降りかかるリスクを合理的に低減することができるだろう。
ここで、課税要件といっても、「〇〇円以上」などの定量的な基準であれば通常は争いが生じないが、上記の「正当な理由」といった定性的な基準の場合に、課税庁との見解の相違が生じやすいところ、我が国の税法はこういった「不確定概念」による課税要件が思いのほか多い。
そこで、本稿は、「不確定概念」を含む代表的な税法規定の課税要件について、国税不服審判所が採用する法令解釈の出所を、事例を題材として解説するとともに、「このような事例は国税不服審判所において争う価値がある(取消しの可能性がある)」「このような事例ではお気の毒ながら救済は難しい(棄却の可能性が高い)」といった目利きを養っていただくことを目的としている。
これによって、税務専門家である読者各位の抱える事例が納税者の勝てる可能性のあるものか否かについて、不服申立てを含む税務争訟に至る前段階で、ある程度の見通しが立てられることによって、税務調査の際に修正申告に応じることが得策か否かといった戦略的な判断に資することを期待するものである。
* * *
1 大阪国税不服審判所平成28年1月20日裁決
(1) 事実関係の概要
① 被相続人には法定相続人はおらず、被相続人の夫の兄弟(A、B)の子4人(Aの子のC、Bの先妻との子のDとE、Bの後妻との子のF)とFの配偶者Gの計5名に対して、均等の割合で包括遺贈し、遺言執行者として信託銀行を指定する旨の公正証書を作成していた。
② 被相続人は、被保険者を被相続人、Fを受取人とする保険契約を締結していた。
③ Fは、相続開始後に保険金を受け取った。
④ 請求人であるEは、遺言執行者が手配した税理士に相続税の申告を依頼し、当該税理士は遺言執行者作成の財産目録のとおりに相続税の申告をしたが、上記保険金は課税価格及び税額の計算の基礎とされていなかった。
⑤ 請求人は、調査担当職員による指摘を受けて、保険金を計算の基礎に含めた修正申告をした。
⑥ 原処分庁は、請求人に対して過少申告加算税の賦課決定処分をした。
(2) 請求人の主張の概要
① 遺言には生命保険に係る記載はなく、遺言執行者が保険金の手続を取り扱うこともなかった。
② 請求人とFは遠戚で交流はほどんどなく、受遺者である請求人に相続財産を調査する権限はなかったため、請求人が保険金の存在を把握できなかったのは当然で落ち度はない。
③ したがって、請求人には、過少申告加算税が課されない「正当な理由」がある。
(3) 「正当な理由」の法令解釈
① 過少申告加算税は、過少申告による納税義務違反の事実があれば、原則としてその違反者に対し課されるものであり、これによって、当初から適法に申告し納税した納税者との間の客観的不公平の実質的な是正を図るとともに、過少申告による納税義務違反の発生を防止し、適正な申告納税の実現を図り、もって納税の実を挙げようとする行政上の措置である。
② そして、このような過少申告加算税の趣旨に照らせば、国税通則法第65条第4項にいう正当な理由があると認められる場合とは、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があり、上記のような過少申告加算税の趣旨に照らしても、なお、納税者に過少申告加算税を賦課することが不当又は酷になる場合をいうものと解するのが相当である。
(4) 審判所の判断の概要・請求人の主張の排斥
① 請求人は、相続税の申告を税理士とF夫妻に任せきりにして、税理士から送付された申告書案について問い合わせることすらせず、相続財産についての調査・確認を行わないまま、漫然と当初申告したものといわざるを得ない。
② 相続財産に計上した預金口座から保険料が支払われていたことからすれば、請求人は保険契約の締結の存在を推知することが可能であったというべきである。
③ 包括受遺者は相続人と同一の権利義務を有し、相続財産を調査する権限を有していることは明らかである。
④ したがって、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情はなく、「正当な理由」があると認めることはできない。
2 法令解釈の出所と判断の分かれ目
上記1(3)の法令解釈は、最高裁判所第一小法廷平成18年4月20日判決をほぼそのまま引用している。
国税不服審判所裁決はあくまで行政判断であり、自らが打ち立てた規範が後に控える司法の場において覆る可能性を可能な限り低減させたいという動機が働くことから、できる限り上級の裁判所の法令解釈を引用することになる。
この法令解釈によっても判断基準が定性的であり、これに事実関係を当てはめるとしても判断権者によって差が生じることは否めないが、大要としては、「客観的・第三者的な事情」であれば是認の方向に、「納税者側による主観的な事情」であれば否認の方向に傾くことになるだろう。
本件については、「保険金を受領したのは遠戚であり、突っ込んで財産を調査するなど事実上無理ではないか」という請求人の抱える事情に同情の余地があるとしても、所詮は「納税者側による主観的な事情」であり、他の過少申告による納税者が加算税を賦課されることのバランスを考えると、国が賦課徴収を諦めることを受忍すべき事情とまではいえないとの判断だったものと考えられる。
3 「正当な理由」が認容された最近の事例
(1) 認容事例は少ない
国税不服審判所は、四半期ごとに、重要な裁決や先例となる裁決を、適切にマスキングを施した上で公表している。
このうち、令和4年12月31日現在で、「正当な理由」を認容した公表裁決は、過少申告加算税で2件、無申告加算税で1件しかなく、これに対して、認容しなかったものは、前者で23件、後者で17件存在する。
そのくらいに「正当な理由」の認容事例は少ないのであるが、最近においても認容された事例はないわけではない。
(2) 広島国税不服審判所令和3年6月24日裁決
登記名義が被相続人から移転していた家屋について、請求人は関与税理士として譲渡所得の申告を行っており、譲受人がその家屋に居住していたことから、売買の有効性を疑うべき状況になく、かつ、売買代金が実質的に支払われていなかったことを把握できたのは、相続税の申告期限後であったことを併せ考えれば、請求人の責めに帰することのできない客観的な事情があったと認められ、請求人には正当な理由があると認められる場合に該当する。
(3) 東京国税不服審判所令和4年6月16日裁決
登記所職員が誤った相続関係の説明を行い、これにより法定相続情報一覧図の記載内容にも誤りが生じたために、請求人が、自己が相続人に該当しないと判断して相続税の申告書を法定申告期限内に提出しなかったことは無理からぬ面があり、期限内申告書の提出がなかったことについて正当な理由があると認められる場合に該当する。
(了)
「〈事例から理解する〉税法上の不確定概念の具体的な判断基準」は、毎月第2週に掲載されます。