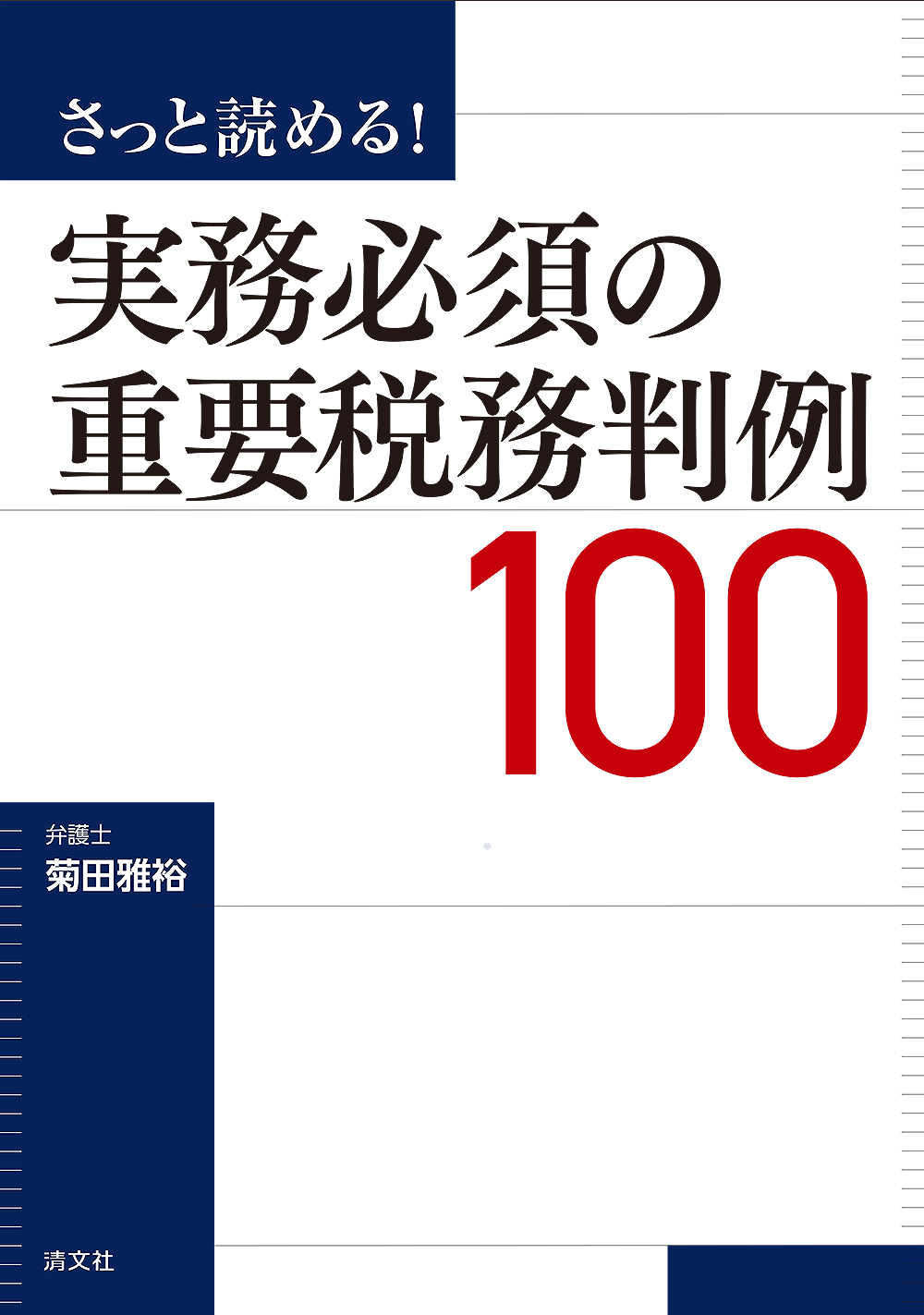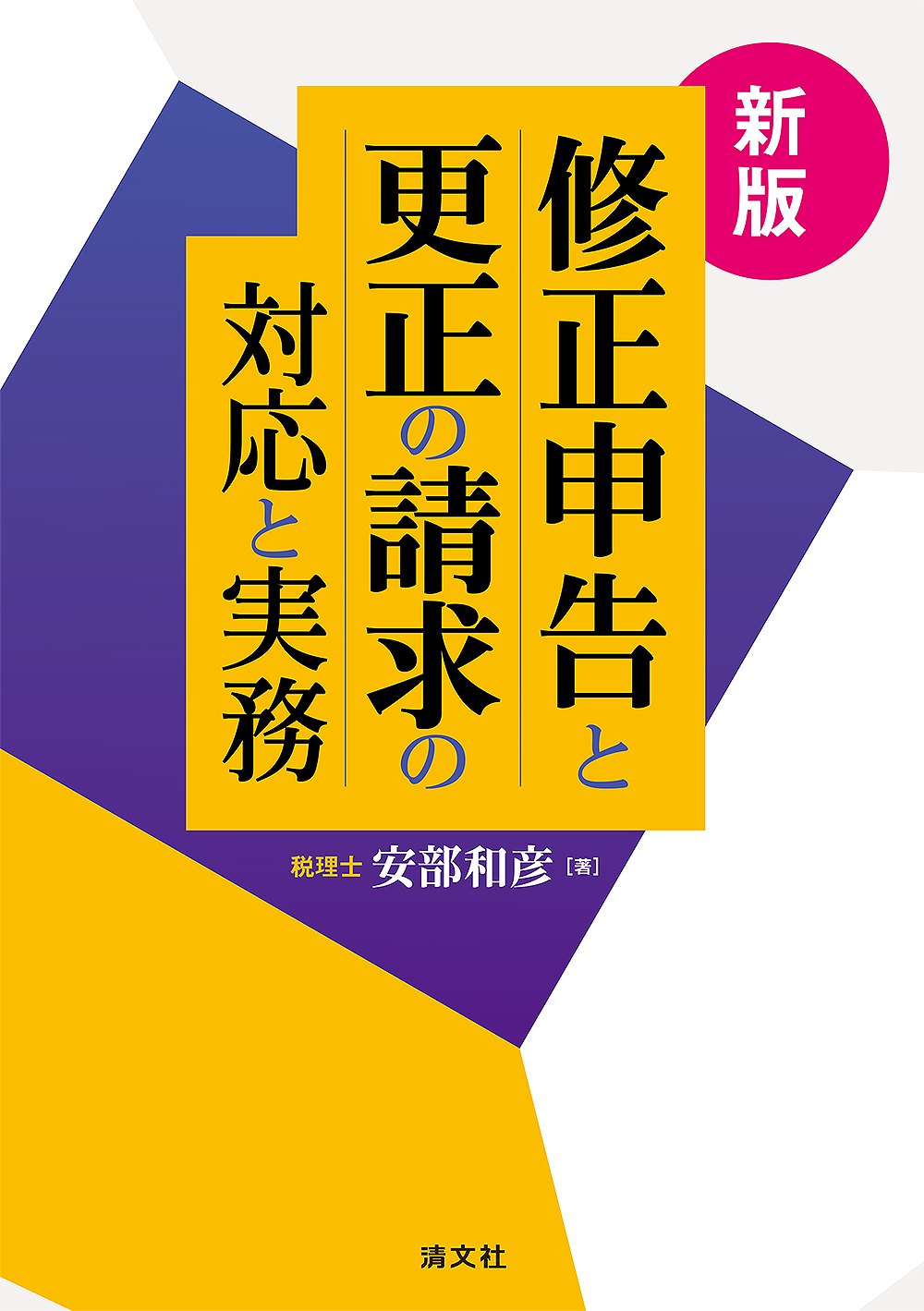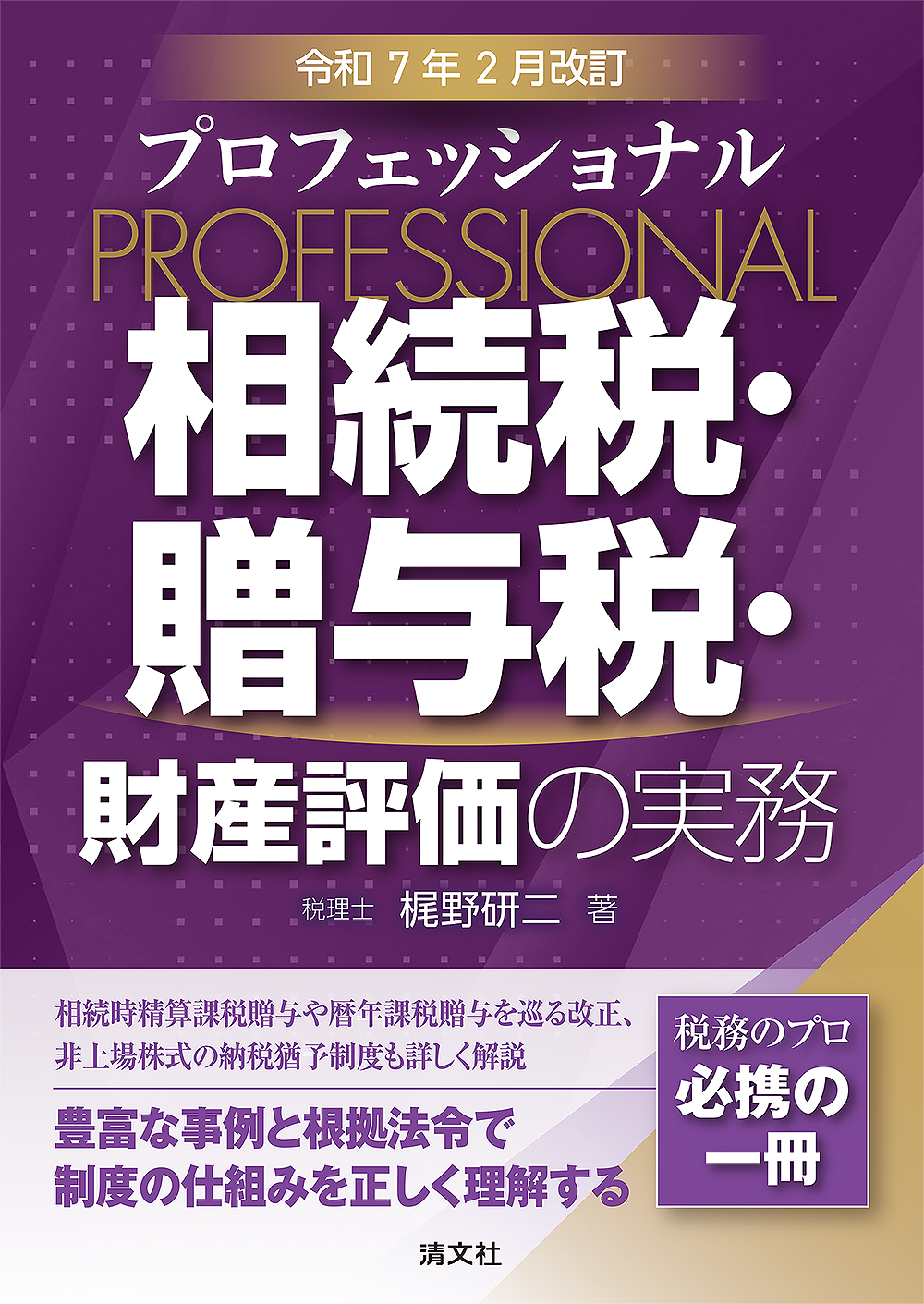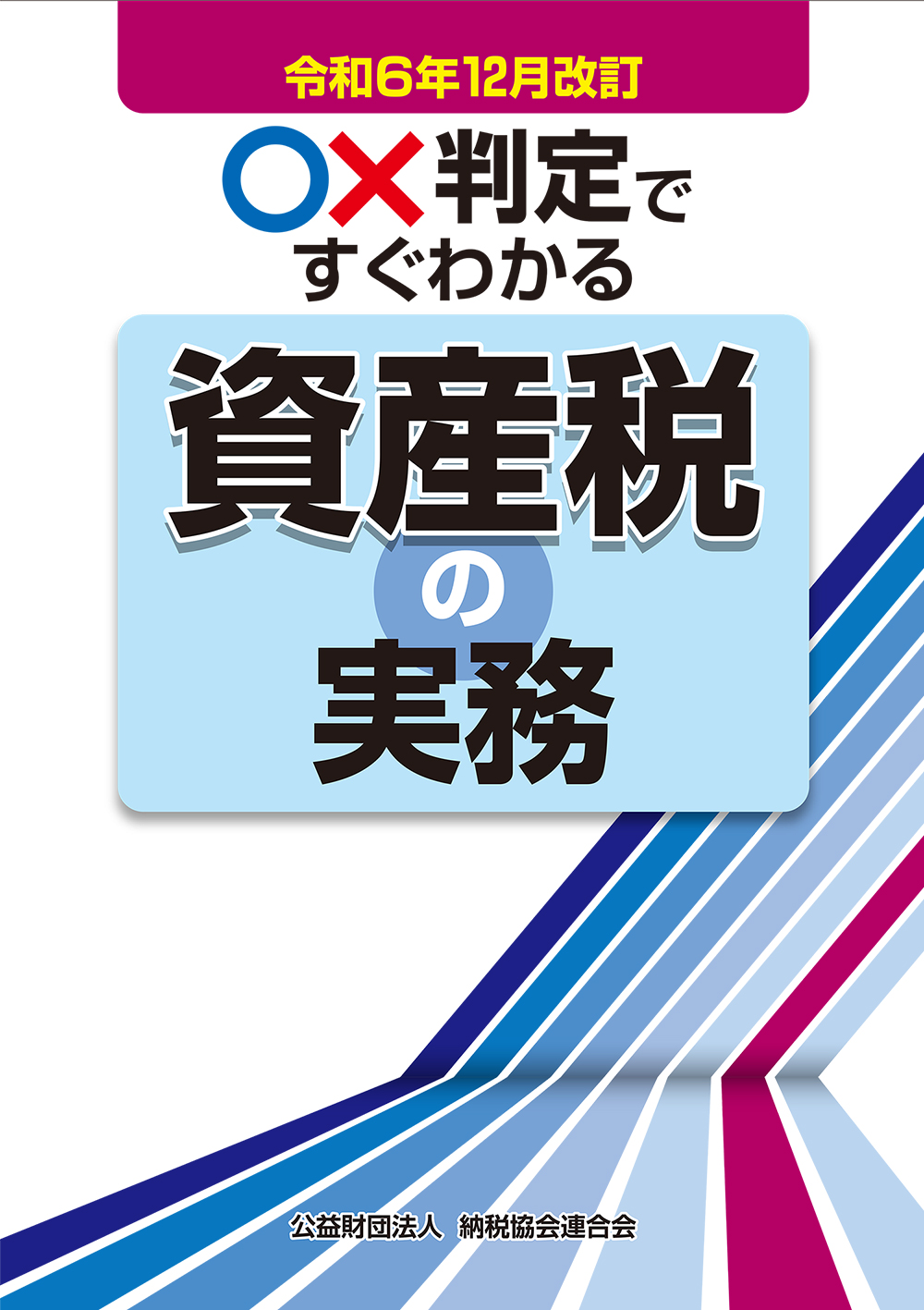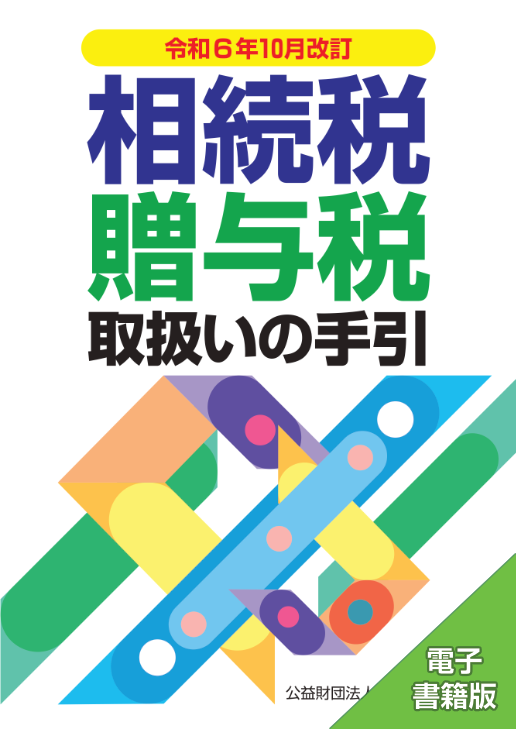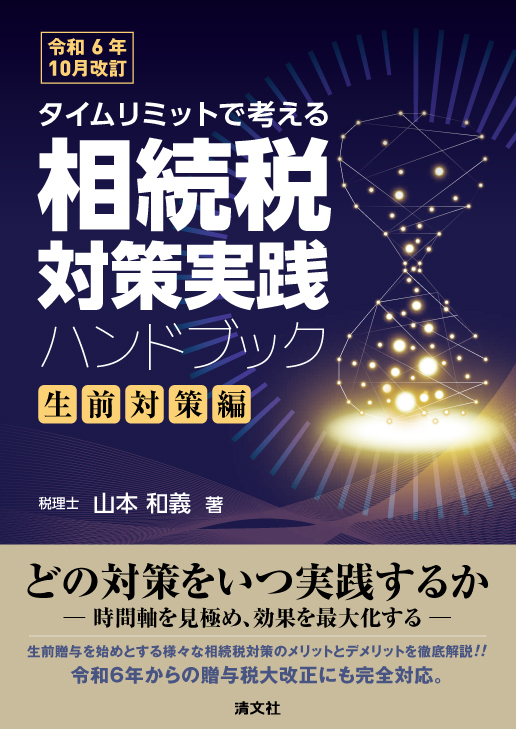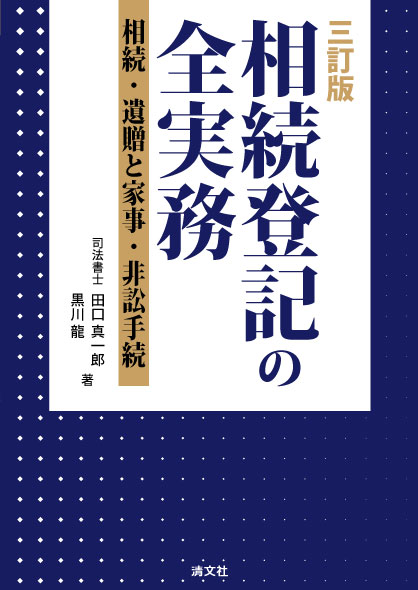さっと読める!
実務必須の
[重要税務判例]
【第51回】
「相続税延滞税事件」
~最判平成26年12月12日(集民248号165頁)~
弁護士 菊田 雅裕
-本連載の趣旨-
本連載は、税務分野の重要判例の要旨を、できるだけ簡単な形でご紹介するものである。
税務争訟は、請求内容や主張立証等が細かく煩雑となりやすい類型の争訟であり、事件の正確な理解のためには、処分経過の把握や判決文の十分な読み込み等が必要となってくるが、若手税理士をはじめとする多忙な読者諸氏が、日常業務をこなしつつ判例研究の時間を確保することは、容易なことではないであろう。他方、これから税務重要判例を知識として蓄積していこうとする者にとっては、要点の把握すら困難な事件も数多い。
本連載では、解説のポイントを絞り、時には大胆な要約や言い換え等も行って、上記のような読者の方に、重要判例の概要を素早く把握していただこうと考えている。
このような企画趣旨から、本連載における解説は、自ずと必要最低限のものとなり、基礎知識の説明、判例の繊細なニュアンスの紹介、多角的な分析、主要な争点以外の判断事項の紹介等を省略することも多くなると思われるが、ご容赦をいただきたい。
なお、より深い内容については、できるだけ論末において他稿をご紹介するので、そちらをご参照いただきたい。
▷今回の題材
相続税延滞税事件
最判平成26年12月12日(集民248号165頁)
《概要》
亡Aの相続人である3名の子のうちB以外のX1・X2は、申告期限内に相続税の申告をし、それとともに、X1は4,185万円、X2は4,556万円を納付した。その後、X1・X2は、相続財産である土地の評価額が時価より高いことを理由として更正の請求をした。
所轄税務署長は、更正の請求の一部を認め、X1の納付すべき税額を3,035万円、X2の納付すべき税額を3,353万円とする減額更正をして、これに基づき必要な還付を行った。X1・X2は、当該減額更正における土地の評価額はなお高いとして、異議申立てをしたが、所轄税務署長はこれを棄却した。
その後、所轄税務署長は、異議申立て棄却の際の土地の評価額の見直しによれば、減額更正時の評価額は時価よりも低かったとして、X1の納付すべき税額を3,071万円、X2の納付すべき税額を3,391万円とする増額更正をした。
X1・X2がこれに従い増差本税額を納付したところ、所轄税務署長は、X1・X2に対し、相続税の法定納期限以降の延滞税の納付を催告する催告書を送付した。そこで、X1・X2は、延滞税の納付義務がないことの確認を求める訴えを国に対して提起した。
《関係図》
▷争点
相続税につき減額更正がされた後に増額更正がされた場合、その増額更正により新たに納付すべきこととなった税額につき、法定納期限以降の延滞税は発生するか。
この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員登録およびログインが必要です。
すでに会員登録をされている方は、下記ボタンからログインのうえ、ご覧ください。
Profession Journalのすべての記事をご覧いただくには、「プレミアム会員(有料)」へのご登録が必要となります。
なお、『速報解説』については「一般会員(無料)」へのご登録でも、ご覧いただけます。
※他にもWebセミナー受け放題のスーパープレミアム会員などがございます。
会員登録がお済みでない方は、下記会員登録のボタンより、ご登録のお手続きをお願いいたします。