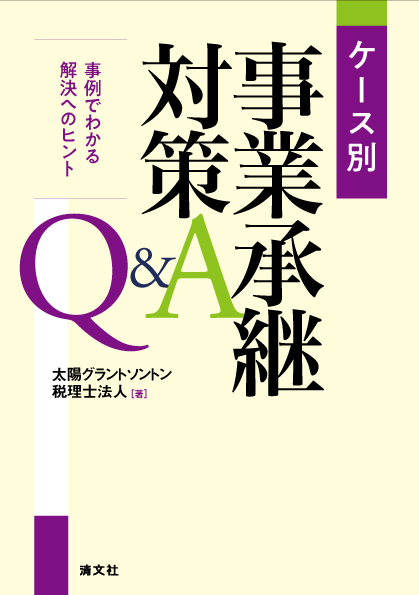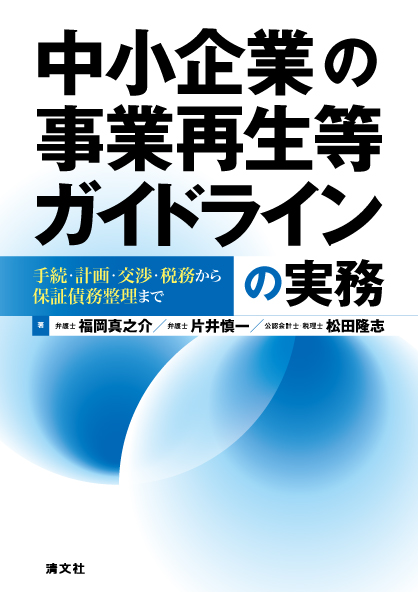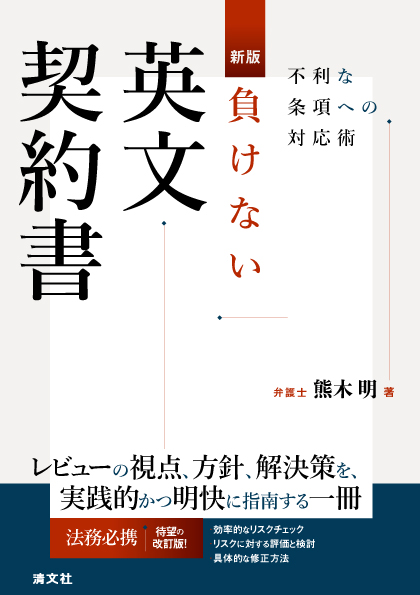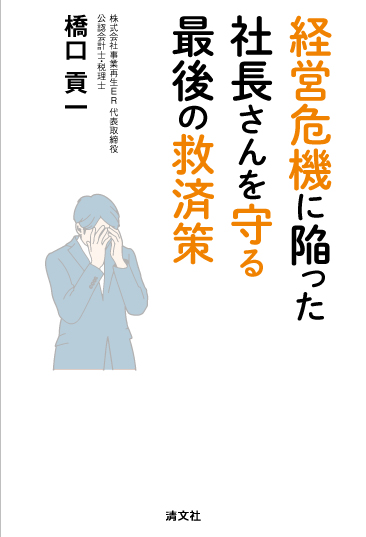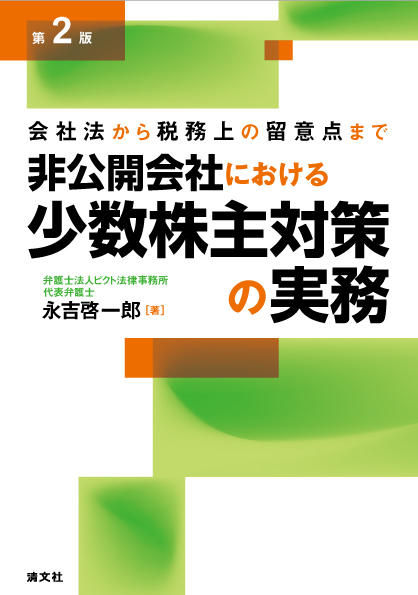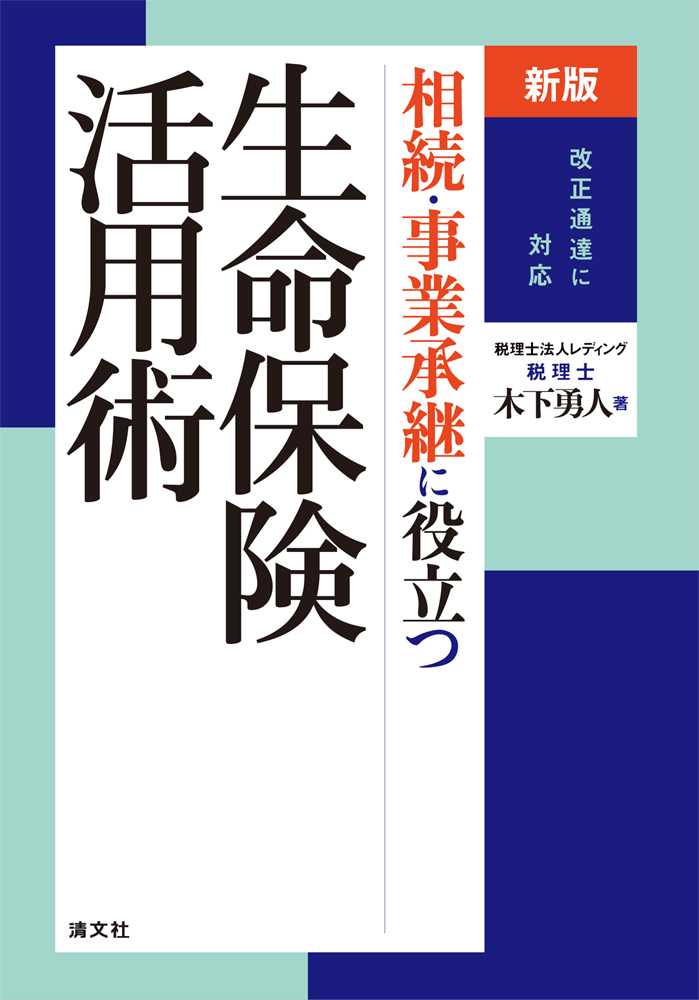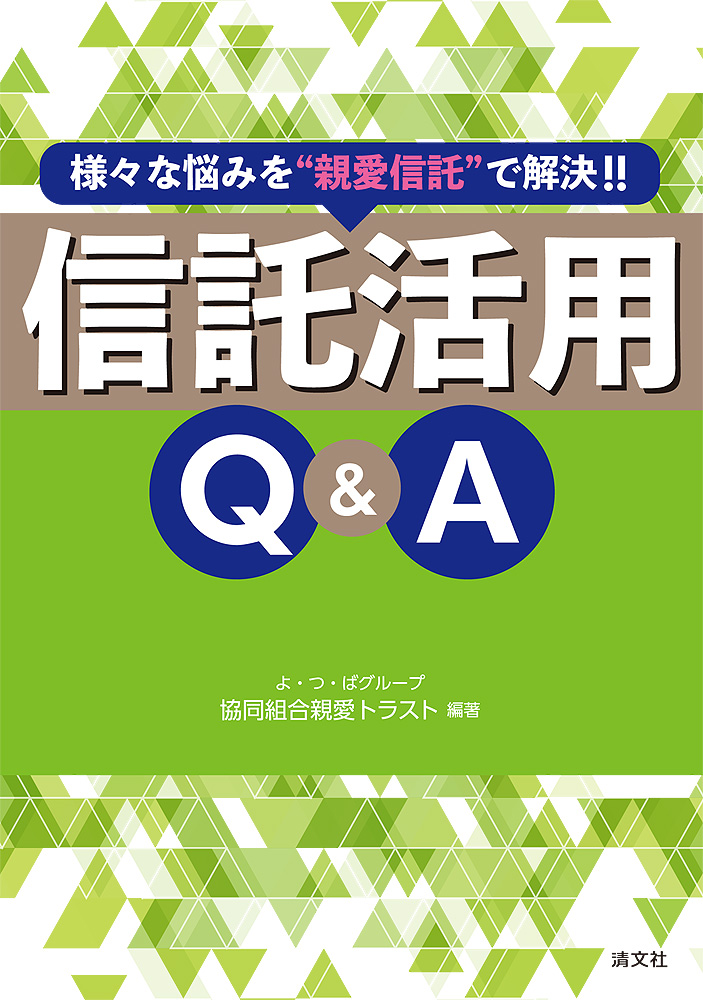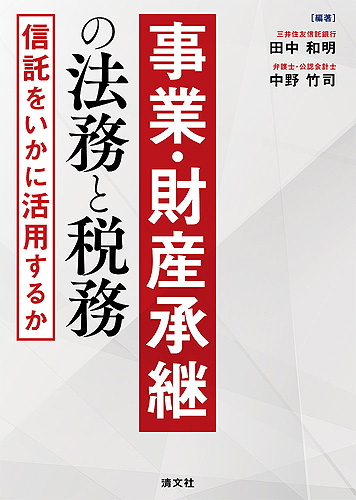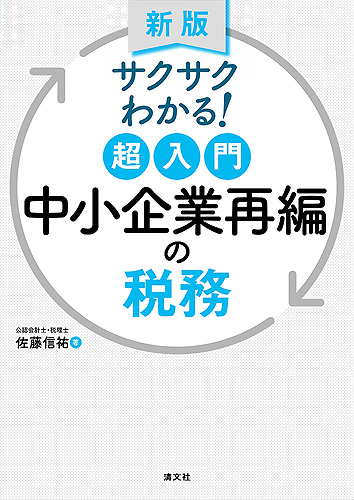事例でわかる[事業承継対策]
解決へのヒント
【第35回】
「属人的株式を使った承継対策」
太陽グラントソントン税理士法人
(事業承継対策研究会)
パートナー 税理士 日野 有裕
相談内容
私SはIT企業V社の株式を100%保有するオーナー社長です。V社は設立後5年しか経っていませんが、業績は順調に拡大しており、2~3年後には売上10億円、営業利益3億円が見えてきました。現状、V社は赤字会社のため、資産管理会社を設立して、私が所有する一部株式を移転してはどうかと顧問税理士より提案を受け、資産管理会社W社を設立し私が持つV社株式の40%を譲渡しました。
私はまだ35歳で事業承継を考える年齢ではありませんが、今後の業績拡大により増加が見込まれる株式の含み益を子供たちに移転できればと思い、私の議決権を保持しつつ、W社の株式を2人の子供に45%ずつ移転しようと考えています。ただ、私の子供はまだ5歳(A)と2歳(B)です。金融機関や従業員にはあまり知られないようにしたいと考えていますが、何か良い方法があれば教えてください。
この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員登録およびログインが必要です。
すでに会員登録をされている方は、下記ボタンからログインのうえ、ご覧ください。
Profession Journalのすべての記事をご覧いただくには、「プレミアム会員(有料)」へのご登録が必要となります。
なお、『速報解説』については「一般会員(無料)」へのご登録でも、ご覧いただけます。
※他にもWebセミナー受け放題のスーパープレミアム会員などがございます。
会員登録がお済みでない方は、下記会員登録のボタンより、ご登録のお手続きをお願いいたします。