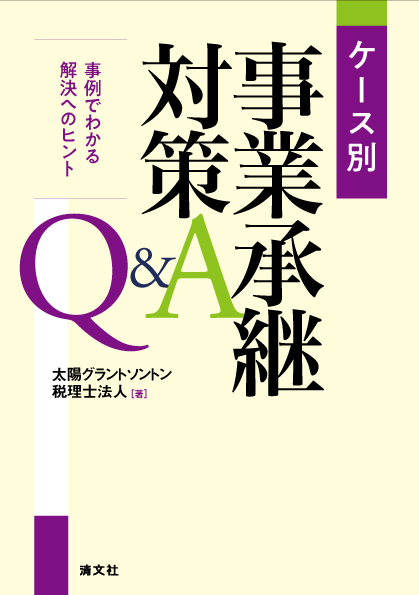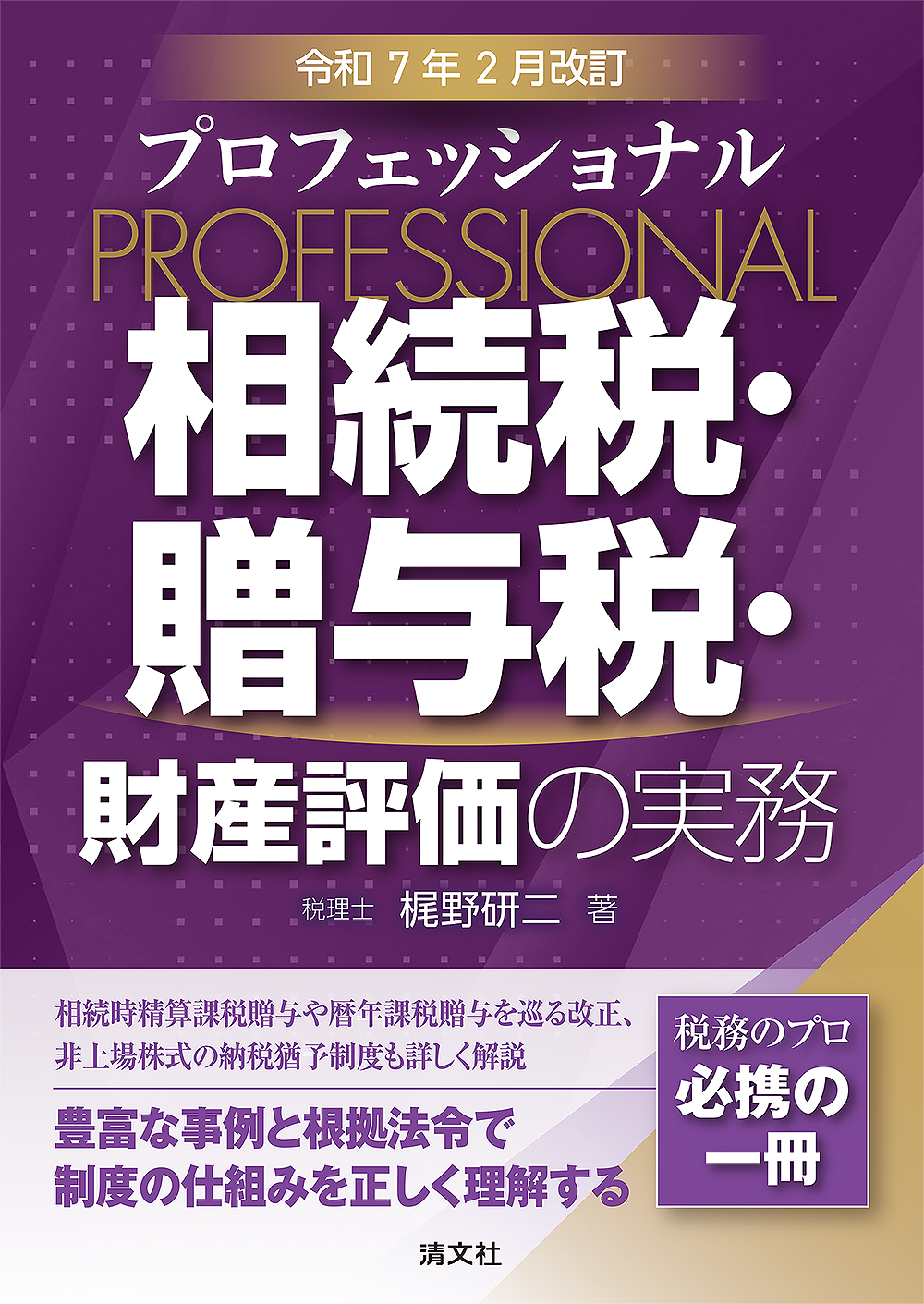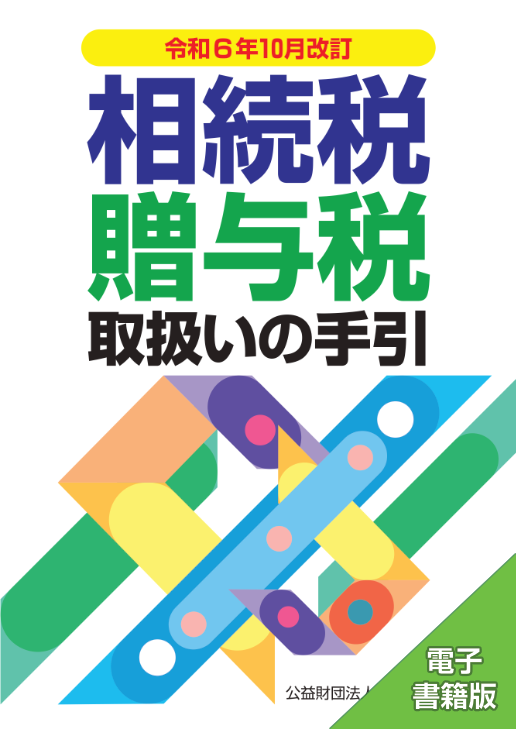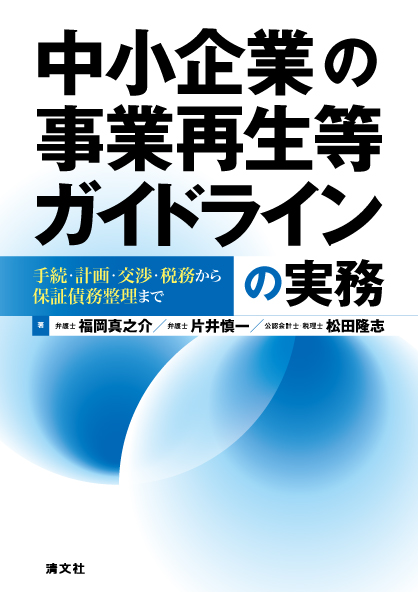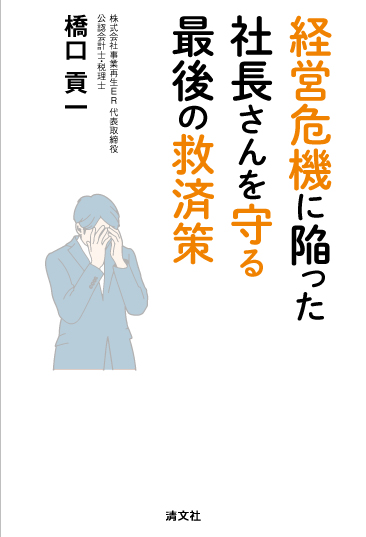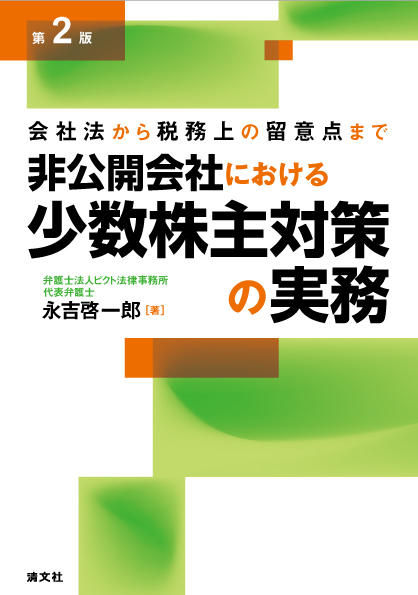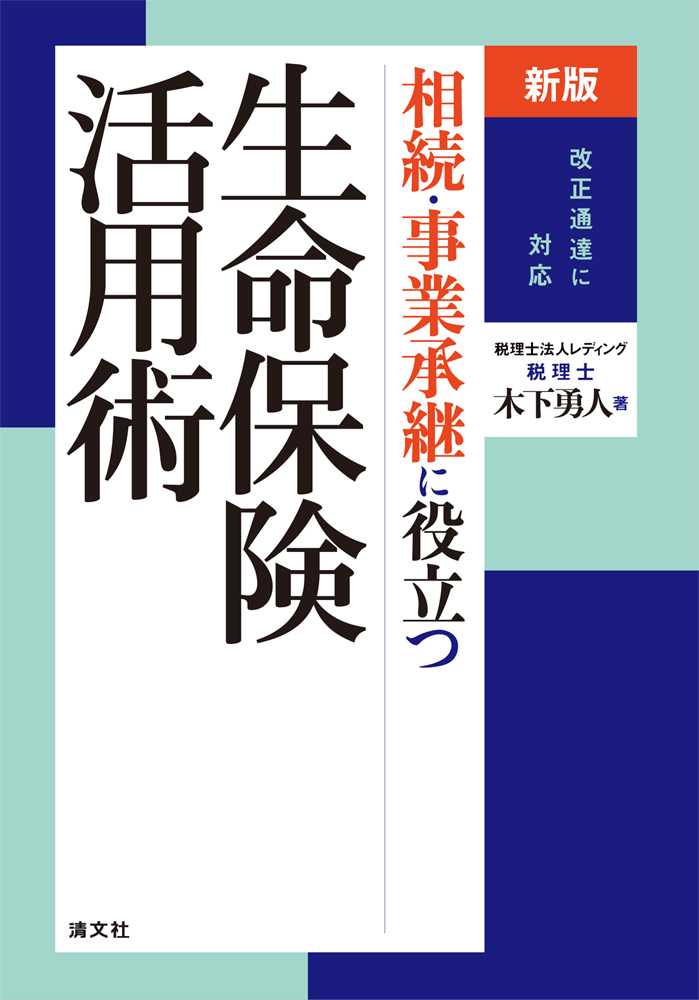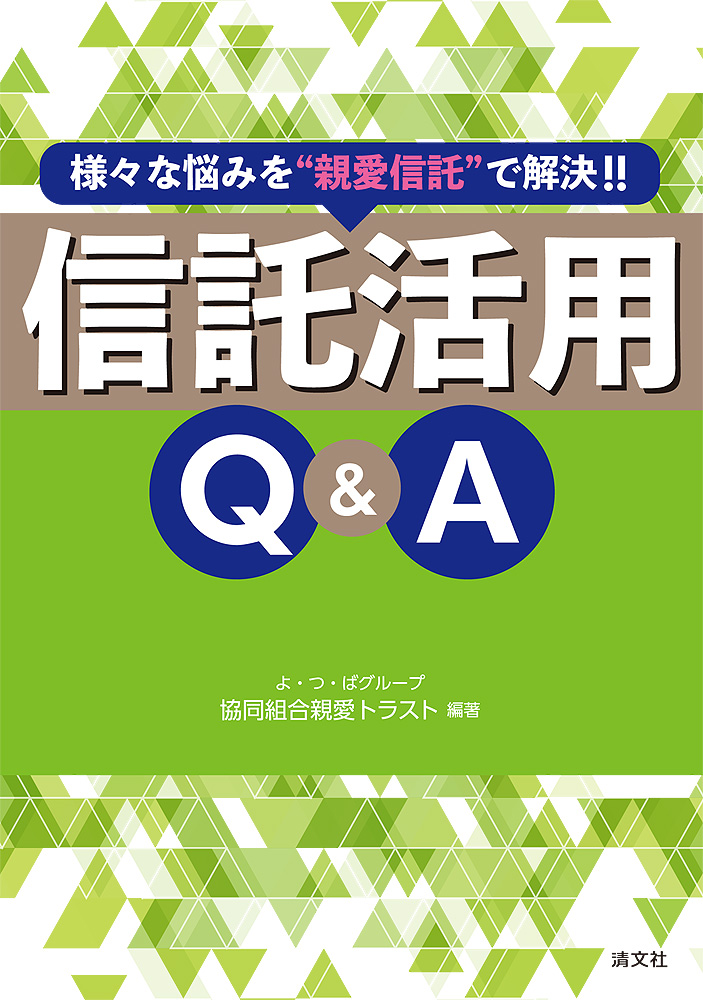事例でわかる[事業承継対策]
解決へのヒント
【第7回】
「配偶者が筆頭株主の場合」
太陽グラントソントン税理士法人
(事業承継対策研究会)
パートナー 税理士 梶本 岳
相談内容
私Tは、電気機器の設計・製造を営むS社を経営しています。S社は私の義父が創業した会社で、婿である私が経営を引き継いで20年になります。私も来年60歳になりますので、後継者である長男Aへの事業承継を意識し始めたところなのですが、経営の承継だけでなく、妻Uの所有するS社株式についてもAに承継する方法を考えるようにとメインバンクからアドバイスを受けました。
S社の株式は、創業者の一人娘であるUが相続し、相続から20年が経過した現在も大半の株式を保有しています。Uは経営には関与しておらず、S社の取締役にも就いていません。
当社は業績が非常に好調なこともあって、Uの所有するS社株式の株価が非常に高額になっています。株価が高い会社にとって事業承継税制は非常に有効な対策であると顧問税理士から説明を受けたのですが、同時に、筆頭株主であるUが代表取締役でなければ事業承継税制は使えないとの説明も受けました。実際、UはS社の経営に関与しておらず、取締役にも就任していません。
Uが株式の大半を保有している現状のままでは、事業承継税制を使ってAに株式を贈与することはできないのでしょうか。
また、どのような対応をとれば、事業承継税制を使ってAに株式を贈与することが可能となるでしょうか。
この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員登録およびログインが必要です。
すでに会員登録をされている方は、下記ボタンからログインのうえ、ご覧ください。
Profession Journalのすべての記事をご覧いただくには、「プレミアム会員(有料)」へのご登録が必要となります。
なお、『速報解説』については「一般会員(無料)」へのご登録でも、ご覧いただけます。
※他にもWebセミナー受け放題のスーパープレミアム会員などがございます。
会員登録がお済みでない方は、下記会員登録のボタンより、ご登録のお手続きをお願いいたします。