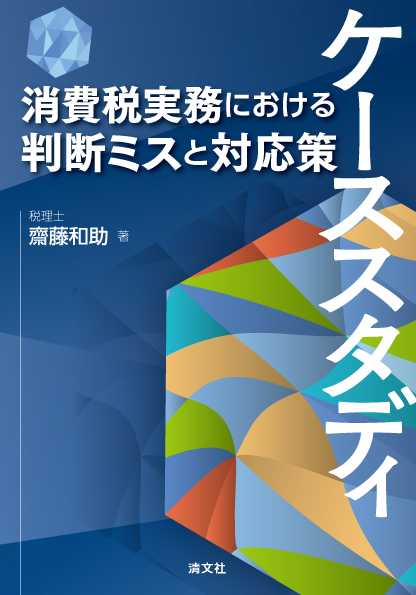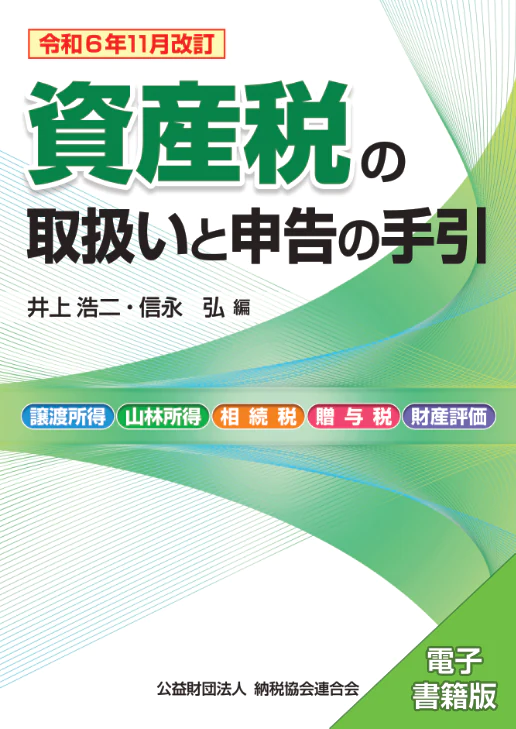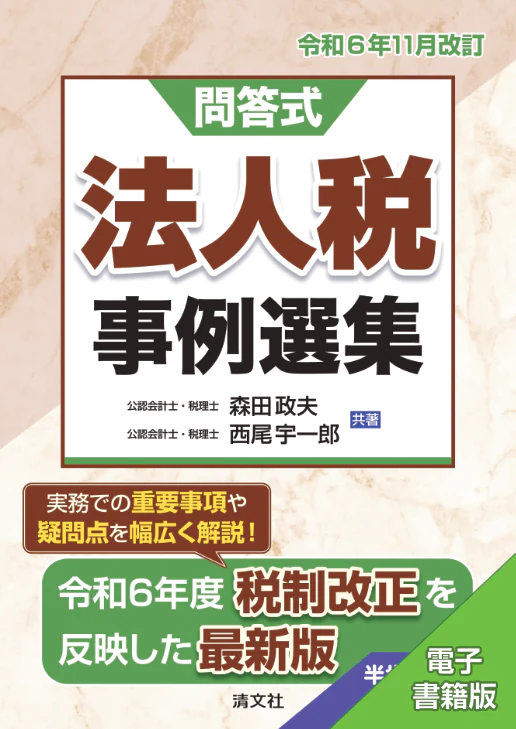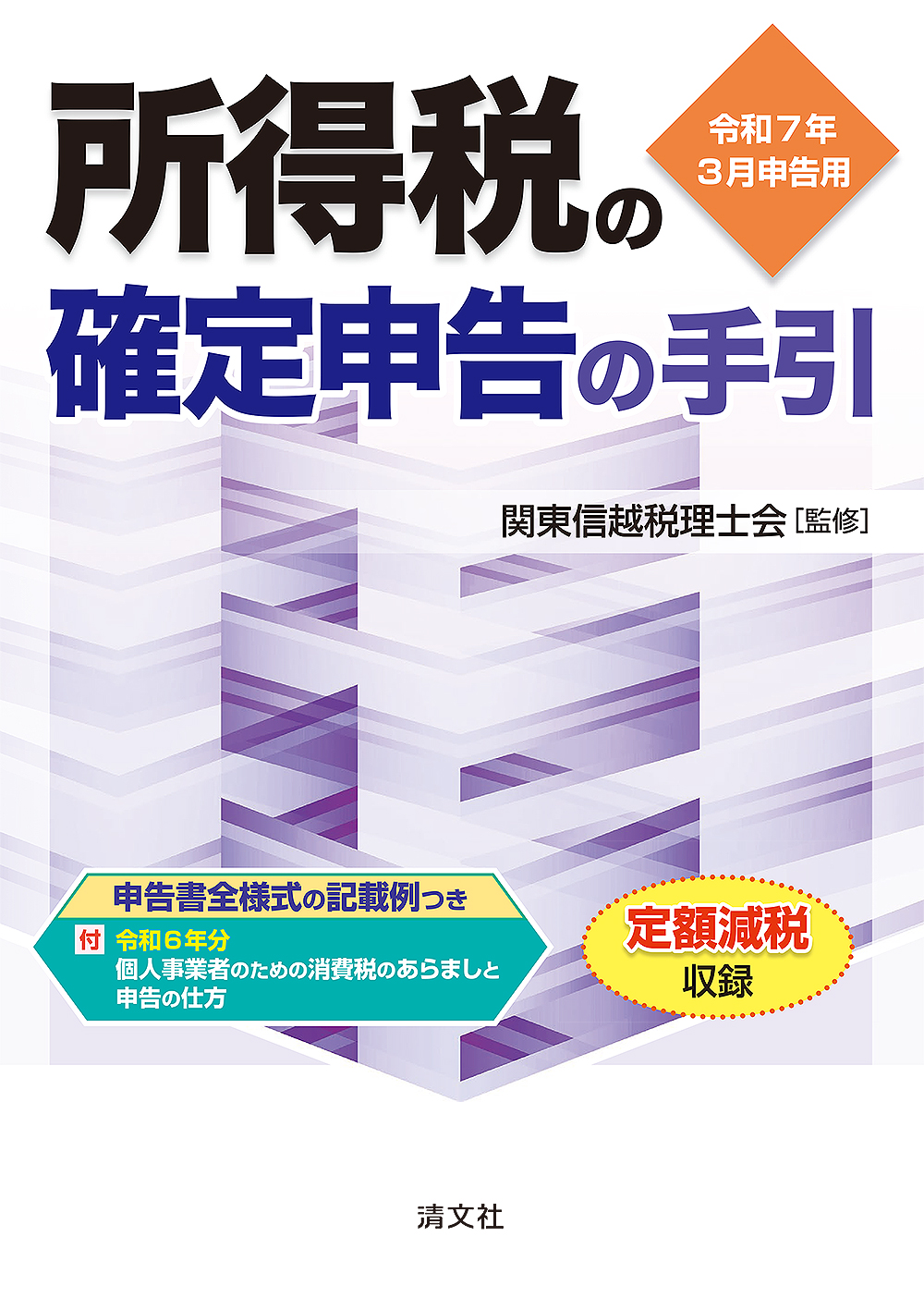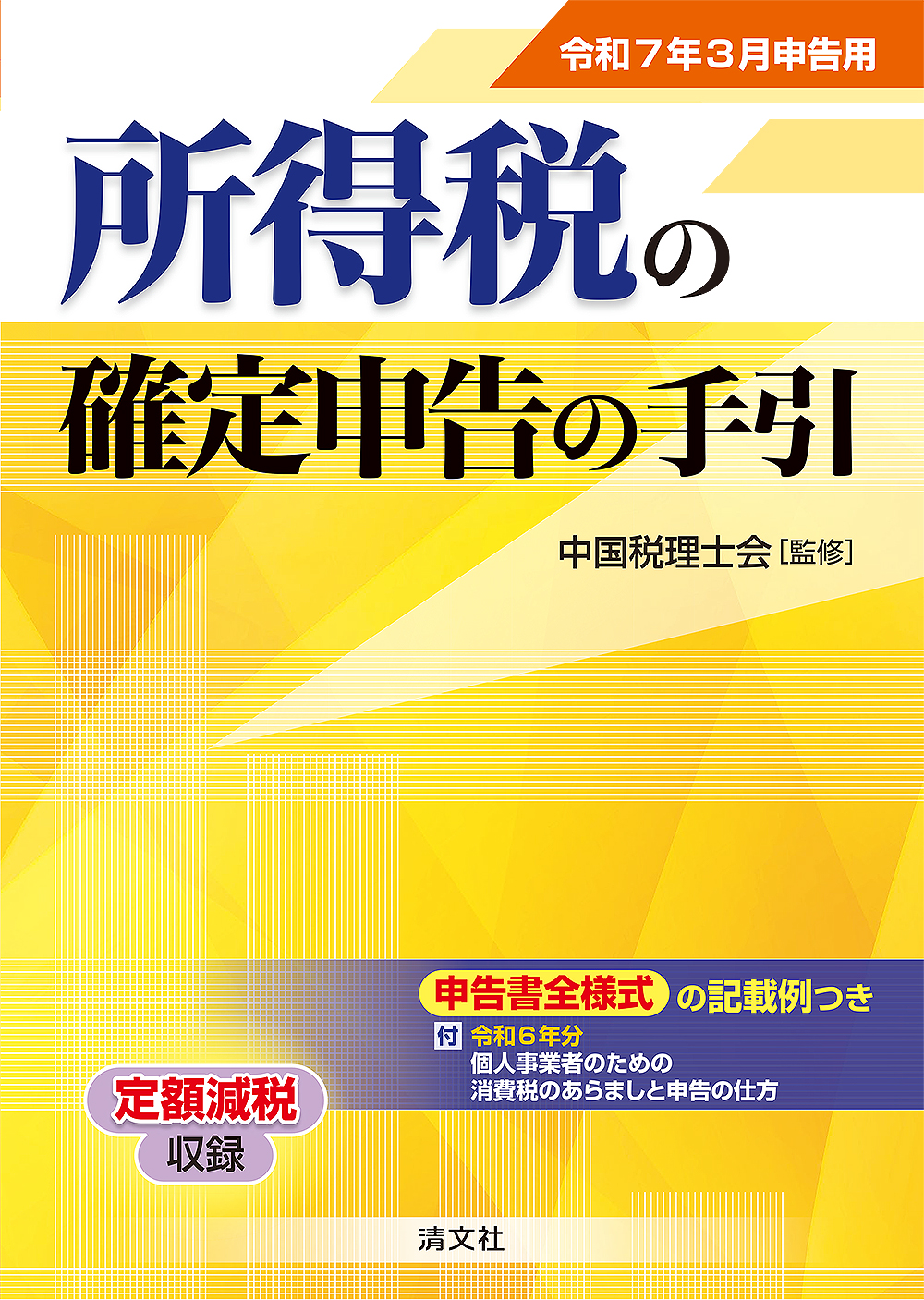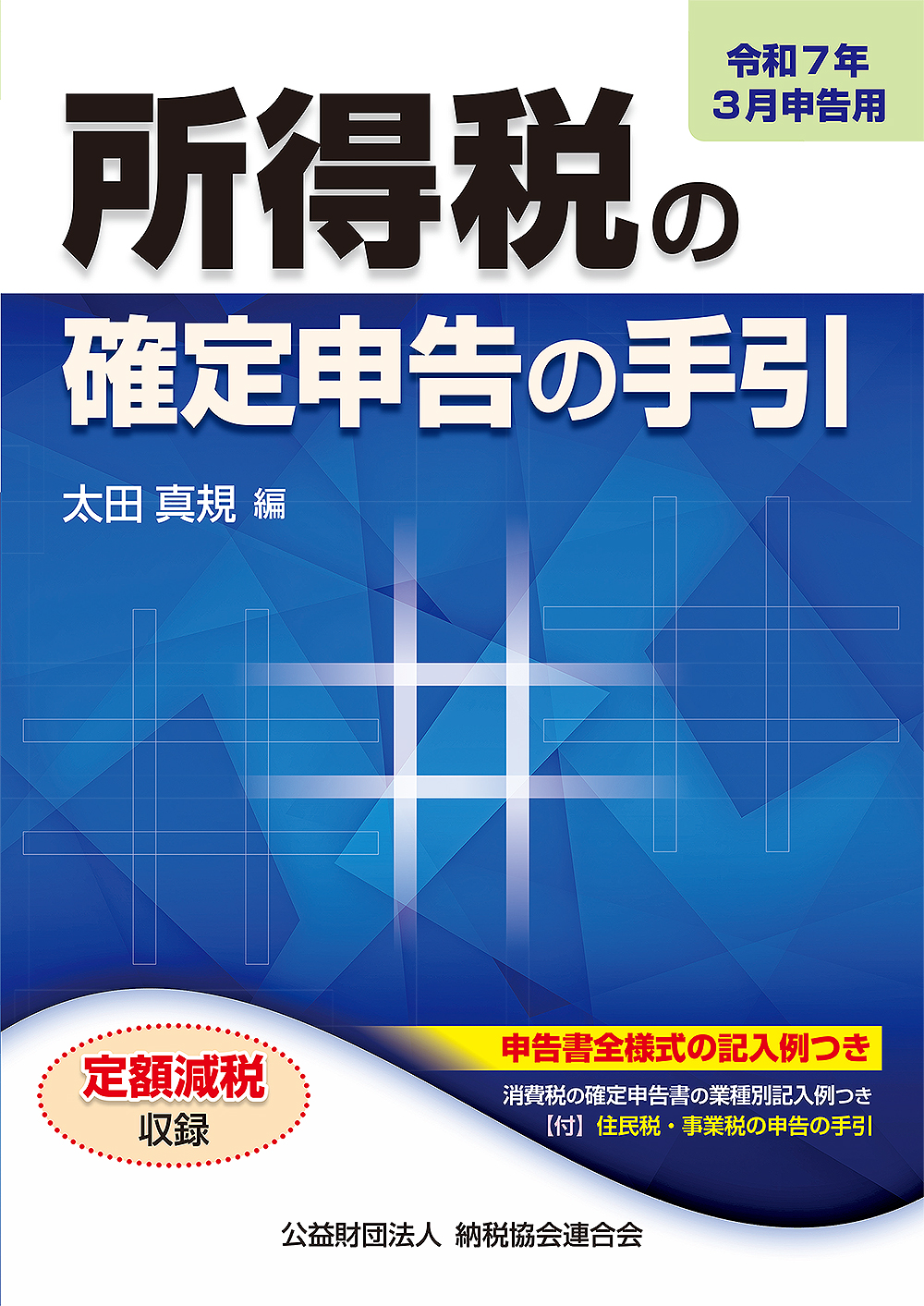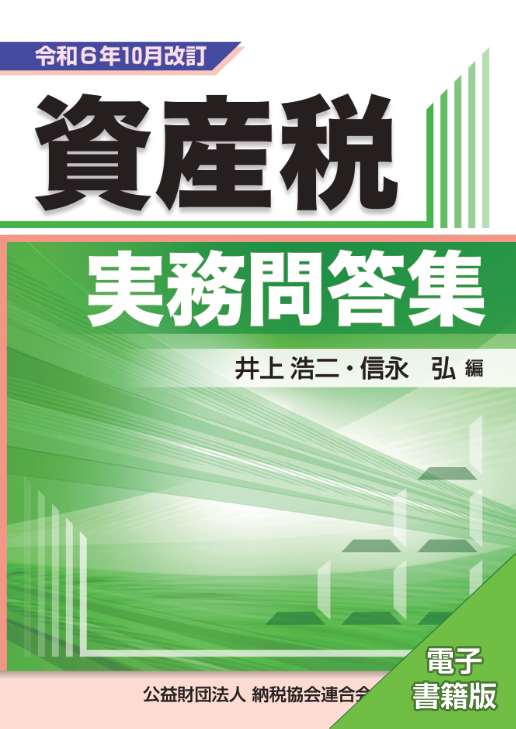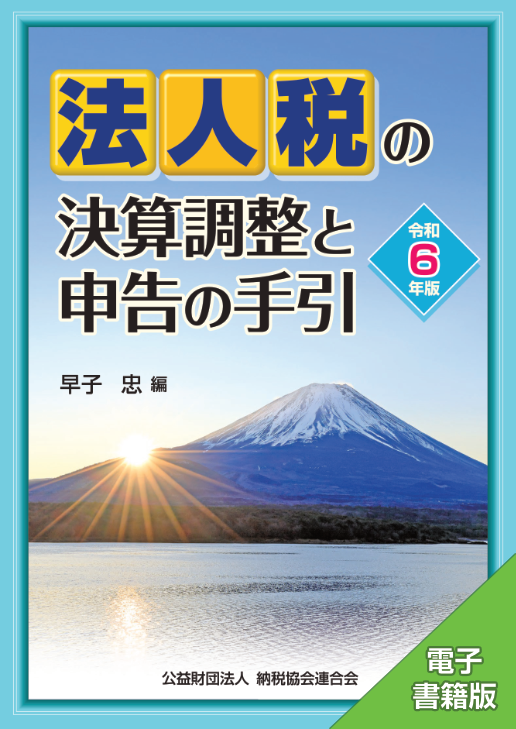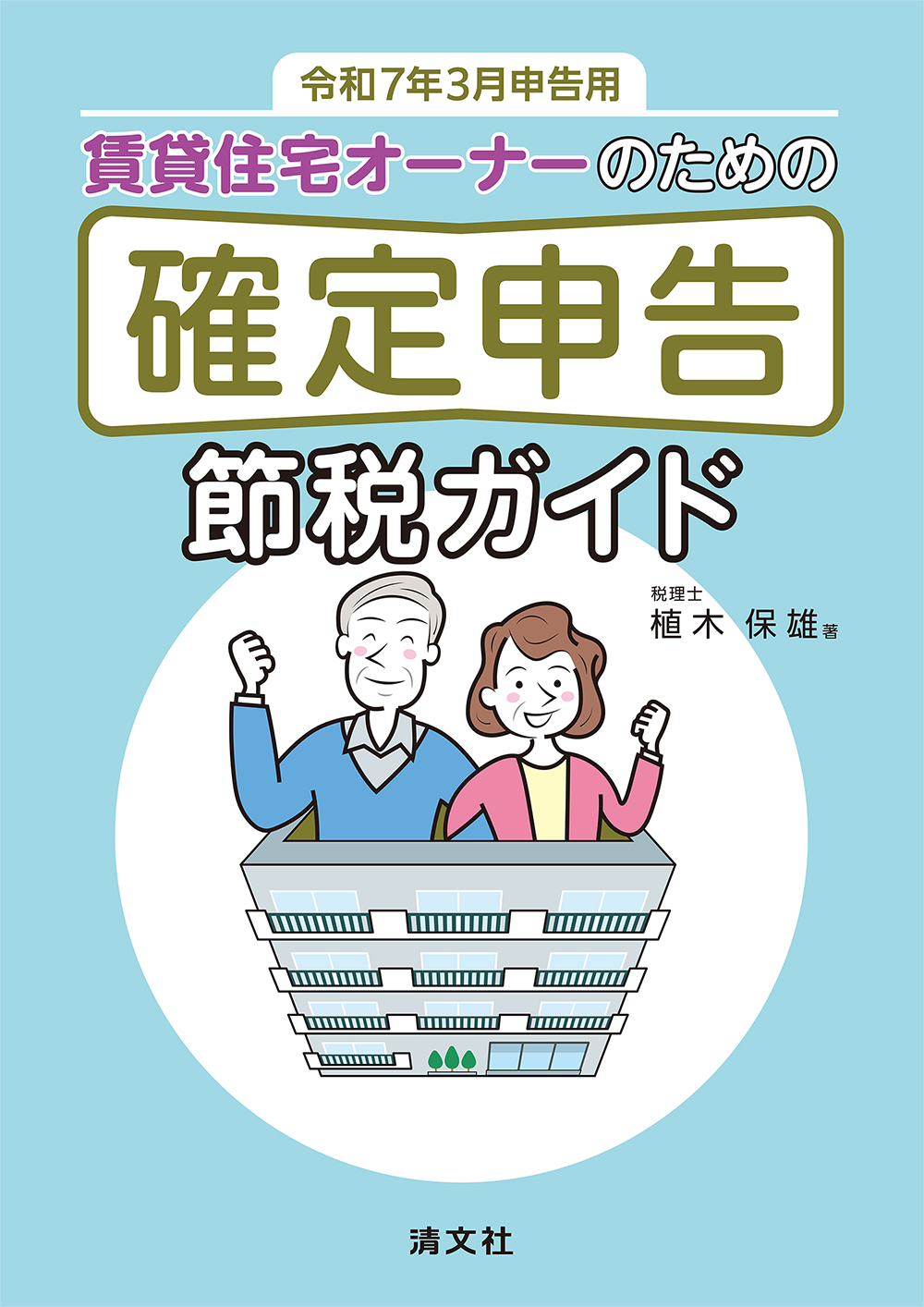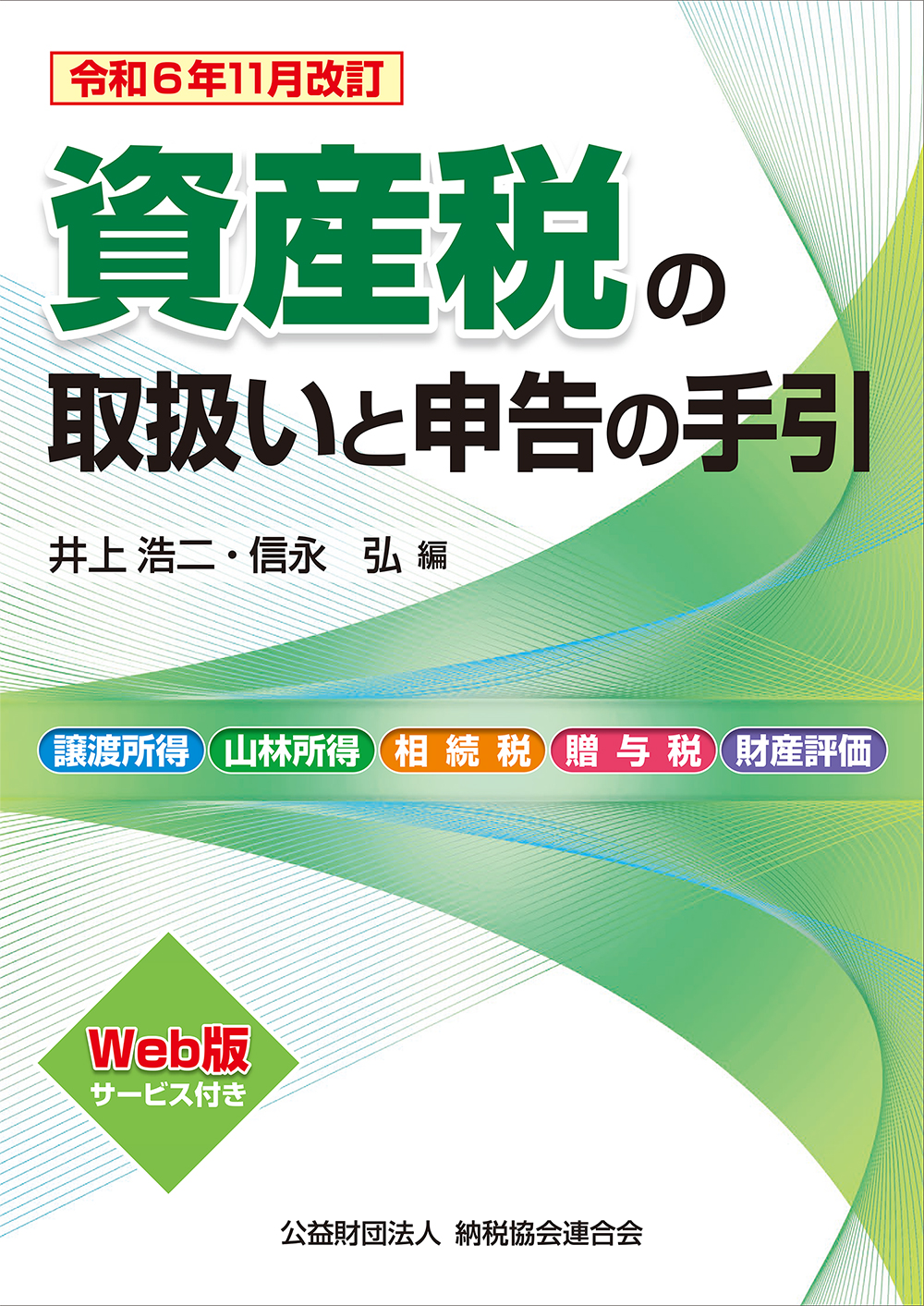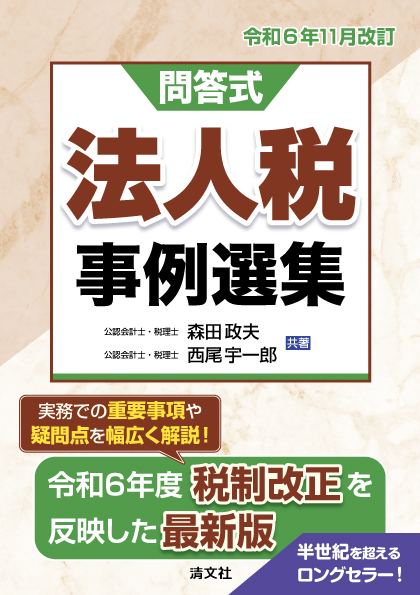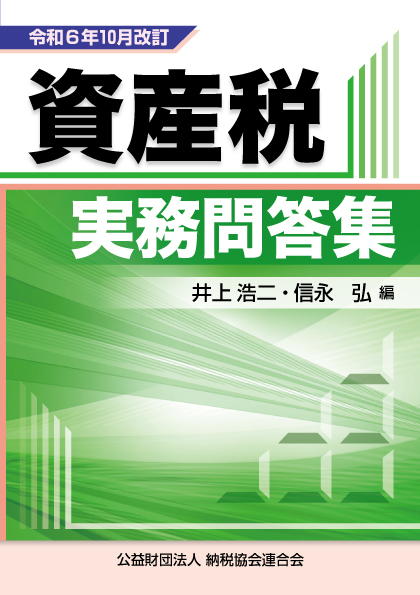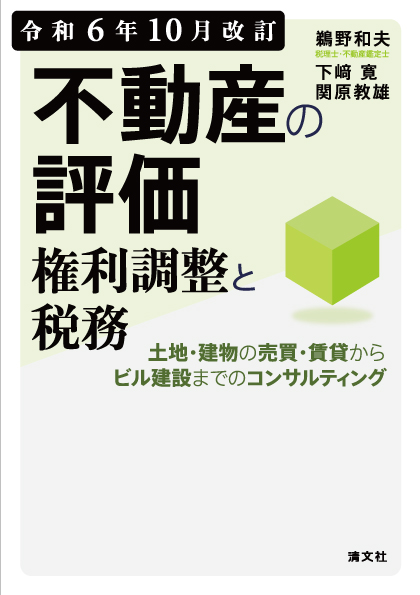「税理士損害賠償請求」
頻出事例に見る
原因・予防策のポイント
【事例32(法人税)】
土地の売却益を圧縮するため、特定資産の買換えの圧縮記帳を適用して申告したが、土地の面積制限により修正申告となった事例
税理士 齋藤 和助
《事例の概要》
平成X5年3月期の法人税につき、土地の売却益を圧縮するため、特定資産の買換えの圧縮記帳(以下「特定資産の買換え特例」という)を適用して申告したが、買換取得資産のうち、マンションの敷地については、土地の面積制限(300㎡以上でなければならない)により、特定資産の買換え特例の適用ができないものであった。
これを税務調査で指摘され、修正申告をすることとなり、修正申告に係る追徴税額につき賠償請求を受けた。
この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員登録およびログインが必要です。
すでに会員登録をされている方は、下記ボタンからログインのうえ、ご覧ください。
Profession Journalのすべての記事をご覧いただくには、「プレミアム会員(有料)」へのご登録が必要となります。
なお、『速報解説』については「一般会員(無料)」へのご登録でも、ご覧いただけます。
※他にもWebセミナー受け放題のスーパープレミアム会員などがございます。
会員登録がお済みでない方は、下記会員登録のボタンより、ご登録のお手続きをお願いいたします。